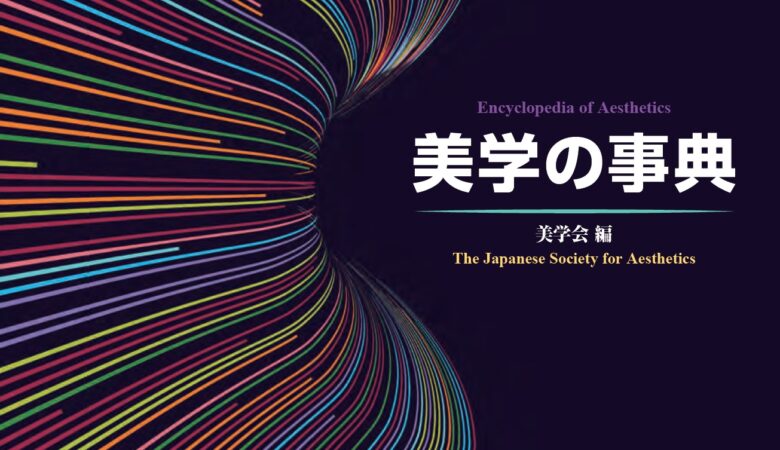【一度展示された展評を再度、ネット上で展示する】
私の執筆した展評を展示するという「I氏の展覧会」(2025年6月23~28日)は、連日多くのお客様でにぎわい、皆さんじっくりと展評を読まれていました。短い会期だったので、展示会場であるギャラリーカメリアにお越しになれなかった方もいるかと思います。ということで、拙い、いや拙すぎる文章ではありますが、「美術評論+」に何回かに分けて展評を掲載することにいたします。
展評は、いずれも400字詰原稿用紙1枚に手書き。国語辞典も見ず、ネットの検索もせず、プレスリリースも見ずに、一気に書いてみました。普段の私は、原稿を書いてから推敲を重ねるように努力しています。また、一度書いたら、原稿を寝かせて、熟成させてから、再度、筆を入れています。しかし、文章に魅力を与える上で一番重要なのは、やはり、筆者の頭に宿った何らかの「発見の瞬間」、その活きのよさが読者に伝わるか否かだと思います。ですから、どんなに熟考を重ねた原稿であったとしても、瞬間瞬間の新鮮な発見がそこになければ、その文章は死んでいると思います。活きのよい文章を読者に届けるためには、たまには一発書きのトレーニングも必要です。
ちなみに、大正時代の書生さながら、時代錯誤な私は、今でも原稿用紙に手書きで文章をしたためることがしばしばあります。どんなにうまく書けたと確信できた文章であっても、どのみち推敲が必要です。私の場合は、原稿用紙に書いた原稿をパソコンで転記する際に推敲をすることにしています。原稿用紙、鉛筆(もしくはボールペン)という組み合わせは、軽くて持ち運びも便利ですし、かかるコストも非常に安価です。不要なメールを受信することもないので、集中するのに持ってこいです。
文章を執筆・発表するということは生き恥をさらすようなものです。己の無知、不見識をすべてさらけだしながら、全裸で大都会の街中を歩くようなものです。大学に通っていたころからなので、すでに文章を熱心に書くようになって35年が経過しましたが、まったく上手にもなっていませんし、相変わらずの恥さらし、です。展評には、自註自解と自己採点も付けてみました。
【展示名】比田井南谷
【会場】東京画廊+BTAP(東京・銀座)
【会期】2024年10月5日~11月16日
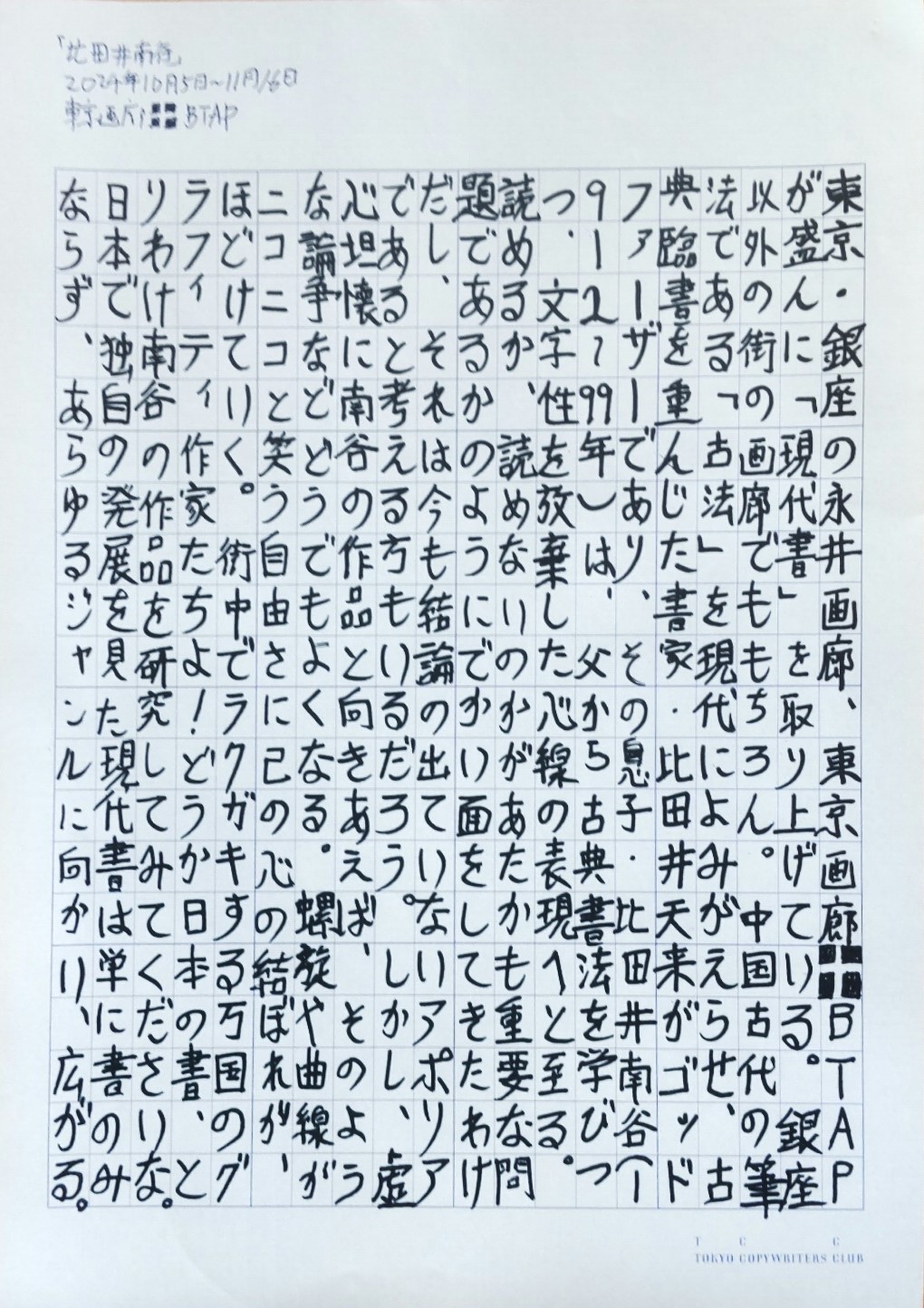
比田井南谷展の評
【展評】
東京・銀座の永井画廊、東京画廊+BTAPが盛んに「現代書」を取り上げている。銀座以外の街の画廊でももちろん。中国古代の筆法である「古法」を現代によみがえらせ、古典臨書を重んじた書家・比田井天来がゴッドファーザーであり、その息子・比田井南谷(1912~99年)は、父から古典書法を学びつつ、文字性を放棄した心線の表現へと至る。読めるか、読めないのかがあたかも重要な問題であるかのようにでかい面をしてきたわけだし、それは今も結論の出ていないアポリアであると考える方もいるだろう。しかし、虚心坦懐に南谷の作品と向き合えば、そのような論争などどうでもよくなる。螺旋や曲線がニコニコと笑う自由さに己の心の結ぼれが、ほどけていく。街中でラクガキする万国のグラフィティ作家たちよ!どうか日本の書、とりわけ南谷の作品を研究してみてくださいな。日本で独自の発展を見た現代書は単に書のみならず、あらゆるジャンルに向かい、広がる。
【自註自解&採点】
「螺旋や曲線がニコニコと笑う自由さに己の心の結ぼれが、ほどけていく」という文章が生まれたので、自分としては上出来。グラフィティを始めとする、あらゆる創造行為と現代書とを結びつけられた点も文章としては良い。故に81点。
【展示名】実さいへたでくさっています/筆のせいかとも思うんですが。 井上有一
【会場】KOTARO NUKAGA(東京・天王洲)
【会期】2025年2月15日~4月12日
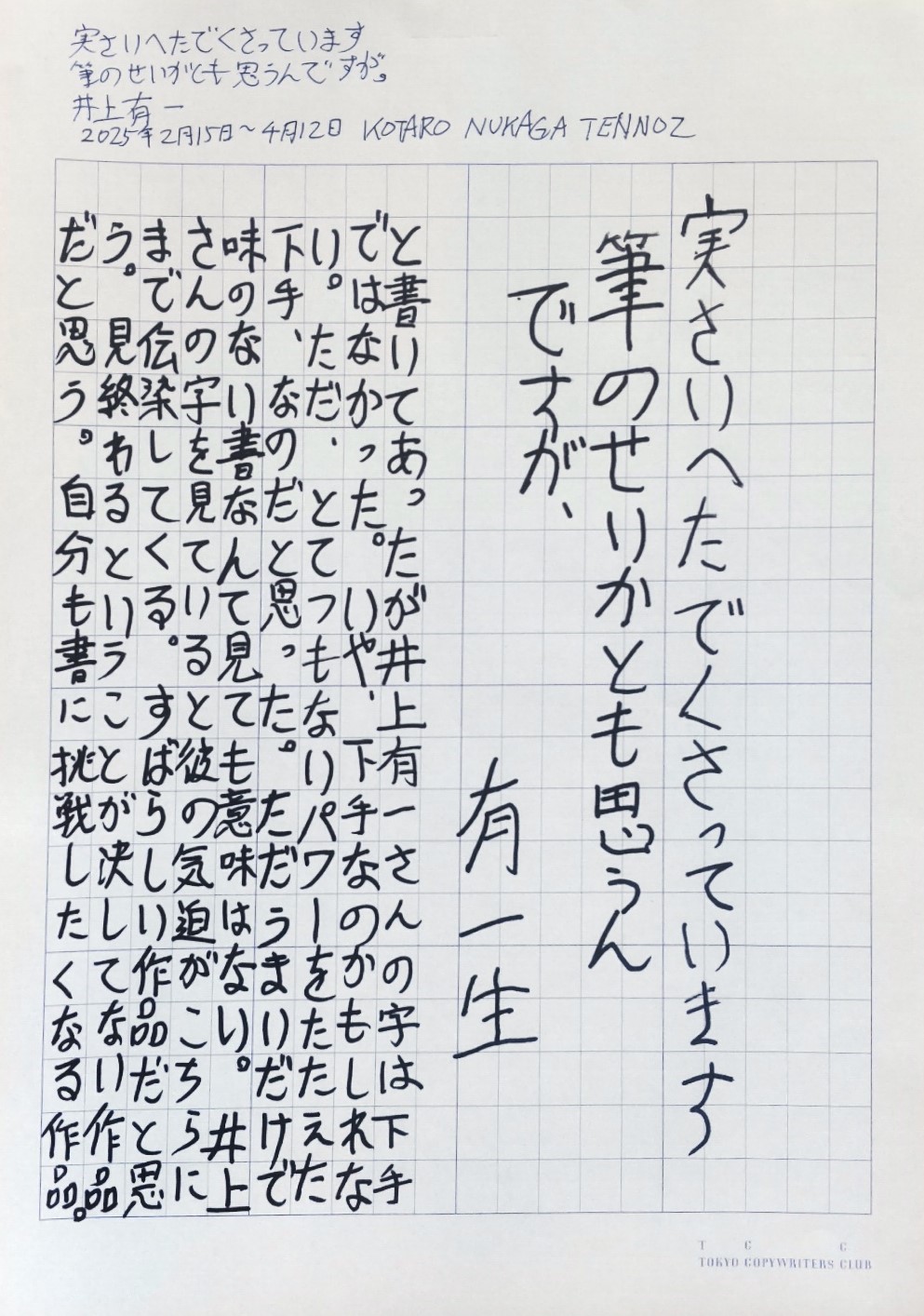
井上有一の展評
【展評】
実さいへたでくさっています/筆のせいかとも思うん/ですが。/有一生
と書いてあったが、井上有一さんの字は下手ではなかった。いや、下手なのかもしれない。ただ、とてつもないパワーをたたえた下手、なのだと思った。ただうまいだけで味のない書なんて見ても意味はない。井上さんの字を見ていると彼の気迫がこちらにまで伝染してくる。すばらしい作品だと思う。見終わるということが決してない作品だと思う。自分も書に挑戦したくなる作品。
【自註自解&採点】
DMに書かれた井上有一の書を真似しようと思って書いたら、まったくマネができず焦った。書の世界の奥深さを思い知らされた。門外漢の自分が書を対象に何かを書こうとすることがいかに愚かな所業であるかを理解した。せいぜい55点。
【展示名】原田郁・衣真一郎 リポジトリ:内と外で出合う
【会場】太田市美術館・図書館(群馬県太田市)
【会期】2025年2月22日~5月18日

原田郁・衣真一郎の展評
【展評】
とてもとても奇妙な(良い意味)展示だった。会場内に置かれた作品が「外」で、原田郁、衣真一郎が制作のため歩き回った群馬県太田市の景観が「内」のように感じられたからだ。もちろん、普通はその逆で景観、大きく広がる街やら山並みが外で、展示会場の作品は内に決まっているのだけれども。でもよくよく考え直せば、やっぱり景観に限界はあるけど日本、世界、宇宙、さらに宇宙の外まで創造・想像して、それを反映できる作品には限界なんてない。だから、最初の感想はやっぱり正しくて、作品こそが外部で、作品の基となった景色は内部なのであった。作品という言葉を「ネット空間」と置きかえることも可能だ。私たちは、すでにネット上の空間を旅することにも人に出会うのにも慣れている。そこに写っている異国の人が実在するか否か、まったく疑いもせずに当たり前のような顔をして相手と会話をしたりしている。「本当に大丈夫ですか。内⇔外は真に存在していますか?」
【自註自解&採点】
作品という言葉を「ネット空間」と置きかえることも可能だ。←この一文の中にある「作品」は「景観」が正しかった。勢いだけで一発で文章を書こうとすると、このような致命的な過ちを犯してしまう。まったくお恥ずかしい限り。故に29点。
【鑑賞ツール名】Patterns B-I-N-G-O/Express Yourself B-I-N-G-O
【配布会場名】ボストン美術館(アメリカ)
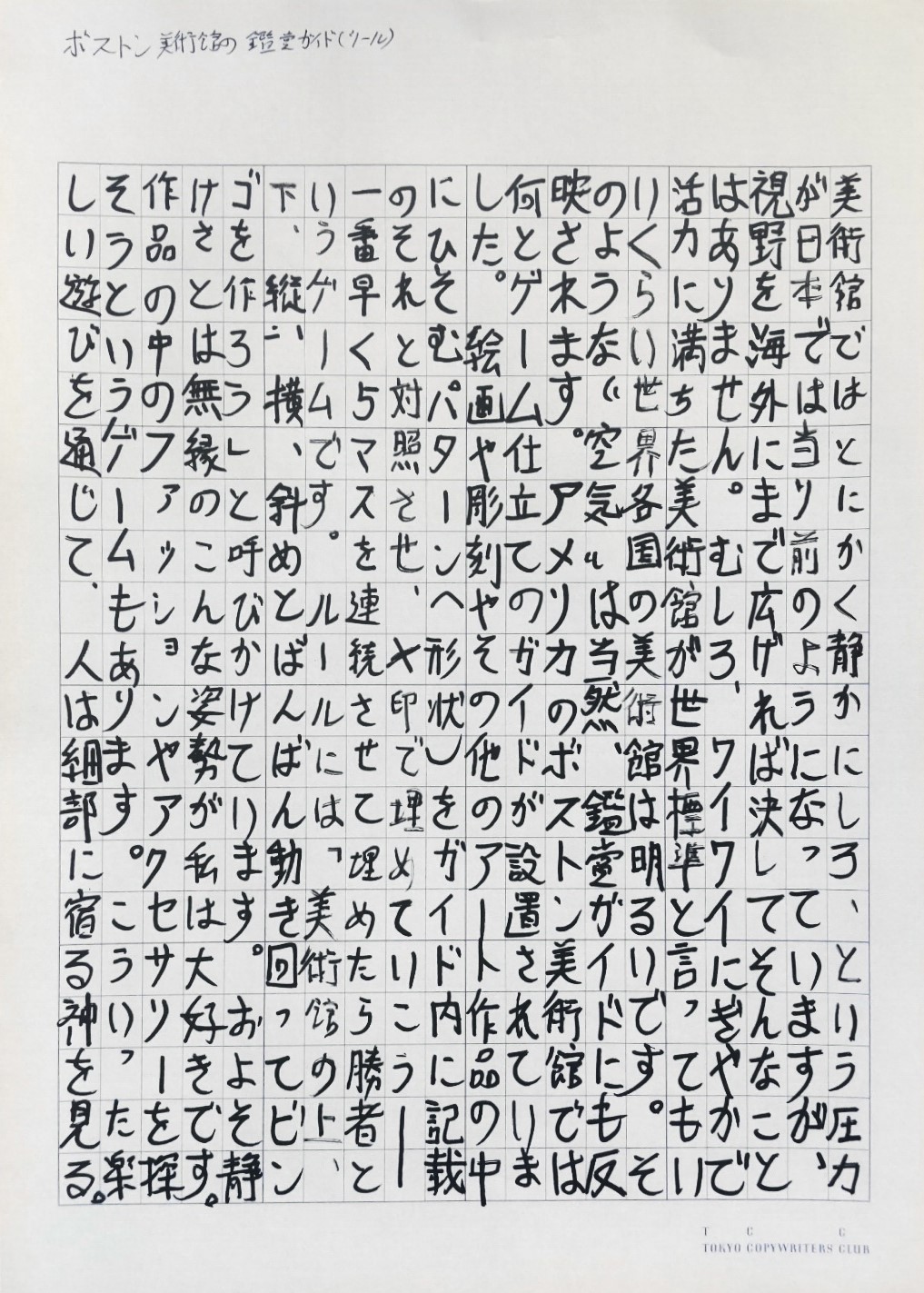
ボストン美術館で配布されている鑑賞用ツールへの評
【評論】
美術館ではとにかく静かにしろ、という圧力が日本では当たり前のようになっていますが、視野を海外にまで広げれば決してそんなことはありません。むしろ、ワイワイにぎやかで活力に満ちた美術館が世界標準と言ってもいいくらい世界各国の美術館は明るいです。そのような“空気”は当然、鑑賞ガイドにも反映されます。アメリカのボストン美術館では何とゲーム仕立てのガイドが設置されていました。絵画や彫刻やその他のアート作品の中にひそむパターン(形状)をガイド内に記載のそれと対照させ、✖印で埋めていこうーー一番早く5マスを連続させて埋めたら勝者というゲームです。ルールには「美術館の上、下、縦、横、斜めとばんばん動き回ってビンゴを作ろう」と呼びかけています。およそ静けさと無縁のこんな姿勢が私は大好きです。作品の中のファッションやアクセサリーを探そうというゲームもあります。こういった楽しい遊びを通じて、人は細部に宿る神を見る。
【自註自解&採点】
「設置」という言葉は「配布」が正解ですね。この過ちが減点要素になりますが、全体としては海外美術館のユニークな取り組みの概要と意義、さらに静粛さを是とする国内美術館関係者への問題提起も簡潔に記せている。故に77点。(2025年7月13日17時39分脱稿)