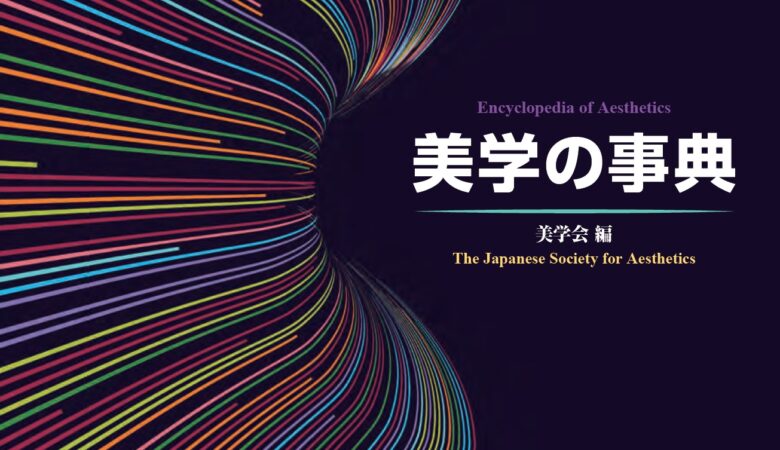真贋の向こう側・前編、後編、反響編の3つの原稿では、繰り返し複製画の有効活用を訴えた筆者でしたが、本稿では、皆さんのお近くにある図書館に足を運んでみてはいかがというご提案をいたします。また、「8月15日」と深い関係がある、福島県内のミュージアムで見かけた奇妙な布についての文章も併せて書いてみました。
【近くの図書館に複製画?】

掛川市立中央図書館の一角にある奇妙な銀色の袋
まずは、上の画像を見てください。これを見て、何だかパッと分かる方はいらっしゃいますか?
静岡県掛川市の掛川市立中央図書館の一角で撮影しました。袋がたくさん並んでいます。この袋の中に入っているのは、いったい何でしょうか?
種明かしをしましょう。この袋にはそれぞれ複製画が入っているのです。「掛川市立図書館だより」2021年7月号の記事によりますと、複製絵画を146点も持っているそうなのです。絵画好きの筆者は、早速、図書館に置いてある帳簿を見ました。かなり長くなりますが、どんな顔ぶれか一部分だけご紹介いたします。
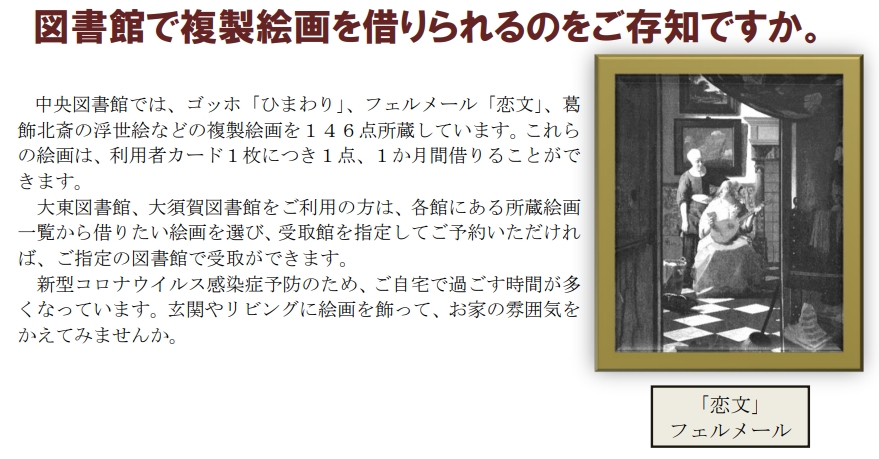
「掛川市立図書館だより」2021年7月号の記事より
まずは、海外の作家から。一部のみの紹介です。
ブーシェ、ミレー、ルソー、ドガ、ルノアール、ロイスダール、モネ、マイヨール、モランディ、ゴッホ、クリムト、ベラスケス、ダリ、マグリット、クレー、ピサロ、ドラクロア、フェルメール、ロートレック、シスレー、ルドン、マネ、ゴーギャン、スーラ、シャバンヌ、コロー、モディリアーニ、レイノルズ、レンブラント、カイユボット、フラゴナール、デュフィ、ミケランジェロ、デューラー、ゲインズボロー、ダ・ビンチ、ピカソ、クールベ、ユトリロ、セザンヌ、ハルス、パスキン、コンスタブル、モディリアーニ、セガンティーニなどなどの顔ぶれです。
続いて日本の作家から。
佐伯祐三、藤井令太郎、井堂雅夫、東郷青児、東山魁夷、竹久夢二、喜多川歌麿、安藤広重、東洲斎写楽、本荘正彦、葛飾北斎、平山郁夫、岸田劉生、浅井忠、池田満寿夫、高沢圭一、伊藤清永などなど。

銀色の袋の中には複製画が入っていた。向かって左は竹久夢二「黄八丈」、右はクリムト「接吻」の複製画
同じ画家で2点収蔵されている場合もあります。すべて、プリハード社(東京都)の複製画でした。もちろん、サイズは本物の絵画と同じですし、なかなかよくできた複製画です。こんな複製画を1か月も借りられるというのだから、これはいい市民サービスです。
筆者は、資生堂アートハウス→掛川市二の丸美術館のルートで年に2、3回掛川市へ美術鑑賞をしに行きます。その旅の中で、図書館の複製画コレクションを知ったのです。パソコンの検索窓に「図書館 複製画」と入れて、検索をしてみてください。掛川市だけでなく、結構、多くの自治体が複製画の貸し出しをしていることがお分かりになるでしょう。
【建築も堪能しよう!】

掛川市立中央図書館の外観。二宮金次郎も立っている
掛川市の図書館に話しを戻します。この図書館の建築がなかなか素敵なんですよ。木の架構、木質内装材など木材を多用した暖かみのある空間で採光も自然光をうまく取り込んでおり、とても寛げます。

淡山翁記念報徳図書館
道を挟んだ向こう側には淡山翁記念報徳図書館という非常にオシャレな外観の図書館が立っており、こちらも興趣深いです。中には入れませんが、外観を周囲から見るだけでも十分、楽しめます。
話しはまたまたそれますが、東京から日帰りで行ける近県には、様々な名建築が存在しております。千葉県の大多喜町役場、埼玉県の埼玉会館、神奈川県の神奈川県立図書館などがパッと頭に浮かびますが、まだまだほかにも多くの名建築があります。筆者は年がら年中、国内外の旅行をしているのですが、その原動力の一つが、これらの建築に出会いたいという欲望なのです。
良い建築を全身で感じることーーそれ自体が一つの小旅行です。筆者にとって、良い建築か否かの判断基準として「自身が建築そのものになれるか?」というものがあります。建築と自身が同化し、自身の視線が建築の放つ視線と重なり、同一になるくらい感情移入が可能な建築、それが筆者にとっての“名建築”なのです。
そんな名建築は、都心のど真ん中というよりは、少し離れた近郊に位置していることが多い気がします。ガウディの建築にしても、バルセロナ中心部の超有名な作品群よりもバルセロナ近郊のサンタ・クローマ・ダ・サルバリョーに建つ「コロニア・グエル教会」が、どう考えても最高傑作だと思います。見る者の心を鷲掴みにする力が、強度が圧倒的な名建築です。建築と自身の精神が混然一体となって融合する感じが、この教会には漂います。筆者は、この教会を訪れた際、「一生、この教会の中に住みたい」と思ったくらい、感動しました。ガウディ建築を一つだけお勧めするとしたら、筆者は自信を持って、「コロニア・グエル教会」の名を挙げたいと思います。
絵画の場合は、複製画の活用を訴えた筆者でしたが、建築に関しては、実見するしかありません。いくら豪華な写真集を見ても、精巧な模型を見たとしても、実際に建っている現地に足を運び、建築の周りを歩き、(入れる場合は)内部にも入り、「この建築が何を考えているんだろう」という問いかけの答えが浮かんでくるまで、建築との対話を繰り返すのです。
自分の心の中に、どれだけ多くの建築を住まわせることができるか?
その豊かなストックがありさえすれば、私たちは自分の内部に巣食う虚無に立ち向かうことが可能なのではないでしょうか?
【80年目の8月15日に】

無数の「カ」で覆いつくされた布切れ、これはいったい何だろう?
最近、福島県内の某ミュージアムを訪れた際、妙な布切れを見つけました。「カカカ…カカカ」と延々と「カ」の字が墨書されているのです。きれいな「カ」もあれば、下手くそでただたどしい筆致の「カ」もあります。どこかおどろおどろしい雰囲気をまとう「カ」を見て、筆者の脳裏に浮かんだのは、福本伸行先生の傑作漫画「賭博黙示録カイジ」に登場するキャラクターの笑い声でした。「カカカ」と彼らは笑うのです。

戦時中の「千人力」
ところが、展示のキャプションを見て、筆者の教養のなさが露呈しました。墨書された字は「カ」(か)ではなく、「力」(ちから)だったのです。異なる千人が一人ひとり「力」と墨書し、出征者に渡した「千人力」(せんにんりき)というものだったのです。白い布に、赤い糸で1000人の女性が一人一針ずつ縫い、結び目を作った「千人針」は知っていましたが、「千人力」もあったのですね。まったく知りませんでした。
福本先生の漫画内でカイジは、しばしば絶望的な状況に追い込まれながら、ギャンブルの勝負にのめり込んでいきます。カイジとその周辺の人物(味方も敵もその他すべて)たちは、極限状況下で極度の緊張や恐怖によって目の輪郭をゆがませながら、勝負に臨みます。そして、そのように賭博をしながら「カカカ」「キキキ」「コココ」といった印象に残る笑い声を披露するのです。楽しいから笑っているのではありません。どちらかと言うと自らの恐怖を打ち消すために懸命に「カカカ」という笑い声で自らを鼓舞しているのです。
筆者は確かに「カ」(か)と「力」(ちから)を勘違いしましたが、実は勘違いではなかったのかもしれません。戦時中の日本は、勝てる見込みがないことを十分、分かっていながら、戦争を自力で終わらせることができませんでした。極限状況下に置かれ、カイジ君同様、目の輪郭をゆがませながら、絶望的な賭博勝負に臨んでいたのです。老若男女、すべての日本国民の最後の一人が倒れるまで、戦争を遂行するとお上が叫ぶ中、大なり小なり、国民は戦争協力を強制されたのです。目をゆがませながら。
「千人力」を見た時、カイジ君が目をゆがませながら笑っている姿が浮かんだのは、こういうことでしょう。戦時中の日本もまず勝ち目がない戦争に足を踏み入れて、まさに絶望的な状況に追い込まれていた。「神風」が吹くといった非科学的な現象を持ち出してまで戦争を続けたのです。千に一つの勝ち目を求めて、国を挙げてギャンブルをしていたのです。ほとんど勝ち目がない訳ですから、どうしたって悲愴感が漂いますし、目の輪郭だってゆがむ訳です。このような状況下で墨書された「力」(ちから)が「カ」(か)に見えて、筆者の頭の中に「カカカ」「キキキ」「コココ」というあの奇妙な笑い声(≒泣き声)が聞こえてきたのでしょう。
国民に甚大な犠牲を強いてまで、“ギャンブル”に励んだ国の末路は読者の皆さんもご存じでしょう。80年目の8月15日に、筆者はジャーナリスト・清沢洌(1890~1945年)の「暗黒日記」(評論社版・復初文庫/編集・解説 橋川文三)を再読しています。1942年から45年の暗黒が理性的な眼差しによって正確に描写されています。清沢の目は戦時中でもゆがんではいなかったのです。現在の日本は、様々な識者が指摘する通り、「戦前」ですらなく、まさに「戦時中」といっても過言ではないほどの「暗黒」に包まれています。
あなたよ、あなたの目はすでにその輪郭がゆがんでいませんか?(2025年8月15日、ポツダム宣言受諾が公表されてから80年が経過した日の18時7分脱稿)