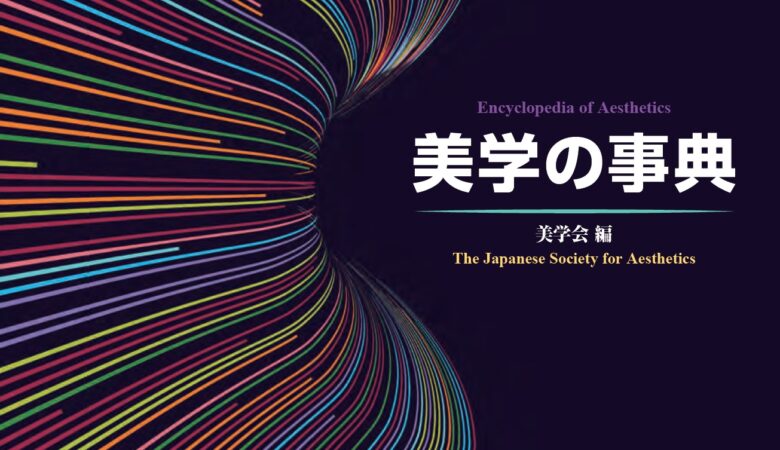古くて新しい話題を前編、後編の2回にわたって取り上げます。テーマは美術作品を巡る真贋の問題です。

徳島県立近代美術館。真贋の向こう側には何が広がっているのか?
いやぁ、大騒ぎになっていますよね。徳島県立近代美術館(徳島市)と高知県立美術館(高知市)が所蔵する2点の絵画の件です。2点のいずれもドイツで詐欺罪の実刑判決を受けた贋作家ヴォルフガング・ベルトラッキ氏による贋作である可能性が高いことが判明し、両県とも対応に苦慮している、とのことですが…。
【真贋なんて見分けられません】
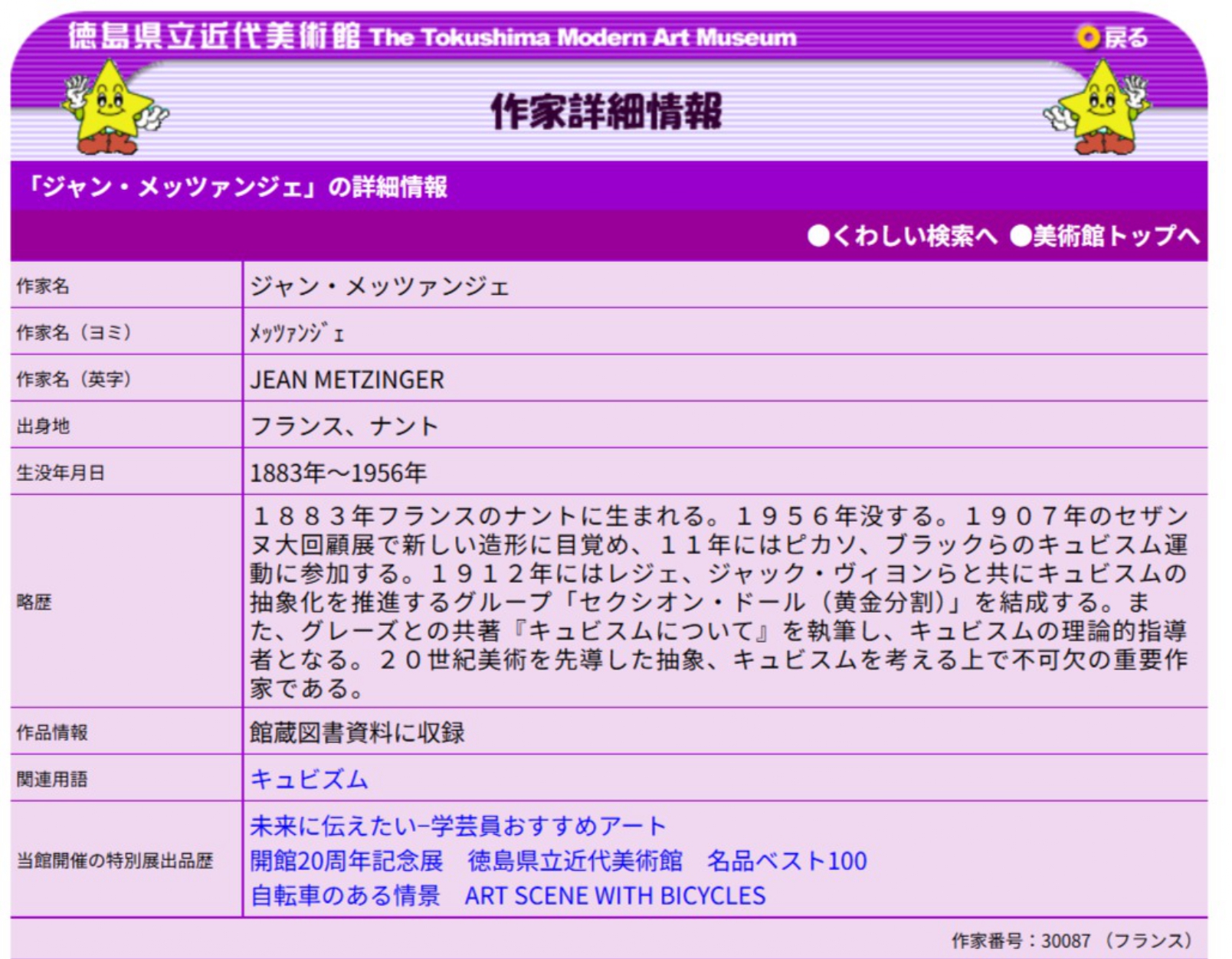
徳島県立近代美術館の公式HPより
ジャン・メッツァンジェ(1883~1956年)の「自転車乗り」(1911~12年)を1999年に6720万円で大阪市の画商から購入したのが徳島県。ハインリヒ・カンペンドンク(1889~1957年)の「少女と白鳥」(1919年)を1996年に1800万円で名古屋市の画商から購入したのが高知県。いずれもベルトラッキ氏による贋作ではないかと取りざたされています。
このニュースを聞いた時に筆者が最初に思ったのは、「ベルトラッキ、渋いなー」でした。モネ、ルノワール、ピカソ、ゴッホ、ダリなど超メジャーな画家ではなく、メッツァンジェやカンペンドンクといったかなりマイナーで渋い画家の贋作を手がけていることに感心したのです。美術史的には価値があるとされる画家でも、一般の方の知名度はあまりない両作家の作品なんて、10点、いやいや5点以上を実見している学芸員、美術史家、美術評論家など、そうそうはいないのではないでしょうか?
世界中の美術館を回り続けてきた筆者にしてから、過去にメッツァンジェとカンペンドンクを実見した数は、どちらも間違いなく5点以下、いや、せいぜい数点だと思います。しかも、この両作家クラスの画家だと、日本国内で充実した画集を見ることも難しいです。ということは、大学院の博士課程でメッツァンジェやカンペンドンクを博士論文のテーマに選び、海外の所蔵美術館を徹底的に回った経験のある俊英の学徒でもない限り、両作家の作品を多く見ている国内研究者などほとんど存在しないということです。
「新潮世界美術辞典」(新潮社)には両作家とも載っていますが、「西洋絵画作品名辞典」(三省堂)には両作家とも載っていないのです。後者は筆者の大好きな本です。黒江光彦さん(1935~2022年)が監修した本書は、著名な美術作家の手になる作品の題名、材質、寸法、所蔵などの重要な情報が記載されています。筆者の活用法は、「●●という作家の作品をまとめて見たい場合、訪れるべき美術館(国・都市)はどこか?」というものになります。ある特定の作家をなるべく多く見るために旅行で訪れる都市を決める際に、本書はとても役に立つのです。この分厚い辞典にも載っていないメッツアンジェとカンペンドンクを選ぶ辺りを指して、筆者は贋作家のことを「渋い」と評したのです。
両美術館は贋作を長年、展示し続けてきたことに恥じ入っているようですが、筆者はあえて嫌なことを言います。「いやいや、普通の美術館の学芸員が、こんなマイナーな作家の真贋を見分けられるはずがないでしょう」と。そもそも徳島の学芸員の方、生まれてからメッツァンジェの作品を何点、実見していましたか? 1956年に亡くなっている作家ですから、アトリエで制作している風景を学芸員が実見したわけでもないでしょう。
両美術館の学芸員が「これは本物だ」と思い、信用したのは、要するにきちんとした正式な鑑定書が付いていて、作品の来歴もちゃんとしていた(ように見えた)からでしょう。つまり、作品に付随している書類が疑わしくなかったから、そして値段もまぁまぁ妥当だったから、購入を決断したのでしょう。過去の作品の流れがうさんくさくないように思えたから購入したーーそれは言い換えれば、過去の「自転車乗り」の持ち主が代々、騙され続けていただけのことなのですが…。
「自転車乗り」には本物の絵が存在しません。ベルトラッキ氏が、メッツァンジェの絵の描き方を研究・参照して描いた、ただの捏造品なのです。本物もない絵が長年、本物として流通していたわけですから、これは、ある意味で“ほぼ本物”と言ってもいいくらいです。真贋を簡単に見分けられるわけはないのです。
【鑑定も最後は勘】
筆者の知り合いに、百戦錬磨の美術品の鑑定家がいます。非常に著名な方なので、名前を伏せて仮にA氏(男性)といたします。彼に両美術館の贋作の件について感想を聞きました。開口一番、「うーん、あれがモネとかゴッホとかならいざ知らず、メッツァンジェとカンペンドンクでしょう。(両美術館とも)県民の血税を投じてまで購入する必要が本当にあったんですかね、あの程度の画家で」と語り出しました。
「美術館の学芸員さんは、しょせん文献主義、書類主義。作品そのものを鑑定するというよりは、作品に付いてくる書類がきちんとしていたら、それで購入を決定してしまいますよ。仔細に作品を調べているわけでもないし、その能力もないでしょう。彼らに真贋なんて判断できるわけはないよ」と厳しいコメントが続きました。
美術品の鑑定に国家資格のようなものは存在しません。だから、周りから「●●さんなら鑑定できるだろう(できるはずだ)」という期待を込めて、過去の実績が豊富な方に鑑定の依頼にくるのです。もちろん、A氏にも多くの実績があるので、今も鑑定依頼が引きも切らないわけです。
そんな彼に「鑑定のコツは?」と直撃したところ、「最後は直感なんですよ、色々と理屈をこね回したとしても最後は直感」と返ってきたので驚きました。贋作を手がける方は、恐ろしいほど上手に似せてくるので、本物との違いは容易に見分けられないそうです。最終的には、作品の放つ“匂い”や“雰囲気”を手掛かりに直感的に真贋を決定するそうです。
社交上は、絶対に聞いてはいけないはずの質問をあえてA氏にぶつけてみました。
「今までたくさんの作品を鑑定してきて、失敗した。つまり、真贋を見分けそこなった経験は何件ありますか?」
彼の表情がたちまち凍り付きました。
「・・・・・・・・・・・・」と10秒以上、無言が続きました。答えられない。この質問には絶対に答えたくない、という明確な意思が彼から感じ取れたので、筆者もそれ以上、問い続けることはやめにしました。
無言の回答が意味するものは、もはや明らかでしょう。「鑑定に失敗してしまった苦い体験は一度や二度じゃきかないくらいある」ということを無言の返事から察してくれというのが彼の真意だと筆者は理解しました。
百戦錬磨の鑑定家にしてみても、真贋を見分けるのがこんなにも難しいのですから、普通の学芸員、美術史家、美術評論家が簡単、お手軽な気持ちで鑑定なんかができるわけはないのです。
【過去の真贋論争】
弁護士・島田真琴氏の好著「アート・ロー入門」(慶應義塾大学出版会)には、第3章「贋作美術品をめぐる紛争」、第4章「贋作売買と画商の責任」という項があります。本書には、過去の贋作騒動が多く紹介されており、大変参考になります。法律にうとい筆者でも知っていた知名度の高い事件から、戦前に起きたマイナーな事件まで様々です。事件名のいくつかを同書から列挙してみましょう。
ハーン対デュヴィーン事件(1929年)
春峯庵事件(1937年)
メーヘレン(フェルメール贋作)事件(1947年)
コンスタブル贋作事件(1950年)
安田靫彦偽筆売買事件(1961年)
アングル贋作売買事件(1983年)
ミュンター贋作売買事件(1991年)
堂本印象贋作売買事件(1998年)
佐伯祐三贋作事件(2002年)
ドレイク対アグニュー、ヴァン・ダイク贋作事件(2002年)
ギュスタヴ・モロー贋作事件(2002年)
ルノアール贋作売買事件(2003年)
藤田嗣治・ルノアール贋作売買事件(2012年)
小林古径作品売買事件(2014年)
ルノアール贋作紛失事件(2016年)
いかがでしょうか?
本書に掲載されているもの以外でも贋作事件、贋作騒動は毎年のように世界のどこかで勃発しています。要するに星の数ほど贋作はあるということです。美術館のガラスケースの向こうに鎮座している美術作品、いかにもありがたそうに展示されていますが、実は贋作なのかもしれないのです。それにしても、島田氏の著作で紹介されている作家の何ときらびやかなことか!
フェルメール、ルノアール、ヴァン・ダイク、藤田嗣治と錚々たる顔ぶれじゃないですか。メッツァンジェとカンペンドンクを贋作の対象として選ぶベルトラッキ氏の渋さ、言い換えれば巧妙さが余計に目立ちますし、驚きあきれてしまいます。
フェルメールや藤田の贋作に騙されるのであれば、メッツァンジェごときマイナー作家の真贋が見抜ける道理はないじゃないですか。しかも、上記の贋作事件には、一流の画商、美術評論家、鑑定家もかかわっているケースが多いです。つまり、プロ中のプロが「これは本物です」と認定したとしても実際は贋作であったというケースはざらにあるということです。前述のA氏が、筆者に対して長い沈黙という回答を返してきたのもむべなるかな、です。
特定の芸術家の作品とされている美術品が贋作ではないことを証明することをオーセンティケーション(authentication)と言います。また、特定の美術品を誰がいつ制作したものであるかを証明することはアトリビューション(attribution)と言います。オーセンティケーション、アトリビューションのいずれも極めて難しい作業であるというのが偽らざる真相です。
島田氏の書名の一部分を一文字だけ、変えてみましょう。アート・ロー(Art Law)が一瞬にしてアウトロー(Outlaw=法律のわくの外)の世界に変容してしまいます。これは決して言葉遊びなんかじゃありません。アート・ローとアウトローは本当に紙一重の世界なのです。
本稿では、真贋を見抜くのがいかに難しいものかを縷々、書き連ねてきました。後編では、筆者の考えた「真贋の向こう側」を提言してみたいと思います。お楽しみに!(2025年8月2日17時46分脱稿)