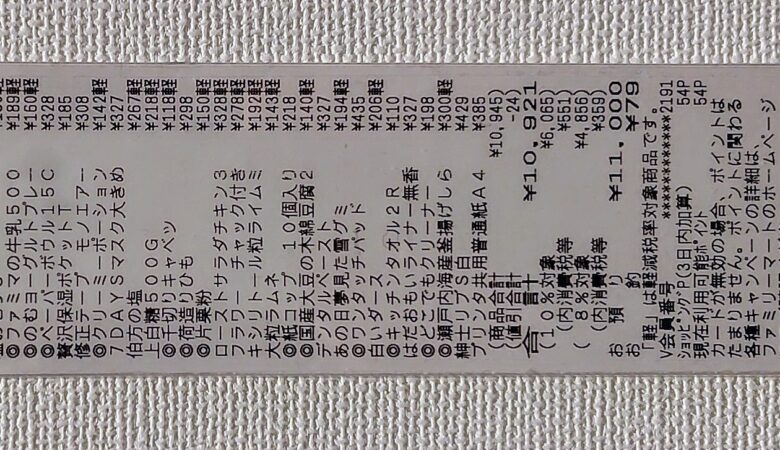ダミアン・ジャレ+名和晃平《Planet [wanderer]》
◼︎ 東京公演
日時:
2025年11月1日(土) 15:00 – 16:00
2025年11月2日(日) 15:00 – 16:00
2025年11月3日(月・祝) 15:00 – 16:00
会場:東京芸術劇場 プレイハウス
(〒171‑0021 東京都豊島区西池袋1‑8‑1)
◼︎ 京都公演
日時:
2025年11月8日(土) 19:00 – 20:00
2025年11月9日(日) 15:00 – 16:00
会場:ロームシアター京都 サウスホール
(〒606‑8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13)
コンセプト・振付:ダミアン・ジャレ
コンセプト・舞台美術:名和晃平
音楽:ティム・ヘッカー
照明:吉本有輝子
衣装:スルリ・レヒト
サウンド・デザイン・コラボレーション:グザビエ・ジャコ
振付アシスタント:アレクサンドラ・ホアン・ジルベール
Outside Eye:カタリナ・ナヴァレテ・エルナンデス
舞台監督:夏目雅也
出演:ショーン・アハーン、エミリオス・アラポグル、カリマ・エル・アムラニ、フランチェスコ・フェラーリ、ヴィンソン・フレイリー、クリスティーナ・ギエブ、アストリッド・スウィーニー、湯浅永麻

©Rahi Rezvani
ダミアン・ジャレ

©Michael Somoroff
名和晃平
2025年11月、振付家・ダンサーのダミアン・ジャレと彫刻家の名和晃平の協働によるパフォーマンス作品《Planet [wanderer]》のアジア初演となる日本ツアーが行われた。東京芸術劇場で3公演、ロームシアター京都で2公演の計5公演である。筆者は、京都公演の最終日に鑑賞した。
本作は、2016年にロームシアター京都で初演された《VESSEL》、2021年に映像作品として発表された《Mist》に続く、二人のコラボレーション舞台の三作目である。本来、2020年か2022年にロームシアター京都で上演予定であったが、新型コロナ禍のため延期され、先にヨーロッパで上演されていた。
具体的には、フランスのパリで初演の後、オランダのアムステルダム、フランスのルーアン、ベルギーのシャルルロワ、ドイツのハンブルク、スイスのジュネーヴ、フランスのレンヌ、ベルギーのブルージュ、ギリシャのアテネを巡回し、今回遂に待望の日本公演である。特に、ロームシアター京都はジャレと名和の10年来のコラボレーション舞台の原点として意義深い。
今回、いずれの公演も座席は早い段階でソールド・アウトしている。ようやく日本での評価も海外の高さに追いつき始めており、全5公演を鑑賞した熱狂的ファンもいると聞いている。
写真集 ダミアン・ジャレ+名和晃平『VESSEL / Mist / Planet [wanderer]』(美術出版社、2022年)
宗教学者ミルチャ・エリアーデは、神話は聖なる出来事を語る超時間的な物語であると説く。そこでは、世界の真理が啓示される。神話に触れることは、その「聖なる時間」を追体験する行為である。その点で、二人のコラボレーション舞台は正に神話的と言ってよい。
実際に、受付で配布されるパンフレットによれば、このコラボレーション三部作は日本最古の神話である『古事記』に取材している。《VESSEL》が死者の世界である「黄泉国(よみのくに)」、《Mist》が神々の世界である「高天原(たかまがはら)」を表したのに対し、本作《Planet [wanderer]》は生者の世界である「葦原中国(あしはらのなかつくに)」を表現しているという。
しかし、日本神話を踏まえているといっても、何か特定の神が登場したり特定の筋が物語られる訳ではない。日本神話は、エリアーデのいう神話の普遍的な構成要素が数多く当てはまるために「世界の神話の集大成」と言われることがある。詩人ゲーテ風に言えば、この三部作は、日本神話の特殊性から出発して神話そのものの普遍性へと至ろうとしているのだろう。
そして、そうした芸術による「新しい神話」を通じて断片化する同時代の人々の心を結び付けようとする点で、この三部作は19世紀のロマン主義の精神的系譜に連なっている。特に、本作は生者の世界である「現世」を取り上げる分だけ前二作よりも親近感が増している。

Planet [wanderer] © Rahi Rezvani
筆者は、天文学者フレッド・ホイルの有名なテーゼ「生命が偶然に生まれる確率は、竜巻が廃品置場を巻き上げてボーイング747を組み立ててしまうような確率に等しい」を知って驚いたことがある。本当に、そんな奇跡が起こったのだろうか?
確かに、太陽は月よりも400倍大きいけれども400倍離れているために両者がちょうど同じ大きさに見えるという、にわかには信じがたい奇跡が現実にはある。しかし、生命は地球で自然発生したとする「アビオジェネシス説」は、単に天文学的に低い確率というよりもほとんど不可能であることを示している。
これに対し、ホイルは「パンスペルミア説」を唱えている。これは、生命の起源は地球外にあり、生命の種(有機分子)が宇宙空間を漂う隕石や宇宙塵に付着して地球に到来したとする考え方である。
いずれにしても、この仮説に示唆されて、本作は冒頭、暗闇の舞台に天から光り輝く粉塵が降り注ぐ。鉱物しかなかった荒野に、最初の生命体が目覚め、胎動し、蠢動する。
やがて、重力に抗うように、大地に根を張る植物が生まれ、四足歩行の動物が誕生し、二足歩行の人間が登場する。誰もが、何かを求めて、もがき、あがき、彷徨い歩く。背景では、海がさざめき、霧が立ち込め、雨が滴り落ち、生命の源である水の循環を表象する。本作は、「現世」としての地球における生命の進化の叙事詩であり、悠久の生命誌の一大ドラマなのである。
なお、環境学者ジェームズ・ラヴロックは地球(ガイア)自体を一つの生命体と捉えている。もし天文学者カール・セーガンが言うように、私達の肉体が「星の塵」でできているならば、ガイアの生命が私達に分有されていると考えることもできるだろう。
さらに、ダンサー達の幻想的に輝く身体は、神智学でいう「アストラル(星幽)体」を想起させる。アストラル体は、夢を見ている時や幽体離脱している時の自分とされる。
ここでは、冒頭で湯浅永麻の演じる最初の生命体が、このコラボレーション三部作の写真集の表紙を飾っていることを付言しておこう。

Planet [wanderer] © Rahi Rezvani
世界中から招集された男女混合の実力派のダンサー達は、個々に磨き抜かれた卓越した身体能力を発揮する。苦悶と煩悶。鳴動と躍動。一見、それぞれ自由闊達に舞い踊りながら、互いに複雑に絡み合い、全体としてその呼応は一糸乱れない。
「多様の統一」を美の本質と見なしたのは、美学者フランシス・ハチソンである。ダンサー達の艶めかしくエロティックでありながらも超然とした美しい秩序は、普段忘却している生々しい哲学的連想を誘わずにおかない。
「人は、生まれたら必ず死ぬ。それなら、なぜ人は生まれたのだろうか?」
「生物学者リチャード・ドーキンスの言うように、人は『利己的な遺伝子』の乗り物に過ぎないのだろうか? それなら、恋愛も錯覚なのだろうか?」
「弱肉強食は、自然界の掟なのだろうか? 人生の目的は、利己なのだろうか、利他なのだろうか?」
「哲学者マルティン・ハイデガーの『存在と時間』の議論の前提として、なぜ知性は生まれたのだろうか? なぜ、私達は死ぬのだろうか?」
「自分とは、一体何なのだろうか? 人生とは、一体何なのだろうか?」
……連想は、尽きない。思考は、堂々巡りを繰り返す。いくら考えても、答えは出ない。それでも、一つだけ分かることがある。
紛れもなく、生命は奇跡である。それも、本来ありえないほどの奇跡である。ナウシカなら、「いのちは闇の中のまたたく光だ!」と叫ぶだろう。刹那の閃光。一瞬の永遠。有限の無限。一即全。
人は、限りある時間の中で、常に何かを求めて時に苦悩し時に歓喜する。打ちひしがれることもあれば、駆け出すこともある。旅路の果てで何を得られるのか、結末は誰も知らない。人は誰でも皆、寄る辺なく彷徨い続ける魂の放浪者である。
タイトルに用いられている、ギリシャ語系の「Planet(惑星)」も、ゲルマン語系の「wanderer(放浪者)」も、共に「彷徨うもの」を意味している。そこには、星々の間を惑いゆく天体の地表を、人々が心身共に当てどなく放浪する外宇宙=内宇宙的なイメージが重ね合わされている。
なお、音楽には一部、現在も宇宙の彼方へ飛行し続けている無人探査機ボイジャーに載せた、人類を地球外知的生命体に紹介するゴールデン・レコードも用いられている。ラテン語系の「Voyager(旅人)」にも、「彷徨うもの」の含意があることを付記しておこう。

Planet [wanderer] © Rahi Rezvani
最も印象的なのは、植物を象徴する場面である。8人のダンサー達がそれぞれ膝まで地中に埋まりながら前後左右に180度身体をくねらせる特殊な演出は、一度見たら忘れられない。
カラヴァッジョの《聖マタイの召命》のように、舞台に立ち並ぶダンサー達が右外側から強烈な光に照らし出される。何度も反り返り、何度も倒れ込みながら、何度も立ち直る草木達。
驚くのは、10分強の間、それぞれ別個に動いていたダンサー達が、前方を見ないまま時々強風に吹き付けられたように順番に後方に仰け反っていくことである。つまり、ダンサー達の長時間の複雑な動きは、実際には前もってジャレのコレオグラフィにより全てタイミングを揃えて一人ずつ最初から最後まで緻密に振り付けられていることになる。
おそらく、そのような超人的な動的かつ同時並行的な空間把握は、左脳の計算ではなく右脳の視覚的イメージ処理によるものだろう。また、そもそも物語全体が、左脳的な明確な筋を持たず、右脳的な印象的なシーンとシーンの繋がりでできている。さらに、右脳は芸術的感受性と宗教的感受性を共に司どることが思い出される(なお、筆者は舞台が跳ねた後でジャレに写真集にサインして貰ったのだが、彼が左利きであることは何か関係があるだろうか)。

Planet [wanderer] © Rahi Rezvani
また、この倒れそうで倒れないダンサー達のパフォーマンスは、東日本大震災の被災地である宮城県石巻市の海岸でのワークショップが元になっているという。
どれだけ打ちのめされても何度も起き上がるような彼等の姿を見ていると、「ネガティヴ・ケイパビリティ(negative capability)」と「レジリエンス(resilience)」という言葉が思い浮かぶ。どちらも、今グリーフケアの分野で重視されている用語である。分かりやすく言うと、人間は不条理に耐える心構えが大切であり、苦難を克服する計り知れないしなやかさも持っているという考え方である。
伝統的に、日本ではそうした精神的な強さを「勁(つよ)さ」と言い表してきた。これは、中国の『後漢書』にある強風でも倒れない「勁草」という言葉に基づくもので、「勁草は疾風に知る」とは逆境の中でこそ真の強さが試されるという意味である。
ただ、そうした「勁さ」が可能になるのは、自らの意志が必要であることはもちろん、他者の支えも必要であることに注意すべきである。確かに、時に人は驚くほどの精神的回復力を示すことがある。しかし、それは決して虚空の自律ではなく、他者からの温かな愛情の供給があればこそであることを忘れてはならない。
相手に密着的に依存するのではなく、ただいつも共にあること。適度に離れながらも息の合った8人のダンサー達の姿に、筆者はそうしたメッセージを受け取った。
さらに、当然この場面には、『古事記』のいう「葦原の瑞穂の国」として大自然の恵みの豊かな日本や、哲学者ブレーズ・パスカルのいう「考える葦」として身体的には最弱でも精神的には最も偉大になりうる人間等の含意も読み取れるだろう。

Planet [wanderer] © Rahi Rezvani
ジャレは、本作に次のようなコメントを寄せている。
「《Planet [wanderer]》はこれまで世界各地で上演されてきましたが、日本の観客の皆様は、この作品のコンセプトの背景と表現形式の両方に見られる、計り知れないほど多くの深く日本的な文化的要素をすぐに認識されることでしょう。この作品は日本でこそ、他の国では成し得ないほどの共感を得ると信じています。」
確かに、コンセプトの背景である『古事記』は日本の神話である。また、ダンサー達が砂の地面に手で描く模様は、禅寺の枯山水庭園を思い起こさせる。
ただ、それら以上に筆者がより日本の文化的要素を感じるのは、能との類似である。言わば、ジャレと名和のコラボレーション舞台は「現代の能」ではないだろうか?
事実、ダンサー達が時折見せる儀式めいたスローな所作は能を連想させる。また、雅楽を電子音楽に取り込んだティム・ヘッカーの音楽も能の囃子に通じている。
より重要なのは、両者の音楽に能管(笛)が用いられていることである。能管の音色が鳴り響く度に、能は異界を垣間見せ、ジャレと名和のコラボレーション舞台も異界を幻視させる。
これに関連して、小説家三島由紀夫は『英霊の聲』(1966年)で、石笛によりトランスする降霊会を描いている。また、哲学者上山春平は、縄文遺跡から出土する石笛を能管の原型と見ている。楽器として直接の発展ではなくても、縄文時代の祭祀から今日演じられる能まで、日本人があの空気を切り裂き脳天を劈くような汽笛音を日常を超える意識変容の契機にしてきたことは確かだろう。

Planet [wanderer] © Rahi Rezvani
能の特徴は、死後の世界と縁が深いことである。現に、「夢幻能」は幽霊を主役に据えることを定式化した世界でも珍しい演劇形式である。
まず、日本には宗教学者折口信夫のいう顕幽循環的な死生観がある。『古事記』が語るように、元々日本では「顕界(生者の世界)」と「幽界(死者の世界)」は地続きである。
大自然は、奥底で幽界としての「根の国(黄泉国)」に繋がっている。本来、この根の国こそが永遠の「常世」であり真実在の世界である。
顕界と幽界は、時空を超えて重なっている。顕界から幽界は見えず音も聞こえないが、幽界からは顕界を全て見聞きしている。だから、昔の日本人は誰も見ていなくても悪いことはしてはいけないと教えられていた。
幽界は暗黒の世界であり、その雰囲気は「幽玄」と感受される。時々、何かの拍子に幽界の住人が透けて見えるのが「幽霊」である。
そもそも、人は神に魂を分け与えられて地上に降り立ったとされる。おそらく、喜怒哀楽を通じて魂を磨く修行のためだろう。
人は死ぬと、魂は幽界に帰る。帰幽した霊魂は、何度か蘇って(黄泉帰って)顕界に生まれ変わるが、それを繰り返す内にやがて祖霊に溶け込み、いずれ神々に包摂され、最終的により大きな神へと回帰していく。
その過程で、時々死者の霊魂は子孫の祭祀を通じて顕界に戻ってくる。神々や死者の霊魂が顕現することで、芸能が成立する。「盆踊り」は、その一つの典型である。
ここで注目すべきは、顕界の生者は、全てがワンネスに貫かれている真実在の「幽界」から切り離されているためにエゴを持つことである。もし顕界だけが世界の全てだとすれば、自分の利益を最大化する利己主義こそが最適解ということになる。それでは、哲学者トマス・ホッブスのいう「万人の万人に対する闘争状態」となり、個人にも集団にも不調和が生まれる。
そこで、再び人々の心に調和を回復するために、幽界の聖なる真理を認識させるのが神話であり、定期的にそれを実感させるのが祭祀や芸能である。現世の我欲を克服し、様々な悲哀を癒すためには、世界は顕界だけではなくむしろ幽界に含み込まれているという認識が必要なのであろう。

Planet [wanderer] © Rahi Rezvani
能は、そうした日本の伝統的な死生観・芸能観を濃密に反映する演劇である。石笛の音色を継承する能管は、その甲高い高周波を通じて束の間人々を幽界にトリップさせる。
それは、本作もまた同様である。非日常的な能管とシンセサイザーの音色が一つの契機となり、舞台は幽冥の度合いを増し、聖なる真理が開示され、鑑賞者の魂を癒して連帯を生む。
ここに、ジャレと名和のコラボレーション舞台が、幽界(黄泉国)を主題とする《VESSEL》から開始される必然性がある。二人のコラボレーション舞台が常に黒色を基調としているのも、このことと無縁ではないだろう。また、二人の舞台の原点が、日本における能の伝統的な中心地である京都であることも示唆的である。
さらに、二人の舞台が常にキラキラと光り輝いているのもこの幽界の印象に通じている。実際に、哲学者オルダス・ハクスリーは『知覚の扉』(1954年)で、宝石等の光り物が美しいのは天界の美を反映しているからだと洞察している。
それを体現するように、ジャレと名和のコラボレーション舞台は、常に金襴で飾られた能衣裳のように繊細に光り輝き、時にこの世のものとは思えない美しさを提示する。そうした暗がりの中で透過的に煌めく夢幻の美もまた、二人のコラボレーション舞台に一貫している。
こうした能に通じる「幽玄の美」が様々に窺えるのが、筆者が二人のコラボレーション舞台が「現代の能」であると感じる所以である。

Planet [wanderer] © Rahi Rezvani
こうした幽界を彷彿させる舞台の印象は、セノグラフィを担当する名和の力量によるところが大きい。
実際に、これらの幽玄の美は、名和の造形作品に通底する特徴でもある。さらに、2024年に名和がダンサーの田中泯とのコラボレーションで文字通り『彼岸より』の舞台美術を手掛けていることも暗示的である。
しかし、おそらく名和自身は制作時に、自覚的に能を意識している訳でも幽玄の美を意図している訳でもないだろう。もしそうした寓意的(アレゴーリッシュ)な心構えでいれば、作品は間違いなく紛い物めくはずだが、そうした不自然さが微塵も感じられないことは誰もが首肯するだろう。
むしろ、名和自身の研ぎ澄まされた美意識と共に、日本の風土に無意識に培われた死生観・芸能観が、表現者としてアクチュアルであろうと努める中で自ずから立ち現れてくるところに価値がある。そこに、人類的な普遍性も現出する。そうした象徴的(シンボーリッシュ)な芸術表現こそ、名和が敬愛するゲーテの理想でもある。
何よりもまず、名和の舞台美術は極めて美しい。その水際立った玲瓏さは、職人的な完全主義と芸術家としての心の自由な飛翔の奇跡的な融合である。
なお、YouTubeには、本作の完成までに生み出された様々な試案を記録する動画も公開されている。作品全体の印象が余りにも自然で一貫しているので、まるで一瞬で完成したように錯覚するが、当然その実現の過程では様々な創意工夫に富む試行錯誤が尽くされていることが感得される。
参考 Kohei Nawa × Damien Jalet「Planet Production Archive 」
もう一つ、能との関連で言うならば、本作はどこか沈痛でシリアスな雰囲気が能と類似している。
宗教学者鎌田東二は、室町時代に大成した能は、直前の南北朝時代の戦乱に対する鎮魂の意味合いがあったと指摘している。本作も、新型コロナ禍を始めとする近年の世界的な天災・人災に対する鎮魂の気配が窺われる。
ジャレと名和のコラボレーション三部作は、さらに2024年に続編としての第四作《Mirage [transitory]》が福岡で上演され、現在そのアップデート版の《Mirage》が世界を巡回中である。そして、名和からは現在五作目の制作も進行中であると聞いている。
夢を語るならば、二人のコラボレーション舞台を第一作から第五作まで改めて順番通りに鑑賞してみたい。筆者は、その日を心待ちにするものである。

左から、ダミアン・ジャレ氏、筆者、名和晃平氏
(舞台写真は全て作家提供)
【関連論考】
ダミアン・ジャレ×名和晃平『Planet[wanderer]』 関連記事 公開トーク ダミアン・ジャレ×名和晃平『Planet[wanderer]』をめぐって|コラム&アーカイヴ|ロームシアター京都
ダミアン・ジャレと名和晃平による舞台作品『Planet[wanderer]』がロームシアター京都で上演!2025年11月8日(土)~11月9日(日) | バイリンガル美術情報誌『ONBEAT』
ダミアン・ジャレと名和晃平のコラボ作品『Planet [wanderer]』が東京芸術劇場で日本初上演|美術手帖
「困難の中生きる」ダンスに…振付家ダミアン・ジャレ×彫刻家名和晃平、京都で11月8、9日:地域ニュース : 読売新聞
劇評「ダミアン・ジャレ+名和晃平《Mirage [transitory]》」THEATER 010(福岡県福岡市)秋丸知貴評