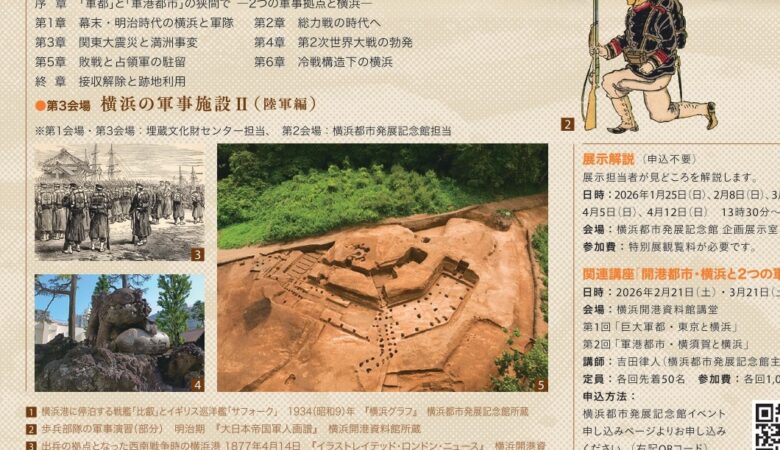八)おっ、親分、てぇへんだ、てぇへんだ
親分)おうっ、八公か、どうした、そんなに慌てくさって?
八)紙魚(しみ)がっ、とんでもねぇ紙魚が、日本のあちこちのミュージアムで見つかってるんでさぁ
親分)そいつぁ捕物だ!

ニュウハクシミ(東京文化財研究所の公式HPより)
とまぁ、こんな調子で、今回は八と親分の掛け合いを織り交ぜながら、恐ろしい紙魚の侵略について記したいと思います。
2022年、東京都や北海道、福岡県など5都道県の博物館、美術館、古文書館、図書館で初めて確認された文化財害虫・ニュウハクシミが2025年9月末時点で19都道府県にまで拡大していることが東京文化財研究所の発表によって明らかになりました。
親分)たかだか紙魚だろ?そんなにびびるこたぁねぇだろぉよ
八)あっしも最初はそう思いやした。でも、東京文化財研究所のHPを見たら、もうこれが恐ろしいのなんのって
親分)どう恐ろしいんだ、八、言ってみな
八)へい、研究所やら新聞記事やらの受け売りですが、こんな感じでさぁ
ニュウハクシミは1900年代初頭にスリランカで発見された外来種の昆虫。成虫は約1センチにまで成長します。紙の表面をかじり取るように食べ、屏風、掛け軸、古文書などを毀損してしまう可能性があります(現段階では被害は未確認)。繁殖力が非常に強く、一度、定着してしまうと駆除が困難になります。害虫の防除方法の調査研究を行う東京文化財研究所は、早期の発見と対応を呼びかけています。
親分)大事な、大事な文化財を派手に食い散らかす恐れがあるんなら、こりゃあ、見過ごすわけにはいかねーな
八)へい、その通りでさぁ
親分)しかも、何だい、繁殖力も強いってーな?
八)へい、またまた受け売りですが、公式発表などにこんなことが書いてありやした
生態が分かっていなかったため、東京文化財研究所が調査したところ、ニュウハクシミは交尾せずにメスが産卵する「単為生殖」であることがわかりました。単独で子どもを作れるので、1匹残らず駆除しなければ増え続けます。1匹が3年後には約2万匹になるといい、交尾で増殖する従来のシミ科の昆虫に比べ、繁殖力は格段に強いのです。
親分)ものすげぇー繁殖力だな
八)まるで、ねずみ講のような増え方をするみてぇーですね
親分)こりゃ、どうしたら退治できるんだい?
八)研究所はこう言ってやした
10度以下または湿度43%以下で死滅することも確認できました。しかし、文化財や書籍を保護するため適度な温湿度に保たれている博物館や図書館などは、ニュウハクシミが生息しやすいのです。
親分)なるほど、寒さと低湿度に弱いんだな。それにしてもよぉ、最初は5都道県でしか確認できていなかったのに…
八)3年か4年そこらで19都道府県にまで広がったわけでさぁ
親分)どうやって、あいつら増えていったんでい?
八)どうも、資料や梱包資材などに付着して移動したらしいですよ、いやはや恐ろしいもんだなぁ
親分)対応策は何か、ねぇーのかい
八)へい、繁殖が起きやすい段ボールじゃなく、スチール製やプラスチック製ケースで資料を保管するのがいいみたいでさぁ
親分)まだ、ほかにも対応策はねぇーのか?
八)壁際への殺虫剤散布やこまめな清掃、毒餌をまくのも有効みたいでさぁーね。研究所では、ニュウハクシミが確認された博物館などに毒餌キットを配布し始めやした。全国に広まっちまう前に何とか食い止めたいもんです
親分)そりゃそうだ。早く駆除しねぇーと、江戸っ子が好きな黄表紙やら浮世絵やら、大昔から伝わってきた大切な古文書なんかがみんなニュウハクシミにやられっちまうじゃねぇか
八)へい、親分、その通りでさぁ
親分)よし、八、こりゃあこうしちゃあいられねぇぞ、全国のニュウハクシミを一匹残らず、とっ捕まえねーことにゃ、枕を高くして眠れねぇ
八)へい、(腕まくりしながら)よし来た…
八と親分は鼻息も荒く意気込みながら、全国行脚の旅に出かけてしまいましたので、ここから先の進行は、筆者が引きとります。
ニュウハクシミの来襲をニュースで知った時、最初に筆者の頭に浮かんだのが、アメリカの小説家ウィリアム・S・バロウズ(1914~1997年)の名言でした。
言語は宇宙から来たウイルスである
Language is a virus from outer space
紙魚はBookwormですから、“Bookworm is a virus from outer space”と思ったのです。紙魚の体が宇宙船のような形状をしていることも手伝って、宇宙から来た存在に思えたのです。また、筆者は残念ながら、まだ一度も遭遇していませんが、ある種の宇宙人はニュウハクシミのような形状をしているような気もしたのです。まぁ、これはあくまでも筆者の妄想に過ぎませんが。
宇宙人たちが、人類の貴重な文化遺産を食い尽くし、知を後世に継承させることを不可能にさせる・・・その結果、知性が衰えた人類をたやすく制圧する。そんな物語を脳裏に浮かべて、心底ぞっとしていたわけです。
そして、バロウズを思い出せば、連想は前衛芸術家ローリー・アンダーソン(1947年生まれ)があの名言を元にして創造した超有名なステージ、Language Is A Virusにまで広がります。いやー、アンダーソンの佇まい、かっこいいですね、しかし。
一冊の本や一巻の古文書を人体に例えるなら、ニュウハクシミはどのような侵入経路で人体に入ってくるでしょうか?
もちろん、答えは簡単です。鼻の穴、耳の穴、口、目、肛門、生殖器にうがたれた穴…これらのうちのどれかですよね。どこから入られても嫌ですよね。筆者が一番恐れるのは、ニュウハクシミが柔らかい眼球をがりがり食べながら、奥へ奥へと侵攻し、脳内に到達するや否や、脳みそもぼりぼり貪られてしまうパターンですね。これをやられたら、もうたまりません。肛門と生殖器を除く、すべての「穴」はいわば脳のすぐ近くの器官ばかりです。知性はぼろぼろに侵食されてしまうわけです。
繰り返します。“肉体(紙)”をばりばりとかじられ、“脳(活字)”も根こそぎ食べられてしまうんですよ。ニュウハクシミによる地球侵略は決して軽微な被害ではないことがお分かりになるのではないでしょうか。レイ・ブラッドベリ(1920~2012年)の代表作「華氏451度」では本が焼却される悪夢のような社会が描写されました。ニュウハクシミがバリバリと本を食べる姿は、めらめらと炎が本を焼き尽くす様とほぼ一緒の意味合いを持っているのです。
たかがニュウハクシミ、されどニュウハクシミです。現代の焚書坑儒の担い手は、たかだか1センチの小さな虫なのです。親分や八公が大慌てで捕物に出かけるのも当たり前なのです。ミュージアムに関係する方々、図書館の方、大学、高校の方、皆さん、本当に知性への侵略者にはお気をつけてください。(2025年11月21日18時42分脱稿)