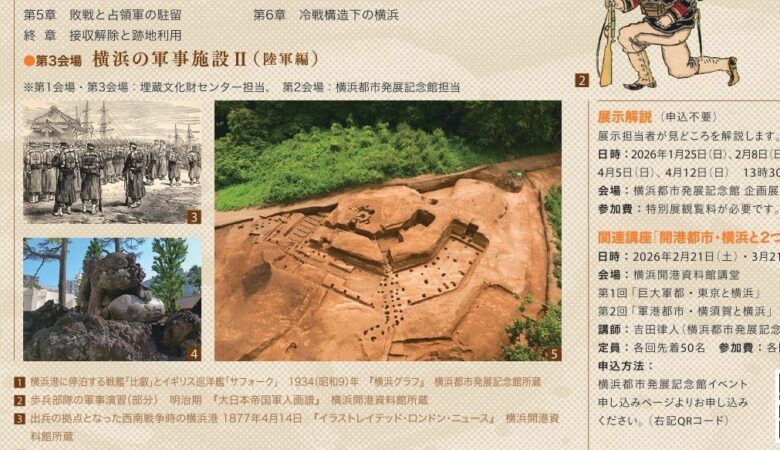「人類よ、撮影本能を滅却せよ! 市原尚士評」を前回、書いたときに、重要なことを書き忘れていました。そもそも、なぜ筆者が港区立郷土歴史館を訪問したかといいますと、「暮らしの中のお菓子展」を見に行ったのでした。港区域の菓子店の移り変わりを追いかけた部分が面白かったですね。港区って、実は“お菓子区”と呼べるくらい、お菓子とのかかわりの深いエリアなんですよね。会場内の撮影は禁止だったので、本稿に写真は掲載しませんが、お菓子好きの方はぜひ鑑賞してみてください。
この歴史館4階にあるギャラリーでは「食べられないお菓子展~食品サンプルでめぐるスイーツの世界~」が関連展示として併催されており、こちらも非常に面白かったです。日本独自の造形文化であるお菓子・デザートの食品サンプルの豊穣な世界観をコンパクトな会場内にぎっしり詰め込んでいます。
-scaled.jpg)
Nompleが作成した「クリームソーダ」
大和サンプル製作所、Nomple(世古紀子)の手になる全23点の作品が一堂に集まっているわけですが、あまりのリアルさに驚かされました。どう見ても、これは本物です。とてもおいしそうです。クリームソーダ(Nomple作)は、あの激甘、かつ色鮮やかで強い炭酸を感じさせる液体が見事に表現されております。小さな頃、親と一緒にデパートにお出かけをして、ちょっとお高めの「●●パーラー」のようなお店で休憩したときに、よく飲みましたね。大人になってからは、ストレートの紅茶やコーヒーばかりを飲むようになってしまいましたが、今、クリームソーダを飲んだら、どんな感想を持つのでしょうか?
.jpg)
大和サンプル製作所が作成した「パンケーキ」
パンケーキは大和サンプル製作所の作品です。ケーキが7段も並び、てっぺんにはアイスクリームがどかんと鎮座しています。ストロベリーソースの赤とミントの緑の葉っぱが目を楽しませてくれます。アイスに突き刺さったスプーンは、視覚的な遊びとしての仕掛けでしょうね。喫茶店やパーラーでスプーンを突き刺したら、親から「お行儀が悪いから、そんなことするのやめなさい」と叱られるのは間違いありません。あくまでも、遊び心でスプーンを突き刺していると、読者の皆様もご理解よろしくお願い申し上げます。
このパンケーキにのっているのは、アイスですが、筆者は何と言っても正方形のバター&ハチミツ派ですね。ケーキの上方からたっぷりのハチミツを注ぐと、タラーリ、タラーリとハチミツが四方に広がります。ケーキの縁まで到達すると、90度折れ曲がって、今度は下方を目指して垂れ落ちていくわけです。皿までハチミツが到達してしまうとなぜか面白みがなくなります。やはり、横方向に進んでいたのが、90度折れ曲がった直後を見るのが一番ワクワクするのですね。バターは溶け始めが一番、興趣を覚えます。

大和サンプル製作所が作成した「ソフトクリーム」
続いて、ソフトクリーム。こちらも大和サンプル製作所の作品です。メロン、サクランボ、ハート形のクッキーなどが頂上に乗っており、こちらも賑やかです。これ、上から順に食べるのはいかにも芸がないですよね。時折、下の方にある層をほじくり返して食べ、また上方の層に戻るという往還運動を繰り返しているうちに、どんどんアイスやコーンフレークの層がぐちゃぐちゃに混ざっていき、食べやすくなっていくわけです。
展示パネルに面白いことが書いてありました。大和サンプル製作所のコメントです。
以前、蝋細工で作製しておりましたが、破損・熱に弱いというデメリットがあり、現在は樹脂で食品サンプルを作製します。今回のスイーツも樹脂で作製しておりますが本物よりも少し派手目に仕上げています。食品サンプルは従来、店舗へお客様を誘導する手段でございましたが、現在はインテリア・アクセサリーとしても注目を浴びています。
筆者はてっきり、サンプルは蝋細工だと思い込んでいましたが、樹脂に代わっていたのですね。また、本物よりも少し派手という点も非常に興味深かったです。少しオーバーなくらいの色彩や質感にしないと、人の五感に訴えないんですね。つまり、本物と同じ色彩だと地味に見えるわけです。
芸術作品を制作する方にも、このサンプルは参考になるかもしれません。つまり、作り手として考える理想の色彩と観客側が考える理想の色彩とはいささか乖離している可能性があると認識した上で制作する必要性があるかもしれないということです。
狭い自宅で制作している時の色彩では、団体展の会場となる巨大な美術館内では、いささか地味に見えるかもしれないわけです。作品を発表するメーンの場所が、どのような光源(光線)を持っているのかは、あらかじめ考えに入れておかないと、せっかくの力作が「地味な作品」と受け止められてしまう恐れもあるわけですから、ご自分としては少し派手目な色遣いにしてみることを試しても面白いかもしれません。
同じく、Nompleが、展示パネルで「(来場者で)自分でも作ってみたいと思った方へのアドバイス」を述べていました。
決まった材料やルールはなく、工夫次第で自由に表現できます。私自身、鰹節を表現する際には、かまぼこの板を彫刻刀で削ることから始めました。100年以上の歴史を持つ食品サンプルの世界に、ぜひ身近な“食べられない材料”を使って挑戦してみてください。本物そっくりの一皿を作る体験は、きっと新しい発見につながります。
なるほど、なるほど。要するに、自由気ままに作っていいんですね、食品サンプルって。作り方に「~流」とか「~派」とかはなくて、自身の発想を生かして製作すれば、それが正解という世界なんですね。素晴らしい!本物に似ているのも重要ですが、筆者が重視したいのは、「おいしさ」です。いかに、おいしそうな雰囲気を醸すことができるかどうかが肝心です。会場内に置かれたサンプルは、すべて合格点です。思わず手に取ってその場で食べたくなるような、リアルな質感と味覚が漂っていました。
ベンヤミンの「技術的複製可能性の時代の芸術作品」のある一節が自然と思い出されました。河出文庫(「ベンヤミン メディア・芸術論集」山口裕之編訳)から。
いくつも複製を作り出すことによって、複製技術は、複製されるものを一回限りのものとして出現させるのではなく、大量に出現させることになる。また、複製技術により複製がどのような状況にある受容者にも対応できるものとなることによって、複製技術は複製されるものをアクチュアルなものにする。
ベンヤミンの言に従えば、複製(食品サンプル)は、オリジナル(食品そのもの)が持つ「いま、ここ」にしか存在しない真正性の価値をより高めてくれるということになります。サンプルは元の食品の価値を落とすものではなく、むしろ、元の食品の価値をよりアクチュアルに高めてくれるというわけです。つまり、食品にとってもサンプルにとってもメリットがあるわけです。
たかが食品サンプル、どころではない。されど食品サンプルなのですね、やっぱり。食品サンプルも、もはや店舗内への誘導役から、店舗など関係なしに単体で視覚的(味覚的)に鑑賞・堪能するものへと変容を遂げました。つまり、ほぼ「アート作品化」しているということです。どんどん作家さんが登場し、公募展などでも食品サンプルが並んだら面白いかもしれません。出品する際のジャンルは、「彫刻」なんでしょうかね…悩むところではあります。
作り手、鑑賞者が共にハッピーな気分になれる“食品サンプル芸術の世界”には、まだまだ大きな伸びしろを感じました。

食品の容器や包装についているシール類を再利用している
閑話休題。先日、銀色のアタッシュケースに大量のステッカーを貼っている方を発見しました。ステッカー好きの筆者が「どれどれ、どんなステッカーを貼ってっかなー?」と見たところ、仰天しました。
スーパーで売っているハムやプリンやお茶などの容器・包装についているシールを丁寧に剥がした上で、それを再利用してアタッシュケースにべたべた貼っているのです。筆者も長年、ステッカー観察をしていますが、食品のシールをステッカー代わりに貼付するという作例は初めて発見しました。
中高年の男性でしたが、彼はなぜ、食品のシールを大量に貼るのでしょうかね? よほどインタビュー取材でもしたかったのですが、赤の他人にアポもなしで突然、根掘り葉掘り聞くこともできず、諦めました。まぁ、このような食品シールの再利用も、徹底的に貫き通せば、一種の自己表現、アートと言えなくもない。とはいえ、初めての事案・事例を目の当たりにして、かなり動揺しました。人間って本当に面白い生き物だな、としみじみ感じ入った筆者でした。(2025年10月29日20時01分脱稿)