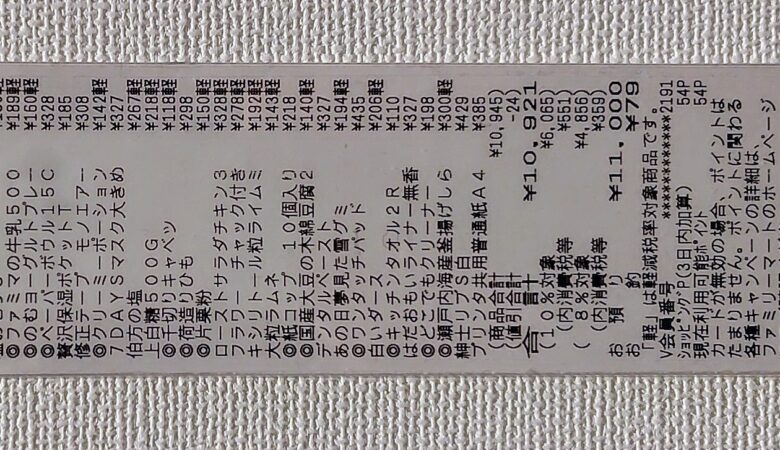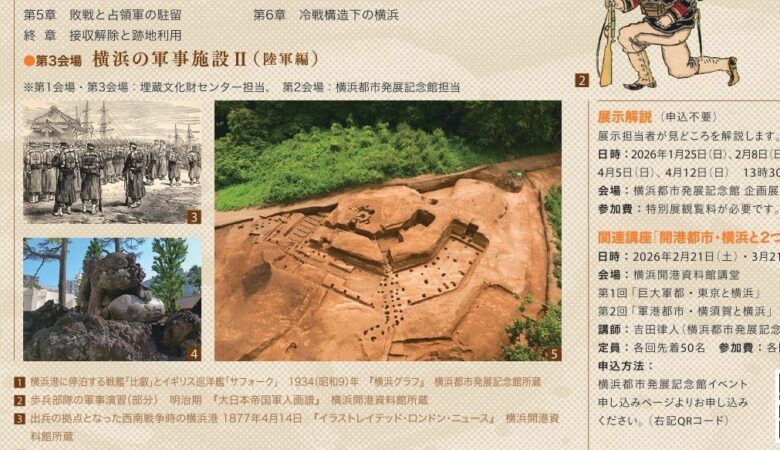群馬県内で面白いものを見ました。
今、「面白い」、と書きましたが、人によっては全く面白くないかもしれません。もし、そうお感じになったら申し訳ございません。
何の変哲もない、工事の途中段階の風景です。

群馬県内で出合った盛り土のピラミッド
手前に盛り土のピラミッドがあります。後ろに重機の一部分が見えていますね。この重機で土を掘って、移動させたのでしょうね。ピラミッドを観察すると木の根っこがあちこち飛び出していたり、大きな丸い石ころがピラミッド下部に横たわっていたりするのが目に入ってきます。そもそもですが、上方から土砂を落としていくという行為を繰り返していると、なぜピラミッドのような形が自然と出来上がっていくのか? その理屈が分かりません。中学か高校の頃、学校で習ったような気もしますが、完全に忘却の彼方なので、どうもすみません。

ピラミッドに近づいて見上げた時に見える頂上
土砂のピラミッドに近づいて、上方を見上げると、てっぺんがきちんと認識できます。これは、間違いなく、このピラミッドの頂点と言っていいでしょう。さて、先ほど皆さんがご覧になった遠方から俯瞰したピラミッドのてっぺんをもう一度ご覧ください。何か違和感を覚えませんか?
このピラミッドの写真を思い切り、トリミングして頂上部分だけを拡大してお見せしましょうね(画質が低くて申し訳ないです)。さぁ、気が付きましたか。頂上だと思っていた部分、実は建売住宅の三角屋根の一部分だったのです。もちろん、私が意図して撮影したわけではなく、偶然の産物です。写真を撮影した後、若干の違和感を覚え、拡大して確認したら、建売住宅の屋根が偶然、写り込んでいたのに気が付いた次第です。

本稿1枚目の写真をアップにしてみると、盛り土の頂上だと思っていた部分は建売住宅の三角屋根だったことが分かる
しかもですね、このピラミッドから、建売住宅の屋根までの距離が、地図上で計測したところ、約150メートルも離れていたのです。写真上は、土砂のてっぺんに見える三角屋根、実は150メートルも先の物体だったというわけです。筆者は、この事実を確認して「案外、こういったことが日常的に起きているのではないか?」と考えたのです。
分かりやすいのが、月や太陽です。手前に高層建築があり、その頂上に月がちょこんと乗っかっているような写真を見た時、人間は「建物の上にお月さんが座っている」と感じ、思わず微笑みます。本当は月と建物との間には長い、長い距離があることを知っていながら、あえて錯覚を楽しんでいるわけです。
しかしですね、本当は、偶然の産物で1キロ先の文物が手前の近景と重なっているだけなのに、ぱっと見た時には同じ場所にあるもののように見えるケースもしばしばあるような気がしたのです。
さて、ここからが重要です。誤った認識に基づいた「偽の風景」は、それを見た人にとっては「真実の風景」なわけです。その人にとっては、もしかしたら永遠に「真実の風景」であり続けるかもしれないということです。その場合、その錯覚している人に「あなたの見た風景は偽の風景ですよ」と指摘できる他者が存在しうるのか否か、という点に筆者は非常に興味を持ってしまうのです。
そもそも誰かが認識した、頭の中の風景は、容易に他者と共有できるものでもありません。ですから、あなたの頭の中の視覚的認識について他者があれこれ口をさしはさむのは難しいです。この論議って、人それぞれ「赤」や「青」といった色を思い浮かべた時に、全然違う色味をそれぞれ頭の中に思い浮かべているという話と共通している点があって、面白いのですね。
工事現場のピラミッドの話を美術館の壁にかかった一枚の絵に変えて、考えてみましょう。この絵の中に描かれた風景や人物や器物などの位置関係、重さなどを人間は一瞬で理解したつもりになりますが、本当にそうなのでしょうか?
実際は、絵の中でくっ付いて見えるものが、本当は1キロメートル離れているのかもしれないのですよ。よーく、絵の隅々まで観察して、見ることによって、錯覚に気が付くこともあるかもしれませんが、なかなか難しそうです。
また、見る側の教養、知識量の深さによっても、絵を鑑賞する際の見え方がかなり変わってきそうな気もします。一枚の絵を見る、と簡単に言っても、鑑賞する方によって、その見え方がまったく異なっている可能性があるわけです。まぁ、これは、美術館やギャラリーをたくさん回っている筆者が一番分かっています。ちょっと哲学的に聞こえたらごめんなさい。「人に美術作品を見ることはできない」と思うのです。いえ、美術作品だけでなく、道も木も空も海も火も車も何も見えていないと思うのです。
人の目と言うのは、恐ろしいほど常にキョロキョロとしており、動き回ります。ぴたりと視線を止めて、一点を凝視することなど、およそ目には不可能です。視線を飛び回らせることによって、この世界の奥行きや距離をどうにかこうにか測定しようと必死にあがいているーーそれが視覚の本質のような気がしてならない。見ているようでいて何も見ていないのです。ただ、キョロキョロと眼球(視線)を世界に向けて彷徨わせているだけなのです。
様々な人が引用した、画家ポール・ゴーギャン(1848~1903年)の名言を改めてご紹介します。
I shut my eyes in order to see.
いかがでしょうか。ゴーギャンの言っていること、1000%正しいと思いませんか?
見るために、人は目を閉じなければいけない、のです。群馬の盛り土を前にしたら、筆者も目を閉じなければいけなかったのです。建売住宅の三角屋根を盛り土が生み出したピラミッドの頂上としばしば錯誤しているであろう筆者は、キョロキョロ動き回る目を閉じ、強制的に闇を生み出す必要性があったというわけです。
絵を制作している皆さん。絵を鑑賞している皆さん。本気で制作や鑑賞がしたかったら、時には目をつぶる習慣を取り入れてみませんか。心眼、つまり心の眼でしか見えてこない世界が間違いなく存在していると筆者は確信しています。(2026年11月19日19時02分脱稿)