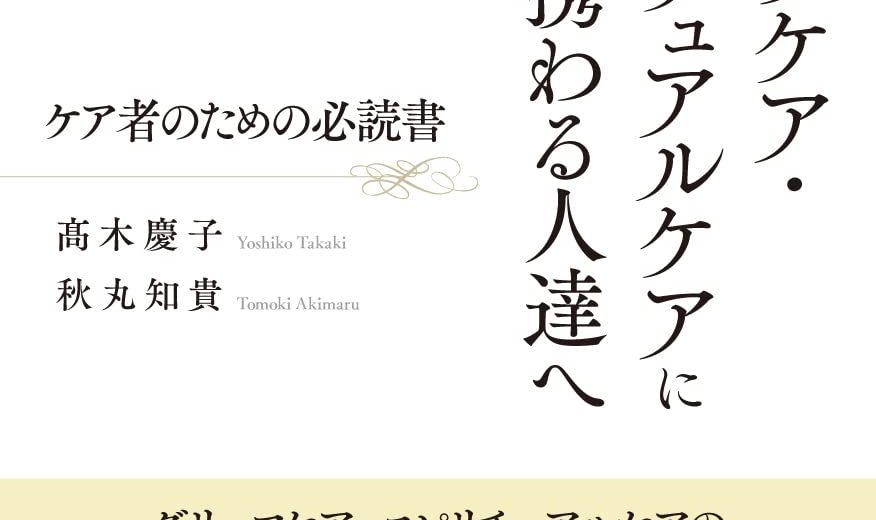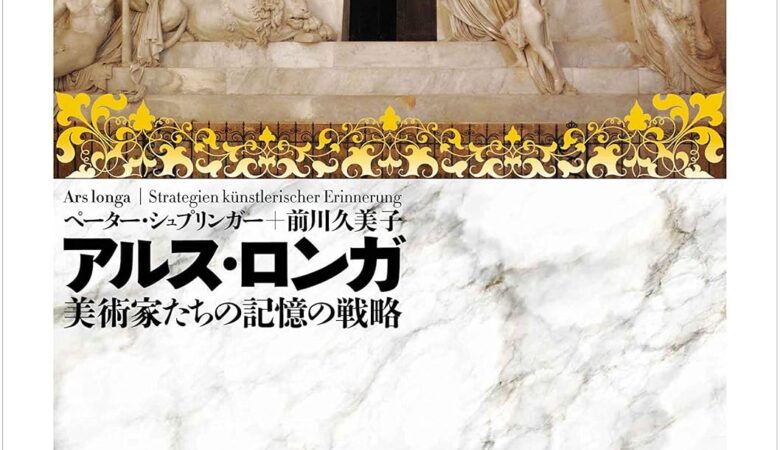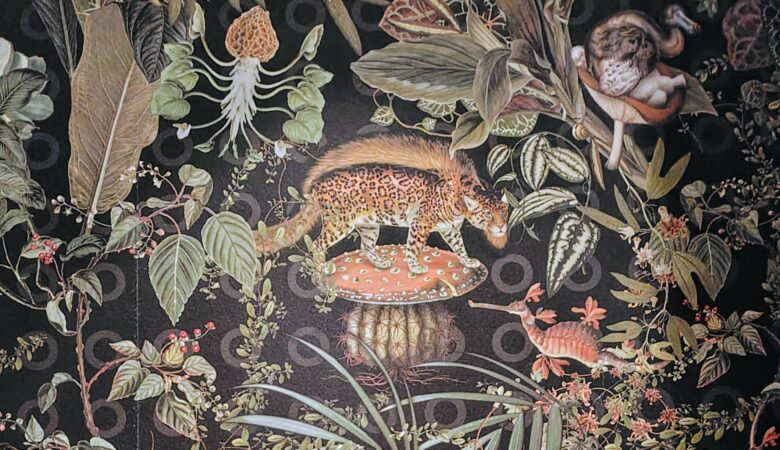本書の最大の特色は、グリーフケア・スピリチュアルケアの先駆者であり第一人者である、髙木慶子先生のケアマインドとケアメソッドを初めて詳細かつ具体的に解説している点である。
人の悲嘆は、多種多様である。その上、悲しみで半狂乱になったり、終末期で絶望したりしている人のケアは、本当にとても困難である。
それにもかかわらず、実際に36年以上、髙木先生は臨床現場で無数の人々の悲嘆を癒やし続けてきた。髙木先生は、一体どのような心構えで、どのような実践を行っているのか。ケアにマニュアルはないとしても、どのようなケースでも一貫するマインドがあり、基本となるメソッドがあるのではないか。髙木先生は特別なのか、それともそれは私達でも共通して実践できるのか。
髙木先生に、ケアの知識と経験をもっとたくさん学びたい。そして、それを自らも臨床現場で実践していきたい。髙木先生が創立所長である上智大学グリーフケア研究所では、日々受講生からそうした要望が数多く上がっていた。
そこで、本書は、2012年に髙木先生が編著者、上智大学グリーフケア研究所が制作協力として勁草書房より出版した『グリーフケア入門』の10年後の続編として、2022年に中級者向けのケアの臨床現場で役立つテキストとして構想された。また、最終的に、ケアの専門家のためだけではなく、これからは誰もがケア者になる時代であるとして、広く一般書として2023年にクリエイツかもがわより出版された。
髙木先生は、まえがきで、「私は全てのケアの基礎は『スピリチュアルケア』であると考えております」として次のように核心に触れている。
スピリチュアルケアは、「魂の苦痛」すなわち「スピリチュアルペイン」を癒すものです。
このスピリチュアルペインについては、まだ多くの人達が「終末期の死への恐怖」とだけ捉えています。確かに、終末期患者が死への恐怖としてのスピリチュアルペインに強く苦しむのは事実です。しかし、私の36年間の臨床経験から明言すれば、スピリチュアルペインは、決して「終末期」に限られず、「死への恐怖」にも限定されません。
実際に、人は誰でも、幼い時から様々なスピリチュアルペインを感じています。なぜなら、スピリチュアルペインは「スピリチュアリティ」に基づく苦痛であり、そのスピリチュアリティは、誰もが物心付いた時から普遍的かつ根源的に持っている、人智を超えた大いなるもの(サムシング・グレート)への信仰心であり、その慈悲と慈愛を感じ取る能力だからです。
これを要約すれば、全てのケアの基礎は「人智を超えた大いなるもの(サムシング・グレート)への信仰心」ということになるだろう。
この観点から、まず髙木先生は、第1章から第4章にかけて、グリーフケアを緻密に説明していく。
第1章 グリーフケアとは何か
1 誰もが悲嘆(グリーフ)を抱えて生きている
2 カウンセリングとグリーフケアの違い
3 なぜ今グリーフケアが必要なのか
4 悲嘆は病気ではない
第2章 悲嘆について
1 悲嘆は画一的ではない
2 悲嘆は特別な問題ではない
3 悲嘆の諸相
4 悲嘆の過程
5 悲嘆感情の例
6 病的な悲嘆の事例
7 ターミナルケアの事例
第3章 子供の悲嘆について
1 子供の悲嘆の原因となるもの
2 子供にとっての悲嘆とは
3 子供へのグリーフケア
第4章 公認されない悲嘆と曖昧な悲嘆について
1 公認されない悲嘆とは何か
2 曖昧な悲嘆とは何か
3 悲嘆を生き抜く力
次に、髙木先生は、第5章から第6章にかけて、より根源的なスピリチュアルケアを綿密に解説していく。
第5章 スピリチュアルケアとは何か
1 スピリチュアルケアとは何か
2 日本スピリチュアルケア学会の創設
3 スピリチュアルケアの諸相
第6章 ケアとスピリチュアリティ
1 ケア者のスピリチュアリティ
2 悲嘆者のスピリチュアリティ
3 髙木慶子の独白
また、続く対談は、筆者が対談相手となり、前章までの髙木先生の説明をさらに深く掘り下げるものである。
第7章 グリーフケア・スピリチュアルケアを巡る対談
1 ケアにおけるチームワークの重要性
2 ケアにおける信仰心の重要性
3 本書の内容についての質問
4 「喪の仕事」と「絆の継続」
5 ケアにおける芸術の重要性
なお、筆者は、髙木先生の下で、上智大学グリーフケア研究所において、2017年から7年間非常勤講師を務め、2020年から3年間特別研究員として勤務した。専門は、ケアとアートである。
筆者が執筆担当した、「第8章 ジークムント・フロイトの『喪の仕事』概念について」では、フロイトの「喪の仕事」概念について、喪失した愛着対象は「忘れるべき」と「忘れないべき」の正反対の解釈がなされている問題をドイツ語原著に即して整理し、後者が現在のケアの主流である「絆の継続」理論に繋がっていることを指摘した。
そして、「第9章 心理的葛藤における知的解決と美的解決」では、苦悩の理性的言語化がケアに有効であるのは古今東西普遍的であるとしても、古来日本では感性的詩歌化による心的な緊張緩和を重視してきた文化的伝統があることを分析し、現代の臨床現場への有効性を提言した。
個人的には、本書の最要点は、「第7章 グリーフケア・スピリチュアルケアを巡る対談」の「2 ケアにおける信仰心の重要性」である。ぜひ、グリーフケア・スピリチュアルケアに携わる人達や関心を持つ人達全員にご一読いただければ心より幸いである。
※初出:日本スピリチュアルケア学会公式ウェブサイト『コラム・読み物・声』「セルフ書評 『グリーフケア・スピリチュアルケアに携わる人達へ——ケア者のための必読書』」
【関連論考】