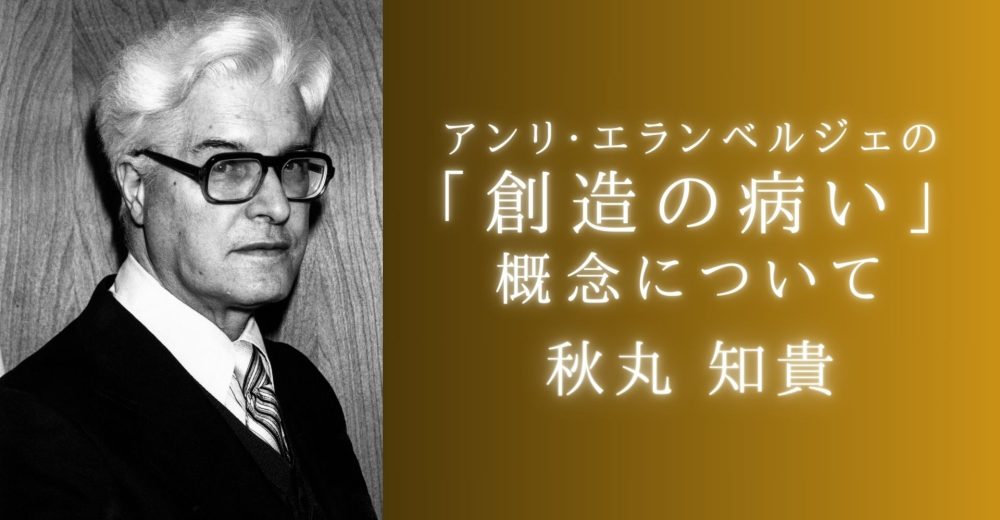エドヴァルト・ムンク《太陽》1909年

カール・グスタフ・ユング『赤の書』より
はじめに
精神医学者アンリ・エランベルジェ(Henri Frédéric Ellenberger: 1905-1993)は「『創造の病い』という概念」(1964年)で[i]、「神経症あるいは心身症の見掛けの背後に時々創造過程が隠れて存在するのではないか[ii]」と指摘した。また、そうした「創造の病い(maladie créatrice/creative illness)は確かに様々な分野に実在し、宗教、文学、哲学の歴史において一定の役割を演じてきたように思われる[iii]」と問題提起した。
本稿は、この「創造の病い」概念についてその思想内容を詳細に分析し、芸術上の創造性の開発はもちろん、そこで得られた知見の一般生活への適用可能性、特にグリーフケアにおける臨床的活用性を模索する。
1 「創造の病い」の先行概念
エランベルジェは、「創造の病い」概念の萌芽を二つ挙げている。一つは18世紀末のドイツ・ロマン派の作家ノヴァーリス(Novalis: 1772-1801)の「崇高なヒポコンドリア(erhabene Hypochondrie)」であり、もう一つは20世紀の精神医学者ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカー(Viktor von Weizsäcker: 1886-1957)の「ロゴファニー(Logophanie)」である。
まず、ノヴァーリスの「崇高なヒポコンドリア(気鬱症)」について見てみよう。この語は、1797年の「ヘムステルホイス・カント研究」と呼ばれる断章の一つに出てくる。
ヒポコンドリアは、とても奇妙な病いである。卑小なヒポコンドリアと崇高なヒポコンドリアが存在する。崇高なヒポコンドリアを介して、人は魂に至ろうと努めねばならない[iv]。
ここで、ノヴァーリスは「崇高なヒポコンドリア」を「卑小なヒポコンドリア」と対比し、「崇高なヒポコンドリア」に「魂」へ至る可能性を見ている。つまり、単に無益で病的なヒポコンドリアとは別に、ある意味で人の内面に有益で健全なヒポコンドリアがあるとするのである。
注目すべきは、ノヴァーリスの個人歴上、この断章が書かれたと推定される1797年秋の約半年前の3月19日に婚約者ゾフィー・フォン・キューンが病死している事実である。ゾフィーはノヴァーリスとの婚約後まもなく結核性の重病に罹り、そのまま回復せずに亡くなった。ノヴァーリスの落胆は深く、ゾフィーが亡くなる5日前の3月14日付のフリードリヒ・シュレーゲル宛書簡では次のように絶望している。
ゾフィーはあと数日しか生きられないという厳然とした確信を抱いて、僕はチューリンゲンから戻ってきました。泣くことができれば良いのですが、僕は呆然とし、虚ろな不安に包まれ、全身が麻痺しています。僕の中にあるのは、終わりのない絶望です。過去、現在、未来の全てが僕に催させる吐き気は、言い表すことができません。ただ稀に数時間、仕事で気を紛らせられるだけです。頭は雑然としており、もう何も見つけられません。彼女と結婚するという信念は、僕にとって不可欠になっていました――僕自身気付かぬ内に、どれほど彼女が僕の安らぎ、僕の活動、僕の全生活の礎石になっていたか今更ながら実感しています。人生への倦厭は甚だしく――際限がありません。僕は学問が補ってくれることを望みましたが――そこでも全てが死に、荒み、何も聞こえず、何も動きません[v]。
さらに不幸は続き、ゾフィーが亡くなった約1月後の4月14日には弟のエラスムスも病没している。その4日後の4月18日から書き始められたノヴァーリスの日記では、日付と共にゾフィーの死から数えて何日目かが記され、ゾフィーやエラスムスの死に関わる言及が数多く見られる。そして、ゾフィーの後を追って自殺することを仄めかすような「決心」や「計画」といった記述さえ散見する。いずれにしても、ノヴァーリスがこの時期に大きな精神的苦悩を抱えていたことは確かである。
例えば、ノヴァーリスは5月4日の日記で次にように書いている。
今朝、ゾフィーを生き生きと思った――決心が少し鈍った。〔…〕食後、ツェトヴィッツと大分話した。その後、二階に上がるまで一般的な会話。今、僕は冷静であると共にあまりにも日常生活の雰囲気に染まり過ぎていると思える。社交は、もう僕のためにならない。より高次の永続する内省とその雰囲気だけを目指そう。ああ、僕は僅かしか高みに留まれない[vi]!
また、ノヴァーリスは5月10日の日記で次のように記している。
ゾフィーを生き生きと思い出した――それから僕はもう少し仕事をして、散歩に出かけ、花を摘んで彼女の墓に行った。〔…〕気分はとても良く、僕は冷静だったが、それでも泣いてしまった。〔…〕夕食後、僕の心は再びとても不安定になり――僕はその場で激しく泣いた。〔…〕朝は決心がとても遠かったが――夜には一層近くなった[vii]。
ところが、ここで興味深いことは、その約1週間後の5月18日に、ノヴァーリスがゾフィーの墓前で死後の霊魂の存続を確信するような不思議な体験をしていることである。一般に「ゾフィー体験」として知られるその神秘体験について、ノヴァーリスは同日の日記で次のように記述している。
夕方、ゾフィーの所へ行った。僕はそこで言葉にならない歓喜に包まれた――閃く至高の数瞬――僕は眼前の墓を塵のように吹き飛ばした――数世紀がまるで数瞬のようだった――彼女が傍にいるのがはっきりと感じられた――僕は彼女がいつでも姿を現すものと思った[viii]。
よく知られているように、ノヴァーリスがこの経験を詩に書き表したのが『夜の讃歌』(1800年)の第三歌である。
かつて、苦い涙に暮れ、希望も苦痛に消えた時に、私は自分の人生そのものだった恋人が狭い暗がりの中に埋葬されている乾いた墓丘で――孤独に、誰よりも孤独に、言い知れぬ不安に苛まれ――無力に、惨めな気持ちで佇んでいた。救いを求めて見回し、進むことも退くこともできず、消え去った生命に限りなき憧憬を抱いていると、その時だ。青き彼方から――懐かしい至福の高みから、光が黄昏に差し込み、一瞬にして臍の緒――煌く足枷――を断ち切り、世俗の栄誉と私の悲哀を洗い流した。それと共に、憂鬱は新しい深遠な世界に拭い去られた――夜の霊験よ、天の微睡よ、私にもたらされたのはあなただった。周囲はそっと浮き上がり――その上に解放され新生した私の霊が漂っていた。墓丘は塵の雲となり、その雲を透かして私は聖化された恋人の顔を見た――彼女の目には永遠が宿っていた――私は彼女の手を握り、涙は輝く不断の絆となった。数千年が雷嵐のように彼方へ飛び去った――私は恋人の首元に縋り付き、新しい生命に感涙した。あれは、最初にして唯一の夢だった。以来、私は夜空とその光である恋人に揺るぎなき永遠の信を抱いている[ix]。
このように、ノヴァーリスは、婚約者ゾフィーと弟エラスムスという二人の愛する身内の死を相次いで経験し、深刻な精神的危機を経て、「ゾフィー体験」による霊魂の不滅という彼自身の普遍的真理に至っている。少なくとも、ノヴァーリスが婚約者との死別により世俗的自我を超える超俗的愛を深める経験をしたことは間違いない。
このことから、ノヴァーリスの言う「崇高なヒポコンドリア」とは、彼自身が実体験したであろう、人に惰性的な日常意識を脱して内省を深めさせ、人生の意味や善性の探求へと向かわせるような抑鬱状態を指すと解釈できる。「多分、病気は私達の内省と行動の最も興味深い刺激であり素材である。そこから――私が思うには特に知的分野において――道徳、宗教、さらには神のみぞ知る神秘の領域において、確かに無限の果実が収穫されうる[x]」という別の断章も、この文脈で理解できる。
次に、ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカーの「ロゴファニー」について見てみよう。エランベルジェによれば、19世紀の実証主義的医学においては、病気の原因はあくまでも生理的なものであり、病気は身体に科学的方法を施して予防あるいは治癒するものであった。20世紀に心身医学が登場して身体疾患の一部が心因性である可能性が認められても、それはまだ例外的な扱いであった。これに対し、心身医学の考えを推し進めつつ逆転させて、「もし間違った方向に導かれた感情や観念が病いに変容しうるならば、病いが観念に変容して消えることもありうるのではないだろうか?[xi]」と洞察したのが、フォン・ヴァイツゼッカーの「ロゴファニー」概念である。
フォン・ヴァイツゼッカーによれば、感情的なものを思考的に表す働きが「ロゴファニー(論理顕現)」であり、思考的なものを感情的に表す働きが「エイドロギー(形象論理)」である。人間において感情と思考は互いを通じて自らを表すことを求めるが、正しく表されないとどちらの場合も病気を引き起こす。「つまり、情念が思考において現れる仕方が間違っていたり病的であったりして病因となる場合がありうる。また、論理が形象化したり感情や情愛において表されたりする仕方が間違っていて病因となる場合もありうる[xii]」。どちらの場合の病気も、それぞれ間違ったかたちで表された感情や思考が互いを通じて自らを正しいかたちで表すことで快癒する。特に、ロゴファニーの場合、思考において間違った仕方で表されていた感情が正しいかたちで表現され直して快癒する過程が、新たな観念の創造と捉えられることになる。
フォン・ヴァイツゼッカーは、この「ロゴファニー」の例として、サルトルの『嘔吐』を挙げている。つまり、主人公が人生を無意味と捉えることに由来する「嘔吐」感を脱却して執筆活動という人生の新たな意味を見出すこの自伝的小説は[xiii]、サルトル自身が神経症を克服して「実存主義」と呼ばれる思想を生み出したことの反映であることを示唆している。
例えば、精神分析が言うように幼児期に愛情喪失から思考が生まれることもあるだろうし、嘔吐感から哲学的思考が生まれることもあるだろう。いずれの場合も、身体=精神的な、少なくとも身体的性質も含めた変化から、新しい思考が生じる。これらは全て、ここでいうロゴファニーの概念に属する[xiv]。
これらのことから、エランベルジェの「創造の病い」概念は、先行するノヴァーリスの「崇高なヒポコンドリア」概念が説く病気による内省の効用と、フォン・ヴァイツゼッカーの「ロゴファニー」概念が説く思考の修正による病気の治癒という二つの要素を包含するものであることが分かる。それでは次に、エランベルジェ自身の「創造の病い」概念の説明を見てみよう。
2 「創造の病い」の一般的図式
まず、エランベルジェは「創造の病い」の症状を次のように説明している。
創造の病いは、どのように自らを提示するであろうか? しばしばありふれた神経症のかたちをとり、その時々の流行の精神医学的概念に従って「神経衰弱」等々の診断名を受ける。抑鬱、消耗、苛々、不眠、頭痛、神経痛などの症状が観察されるだろう。時々、多少深刻な精神病のかたちをとることもある。あるいは、心身症の性格が加わることさえある[xv]。
このことから分かることは、エランベルジェが「創造の病い」を主に精神的な病気(神経症、精神病、心身症)と見なし、肉体に影響があるときもまず精神の問題が先行していると考えていることである。その上で、エランベルジェは「創造の病いはいかなる場合でも次に挙げる幾つかの特徴によって際立っている[xvi]」として次の四段階を挙げている。
(1)病いの開始は、一般に、知的集中作業、長い内省、瞑想の時期に続いて起こる。あるいは多分、よりテクニカルな思考素材の探求や蓄積の作業の時期に続いて起こることさえある。ドイツ系スイス人の日常言語で用いられるstudieren(勉強する)という語には「勉強や気遣いのしすぎで病気になる」という意味があるが、これは集中的な思考作業と神経障害の間の(この場合には的確な)関係をかなりよく表している。
(2)病いの間中、一般に、患者は一つの支配的な関心に執着する。それは時々外に現れるが、しばしば隠されている。患者が探求に没頭する一つの物事や観念は、本人にとっては何よりも重要であり、本人がそれを完全に見失うことは決してない。
(3)病いの終結は、単に長期間の苦しみからの解放体験であるだけではなく、一つの開悟体験である。その時、本人の精神は、一つの啓示あるいは複数の啓示のアンサンブルとして現れる一つの新しい観念によって貫かれる。快癒はしばしば急速であり、本人がその正確な日付を報告できるほどである。一般に快癒の後には、高揚感、至福感、熱狂感が続き、その強烈さは過去の苦しみの一切がただの一度で報われたと感じられるほどである。
(4)病いの快癒に続いて、人格の持続的変容が生じる。本人は、新しい人生に到達したという印象を持つ。彼は知的あるいは霊的な発見を成し遂げたのであり、今後はその発見に価値を置いて生活するだろう。彼は新しい世界を発見したのであり、その探検には残りの人生全てを捧げても十分ではないとするだろう。もしそれが新たな観念である場合は、本人はそれを普遍的真理として提起する傾向を有するだろう。本人はそれをとても深い確信を持って行うので、あらゆる困難にかかわらず他人を信従させることに成功するだろう[xvii]。
このことから、エランベルジェの「創造の病い」概念における創造とは、基本的に新たな観念の創造を意味することが分かる。そして、これが三段階目の開悟体験により生じるので、その前段階の病的状態が「創造の病い」と見なされるのだと解せる。
ここで、エランベルジェ自身が「この一般的図式は今後多くの手直しが必要だろう[xviii]」と留保するように、彼の「創造の病い」概念の説明には幾つかの問題がある。第一に、「創造の病い」は「知的集中作業、長い内省、瞑想の時期」に続いて起こる(succède)とされているが、「知的集中作業、長い内省、瞑想の時期」自体もまた「創造の病い」に含まれうるのではないかという疑問が挙げられる。つまり、この時期に、本人が何らかの関心事に日常生活に支障をきたすほど異常な専心没頭を示す場合、それは既に「創造の病い」に含めても良いように思われる。そこで、本稿では「創造の病い」概念の一般的図式を改めて次の四段階に整理し、二段階目を「創造の病い」と捉えることを提案しておきたい[xix]。
(1)思考素材の蓄積
(2)異常な専心没頭(=創造の病い)
(3)開悟による快癒
(4)持続的人格変化
3 「創造の病い」の実例
次に、エランベルジェが挙げている「創造の病い」の実例を見てみよう。ただし、ここでもエランベルジェの説明はあまりよく整理されているとは言いがたい。そこで、エランベルジェの説明を補足しつつ要約すると次のようになる。
まず、エランベルジェが挙げている「創造の病い」の実例は、シャーマン、宗教家、作家、学者の四つのグループに分類できる。
シャーマンの例としては、シベリア・シャーマンとアラスカ・シャーマンが挙げられている。その特徴は、一貫した探求心に基づき病的な苦行や亡霊との対話を先達の指導の下に行い、修行期と病期が一致し、超俗的な自己変容が生じることである。ここで創造される新たな観念は、死後世界の実在の確信と察せられる。特にシベリア・シャーマンの場合、導師の指導の下に行われる「創造の病い」は「入門の病い」と呼び表されている。
宗教家の例としては、ホワン・デ・イェペス(十字架のヨハネ)と英国信仰復興運動が挙げられている。その特徴は、一貫した探求心に基づき病的な苦行や神との対話を先達の指導の下に行い、修行期と病期が連動し、超俗的な自己変容が生じることである。ここで創造される観念も、死後世界の実在の確信と推察される。特にホワン・デ・イェペスの場合、「創造の病い」における霊的苦悩は「魂の闇夜」と形容されている。
作家の例としては、フーゴー・フォン ホーフマンスタールが挙げられている[xx]。その特徴は、作家の創作活動においては、無意識における心象と観念を意識化させる病的な苦難の過程としての枯渇期を経て文学的霊感が発揮されることである。ここで創造される観念の例として挙げられているのは、死別の受容である。
学者の例としては、フリードリヒ・ニーチェ、グスタフ・テオドーア・フェヒナー、ジグムント・フロイト、カール・グスタフ・ユングが挙げられている[xxi]。その特徴は、一貫した探求心に基づき病的な苦悩の時期を経て知的啓示と共に快癒と高次の自己変容が生じることである。特に、その「創造の病い」の観念的産物として、ニーチェは「永遠回帰」を、フェヒナーは「快楽原則」を、フロイトは「精神分析学」を、ユングは「分析心理学」を創出したとされる[xxii]。
ここで注意すべきは、エランベルジェ自身はあまり強調していないが、これらの実例によって示される「創造の病い」により創造された観念が、いずれも単なる机上の抽象概念ではなく、本人とって人生の意義を示す普遍的真理と読み解けることである。言い換えれば、それは決して本人の人生と無縁なものではなく、本人の生き方の指針あるいは人生観の要約としての「観念」であると解釈できる。
さらに留意すべきは、エランベルジェが「創造の病い」の実例として取り上げているのが、宗教、文学、哲学というある意味で非日常的な文系の言語的活動に限られている問題である。そのため、エランベルジェの文章からは、ここで言う「創造の病い」概念が、家事やビジネス等の日常生活における創意工夫や、理系の科学や技術における発見・発明や、労働やスポーツ等の身体運動における優れたパフォーマンスや、絵画・彫刻・音楽等の非言語的芸術におけるインスピレーションについても妥当するのかどうかは判然としない。
しかし、もし「創造の病い」により創造される観念が本人の人生と無縁なものではないとすれば、当然これらの諸活動においても「創造の病い」が生じることは十分に考えられる。むしろ、自らの生き方が改めて問われる場面――つまり、出会いと別れに関わる外的な環境変化(入学・卒業、就職・退職、恋愛・失恋、結婚・離婚、出産・死別等)や、自らの生老病死に関わる内的な状態変化(初潮・閉経、声変わり・白髪禿頭、各種の病気・怪我・老化等)、さらに不慮の事故や事件や不幸等に直面する場面ではいつでも、「創造の病い」は生じうると想像される[xxiii]。その意味で、「創造の病い」は「マリッジ・ブルー」や「中年の危機」がそうであるように誰にでも生じうる問題であり、多少の程度の差こそあれ人生とは正に「創造の病い」の絶えざる連続であるといえる。
なお、科学や技術における発明・発見の場合を典型として、「創造の病い」により創造される観念が直接的には生活に役立たず、一見すると本人の人生とは無縁であるように思われる場合もありうる(例えば、パンダの「第六の指」の発見等)。しかしその場合でも、そうした新たな観念を創造することが本人の社会的評価に繋がり人生を左右するような場合(さらには死後に生前の評価を左右するような場合)には、それはやはり本人にとって自らの生き方が改めて問われる場面として「創造の病い」を発生させることは十分に想定できる。
4 「創造の病い」の発見上の価値
さらに、エランベルジェは「創造の病い」について、発見上の価値の問題について言及している。つまり、創造される観念の普遍妥当性の問題である。
創造の病いに起因する発見上の価値の問題は、重要であるが難しい。詩人の場合を除いて、試練の通過に成功できた人の発見の価値はどのようなものであろうか[xxiv]?
この文章から、エランベルジェは「創造の病い」により創造される観念には、芸術的なものと非芸術的なものがあると考えていることが分かる。そして、芸術的な観念については全て価値があるけれども、非芸術的な観念についてはそうではないと考えていると察せられる。
ここで、エランベルジェが「創造の病い」により創造される観念に価値がない場合の例として挙げているのは、その観念が他人にとって有効でない場合である。実際に、エランベルジェは、フロイトとユングが「創造の病い」により創造した観念は相互に無価値であることを示唆している。
フロイトは、エディプス・コンプレックスの普遍性を確言した。それに対しユングは、フロイトが自己分析の過程で発見したエディプス・コンプレックスはフロイト自身にしか価値がなく、それを普遍法則とするのは誤りであると応じた。しかし、フロイト派の人達も意趣返しで、ユングにユング自身の自己分析で発見された例えば「アニマ」概念を一般化することは間違っていると言うことができる[xxv]。
確かに、フロイトの「エディプス・コンプレックス」概念やユングの「アニマ」概念が万人に同じ水準で有効かどうかは現在でも議論の分かれるところである。しかし、ここで重要なことは、その場合でもそれらの観念は創造した本人以外に価値が全くないのかそれとも少しはあるのかという問題である。エランベルジェは、フロイトの「エディプス・コンプレックス」概念もユングの「アニマ」概念も当人以外には当てはまらないことに注意を促しているが、やはりそれぞれ程度の差こそあれ少しは妥当し、その分だけ少しは価値があるのではないかと反論できる。
むしろここで重要なのは、なぜ「創造の病い」により創造される観念にはそうした妥当性の程度の差異が生じるのかという問題である。エランベルジェは、この問題についてもまたあまり明確に回答していないが、論理上この差異は、事前に蓄積される思考素材の質・量や、それに対する本人の知的能力や精神的成熟の差異から生じるように思われる。いずれにしても、本人の自らの生き方の指針を巡る苦悩が人間として本質的で根源的であればあるほど、そこから創造される観念が他人にも広く有効性を持つことは十分に考えられる。その場合、その分だけその創造された観念が優れた価値あるものと見なされることは、それが芸術的な観念である場合でも非芸術的な観念である場合でも同様である。
5 「創造の病い」の臨床形態における多様性
さらに、エランベルジェは「創造の病い」について臨床形態における多様性の問題を取り上げている。それはまず、病期の長短、症状の軽重、発症の頻度である。
まず、創造の病いの臨床形態にかなり多様性があることは明らかである。病期が長い場合も短い場合もあり、症状が神経症の場合も、精神病の場合も、心身症の場合もある。ある時には、人生の半ばで生じ、人生を言わば前後に分かつ一度きりのエピソードである。またある時には、むしろ危機の連続である(おそらくニーチェの場合のように)。一部の人々の場合、創造の病いは慢性的であり、生涯の大部分に渡っているように思われる[xxvi]。
これに加えて、エランベルジェは、「創造の病い」に先行モデルがある場合とない場合の差異を指摘している。そして、先行モデルがある場合はない場合に比べて創造性の程度において劣ることは明らかであると主張している。
先達のいる創造の病い(シャーマンやキリスト教的神秘主義者の場合ように)と、患者が自分自身の資源のみに頼る創造の病い(詩人や哲学者の場合のように)を区別する必要がある。フロイトとユングの実例は、本来は独特で自発的な創造の病いが、もしこう言って良ければ、様式化され無数に再生産される創造の病いの範型になりうることを示している。教育分析の原則を徹底させたのが、まだフロイトと共に働いていた頃のユングであることを想起しよう。ユングの頭の中ではそれは実践による学習法であったが、後にユング派は教育分析をシャーマンの入門の病いと同一視するようになった。しかし、フロイト派であれユング派であれ、いかなる教育分析もそれを受ける入門者を、その範型の作者において創造の病いが創り出したものに匹敵するほどの成果にまで導くことができないのは明らかである[xxvii]。
確かにエランベルジェが言うように、「創造の病い」において先行モデルがあると、産みの苦しみが軽減される分だけ後続者の創造力の程度がそれより低くなることはありうる。しかし、ここでもエランベルジェがそれを絶対視することには疑問がある。なぜなら、もし先行モデルがある場合には必ず後続者の「創造の病い」の創造力の程度がそれより低くなるとするならば、宗教は世代を経るに従って必ず貧弱になっていくことになってしまうからである。
しかし、実際にはユダヤ教からキリスト教が生まれさらにイスラム教が生まれたことを考えるだけでも、後続者の「創造の病い」が先行モデルを超えるとまでは言わなくとも少なくとも同程度の創造力を示しうることは間違いない。そうであるならば、理論上は、たとえ先行モデルがある場合でも、本人の自らの生き方の指針を巡る苦悩が先行者のそれよりも人間的に本質的で根源的である場合には、先行モデルを超える創造力を示すことは十分にありうる。その意味で、臨床的見地からは、「創造の病い」に先行モデルがあるかどうかはあまり重視しすぎない方が良いように思われる。
もちろん、先行モデルがあると産みの苦しみが軽減されるために、その方向に沿って創造力を発揮しやすくなる(すなわち何らかの答えを見つけやすくなる)ということはあるだろう。それは、やはりその創造される観念が、芸術的な観念である場合でも非芸術的な観念である場合でも同様である。
6 「創造の病い」の始終の諸条件
それでは、「創造の病い」はどのように始まりどのように終わるのであろうか?
この「創造の病い」の開始と終結の理由についてもまた、エランベルジェはあまり明確に説明していない。「創造の病い」は知的作業をきっかけに始まるとされるが、その関心対象についての共通性は不明である[xxviii]。また、開悟による終結も何か特別な要因があるとは説明されず、自然にあるいはまるで偶然に生じるかのようである[xxix]。
しかし、「創造の病い」の発症と収束にはやはり何か一定の要因があると思われる。つまり、まず開始について言えば、もし「創造の病い」により創造される観念が本人のその後の生き方の指針そのものであるとするならば、「創造の病い」の開始はそれまでの生き方の指針が行き詰まることが契機と考えられる。言い換えれば、それまで通用していた自らの生き方の指針が通用しなくなり再編成を迫られるような苦境に陥った時に、「創造の病い」は開始されると推測される。だからこそ、本人はその病期において、自らの生存に関わる切実な問題として生き方の指針となる唯一つの観念を常に視野から完全に見失うことなく追求し続けるのだと推定される。
そして、「創造の病い」の終結についても一定の要因が想定される。つまり、人がどのように自らの生き方の新しい指針を発見するか自体は説明が不可能であるが、どうすればそれを発見しやすいかの諸条件については説明が可能である。ここでは、少なくとも三つの条件が考えられる。一つ目の条件は、既に述べたように、先行モデルがあることでその方向に沿って答えを見つけやすい場合である。例えば、対話や読書等を通じた先達の開悟の追体験はそのような有利な条件となるだろう。二つ目の条件は、創造力を発揮しやすい安心して寛げる環境である場合である。例えば、親類・友人・知人からの応援や、社会的な賞賛や、経済的な安定は、そのような有利な条件となりうる。三つ目の条件は、問題を解決しようとする本人の意志が強い場合である。実際にエランベルジェは、「創造の病い」と単なる精神障害の違いは、自らの抱える問題に立ち向かう意志の強さであることを暗示している[xxx]。この場合の意志の強さは、周囲からの愛情による自己肯定感で強化されると考えられるので、二つ目と三つ目の条件は連動していると推量される。
いずれにしても、こうした諸条件が整っている時に人の内面的創造力は賦活され、「創造の病い」を快癒させる開悟が生じやすいと推論できる。もし人生が「創造の病い」の連続であるならば、これらの諸条件の整備改善は個人的・社会的に必要不可欠な課題であるだろう[xxxi]。
7 「創造の病い」の臨床的活用性
それでは、エランベルジェが提出した「創造の病い」概念は、臨床の現場、特にグリーフケアについてどのように応用できるだろうか?
この問題について重要な示唆を与えてくれるのが、心理学者河合隼雄(Hayao Kawai: 1928-2007)が「創造の病(い)」について論じた「物語ることと創造性」(2000年)である。
筆者は、エレンベルガーの考えを拡張して、彼のいう「病」を精神の病のみでなく、身体の病や事故、不幸な出来事などにまで適用するとよい、と考えている。実際に、創造的な人の伝記を見ると、このような拡大解釈が当てはまるように思うことが多い。たとえば、夏目漱石はいわゆる修善寺の大患によって命を失いかけるほどになるが、その後の彼の作風は一変して、より創造的なものになったのである[xxxii]。
ここでまず河合は、エレンベルガー(エランベルジェ)の「創造の病い」概念について、ノヴァーリスの「崇高なヒポコンドリア」概念の病気による内省の効用の側面を重視していることが分かる。そして、それは精神的な病気のみならず身体的な病気や怪我などにも拡大解釈できると考えていると推察される。
もちろん、河合はここで、単に病気や怪我をすれば創造力が高まると言っているのではない。そうではなく、そうした外に対する不如意が内に対する省察を深めさせることで内面的創造力が賦活されやすくなると述べているのだと解釈できる。
そして、精神的な病気や肉体的な病気や怪我は全て「不幸な出来事」に包含されうるが、それは既に見た本稿の文脈では、それまで通用していた自らの生き方の指針が通用しなくなり再編成を迫られるような苦境と換言できる。そしてそのような場合には、やはりいつでもどこでも誰にでも内面的創造力を発揮させる「創造の病い」は生じうると述べているのだと理解できる。
それでは、ここでいう「創造の病い」は具体的には一体何を創造するのであろうか。この問題について、河合はそれを「人生」という「物語」であると解説している。
個々人が自分の人生を生きようとする限りは、自分の「物語」をつくりあげることが必要であり、それはまさに創造のしごとである。先にあげた「創造の病」の拡大解釈と結びつけて考えるならば、何らかの「病」に苦しんで心理療法家のところを訪れる人に対して、それを創造の病であるとして、そこにつくり出されている物語をその人がいかに生きるか、あるいはその人の今後に生き抜くべき物語をいかにつくり出すか、その仕事を援助しているのが、心理療法家の仕事であるともいうことができる[xxxiii]。
ここで、やはり河合は「創造の病い」を学問や芸術だけでなく万人の一般生活にも応用可能と見ていることが分かる。そして、「創造の病い」により創造される観念とは「物語」であり、ここで言う「物語」とは人生の意味付け、つまり自らの人生をどのように納得可能なかたちで解釈するかを指すと了解できる。
ここで河合は、「創造の病い」に陥った患者が自分の人生を物語化することを援助することを心理療法家の役割として説いているが、当然これは心理療法家だけに限られるのではなく患者を支援する周囲の人達全てにも当てはまるだろう。すなわち、「創造の病い」のグリーフケアへの応用としては、まず本人が愛着対象の喪失をどのように受け入れやすいかたちで意味付けるかが大切であり、さらに周囲がその意味付けをどのように精神的・物質的に支えるかが重要であると要約できる。
例えば、死別に悲しむ人の場合、本人が問題解決の強い意志を持ち、その死別の妥当な意義を模索すると共に、周囲はその模索の自発性を損なわない程度に寄り添い、その悲哀や意味付けに共感し、経済的な安定についてもまた便宜を図ることが肝要であると考えられる。その点で、これまで近代的な世俗化の過程で衰退してきた、生死の意味を説く宗教・信仰や相互扶助のための儀礼・儀式等の役割は、今日その価値と有用性を改めて再評価する必要があるように思われる。
おわりに
最後に、エランベルジェが提唱した「創造の病い」概念の長所と短所についてまとめよう。
エランベルジェの「創造の病い」概念の学問的貢献は、何よりもまず、宗教、文学、哲学における創造行為の前段階に病的状態が広範に見られることを「創造の病い」として的確に用語化したことである。特に、フェヒナーの「快楽原則」、フロイトの精神分析学、ユングの分析心理学といった力動精神医学の発達過程にこの「創造の病い」が共通して看取されることを、「『創造の病い』という概念」で初めて本格的に指摘し、さらに力動精神医学の最初の網羅的通史である『無意識の発見』(1970年)を通じて世間一般に広めた意義はどれだけ強調してもし過ぎるということはない[xxxiv]。
しかし、同時にエランベルジェの「創造の病い」概念の問題点は、知的能力が極めて高くそれゆえにその観念的産物の知的水準も非常に高い、フェヒナー、フロイト、ユング等を「創造の病い」の共通例として強調するあまりに、本来「創造の病い」が偉人達だけや宗教、文学、哲学等の特殊分野だけに限られず、多少の程度の差こそあれいつでもどこでも誰にでも起こりうる一般現象であることを見えにくくしてしまったことと指摘できる[xxxv]。
「産みの苦しみ」は、肉体にだけではなく精神にも起こりうる[xxxvi]。すなわち、あらゆる「苦悩」は、「精神的な産みの苦しみ」としての「創造の病い」になりうる。本稿は、エランベルジェが提出した「創造の病い」概念を、人間が真摯に自らの人生を見つめ直し生き方の新しい指針を見出そうと努める際には常に発生しうる普遍現象として捉えることを提案したい[xxxvii]。そして、あらゆる逆境は人生をより良いものへ高める契機となりうることを認識することこそが、「創造の病い」概念のグリーフケアにおける最も重要な臨床的活用性であることを提唱したい。
註 引用は全て、既訳を参考にさせていただいた上で原著から拙訳している。
[i] Henri F. Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” in Dialogue: Canadian Philosophical Review, 1964, pp. 25-41. 邦訳、「『創造の病い』という概念」(中井久夫・西田牧衛訳)、『エランベルジェ著作集 第二巻 精神医療とその周辺』中井久夫編訳、みすず書房、一九九九年、一四二‐一六一頁。なお、「maladie créatrice」は、既に「創造の病(い)」という訳語が多くの先行文献で用いられ学術上定着しているように思われるのでそれを踏襲するが、この訳語は「創造が病んでいる」のか「病気が創造する」のか混乱を招きやすい。また、「病(い)」も「病気」と訳した方がエランベルジェの原意をより明確に伝えているように思われる。一般に、アンリ・ベルグソンの「évolution créatrice」を「創造の進化」とは訳さず「創造的進化」と訳すように、本来「maladie créatrice」は「創造的病気」と訳す方が適切であり誤解の余地が少ないことを予め付記しておきたい。
[ii] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 26. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一四四頁。
[iii] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 26. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一四四頁。
[iv] Novalis, “Philosophische Studien 1797 (Hemsterhuis- und Kant-Studien),” in Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Vol. 2, C. Hanser: München, 1978, p. 223. 邦訳、ノヴァーリス「断章と研究 1797年まで」『ノヴァーリス全集 第二巻』青木誠之・池田信雄・大友進・藤田総平訳、沖積舎、二〇〇一年、六二頁。
[v] Novalis, “Briefe von Novalis,” in Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Vol. 1, C. Hanser: München, 1978, pp. 617-618. 邦訳、「日記」飯田安訳、『ノヴァーリス全集 第二巻』飯田安・今泉文子・柴田陽弘・深田甫・山室静訳、牧神社、一九七七年、四五八頁。
[vi] Novalis, “Tagebücher,” in Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Vol. 1, C. Hanser: München, 1978, p. 460. 邦訳、ノヴァーリス「日記」『ノヴァーリス全集 第三巻』青木誠之・池田信雄・大友進・藤田総平訳、沖積舎、二〇〇一年、三三五‐三三六頁。
[vii] Novalis, “Tagebücher,” p. 462. 邦訳、ノヴァーリス「日記」三四一頁。
[viii] Novalis, “Tagebücher,” p. 463. 邦訳、ノヴァーリス「日記」三四四頁。
[ix] Novalis, “Hymnen an die Nacht,” in Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Vol. 1, C. Hanser: München, 1978, pp. 153-154. 邦訳、ノヴァーリス「夜の讃歌」斎藤久雄訳、『ノヴァーリス全集 第一巻』飯田安・斎藤久雄・佐藤荘一郎・笹沢美明・山室静・由良君美訳、牧神社、一九七六年、三六頁。ノヴァーリス「夜の讃歌」『ノヴァーリス全集 第一巻』青木誠之・池田信雄・大友進・藤田総平訳、沖積舎、二〇〇一年、一四七‐一四八頁。ノヴァーリス「夜の讃歌」『夜の讃歌・サイスの弟子たち 他一篇』今泉文子訳、岩波文庫、二〇一五年、一一‐一二頁。
[x] Novalis, “Fragmente und Studien 1799/1800,” in Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Vol. 2, C. Hanser: München, 1978, p. 828. 邦訳、ノヴァーリス「断章と研究 1797年まで」『ノヴァーリス全集 第二巻』青木誠之・池田信雄・大友進・藤田総平訳、沖積舎、二〇〇一年、三二九頁。
[xi] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 26. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一四三頁。
[xii] Viktor von Weizsäcker, “Pathosophie,” in Gesammelte Schriften, Vol. 10, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 2005, p. 200. 邦訳、ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカー『パトゾフィー』木村敏訳、みすず書房、二〇一〇年、二四六頁。
[xiii] Jean-Paul Sartre, La nausée: roman, Paris: Gallimard, 1938. 邦訳、ジャン=ポール・サルトル『サルトル全集 第六巻 嘔吐』白井浩司訳、人文書院、一九五一年。
[xiv] Viktor von Weizsäcker, Der kranke Mensch: eine Einführug in die medizinische Anthropologie, K. F. Koehler: Stuttgart, 1951, p. 326. 邦訳、ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカー『病いと人――医学的人間学入門』木村敏訳、新曜社、二〇〇〇年、二九九頁。
[xv] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 27. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一四四頁。
[xvi] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 27. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一四四頁。
[xvii] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” pp. 27-28. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一四四‐一四五頁。
[xviii] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 28. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一四五頁。
[xix] エランベルジェは『無意識の発見』(1970年)で、「創造の病い」概念を次のように再定義している。「創造の病いは、一つの観念に強烈に没頭し、ある一定の真理を探究する時期に続いて起こる。これは、鬱病、神経症、心身症、さらに精神病というかたちさえ取りうる多形的症状である。症状が何であれ、それは当人には死ぬほどではないとしても苦痛に感じられ、軽快と悪化の時期を繰り返す。病いの間中、当人は自らを支配している関心の導線を決して失わない。創造の病いは、しばしば正常な職業活動や家庭生活と両立している。しかし、もし社会活動を保っていてさえ、当人はほとんど完全に自分自身に没頭している。当人は、完全な孤独感に苦しむ。たとえ、(シャーマン見習いとその導師のように)この試練の間自分を導いてくれる指導者がいたとしてもである。病いの終結は、しばしば急速で爽快な状態によって特徴付けられる。当人は、人格の永続的変容と、一つの偉大な真理あるいは一つの新しい精神世界を発見したという確信を伴ってこの試練から現れ出てくる」(Henri F. Ellenberger, The discovery of the unconscious: the history and evolution of dynamic psychiatry, New York: Basic Books, 1970, pp. 447-448. 邦訳、アンリ・エレンベルガー『無意識の発見――力動精神医学発達史 下巻』木村敏・中井久夫監訳、弘文堂、一九八〇年、三五‐三六頁)。
[xx] エランベルジェ自身は直接触れていないが、冒頭で言及していることから考えてノヴァーリスもこの作家の例に含まれていると推定される。
[xxi] その他、エランベルジェは学者の例としてルネ・デカルトやチャールズ・ダーウィンも含められるのではないかと示唆している。また、『無意識の発見』ではルドルフ・シュタイナーも「創造の病い」の例に含めている。
[xxii] 「創造の病いの特徴として、当人が回復後、自分が発見したものはそれが何であれ普遍的真理であると確信を持つことを挙げられる。メスメルが動物磁気の真理を主張し、フェヒナーが快楽原則を、ニーチェが永遠回帰を、フロイトがエディプス・コンプレックスと神経症の小児性欲起源を、ユングがアニマと個性化過程を真理として主張したのがそうである」(Ellenberger, The discovery of the unconscious, p. 890. 邦訳、エレンベルガー『無意識の発見 下巻』五五九頁)。
[xxiii] エランベルジェは「創造の病い」の説明において、観念の内的な獲得と、その観念の文章による現実化と、その文章の出版による社会化等の関係についてあまり明確に分節していないが、これらは段階を経るごとに相乗効果的に治癒効果をもたらすと考えられる。
[xxiv] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 40. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一六〇頁。
[xxv] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 40. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一六〇頁。
[xxvi] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 39. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一五九頁。
[xxvii] Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 40. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一五九‐一六〇頁。
[xxviii] エランベルジェは『無意識の発見』でも、「創造の病い」の開始の原因について何らかの知的関心から始まるという以上のことは実質的に説明していない。「ユングの創造の病いも、既に私達がフロイトの創造の病いに見出したのと同じ特徴を持っている。二人の創造の病いはどちらも、人間の魂の謎への強烈な没頭の時期に続いて起こった」(Ellenberger, The discovery of the unconscious, p. 672. 邦訳、エレンベルガー『無意識の発見 下巻』三〇五頁)。
[xxix]「この稀な病いは、長期間休みなく知的作業に没頭した後に始まる。主な症状は、抑鬱、消耗、苛々、不眠、頭痛である。要するに、深刻な神経症、時には精神病の病像を示す。症状の強さには変化がありうるが、しかし病いの間中、本人は一つの支配的な観念や何らかの困難な目的の追求に執着し続ける。彼は完全な精神的孤独の中で生き、誰も自分を助けられないと感じるので、自分で自己治療を試みる。しかし通常、自己治療の試みは却って苦しみを強めるように感じられるだろう。この病いは、三年かそれ以上続くかもしれない。回復は、自発的(spontaneously)かつ急速に起こる。回復は多幸感によって特徴付けられ、人格の変容が続く。本人は、自分が新しい精神世界に到達したと確信したり、自分が世界に広めことになる一つの新しい精神的真理を獲得したと確信する〔傍点引用者〕」(Ellenberger, The discovery of the unconscious, p. 889. 邦訳、エレンベルガー『無意識の発見 下巻』五五八頁)。
[xxx] 「注意すべきは、病いの間中、フェヒナーの精神が極めて活発であり、最後の年は病いに対する直接的闘いに明け暮れていたことである」(Ellenberger, “La Notion de maladie créatrice,” p. 35. 邦訳、エランベルジェ「『創造の病い』という概念」一五四頁)。
[xxxi] ここで考えるべきは、数学的合理化が進み、宗教に対する信仰心が薄れたり、地域共同体が解体していく近代社会では、「創造の病い」の終結を促進するこれらの諸条件が衰退する一方で、反動的に「創造の病い」が紛い物に左右されやすくなるのではないかという問題である。オウム真理教事件や酒鬼薔薇聖斗事件は、この観点から捉え直す必要があるように思われる。
[xxxii] 河合隼雄「物語ることと創造性」、福島章・中谷陽二編『パトグラフィーへの招待』金剛出版、二〇〇〇年、二〇七頁。
[xxxiii] 河合隼雄「物語ることと創造性」二一一頁。
[xxxiv] 『無意識の発見』においても「創造の病い」の概念上の進展はほとんど見られないが、「創造の病いの終結に典型的なことは、関心が内面から外界へ次第に移行することである」は新たに加わった説明といえる(Ellenberger, The discovery of the unconscious, p. 449. 邦訳、エレンベルガー『無意識の発見 下巻』三八頁)。
[xxxv] エランベルジェは『無意識の発見』でも、「創造の病い」を次のように特権化している。「さらに、心を研究する者は、自分自身の神経症や自分の人格における神経症的要素に直面するかもしれない。しかし、単に研究対象として自分自身の神経症を扱う精神科医と、創造の病いの結果がライフ・ワークとなる精神科医の間には、基本的な区別がなされなければならない。〔…〕精神科医に内省の主題を供給し多分自己治療の努力を促す普通の神経症と、創造の病いの発現は混同されるべきではない」(Ellenberger, The discovery of the unconscious, pp. 888-889. 邦訳、エレンベルガー『無意識の発見 下巻』五五七‐五五八頁)。しかし論理上、「単に研究対象として自分自身の神経症を扱う」ことと「創造の病いの結果がライフ・ワークとなる」ことを明晰に分節することはできないので、これは概念定義として有効であるとは思われない。
[xxxvi] ここで注意すべきは、エランベルジェ自身は明言していないが、彼が提出している「創造の病い」の関連事例の多くが死後世界の問題に関係していることである。例えば、ノヴァーリスの「ゾフィー体験」や、シャーマン・宗教家の神秘的確信や、作家の死別の主題化がそうであり、フェヒナー(やシュタイナー)は死後の霊魂の存続を説き、ユングは心霊現象に関心を抱いたことで有名である。このことから、エランベルジェは「創造の病い」は特に死別の際に超俗的な観念を創造しやすいと考えていた可能性がある。この問題については、グスタフ・フェヒナー『フェヒナー博士の死後の世界は実在します』服部千佳子訳、成甲書房、二〇〇八年や、カール・グスタフ・ユング『心霊現象の心理と病理』宇野昌人・岩堀武司・山本淳訳、法政大学出版局、一九八二年等も参照されたい。
[xxxvii] ここで留意すべきは、エランベルジェ自身は論及していないが、実は「創造の病い」概念の萌芽は、ノヴァーリスの「崇高なヒポコンドリア」概念やフォン・ヴァイツゼッカーの「ロゴファニー」概念だけではなく、既にフロイトの「退行」「昇華」概念やユングの「個性化」概念の中に窺われることである。その後のフロイト派の展開においては、エルンスト・クリスが『芸術の精神分析的研究』(1952年)で「自我に奉仕する一時的・部分的退行」概念を提出し、ロイ・シェイファーが『ロールシャッハ・テストの精神分析的解釈』(1954年)で「創造的退行」概念を提唱したことが名高い。なお、トランスパーソナル心理学の分野では、スタニスラフとクリスティーナのグロフ夫妻が『自己の暴風的探求』(邦訳『魂の危機を超えて』)(1990年)で提案した「スピリチュアル・エマージェンシー」概念が著名である。
【初出】秋丸知貴「アンリ・エランベルジェの『創造の病い』概念について――グリーフケアの観点から」『グリーフケア』第6号、上智大学グリーフケア研究所、2018年、97-113頁。ただし、文言を多少変更している。
■ 秋丸知貴『芸術創造の死生学』
第2章 ジークムント・フロイトの「昇華」概念について
第3章 カール・グスタフ・ユングの「個性化」概念について
第4章 エーリッヒ・ノイマンの「中心向性」概念について
第5章 エイブラハム・マズローの「至高体験」概念について
第6章 ミハイ・チクセントミハイの「フロー」概念について