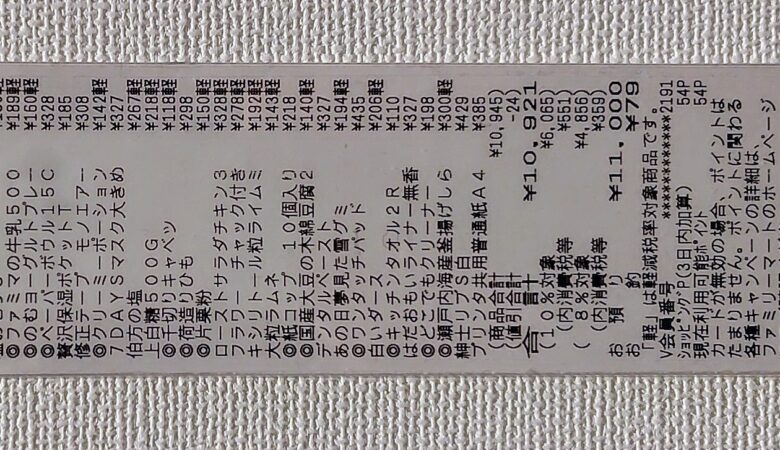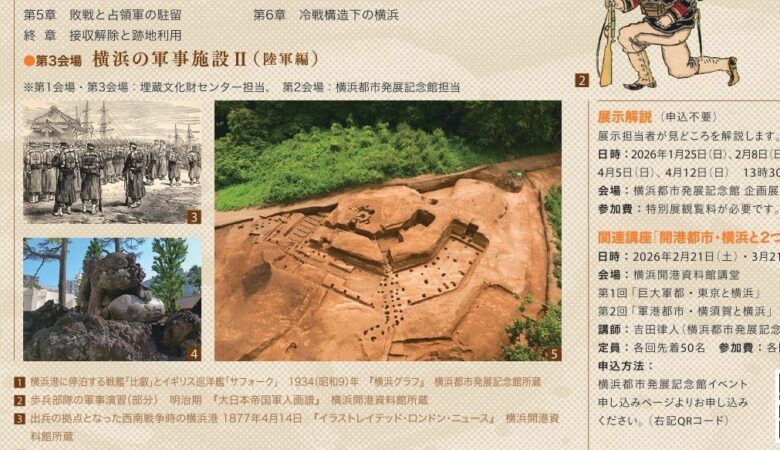【ステッカーの祭典@ダブリン】
アイルランドにちょいと、行ってきました。主な目的は3つあります。敬愛するフランシス・ベーコン(1909~92年)のスタジオを視察する、これが一つ目です。自然豊かなアラン諸島を堪能する、これが二つ目です。そして、ステッカーとグラフィティが盛んに実践されているといううわさを聞きつけ、実際にどの程度のものなのかを体感するというのが三つ目です。
本稿では、ダブリンのgalleryXで開催されていた「DUBLIN STICKER EXPO2025」の内容をリポートします。
ダブリン屈指の高級ホテル「シェルボーン」から歩いて数分の場所に立地するgalleryXは、そこそこ広い空間でした。壁という壁にステッカーが大量に展示されています。無秩序、でたらめに展示しているのではなく、ステッカーの色彩、テーマ、形状などによってグループ分けしているようにも見えます。

黒っぽいステッカーたち

ガーリーな感じのステッカーたち

上は青、下は黄、故に真ん中は緑
私以外にもお客さんがいます。イタリア語を話しているので多分イタリア人と思われる20歳代の女性3人組です。あと、アイルランドの方と思われる女性が1人。ギャラリーのオーナーは、Giovanni Giusti(ジョヴァンニ・ジュスティ)さんです。イタリア人男性のよくある名前ですね。つまり、スティングの名曲「English man in New York」ならぬ「Italian man in Dublin」ということのようです。

テーブルに山盛りに置かれたステッカー
特筆すべきは、ギャラリーの真ん中に置かれた大きなテーブルです。大量のステッカーが山盛りになっているのです。最初、私は販売しているのかなと思ったのでジュスティさんに「これは1枚いくらで販売しているんですか?」と尋ねたのですが、彼は「全部無料だよ」と答えてきました。
「熱心にステッカーを作っている人たちの“作品”を世に広めるためにやっている展示。だからお金は取らない」
「10枚でも20枚でも好きなだけ取って行っていいよ」とジュスティさん。

緑と黒が多いステッカー

ピンク主調だが、あまりガーリーではないステッカー

宅配便のシール状のものを用いたステッカー
欲張りな筆者は「それなら、お言葉に甘えましょか」と心の中で呟きながら、好きなステッカーを選びに選び抜いて大量ゲットいたしました。ただ、自称ステッカーソムリエの私に言わせれば、この展示に並んでいる作品は、ABCDの四段階評価で言いますと、BのマイナスからCくらいのものばかりでした。ステッカーの評価と聞いて「?」の読者の方もいるでしょうから、(あくまでも私の)評価基準をお伝えしますと…。
【A評価】
どこの誰が作っているのか、まったく秘密の作品。完全に手作りのもので「アート」というよりは、ステッカーで社会をひっくり返してやろうと本気で考えている人間の「荒ぶる魂の結晶」。ベルリンの壁に最初に落書きしたティエリー・ノワールの勇気に通じる、気合のこめられたステッカー。「販売される」ものではなく、闇から闇を動き回り、都市に感染し、権力機構を麻痺させるほどの潜在力を秘めた結構やばい作品。これだけのパワーを持ったものは、なかなかお目にかかれない。ベルリンの壁をおちょくったノワールも偉いが、良質なステッカーも偉い。くだらない専制政治や悪質な資本主義を溶解させるための“武器”、そしてレジスタンスとなりうるアートを超えたアート。直截な政治的なメッセージが描かれている(書かれている)訳ではない点に注意してほしい。
【B評価】
かなり著名なアーティストが、こっそり陰で作っている作品。見る人が見ると、「これは、あの●●さんの作品では?」と分かる。こっそりとは言いながらも、実は普通に販売されていることもあるので、あまりこっそり感はない。ただ、制作・販売している数は極めて少数に抑えられているので、アート作品の一種として受け止めることができるだろう。A評価の作品は実際にストリートに貼る前提だが、B評価のものは、むしろ将来、「値上がりするかも」といったスケベ心からか、貼る(=所有権を放棄する)わけではなく、大事に大事に保管するケースが多い気がします。アートピースとしてのステッカー。
BとCの中間に位置するのが、政治的な主張を力強く訴えるもの。「パレスチナに自由を」「ガザに自由を」「くたばれプーチン」「ナチスのごろつきどもは消え失せろ」みたいなことが書かれている。文字ベースのものが多い。
【C評価】
それほど著名でもないアーティストやアーティスト志望の人間が、自分の名前を世の中に広く知らしめようという欲望から制作した作品。社会変革というよりも、自己顕示欲の表現の一種と捉えることができる。一点物というよりも大量生産し、様々な場所に貼りまくることが目的。このレベルのステッカーだと、一般市民からはただの「愉快犯」みたいに見られてしまう、街中に貼ることが。そもそも無名に近い作り手の作品ではあるが、クオリティーが高いと、まれに「この作品、値上がりするかも」と保管されることもある。
日本におけるC評価のステッカーで一番、多く見られるのは、社寺の建物に貼られた千社札である。言い換えると、日本ではそこまでステッカー文化が広まっておらず、千社札を貼るのがある種の代替的行為として広がっていた。千社札も禁止されることがあるのは、やはりただの自己顕示欲に根差した行為だからだろう。
【D評価】
お店やブランドや何らかのサービスなどの宣伝のために作られたゴミ。いくら、デザイン的に凝った作品であったとしても、この手のステッカーには何の価値もない。商品・商売の宣伝のためのステッカーを街中に貼る行為には、社会に対する批評性がまったく感じられない。むしろ、本来、ステッカーが戦うべき資本主義の悪弊に加担、上書きするだけのものに過ぎない。海外、日本のどちらの場合も、街中に貼られているステッカーの8~9割は、このD評価のもの。筆者は大嫌いです。

「ART IS DEAD」などと訴えた作品が見える
galleryXで展示・無料配布されていたステッカーはほとんどが、C評価のものばかりで、私は正直、物足りなさを覚えましたが、中には、監視カメラが蔓延する社会を批判した(ように思える)作品や世界的に展開する企業を批判した(ようにも見える)作品や「ART IS DEAD」と男が叫ぶ作品なども少数ですが混入していました。
さて、ダブリンの街中ですが、これはもうものすごい数のグラフィティが描かれていました。ステッカーもあちこちに大量に貼られていました。C評価のものが多かったとはいえ、一般のギャラリーで大量のステッカーを無料で流通させているダブリンの底力に感心した筆者でした。日本でも同様の試みがあったらいいなと思いました。通常、国内外のギャラリー等で販売されるステッカーは1点で数百円以上、ものによっては数千円することもあるので、結構な「商品」なのです!
資本主義への抗議を込めた、本物のステッカーには本来、値段なんか付けられないはずなので、ステッカー好きの筆者は、ギャラリーで購入する時、いつも「これは本物のステッカーじゃないよね」と思っています。ご縁があって、たまたま入手できたA評価のステッカーを数枚、持っていますが、あまりにも素晴らしい作品なので、大事に保管しています。このレベルのものこそ、本来は街中に貼るべきだとは分かっていても、です。人間の好きなものを私有したいという欲望、エゴというものには限りがありませんね。
本稿では、本来、評価や定義づけとは関係のないステッカーの世界を、筆者の独断と偏見で分析してしまいました。このような行為がステッカーの世界を窒息させるかもしれない恐れがあることはもとより承知しています。好きでたくさん見ていると、どうしても審美的な価値観で優劣を感じてしまうのは確かなので、「(自分は)無邪気だなー」という自覚を持ちながらも、あえてステッカーの優劣を評価するという蛮勇ぶりを披露した次第です。ただ、言い訳ではありませんが、私ごときの評価付け(格付け?)ごときでステッカー関係者の皆さんが萎縮したり、動揺したりするわけもないので、私は最初から安心していますが。
筆者の場合、集めたステッカーは自身が日々使うノート、メモ帳、スクラップブックなどにべたべた貼っています。本当は、平面の任意の場所に1枚だけピシッと貼って、空間を引き締めたいのですが、実際は空間を埋め尽くすために大量のステッカーを貼りまくってしまうことが多いです。これは私だけの傾向ではありません。大きな旅行用トランクに多くのステッカーを貼っている人がよくいますよね。「自分は旅慣れている国際人です」というメッセージにも受け取れますよね(失礼)。また、パソコンのケース上面にもステッカーをたくさん貼っている人もいます。こちらの場合、「私はクリエイティブでオシャレな人間です」という主張を秘めているようにも見えます(これまた、失礼)。自己顕示欲というにはあまりにもささやかな自己主張、個性の開示としてのステッカー貼付はなぜか、空間を大量のステッカーで埋め尽くします。
どうして、そうなってしまうのか?
タトゥーを補助線として考察すると、ステッカーの謎も分かるような気がします。タトゥーを体にいれる方は、一か所(小さな部分)にとどまらず、身体の各所にどんどん広がっていく傾向があります。隙間を埋め尽くそうとする意思は、ステッカーの貼られ方とそっくりです。この理由を考えると、ずばり「魔除け」こそがステッカーやタトゥーの理由だという気がします。皮膚でもパソコンでもノートでも、何も防護をしていないまっさらな平面には、邪悪なものが入ってきやすい。それを守るために、ステッカーを貼り、タトゥーを彫る。隙間があれば、そこから悪が入り込む恐れがあるから、どんどん増殖をさせていくしかないわけです。
完全にファッション感覚でタトゥーを入れる方は、アクセサリーの変形版と捉えていらっしゃるので、どんどん増えることはないと思いますが、ファッション感覚ではなく、もう少し本気の方の場合は、魔除けであったり、「(精神的にもっと)強い人間になりたい」という祈りが込められていると思うのです。日本でも危険な環境で働く方たちが彫り物を施すケースが多かったことを考えると、どんな状況でも怯まず、勇気を持って困難と立ち向かいたい、という決意表明こそがタトゥーであったようにも思える訳です。
身体へのタトゥー、ノートやPCへのステッカーを大きな街へと“応用する”とどうなるでしょうか?
グラフィティは街という大きな身体に施されたタトゥーに見えてきませんか?
街のあちこちに増殖していくステッカーは、街という大きなノートに貼られていると思えませんか?
金儲け至上主義で猪突猛進していく社会からは、いともたやすく経済的弱者、精神的弱者が切り捨てられていきます。そんな無情な社会に対して“悪魔祓い”を敢行するためにグラフィティは描かれ、ステッカーは貼られていると言えなくもない。
単なる犯罪行為と片付けてしまう訳にはいかない、グラフィティ&ステッカーの前向きな“意義”を筆者は感じてしまうのです。
丁寧に観察すると、グラフィティにもステッカーにも、暗黙のルールが存在しています。「描いてもいいところ、貼ってもいいところ」と「描いてはダメなところ、貼ってはダメなところ」というのが明確に区分けされているようにしか思えないのです。単なる自己顕示欲からイタズラ感覚で行う方からは、この区分けは感じられませんが、自身のやっていることの意味を明確に自覚している方には、ある種の倫理観、秩序感覚が自ずから備わっているということです。
私が本稿で書いている、諸々の言説、「こいつ何言っているの?」と呆れている方もいると思います。しかし、街を隅々まである種の身体として観察するという行為をじっくり継続すれば、徐々に私の言っていることの意味を理解していただけるのではないでしょうか?
冷酷非情な現代社会という魔物に対して、何とか抗せんとする弱き人間のレジスタンス、悪魔祓いとしてのグラフィティ&ステッカー!
そんな視点を持ちながら、あなたも街歩きをしてみませんか?
きっと新しい発見がありますよ。(2025年7月19日9時48分脱稿)