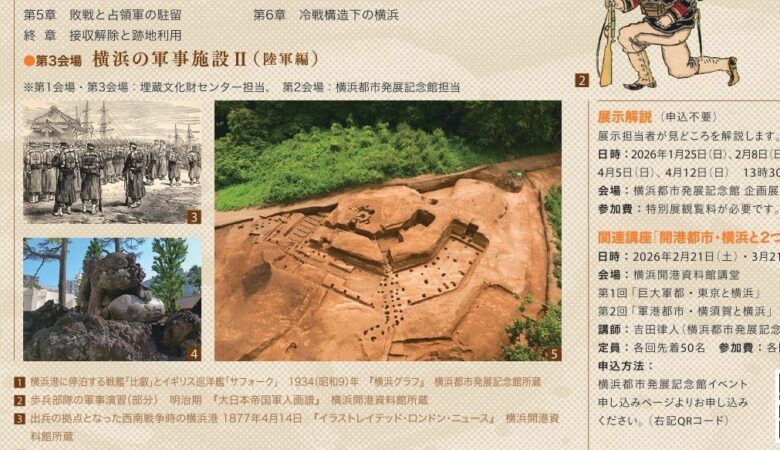【みんなで実/家に帰ろう】
突然ですが、皆さん、実家にちゃんと帰っていまか?
私は全然、帰っていませんが、良識ある皆さんはちゃんと帰りましょうね。ご両親はいつまでもあなたが子どもだったころと同じ姿はしていませんよ。どんどん老いていきます。定期的に実家に帰ることによって、親御さんの肉体的変化や実家の老朽化などなど様々な気づきを得ることができるのです。
儒教道徳に徹底的に抵抗することを人生のモットーとする筆者が、こんな抹香臭いことを書いているのには訳があります。2025年3月23日に閉店してしまったアートショップ、ギャラリー「NADiff a/p/a/r/t」(東京・恵比寿)のビルにいつの間にか、非常に有名な言葉が書かれていたからです。

ナディッフが入居していたビルの入り口横に大書された「実家帰れ」
ナディッフが入居していたビルの入り口左脇の壁に「実家帰れ」の4文字が黒のスプレーで大書されています。この4文字は、ステッカー化もされていて、都内の電柱などに貼られているのを見かけたことがあります。
ステッカーは小さすぎて、いまいちインパクトに欠けるのですが、グラフィティとして書かれていると、そのサイズの大きさが思わぬ効果を生み出すことに筆者は気付いてしまいました。

赤い支柱(右)
出入り口前には、真っ赤に塗装された支柱が設置されています。「実家帰れ」と支柱の間には若干の距離があるため、支柱よりも前に立って写真を撮影すると「実家帰れ」の4文字しか撮れません。しかし、支柱の後ろ側に立って撮影すると「実家帰れ」と支柱が同時に撮影できるのです。
己の立ち位置を右側、つまりドアの方向に寄れば寄るほど、真っ赤な支柱は、「実家帰れ」の左側に移動していきます。そして、少しずつドアの方に寄りながら、写真を何枚も撮っているうちに決定的瞬間(少し、大袈裟ですね)が訪れました。「実家帰れ」の4文字が見事に赤い支柱によって分断されてしまったのです。「実」と「家」が真っ二つ。「帰」と「れ」がやはり真っ二つです。

自分の体を右に移動させると、赤いバーは左に動き、ついに実家を分断した
実家とは何ぞや?
帰ることは正しいのか、それとも正しくないのか?
そのような批評的な問いかけを、グラフィティと支柱が生み出す視覚的なイタズラから感じ取りました。
と同時に、「実家(に)帰れ」と作者が呼び掛けているのではなく、まとわりついてくる実家的なるものに対して、作者が「実家(よ、向こうに)帰れよ(戻れよ)」「実家なんかあっちに行ってしまえ」と拒絶の意思を示していると考えることもできると思いました。
作者が、そこまで計算して、この場所に「実家帰れ」を書いたのかどうか、私は分かりません。ただ、グラフィティに限らず、作品と言うものは、作品単体で成立するものではなく、周囲の環境も含めて鑑賞することによって、より味わいが深くなるものだという事実を改めて教えられた気がしました。
家に真「実」の家なんてありますか? 実の家があると仮定するなら、虚や偽りの家もあることになってしまいます。偽りの家、ってなんだそりゃ、という感じですよね。どんな形態を取っていようが、どんな中身であろうが、家は家、です。「実家」という言葉の中に潜む、排他性を鋭く批評しているような気がして、私は、「実家帰れ」という作品がとても気に入りました。
と、同時に「実家帰れ」を見ている時に、私の頭の中にある風景が瞬時にしてよみがえりました。横浜駅とその周辺地域で何度も見かけた、私が勝手に「オペラおじさん」と名付けている方の歌唱風景です。
彼は、終電後の横浜駅構内や、朝4時くらいの「野毛の切通し」と呼ばれるエリアの路上などなどで、それはもう、大きな、大きな声量でカンツォーネやオペラを歌いまくっているのです。夜の闇、人もほとんどいないような場所を前に前に歩きながら、彼は歌い続けています。お酒に酔っ払っているのでしょうか? 私には分かりません。そのオペラおじさんのレパートリーの一つがナポリ民謡「帰れソレントへ」なのです。
帰れ君 ふるさとの町
このソレントへ帰れよ
自分に陶酔しきったかのように、朗々と歌い上げるおじさんに月光が注ぎます。しかも、このおじさん、結構、歌唱力があるのも心憎いんです。決して、下手じゃない。だから、聞き入ってしまう私がいます。オペラおじさんは、深夜から未明にかけての横浜市内にしか登場しません。遭遇したら、かなりラッキーです。
少し話しが脱線しましたね。元に戻りましょう。「実家帰れ」を見たときに、私の頭の中では、なぜかオペラおじさんの「〽このソレントへ帰れよ」が鳴り響きました。また、同時に過去のナディッフと自分自身とのかかわりも思い出しました。
2012年2月19日には、オーストリア・ウィーンで長年、活動を続けるアーティストの丹羽良徳さんと「トランスナショナルな個人映像記述術」をテーマにトークしたこともありました。また、数多くの素敵な展示をギャラリーで拝見し続けました。螺旋階段をつたって下方に広がる、やや小ぶりで個性的なあの空間をもう味わえないんだと思うととても寂しいです。私にとって、ナディッフは間違いなく「大切な家」だった。もはや、帰ろうにも帰れない「家」になってしまいましたが。
入り口の「実家帰れ」を見ること。「帰れソレントへ」の歌声を想起すること。そして、ナディッフの前に立ち尽くし続けて生きるわけにはいかない私が存在すること。私自身は常に時空を移動しています、完全に「静止(=死)」するまでは。
さあ、あなたは「実/家」に帰りますか、それとも帰りませんか。すべては、あなた次第です。あなたが決めることです。
【風化恐るべし!】
栃木県の足利駅から約1・5キロほど離れた場所に、龍泉寺美術館という隠れたアートスポットがあるのは皆さんご存じですか?
棟方志功、俵屋宗達、横山大観、伊藤若冲らの名品と出会えますので、筆者は足利を訪れる際はちょくちょく鑑賞しに行っています。つい最近も、足利市立美術館の展示「橋口五葉のデザイン世界」を見に行ったついでに龍泉寺美術館にも足を運んだ次第です。

足利・龍泉寺美術館の近くで見つけた扉
鑑賞後、足利駅の方に徒歩で戻っている途中、私は妙な扉を発見しました。誰も人が住んでいなさそうな家ではあるものの、まだ建物そのものはしっかりしていそう。廃墟未満、でも結構無人になってから時間が経過しているような家の扉なのですが、遠目で見た時に、やけに模様が美しく、凝って見えたのです。
近づいて、じっくり鑑賞してみました。すると、これは「模様」ではないことが判明しました。筆者の分析結果を披露いたしますね。
この扉はコストを削減するために、また軽量化するために、木材をほとんど使っていません。ペラペラで薄い縦長のベニヤ板を用意し、細い棒を「日」の字形で接着し、フレーム部分を作成。上下に二分割された空間上にミツバチの巣のように正六角形の形状をした立体のボール紙を挟み、あとは上からベニヤ板を接着すれば完成です。

雨風にさらされ、ボール紙のハニカム構造はすっかりぐちゃぐちゃになった
いわゆる「ハニカム構造」をボール紙で作り、それを2枚のベニヤ板の間に挟み込んでいるのです。このような、安直な作りの扉は時間の経過と共に急速に劣化していくのです。扉手前のベニヤ板が割れ、剥がれ、最終的にほとんどなくなってしまいました。ボール紙のハニカム構造は、多分、最初は美しい六角形だったのが、風雨にさらされて、四角形やゆがんだ三角形に変容してしまいました。この変形したハニカム構造が偶然、生み出した形象が私の目をひいたのです。
私は某県にある大きなアンティークの家具屋さんでご主人にうかがったお話しを思い出しました。「安物の家具は、良い木をほとんど使っていない。家具の表面付近に本物の木を薄くスライスして貼っているだけの粗悪品が結構あるので気を付けなさい」。100%木材を使用して、100年たっても使える本物の家具は、それなりの重さがあるそうです。
本当は安物のペラペラ家具なのに、「高級家具」を装って販売されるケースもあるそうなので、読者の皆さんも本当に気を付けてください。
足利の安物扉の場合は、たまたま、風化によって破壊された表面が面白い形を生み出してくれましたが、これも実用性を考えたら、無価値の扉です。表面だけきれいに整えてはいても、内実がスカスカでボロボロなものには手を出さないのが賢明と言うことです。
これが家具や扉なら、まだ買わなければいいだけですが、「政治」「経済」「教育」だと困ります。表面だけきれいで中身がないと、困るのは国民です。私たちが高い税金を納めている「国家という名の家具」が風化して、ぼろぼろになっていないか、私たちは常に注視する必要性があるーーそんな真面目なことも足利の安物扉からついつい考えてしまいました。(2025年5月18日16時45分脱稿、5月22日8時53分に一部加筆)
*「彩字記」は、街で出合う文字や色彩を市原尚士が採取し、描かれた形象、書かれた文字を記述しようとする試みです。不定期で掲載いたします。