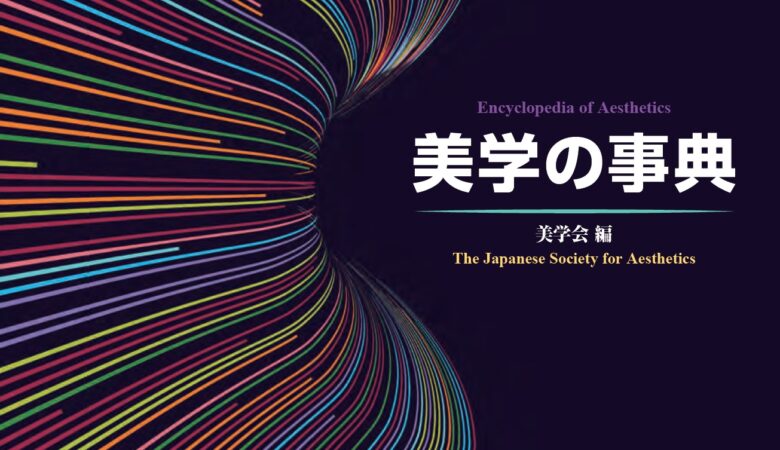厳島(宮島)
MAFIN(Miyajima Art Festival in the Narrative)
会期:2025年4月26日(土)〜2025年5月25日(日)
会場:宮島弥山大本山 大聖院
開館時間:9:00 〜 17:00
入場料:無料
住所:〒739-0592 広島県廿日市市宮島町210
URL:MAFIN(Miyajima Art Festival in the Narrative)
端的に言えば、2014年秋に藤田直哉が『すばる』で発表して広く話題を呼んだ「前衛のゾンビたち――地域アートの諸問題」が提起したのは、1990年代以降日本各地に広まった地域名を冠した期間限定の芸術祭は「クオリティが低いのではないか」という問題である(1)。
まず前提として、「大きな物語」が失われたポストモダンの状況では、芸術作品のクオリティを測る価値基準が失われる。また、市場経済が進展して万物が交換価値に還元され、情報社会が発展して万物が記号化されると、芸術作品も物体性よりも関係性が重視される。さらに、「芸術のための芸術」が先鋭化して芸術作品が自閉的になると、一般人から理解されない「現代美術」と化すと共に、外見上は絵画と彫刻という伝統形式の内的な完結性よりも、形式打破による外的な連関性が意識され「インスタレーション」が隆盛する。
こうした世界的な状況下で、1990年代以降の日本では、長引く不況と少子高齢化により衰退する地方を活性化するために、国は地域振興政策に力を入れ、地方自治体も「村おこし」に取り組む。そうした中で、1980年代のバブル期に地方創生事業の主役であった「箱モノ」としての「美術館」設立が恒久運営のコスト苦により避けられるのに代わり、新たに日本全国で大から小まで乱立するようになったのが、期間限定で開催される「現代美術」による「インスタレーション」を主流とする「芸術祭」である。
しかし、そうした「芸術祭」には困った問題がある。それは、公金が使われる場合でさえ展示される芸術作品のクオリティが問われないことである。なぜなら、そもそも現代美術は「よく分からない」上に、インスタレーション主体の公共事業としての「芸術祭」は多少プラスの人的交流や経済効果をもたらすので、芸術上の議論は棚上げされる。そこでは、現代美術が当初持っていた前衛的革新性は弱まり、ゾンビのように形骸化した紛い物が横行する。また、郷土作家や迎合作家を重視する分、作家性の低いアマチュアや二流作品も紛れ込む。そのため、批評に値する意義深い作品が少なく発展性も乏しい。従って、そうした一見賑やかだけれども中身の薄い「芸術祭」は、実際には「地域の滅亡の際の鎮痛剤」(38頁)に過ぎないことになる。
それにもかかわらず、こうした作家の自律よりも制度の維持を優先し、芸術作品の自己完結よりも様々な過程や関係を尊ぶ「芸術祭」は、日本の「和(≒内輪)」を尊重する文化と親和性があるので無反省で大いに流行する。その際、現状を肯定する舶来思想としてニコラ・ブリオーの「関係性の美学」がしばしば引用されるが、実はブリオー自身はこの用語を反商業主義の文脈で用いており、関係性の提示と芸術作品のクオリティを直接結び付けている訳ではないという日本独特の奇妙な誤用現象も発生する(2)。
こうした藤田の提出した「地域アート」批判が巻き起こした反響は非常に大きかった。あれから、約10年。そうした批判を受け止めて、今日地方ではどのように意欲的な芸術祭が開催されているのであろうか。筆者がその価値ある真摯な試みの一つとして注目するのが、現在広島県の厳島(通称「宮島」)で開催中の「MAFIN(Miyajima Art Festival in the Narrative)」である。
◇◇◇

厳島神社 大鳥居

厳島神社・大聖院・弥山
広島湾の北西部、瀬戸内海に浮かぶ宮島は、古来聖地とされてきた。島全体が御神体とされ、神社仏閣も数多い。
一番有名な厳島神社は、水の守り神である宗像三女神を祀り、全国に約500社ある厳島神社の総本社である。満潮時に波間に浮かぶ朱塗りの大鳥居や、平清盛が奉納した豪華絢爛な「平家納経」でも名高い。1996年には、ユネスコの世界文化遺産にも登録されている。
その背後には、島内最高峰の弥山がある。この弥山で修業した空海が、山頂から山麓にかけて約1200年前の806年に開創したと伝わる真言密教の寺院が大聖院である。大聖院は、厳島神社の別当寺となった真言宗御室派の大本山であり、日本三大厄除け開運大師の一つとされる。なお、山頂付近にある不消霊火堂では空海が護摩修法で用いた火を「きえずの火」として長年守り続けており、広島平和記念公園の「ともしびの火」の元火にもなっている。

大聖院 境内
元々、今回が初回となるMAFIN(Miyajima Art Festival in the Narrative)のきっかけは、大聖院境内の厳島御室会館の落慶記念で5月17日に開かれるテクノオペラ「観音抄」の会期前後に、現代美術の展覧会も同会館や境内寺院で「大聖院アートミッション」として開催することを第77代目座主の吉田正裕氏が決定したことである。
これを受けて、広島市立大学大学院の博士後期課程に在籍して彫刻を専攻しつつ地域文化の実践研究をしているイタイミナコを実行委員長として宮島芸術祭実行委員会が発足し、サイトスペシフィックな展覧会やアートプロジェクトの企画運営を数多く手掛ける戸塚愛美がキュレーターとして東京から招聘された。
宮島は、人々の平和と安寧を祈る日本有数の国際的な信仰空間である。また、広島は本年2025年に被爆80周年を迎える。そこで、MAFINのテーマは「祈り・平和・時間」とし、現代美術を通じてこの土地に根差した物語を丁寧に紡ぐことが目指された。それは、「物語(ナラティヴ)」は心の居場所を作ることで「癒し(ケア)」に繋がるからである。そのため、広島にゆかりの深いアーティストとして、康夏奈、久保寛子、Chim↑Pom from Smappa!Groupの3組が選出された。
◇◇◇


康夏奈《Beautiful Limit》2010年
康夏奈は、1975年に東京都で生まれ、2002年に広島市立大学芸術学部デザイン工芸学科を卒業した。ロサンゼルス、フィスカルス(フィンランド)、瀬戸内海の小豆島でアーティスト・イン・レジデンスをした後、小豆島に移住している。2010年から吉田姓で展覧会活動をしていたが、2016年に在日韓国人の父親の姓である康に変更している。
康は大学時代に登山を始め、日本国内のみならず、ヨセミテ、イエローストーン、ニューメキシコ、ボルネオ、ノルウェーのフィヨルド等の世界中の難山に挑戦している。本展出品の《Beautiful Limit》は、その「美しき限界」のタイトル通り、そうした「登山の最中の危険な状態や体力の限界の時に見える自分の認識を超えた風景を捉えたい」(3)とするもので、そのクレヨンとパステルによる明快な描線と彩色は極限状況における「末期の眼」(川端康成)としての意識の明澄さを反映している。
また、康は「風景には、はじまりと終わりがない」と語ったという。さらに、夜の屋久島で海亀10数頭と自分だけになったり、ボルネオのジャングルの川沿いでクロコダイルの喧嘩に出会ったりした時に、「人間が住む領域以外に足を踏み入れてしまった」が「その世界の方がずっと大きい」と感じたという(4)。これらも、人間を凌駕する悠久の大自然の側から、つまり限定された日常意識の外側から人間の生死を見つめ直す視線と言えよう。
厳島御室会館に展示されている本作は、パネルを延々と繋ぎ合わせる構造で、本来は全て展開すると50メートルを超す大作である。さらに、康は他の作家にこの作品を描き継いでもらうことを希望していたという。康は、癌を患い2020年2月に44歳で早逝している。実は、私は今回の作品で初めて康というアーティストの存在を知ったのだが、調べてみて他にもたくさん素晴らしい作品があることに驚いたことを付記しておく。

久保寛子《ライスフィールド》2024年

久保寛子《鉄骨のゴッデス》2024年
久保寛子は、1987年に広島県で生まれ、広島市立大学芸術学部彫刻専攻を卒業し、テキサスクリスチャン大学美術修士課程を修了した。久保は、近代文明が生み出した現代社会を受け入れつつ、そこで抑圧されてきたものを現代美術を通じて再評価しようとしている。
久保が念頭に置いているのは、柳宗悦の民藝論である。つまり、柳は民衆が生活の必要から生み出す素朴な工芸品を「民藝」と呼び、その「用の美」を評価した。その一方で、「用」から離れた「美」を追求する美術品や、「利」を追求する工業品を批判した。もちろん、現代では美術品も工業品も既に生活に定着したある意味で日用的な「民藝」である。従って、ここで重要なことは、伝統的な民藝を創造してきた「心の用」、すなわち精神的な必要性であろう。
この観点から、久保は、近代文明の産物である身近な工業素材を用いて、近代文明に抑圧されてきた神話や農耕を現代美術の主題として復興することを試みる。それは、エーリッヒ・ノイマン、リーアン・アイスラー、マリヤ・ギンブタス等が先駆けとなった、心性における「グレート・マザー」あるいは「大地母神」の復権と言っても良い。そこには、近年天災や人災が頻発する時代状況の中で久保が出産を経験し、より自然で根源的な精神的必要性に回帰しようとする心の働きも加わったようだ。
実際に、本展でまず久保は、観音堂の入口の左右に日常的な工業素材である風防ネットを用いた《ライスフィールド》を展示している。「ライスフィールド」とは、日本の伝統食である米を生み出す「稲田」の意である。風防ネットには左右それぞれ青地に黄色い円が示されており、青空の太陽や夜空の満月を想起させる。また、その黄色い円の高さが左右で違うことで時間の推移と季節の循環も連想させる。さらに、風防ネットの下部は緑色で草葉を暗示している。これらが、全て透過的に風に揺らめくことで伝統的な宗教建築に違和感なく溶け込んでいる。つまり、ここでは大自然の中の人間の日々の営みの理想的な調和が含意されている。
また、堂内に入ると、厳島神社の本地仏であった本尊の十一面観音菩薩像を祀る内陣の左の部屋に、《鉄骨のゴッデス》が展示されている。ここで、久保は大自然を象徴する女神として「スフィンクス」を引用している。それは、時に生命を脅かすほど猛威を振るうと共に、常に生命を養い育ててくれる豊穣のシンボルである。仏教寺院にエジプト神話の半神半獣はそぐわないと思うかもしれないが、実は仏教の「閻魔大王」のルーツはエジプト神話の「冥王オシリス」であり、さらにここでは背後で仏に仕えている聖獣の白象や孔雀の彫像とも呼応しているので全く違和感がない。むしろ、ここでも日常的な工業素材である風防ネットにより霊妙な透過性を示すスフィンクスは、内陣の右の部屋に鎮座する弥勒菩薩像と共に本尊の脇侍として、古来人々の暮らしの中で息づいていた祈りの形を現代的に表象している。
これらの作品を通じて、久保は現代の合理的思考の行き詰まりを補う、失われた古代の神話的感性を蘇生しようとしているようだ。ここでは、久保を継続的にフォローしてきた戸塚のキュレーションが冴えている。

大聖院 客殿
Chim↑Pomは、卯城竜太、林靖高、エリイ、岡田将孝、稲岡求、水野俊紀による、2005年8月に東京で結成されたアーティスト・コレクティヴである。2022年4月に、Chim↑Pom from Smappa!Groupに改名している。
Chim↑Pom from Smappa!Groupも、広島と縁が深い。まず、2008年10月21日に、彼等は広島市現代美術館での個展に先立ち《ヒロシマの空をピカッとさせる》という作品を作るために、広島市の原爆ドームの上空に飛行機雲で「ピカッ」という文字を描き広島平和記念公園等から撮影した。翌日、これが地元の中国新聞の報道を発端に炎上し、3日後に被爆者とその関係者に対して事前告知の不徹底を謝罪会見している。結局、予定されていた個展は中止になっている。
その後、彼等は広島で被爆者や市民等との対話を持続的に続け、時にコラボレートし、様々なプロジェクトを継続していく。実際に、2009年3月には一連の騒動を検証し、被爆者団体との対談も収めた『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』を出版している(5)。それに合わせて、戦争と平和をテーマとする「広島!」展を東京原宿のVacantで開き、さらに同展は「!」を一つずつ増やしながら各地を巡回し、2011年には埼玉の原爆の図丸木美術館で「広島 !!!!」展、2013年には広島の旧日本銀行広島支店で「広島!!!!!」展、2019年にはニューヨークのArt in Generalで「Threat of Peace(広島!!!!!!)」展を開催している。なお、旧日本銀行広島支店は現存する被爆建物である。

Chim↑Pom from Smappa!Group《パビリオン》2019年

Chim↑Pom from Smappa!Group《ノン・バーナブル》2019年
また、彼等は広島の原爆を主題とする作品を制作し続けている。その内、本展では《パヴィリオン》と《ノン・バーナブル》が大聖院の客殿の大広間に展示されている。
当初、《パヴィリオン》は、広島市より平和を祈念して世界中から送られてくる大量の千羽鶴の提供を受け、2013年の「広島!!!!!」展の会場である旧日本銀行広島支店に高さ7メートルの山状に積み上げ、その内部で四方を取り囲む膨大な量の折鶴を体験できる立体作品として発表された。後に、この時に用いた折鶴は、広島市の指定の下に大聖院の庭園でお焚き上げをしている。本展では、この延長上の連作として、2019年にニューヨークで「Threat of Peace(広島!!!!!!)」展の際に焚き上げられた折鶴の灰と、それとほぼ同量のまだ燃やされていない折鶴を畳の上で対置している。
さらに、《ノン・バーナブル》は、同じく広島市より平和を祈念して世界中から送られて来る大量の千羽鶴の提供を受け、それに囲まれてエリイが折鶴を一つずつ元の四角い折紙に広げ戻しつつ、そこに描かれたメッセージを英語で読み上げるパフォーマンスを撮影した動画作品である。この《ノン・バーナブル》は、2017年にアメリカで最初に展示された時には、鑑賞者は展示室の机に置かれたその広げ戻された四角い折紙を自分で再び折鶴に折り直すことができ、それらは会期終了後に再び広島市に返却された。タイトルの「ノン・バーナブル(Non-Burnable)」は、世界中から送られて来る大量の折鶴の保存に苦心する広島市が、それでもそれらを「燃やしてはいけないもの」として不燃物倉庫に大切に保管していることに由来している。つまり、この一連のプロジェクトには、折紙の総量を増やさずに平和への願いだけを蓄積するという含意がある。
ここで、Chim↑Pom from Smappa!Groupは、純粋な善意が相手の負担になることもあるという逆説をテーマにしている。しかし、そうしたシニカルな見方だけではなく、ここには、その逆説をどうポジティヴに解消するかや、世界中の人々の反戦反核への本気の真剣な祈念や、そして広島市はたとえ負担になってでも世界中で一人でも多く平和を祈願する人々の数が増加することを心から切望していること等も多層的に表現されている。
筆者自身は、Chim↑Pom from Smappa!Groupの芸術活動は、常に誰もが看過している矛盾や陥穽を子供のように純朴にユーモアを交えて取り上げるところに一貫した特徴があると考えている。ただ、それだけではなく、彼等の魅力は、人間社会のリアルな現場では常に物事には複雑な両面性や多義性があることもしっかり表現するところであると考察している。

折鶴のお焚き上げ法要
前述した通り、Chim↑Pom from Smappa!Groupは、2013年に最初の《パヴィリオン》で使用した大量の折鶴を大聖院の庭園でお焚き上げしている。大聖院では、それが一つの機縁となって、現在まで10年以上毎年折鶴のお焚き上げ法要を行っている。会期中の5月11日には、メンバーも参加して本年のお焚き上げ法要が開催された。こうした大聖院に縁深い継続的な物語(ナラティヴ)もまた、彼等が本展の出品作家に選出された理由の一つである。
なお、メンバーの一人の水野俊紀は、2013年に旧日本銀行広島支店で開いた「広島!!!!!」展を手伝ってくれた、広島在住の本展出品作家の久保寛子と2016年に結婚して広島に移住した来歴を持つ。水野と久保は、2017年に旧「原爆スラム」の場所に建つ市営基町高層アパートの一角に「オルタナティブスペースコア」も設立している。ここは、広島におけるジャンルを超えた芸術文化の一つのハブとなり、後に二人が千葉に移住した後も地元の芸術関係者に受け継がれ現在も一般社団法人として運営されている。この「オルタナティブスペースコア」で5月10日に開催された本展関連トークイベント「広島の残影」では、参加していたメンバー達と、権鉉基、カルロス、松波静香等の地元関係者達が、アットホームな雰囲気で交流していることに筆者はとても感銘を受けた。
2008年の《ヒロシマの空をピカッとさせる》では、Chim↑Pom from Smappa!Groupは当事者意識の低さを批判された。しかし、そのことを真摯に反省し、それから15年以上誠実かつ持続的に広島の被爆問題と向き合ってきた彼等をもはや当事者意識が低いと非難できる人間は一人もいないだろう。むしろ、筆者が彼等の作品を見て深く考え込まざるを得なかったのは、当事者性の問題以前にそもそもなぜこうした広島や長崎の原爆の悲劇が起こらなければならなかったのか、そしてまたなぜ今もなお世界では戦火の悲劇が絶えないのかという問題についてである。
なお、Chim↑Pom from Smappa!Groupには、他にも被爆直後に採取され現在も灯し続けられている原爆の残り火を世界中の美術館に分火していくことを目指す2018年の《We Don’t Know God》という作品がある。そうした彼等の芸術活動は、約1200年間「きえずの火」を守り続ける宮島や、それを分火した広島平和記念公園の「ともしびの火」と極めて呼応的に感受されたことも付言しておこう。
◇◇◇
このように、今年新たに開幕したMAFIN(Miyajima Art Festival in the Narrative)は、小規模だが非常にクオリティが高く密度の濃い内容であった。現在、全国各地で開催される芸術祭は、出品作家の数が多く会場も広大な場合が多いが、実際に宮島のような観光地では、限られた滞在時間で他の観光名所を見て回ることができるためにも、こうした小規模で密度の濃い内容の方が観光客にとって利便性の点でも印象深さの点でも有益であるように思われた。
今後、MAFINの課題は、より一層地元の芸術関係者や観光関係者と連携を深めると共に広く国内外に情報発信し、地域全体を盛り上げていくことであると思われる。大きなポテンシャルを秘めたMAFINの今後の発展に、心より期待したい。
註
(1)藤田直哉「前衛のゾンビたち――地域アートの諸問題」『すばる』集英社、2014年10月号。
(2)星野太×藤田直哉「まちづくりと『地域アート』――『関係性の美学』の日本的文脈」、藤田直哉編著『地域アート――美学・制度・日本』堀之内出版、2016年。
(3)「自身の体験から得た風景から心象風景が広がるパノラミックへ」『吉田夏奈―Panoramic Forest, Panoramic Lake―展』LIXILギャラリー、2012年。
(4)「死を見て生を知る」駆け抜けたアーティスト康夏奈が描いた世界観:朝日新聞GLOBE+。なお、(3)も本記事を参照させていただいた。
(5)Chim↑Pom『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』河出書房新社、2009年。
(写真は全て、2025年5月11日筆者撮影)