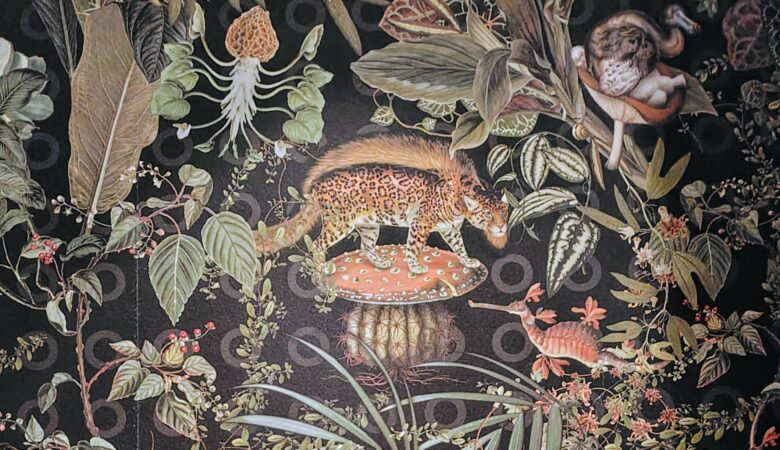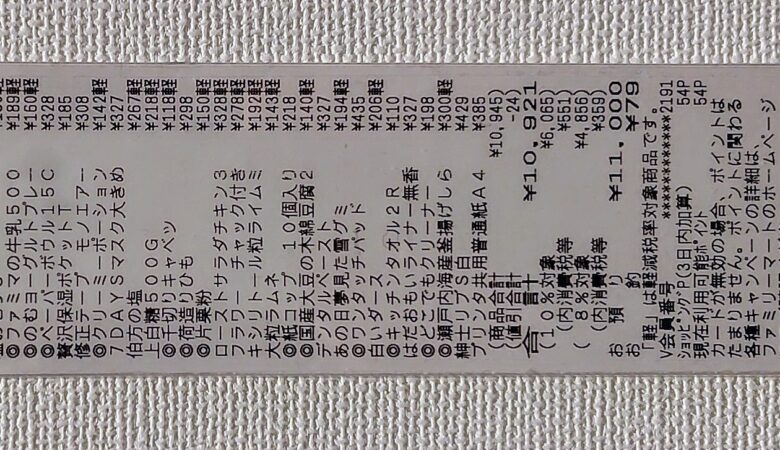質問1これまでの美術評論でもっとも印象的なものについてお答えください。
数限りなくある名著の中でも筆頭に挙げるべきは、高階秀爾氏の『日本近代美術史論』(初版1972年)である。巻頭論文「高橋由一」の冒頭における、「《花魁》違和感問題」はあまりにも鮮烈だった。
作家論から比較文化論へ、美術史から精神史へ。極めて明晰に、政治史や経済史と同じかそれ以上に、美術史が人間精神の営みや文化・社会・時代の実相を捉える学問として重要であることを啓示された。
その衝撃は、20歳の私に、美術史こそが自分の取り組むべき価値ある一生の仕事であると決意させるのに十分な魅力と説得力を持っていた。以来、本書は約30年間常に私の座右にあり、波高い暗夜の航路を指し示す一筋の灯台の光であり続けている。
誰も申し上げないので敢えて蛮勇を揮って申し上げるが、高階氏は美術史の第一人者でありながら美術史を超えている。ここでは、敢えてそれを「美術評論」と言っておこう。2012年に高階氏が文化勲章を受章されたときに分野が「美術史」ではなく「美術評論」だったことは、そのことと無縁ではないはずである。
そして、高階氏の美学的・美術史学史的背景を伺えるのが、『美の思索家たち』(青土社・新装増補版1987年)の「カッシーラー 人間と象徴」(初出1969年)である。この文脈では、高階氏の処女作『芸術・狂気・人間』(番町書房・1966年)における、最初のカッシーラー論というべき「かたちの誕生」が特に重要であることも付言しておこう。
これに関連して、美術の制度論的研究が進んだ現在、内的必然性に基づく意味ある形の一回的な創造こそが“芸術”であり、それを視覚的鑑賞の観点から捉えれば“美術”と見なされることを、この場を借りて一つの学説として正式に提起しておきたい。
質問2これからの美術評論はどのようなものになりうるかをお答えください。
学問制度上、私は世界で初めてポール・セザンヌに蒸気鉄道が与えた影響を解明した「美術史家」であり、世界で初めてヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を解読した「美学者」ということになる。しかし、基本的に、美術史家は存命の作家を扱えないし、美学者は評価の定まらない生な事象に取り組むのは憚られる雰囲気がある。そこで、私は芸術について既成の制度的枠組みに縛られずに自由に思考し発言するときには「美術評論家」を名乗ることにしている。
私には、「これからの美術評論はどのようなものになりうるか」はうまく予言できない。そこで、自分がどのような美術評論を書きたいかを書かせていただきたい。
個人的に、私は作品の良し悪しを判断するのが「美術批評」、作品の良し悪しではなく価値のある文脈を説明するのが「美術評論」と使い分けている。また、私の目指す美術評論は、ジャーナリズムの大衆性、アカデミズムの専門性、クリティシズムの面白性のバランスの取れたものである。そして、私にとって望ましい美術評論は、価値があるけれども世の中に知られていない作家や、有名な作家の知られていない価値のある側面を世の中に紹介することである。
高階秀爾氏は『美の思索家たち』で取り上げる本の基準について、「専門家にしか用のないような特殊な研究や論文はこれを避け、といって一般の人びとだけを対象とした通俗的啓蒙書でもなく、一般愛好者にも専門家にも意味があって、しかも単に知識を与えてくれるだけではなく、美術に対する新しい見方を教えてくれる古典的名著」(163‐164頁)と説明した。これは、そのまま私の考える理想の「美術評論」の定義でもある。
この記事の執筆中に、2024年10月17日に高階秀爾氏が満92歳にて逝去されたという訃報に接した。美術史・美術評論の世界に導いていただいた学恩に、末席の弟子として心より感謝の意を捧げます。