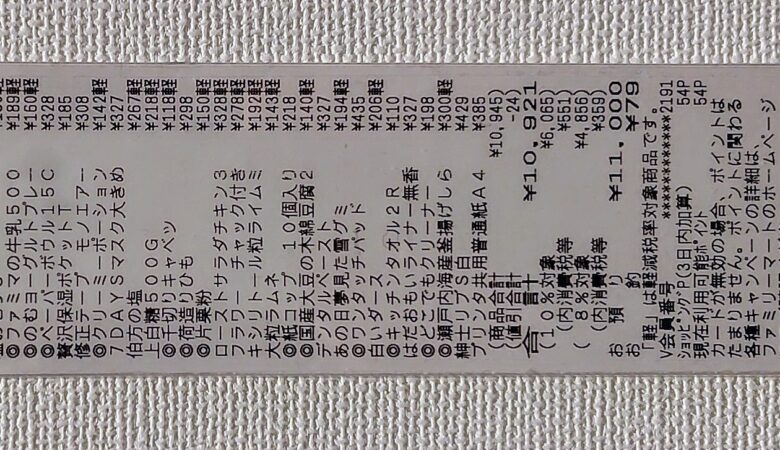美術館外観
岡本光博「イメージを突き返す」
会期:2025年9月6日(土)〜2025年11月24日(月)
休館日:毎週水曜日(祝日の場合は翌平日)
時間:10:00 〜 17:00
会場:つなぎ美術館
(熊本県葦北郡津奈木町岩城494)
現在、熊本県の津奈木町で、アーティスト岡本光博(1968‐)の個展「イメージを突き返す」が開催されている。副題は、「岡本光博つなぎプロジェクト成果展2025」である。
津奈木町は水俣市に隣接し、水俣病からの地域再生と魅力ある文化的空間の創造を目指して、1984年以来「緑と彫刻のある町づくり」に取り組んでいる。その活動拠点が、2001年に開館したつなぎ美術館である。
つなぎ美術館では、2008年から数年おきにテーマを変えて様々なアーティストを招聘し、毎年住民参画型アートプロジェクトを行っている。前回、2023年から2年間行われた「小田原のどかつなぎプロジェクト」は、「近代を彫刻/超克する 津奈木・水俣編」と題して実施され、全国的な注目を集めたことは記憶に新しい。
今回、2025年4月から2年間の計画で始まったのが「岡本光博つなぎプロジェクト」である。1年目の成果展である本展では、岡本の過去の代表作の歩みを辿れる他、彼が地元住民で構成される実行委員と意見交換しながら構想した2年目に向けた作品プランが展示されている。

岡本光博氏
一般に、アーティストとしての岡本光博の名前は、ブランド物のバッグを思わせる生地で縫製されたバッタ型のオブジェ「バッタもん」シリーズや、人気漫画のネコ型ロボットが溺れているようなオブジェ「ドザえもん」シリーズで知られているだろう。これらが典型的に示すように、岡本の作風の第一の特徴は言葉遊びとブラック・ユーモアである。
マルセル・デュシャン(1887‐1968)以降の現代美術には、一つの潮流としてこの言葉遊びとブラック・ユーモアの系譜がある。そもそも、「ブラック・ユーモア」の語源自体、1935年のアンドレ・ブルトン(1896‐1966)によるジョナサン・スウィフト評とされる。
同時代の現代日本美術では、この系譜にはサブカルチャーが持ち込まれることが多い。代表的な作家としては、1960年代生まれの村上隆(1962‐)と会田誠(1965‐)や、メンバー全員が1970年代後半から1980年代前半生まれのChim↑Pom from Smappa!Groupを挙げられる。その作品のクオリティの高さにおいて、1968年生まれの岡本は彼らに匹敵している。将来、もし他の三者が美術史の教科書に載るならば、岡本も載らないということは考えられない。

参考 岡本光博「バッタもん」シリーズ 2007年-2010年
ブラック・ユーモアは、誤解されやすい。なぜなら、本来笑ってはいけないものを笑いの対象にするからである。
そこでは、主に生死・政治・社会・文化等に関わる禁忌やセンシティヴな問題が扱われる。メッセージとして強烈である分、関係者にとっては無神経や不謹慎と受け取られる場合がある。また、皮肉を基調とし、反語や言外の意味を含むために読解には高度な共通理解が必要であり、ストレートに受け取られた時には反発を招きやすい。特にSNSでは前後の文脈が切り取られて、意図がねじ曲がって伝わりやすい傾向がある。さらに、それが高度な知的・感性的リテラシーを必要とするアート作品となればなおさら抵抗や曲解を招きやすいことになる。
特に、他の三者と比べても岡本は誤解されやすい。その理由の一つは、他の三者が基本的に東京を拠点としているのに対し、岡本は京都を拠点としているからである。そのため、報道メディアの取り上げ方も相対的に低く、説明不足のまま表層的なイメージだけが流布して無用な反感を買ってしまいがちである。
また、岡本作品の風刺の「毒」は、他の三者に比べても相対的に強い。確信犯的に「腫れ物」に触る作風であり、取り上げれば人の神経を逆なでしかねない政治問題や社会問題を敢えて取り上げるところがある。そして、毎回急所や核心を的確に突くために、相手の過剰反応を引き起こし態度の硬化を招くことが多い。
実は、岡本に直接作品の解説を聞けばその真意はよく分かる。彼は悪ふざけがしたいのでも目立ちたがり屋なのでもなく、純粋にアートには世の中をより良く変える力があると信じている。岡本は極めて頭脳明晰であり、全ての作品において自分が何を意図しているのかきちんと理解している。ただ、彼自身はアーティストとして、作品はタイトル以上に言葉で説明すべきではないと考えているらしい。
確かに、それはアーティストとして尊重すべき一つのスタイルである。それでも、筆者はあまりにも誤解されることの多い岡本を見ていると、例えば赤瀬川原平(1937‐2014)のように、もっと自分で作品意図を言葉で論理的に説明しても良いのではないかと思うときがある。

参考 岡本光博《ドザえもん》2017年
ここで重要なことは、岡本は決してよくいる「炎上狙いの一発屋」ではないことである。常に綱渡りの「際物」ではあっても、彼自身はアーティストとしてどこまでも生真面目に作品を発表し続けている。
実際に、よく注意して見ると、岡本の作品はいつも全て子供のように純粋な問題提起から出発している。その問いかけは、今自分の生きている状況や環境をもっとよく知りたいという素朴な欲求に基づいており、もしそこに何か問題があればその改善を促そうとするものである。
しかも、そこには常に緊張を和らげる笑いがある。それも、単なる「内輪ネタ」や「おやじギャグ」ではなく、老若男女に通じる分かりやすい笑いである。複雑な背景事情を持つ問題を扱う場合でも、決して説教臭くなく誰にでも分かる形でその要点を簡潔に引き出す手腕には誰もが感服せざるをえないだろう。
また、岡本の作風のもう一つの特徴は、職人気質で「芸が細かい」ことである。実際に、彼の作品はコンセプトはもちろん造形においても極めて細部に至るまで作り込まれており、手を抜いたところが全くない。本展初日の開幕記念対談において、今回の岡本の対談相手で学芸員として長く交流のある工藤健志田川市美術館館長も指摘したように、岡本の作品は一貫して造形作品としても極めて完成度の高いものである。
これらに関連して、かつて美術評論家の篠田達美がアンディ・ウォーホル(1928‐1987)の作品について、一見簡素に見えても「言うべきことを全て言い切っている」と評したことがある。それと同じ感想を、筆者も岡本の作品に抱く。
私の知る限り、岡本がこれまで発表してきた作品はほぼ全て社会的に一定の物議を醸している。逆に言うと、その社会批評の精度は見事と言わざるをえない。その点で、岡本には一つとして「駄作」がない。彼の作品が全て練り込まれクオリティが非常に高いことは、公式ウェブサイトの作品一覧を見れば明らかである。その全てに通し番号が振られているのは、彼が人生を賭けてアートで真剣勝負をしている現われであろう。
なお、岡本は1988年の自身の成人式の日に、自分なりの成人の儀式として当時開催されていた「ポップ・アートの神話 アンディ・ウォーホル展」を観に行ったと語っていることを書き留めておこう。

参考 岡本光博《UFO-unidentified falling object(未確認墜落物体)》2015年
例えば、岡本が2015年に青森県立美術館の「化け物」展に出品した《UFO-unidentified falling object (未確認墜落物体)》を見てみよう。ここでは、日本全国で販売されており、日本人なら誰でも知っている日清食品のカップ麺「U. F. O.」が、パッケージの絵柄を左右反転しつつ巨大化されて美術館の敷地内に展示されている。
これは、当時岡本が現場に下見に行った際に、UFOが墜落したという噂が話題になっていたことにインスパイアされた作品という。無粋を承知で説明すれば、インスタント食品「U. F. O.」を連想させる容器があり得ない巨大さで本当のUFOが墜落したように提示されているのが何ともナンセンスで可笑しい。

参考 岡本光博《UFO-unidentified falling object(未確認墜落物体)》2015年
なぜこれがアートなのかについては、アンディ・ウォーホルのシルクスクリーンの絵画作品や、彫刻作品《ブリロ・ボックス》(1964年)と比較すると分かりやすいだろう。
ウォーホルの作品がアートであるのは、私達の今生きている世界を的確に捉え表現しているからである。つまり、彼のシルクスクリーン絵画に刷り込まれたマリリン・モンローやエルビス・プレスリー等のスターを、私達は一度も会ったことがないのに極めて身近に感じている。時には、実際の家族や隣人以上によく知っていることもあるだろう。それは、マスメディアがそのイメージを繰り返し私達に反復し植え付けているからである。
言わば、マスメディア・イメージは私達の「第二の自然」であり、ウォーホルのシルクスクリーン絵画は「現代の風景画」である。そこでは、私達を包囲している膨大なマスメディア・イメージは色彩を変更しても本質的に変質しないことが象徴的に表現されている。
同様に、ウォーホルの《ブリロ・ボックス》が題材としているのは、日本で言えば「キュキュット」や「チャーミーグリーン」等のような、アメリカにおける市販のありふれた馴染み深い食器用洗剤製品である。大量生産・大量消費の資本主義社会に生きる私達にとって、そうした製品イメージはやはり「第二の自然」として感受される。つまり、その製品イメージの外観を木板で模したこの立体作品も、ある意味でやはり「現代の風景画」なのである。

参考 岡本光博《UFO-unidentified falling object(未確認墜落物体)》(2015年)を美術館の屋上近くから監視する宇宙人「グレイ」
成立背景において、「芸術」は「科学技術」の補完概念であり、その「反復不可能な術」としての究極は一回的なアイディアである。それにより、心を情緒的かつ理知的に安定させるために、私達が今生きている環境世界を象徴的に捉え表現するのが芸術の一つの役割である。美術史家ジークフリート・ギーディオンが説くように、それこそがどれだけ「無用の長物」に思われても必ず社会が芸術を必要とする理由である。
本来、芸術の対象ではないと思われているものが芸術の対象にされたときには滑稽味が生まれ、笑いによるカタルシスが生じる。もし鑑賞者が注意深ければ、そこからさらに自分達が現在生活している世界や時代がどのようなものなのかを相対化し客観化する認知の変容が生じる。ウォーホルを筆頭とするポップ・アートの核心は、ここにある。よく言われる、サブカルチャーや工業製品がアートかどうかという議論は二次的な問題に過ぎない。

参考 岡本光博《UFO-unidentified falling object(未確認墜落物体)》2016年
岡本の《UFO-unidentified falling object(未確認墜落物体)》に話を戻せば、カップ麺「U. F. O.」の図柄を引用するのは、その製品イメージがそれだけ現代日本の一般社会に浸透しているからである。
このとき、カップ麺「U. F. O.」の製品イメージが広く人々の意識に定着していなければこの作品はアートとして意味をなさない。その点で、これは「パクリ」ではなくある種の「リスペクト」でさえある。同様に、カップ麺「U. F. O.」の図柄が左右反転しているのも、普及したマスメディア・イメージは色彩が自由に変更可能なのと同じように、定着した製品イメージは反転させても変質しないという含意がある。
そもそも、「UFO-Unidentified Flying Object(未確認飛行物体)」という科学的に証明されていないものが日常的に人口に膾炙し、さらに市販のカップ麺の製品名に使われているのも、改めて考えてみれば奇妙である。ユングによればUFOは集合的無意識の産物であるが、たとえそうだとしても、得体の知れないものが庶民的なインスタント焼きそばの製品名として流通している現実は、いかに気付かない内に私達にとってオカルト的なサブカルチャーが自明で違和感のないものになっているかを示す具体例であるだろう。
そのように、笑いのカタルシスに続く認知の変容により、私達は自分自身の周囲を取り巻く状況や環境を新鮮な目で深く把握することができる。それは、紛れもなくアートの持つ力の一つである。その意味で、岡本を「現代日本のアンディ・ウォーホル」とまで言うのは言い過ぎにしても、「現代日本のポップ・アーティスト」の代表的な一人とは言えるだろう。

参考 岡本光博《UFO-unidentified falling object(未確認墜落物体)》2018年
もちろん、それでも題材にされた企業としては商標や著作権に留意して欲しいと注文を付けざるをえないだろう。すると、問題は、アートとそうでないものの境界はどこにあるのかや、著作権や「表現の自由」とは何かという次のフェーズに移行することになる。
実際に、岡本はその後もこの「UFO」シリーズを、池に墜落させたり高速で回転させて図柄を認識できなくさせたりする作品を発表している。さらに、日清食品から送られてきたクレーム文章を取り込んでそのまま作品化もしている。それらにより、両者の関係はどんどん抜き差しならなくなり緊張感が増していくが、ある意味でこれは岡本の作風に内在している方向性の必然的な発展であり、アーティストとしては誠実な行為といえる。
なお、この「UFO」シリーズでは、周囲に宇宙人のステレオタイプである「グレイ」が添えられている等色々と芸が細かいことも付言しておこう。

フライヤー(表)
元々、岡本は高校生の頃からアーティストを志し、石膏デッサンは芸術的創造力をスポイルするという信念から、入試科目に石膏デッサンがなく芸術教育を受けられる滋賀大学の教育学部に進学している。そして、入学後も彫塑の授業の全課題を愚直に批判し続けたために一時は退学の危機に陥るが、当時教員だった村岡三郎(1928‐2013)や鴫剛(1943-)の応援等もあり危うく難を逃れたという。
なお、おそらく岡本の影響でその後間もなく同学部では入試科目に石膏デッサンが復活している。いずれにしても、岡本の「疑問と議論」というスタイルはアーティストとしての出発点から一貫している。
1994年に滋賀大学大学院(教育学)を終了後、岡本はアメリカのアート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークに留学している。また、縁があり、宮本和子(1942‐)を通じて、ソル・ルウィット(1928‐2007)の仕事を約1年半手伝っている。
周知の通り、ルウィットは1967年に発表した「コンセプチュアル・アートに関する断章」によりコンセプチュアル・アートを確立したと言われる第一級の理論家である。同時に、彫刻家としては草創期からのミニマル・アートの中心作家の一人として国際的に名高い。
また、宮本はルウィットの助手を長く務めており、現在日本のミニマル・アートの草分けとして再評価の機運が高い。実際に、2021年に森美術館で開かれた、50年以上制作活動を行っている女性アーティスト16人を扱う「アナザー・エナジー展」でも取り上げられている。
つまり、岡本は既に20代で国際的なアートの最前線に触れている。岡本自身は、ルウィットの作風からは、言葉とイメージの関係や、作品を巡る「証明書」の持つ効力等を学んだという。さらに、その造形上の完璧主義にはミニマル・アートの研ぎ澄まされた造形意識が反映しているように思われる。
少なくとも、長期間にわたる岡本のアーティスト活動において、作風やクオリティに一切ブレが感じられないのは、早くからそうした本場の一流アーティスト達の創作を間近に見ていた経験が影響していることは間違いない。なお、岡本はクレス・オルデンバーグ(1929‐2022)が購入したルウィットの作品の定期塗り直しのために、オルデンバーグの事務所に数日通ったこともあるという。
また、岡本が帰国して設立年の1997年から1999年まで在籍したCCA北九州は、当初から日本人作家を海外に進出させることを目標としており、全部英語で運営され、海外から第一線のアーティスト達も招聘していた。この時、岡本が交流したアーティストには、マリーナ・アブラモビッチ(1946‐)、ハミッシュ・フルトン(1946‐)、ホァン・ヨン・ピン(1954‐2019)、チェン・ゼン(1955‐2000)、ケリス・ウィン・エヴァンス(1958‐)、マリア・アイヒホルン(1962‐)、グザヴィエ・ヴェイヤン(1963‐)、オラファー・エリアソン(1967‐)等がいる。
その後、さらに岡本は、ドイツ、スペイン、インド、台湾等の複数のレジデンス・プログラムに参加している。これらのことから、岡本が当初から単に国内向けではなく世界水準のアートを目指して活動していることは明らかである。
なお、2012年から岡本は、自らの作家活動に並行して、京都における美術館の集積地である岡崎地区でギャラリー「KUNST ARZT」を運営している。これは、岡本が商業主義や経済事情に左右されずに作家活動を貫徹するための方策でもあり、その筋の通った信念と行動力はやはり並いるアーティストの中でも抜きん出ている。
ちなみに、ギャラリー名の「KUNST ARZT」はドイツ語で「芸術・医者」を意味し、芸術を通じた社会医療の含意がある。おそらく、そこには「劇薬」も含まれるだろうが、ある意味でこのギャラリーも岡本の「芸術作品」の一つであり、京都はもちろん全国的に見ても最も先鋭的で前衛的な展覧会活動を行っていることを付記しておこう。

フライヤー(裏)
1837年にアンデルセンが発表した有名な童話に、『裸の王様』がある。詐欺師の仕立屋が「馬鹿者には見えない生地」で作ったという服を、「見えない」とは言えない王様が裸の上に着ているふりをして歩いたところ、子供から「何も着ていないじゃないか!」と指摘されて恥をかいたというあの童話である。
この童話の教訓は、裸で歩くのが恥ずかしいということではない。権威の欺瞞性こそが、恥ずかしいということである。
岡本の作品を見るたびに、筆者はいつもこの「王様は裸だ!」と叫ぶ少年を思い出す。岡本は、生粋の京都人らしく反骨精神の塊であり、権威主義的なものを見るとつい茶化さずにはいられないらしい。そして、たとえ相手とトラブルになっても、普通は空気を読んで矛を収めるところをどこまでも正論で挑みかかっていく。相手からすれば、これ以上なく「ややこしく困った奴」であり、岡本が「ミリタント(好戦的)なアーティスト」と形容される所以であるが、それでも彼の作品には常に毒を含みつつも朗らかな笑いがあり、間違っていないことについては一歩も引かないという強固な信念が一貫している。それは、一流のアーティストに必要な資質でもあるだろう。
実際に、岡本は本展初日の開幕記念対談で、「日常を斜めから見るのはアートしかできない」と発言している。それは、筆者の言葉では「カタルシスと認知変容」であるが、「より良く生きるための気付き」と言い換えても良い。自明に思われていたこと、自明に思わされていたこと、気付いていなかったこと、気付いていたけれど口に出せなかったこと、アートがそれらを表現する手段の一つであることは確かである。
岡本の作品について言えば、まずアートとして鑑賞する度量と心の余裕が欲しい。その前提を無視してしまうと、作品に込められた真意を巡る本来深めるべき議論も全て吹き飛んでしまうからである。
気付かぬ内に私達を洗脳しているパブリック・イメージを、飄々と洒落のめして突き返し、鑑賞者に新たな視野を開かせること。それこそが、アーティストとしての岡本の真骨頂である。本展「イメージを突き返す」では、岡本の過去作品の経緯や結末が新たに作品として再構成された「著作権の机」「表現の自由の机」「JKnell」シリーズも展示されている。その意味で、岡本の「小回顧展」ともいえる本展は、正にそうした岡本芸術の真髄を実体験できる絶好の機会と言えるだろう。
(作品写真は全て作家提供)