幕末明治の先覚者岸田吟香(一八三三(天保四)年‐一九〇五(明治三八)年)が、近代日本洋画の発達に深く関与し、それが息子岸田劉生(一八九一(明治二四)年‐一九二九(昭和四)年)に影響を与えていることは既に多くの研究が示唆している[i]。二〇一四年には、その集大成といえる『岸田吟香・劉生・麗子』展が世田谷美術館と岡山県立美術館で開催された[ii]。
しかし、後の日本趣味・東洋趣味への傾倒を考えれば、日本画家の道を選んでもおかしくなかった劉生がなぜ洋画家として出発したのかは従来必ずしも明確に議論されてきた訳ではない。本章は、まずこの問題について先行研究を整理しつつ、これまであまり検討されていなかった吟香の活動拠点であり、劉生の生れ故郷である銀座という地理的条件に注目して考察する。
一 岸田吟香について
岸田吟香は、一八三三(天保四)年に、美作国久米北条郡中垪和谷村(現岡山県久米郡美咲町栃原)の裕福な農家の長男として生まれた。幼名は辰太郎で、幼少期から才覚を発揮し神童と呼ばれたという。一八四五(弘化二)年の一二歳の時に、吟香は地元の大庄屋安藤家の学僕となり、漢籍と和歌の手ほどきを受けている。また、一八四七(弘化四)年の一四歳の時には、少し開けた津山に出て漢学と剣術を学び、勤王思想の学者・歌人や文人画家等と交流している。
黒船来航の前年の一八五二(嘉永五)年、一九歳の吟香は江戸に出て、津山藩主に仕える儒学者昌谷精渓の門に入る。また、幕府直轄の国学・儒学の教学機関である昌平坂学問所でも学んでいる。続く二〇代は、江戸や大阪で儒学を学んだり、儒学者として藩に仕えたり脱藩したりしながら、尊王攘夷派の志士として活動している。
その後、薩英戦争が勃発した一八六三(文久三)年の三〇歳頃から、吟香は身を隠す必要もあって深川や浅草等の町人の中で暮らすようになり、左官、八百屋の荷担、湯屋の三助、芸者の箱丁、妓楼の主人等の職を転々として日々を送っている。
吟香は一八六四(元治元)年、三一歳の時に眼病に罹り、名医として評判の高かったヘボンを横浜に尋ねる。そして、ヘボンの治療により眼病が快癒したことで西洋医学の実用的有益性を身を持って実感することになる。また吟香は、キリスト教の博愛精神により無償で治療を行っていたヘボンの高潔な人格にも強く感銘を受けている。そうした理由で、吟香はそのまま横浜に留まり、ヘボンが取り組んでいた和英辞書の編纂を助手として手伝うことになる。

図1 ジェームズ・ヘップバーン(ヘボン)
ジェームズ・カーティス・ヘップバーン(James Curtis Hepburn:一八一五(文化一二)年‐一九一一(明治四四)年)、通称ヘボンは、吟香より一八歳年上のアメリカ人で、一八一五(文化一二)年にペンシルヴァニア州の裕福な家庭に生まれた。ヘボンは、若くして医学の博士号を取り、ニューヨークで開業して成功を収める。しかし、日本が長い鎖国の後に開国したという報を聞き、長老派教会系の宣教医として日本で布教する志を立てる。そして、安政の大獄に揺れる幕末動乱期の一八五九(安政六)年、四四歳の時に来日する。
当時、日本ではキリスト教はまだ禁教であったので、ヘボンはまず横浜で暮らすため医師として開業している。ヘボンは日本語を話せないまま精力的に活動し、士農工商の身分や貧富の分け隔てなく、治療費は一切受け取らずに五ヶ月間で三五〇〇人を診療している。その高潔な人格と医療技術の高さは、一八六二(文久二)年の四七歳の時には信用されて生麦事件(図2)の被害者の治療も依頼されるほどであった。

図2 チャールズ・ワーグマン画《生麦事件図》1862(文久2)年頃
ヘボンは、医者としての活動と並行して和英辞書の編纂にも取り組んでいる。これは、聖書を重視するプロテスタントの牧師として、日本への宣教のためには和英辞書が必要不可欠であると考えていたことが大きい。この時、見出語に使われた日本語のローマ字表記、いわゆる「ヘボン式ローマ字」により、西洋人でも日本語を発音することが可能になったことはよく知られている。その際に、日本語側の助手として、学問的素養があり、その経歴により士農工商あらゆる身分の言葉にも詳しかった吟香が大いに活躍したと言われている。
一八六六(慶応二)年、吟香三三歳の時に、ヘボンが着手から七年余りの歳月を費やした和英辞書の原稿が仕上がる。しかし、当時日本には実用的な活版印刷の技術がなかった。そこで、当時アジアで最先端の活版印刷設備を持つ長老会派の美華書館があった上海に、ヘボンと吟香は渡航して印刷校正に取り組むことになる。この時、現地には英語と中国語の活字はあったものの仮名の活字はなかったために、吟香が版下から作成して鉛の活字を作らせている。また、吟香はヘボンに辞書の書名として『和英語林集成』を提案し、その題字も書いている(図3)。

図3 『和英語林集成』初版 1867(慶応3)年
『和英語林集成』が完成した一八六七年(慶応三年)、吟香は三四歳の時にヘボンと共に日本に帰国する。それ以来、ヘボンが横浜の自宅で販売した『和英語林集成』は、一八両という高額にもかかわらず飛ぶように売れたと言う。この年、吟香はヘボンから『和英語林集成』編纂の謝礼として処方を伝授された液体目薬を「精錡水」と名付けて販売を開始している。「精錡水」は、日本最初のガラス瓶とコルク栓の液体点眼薬として人気商品になり、後に中国に販売店を広げるほど大成功を収めることになる。
この頃、吟香は目薬販売業だけではなく日本最初の事業を数多く手がけている。まず、一八六四(元治元)年に、ヘボンを介して知り合ったジョセフ・ヒコ(浜田彦蔵)と共に、海外で発行された英字新聞を和訳して販売する日本最初の民間日本語新聞『海外新聞』を創刊している。また、一八六八(明治元)年には蒸気船で江戸=横浜間を往復する最初の定期航路を開き、翌一八六九(明治二)年には氷製造販売業や石油採掘業も試みている。これらの多くは時期尚早で、事業としては「精錡水」ほどには成功しなかったらしい。しかし、こうした吟香の日本最初の事業には、単なる利益追求のみならず、一貫して人々の日常生活に役立つ西洋の先進文明を日本に導入しようとする志が窺える。
そのことは、吟香が目薬販売業に力を入れただけではなく、そこで得た利益で福祉事業に力を尽くしたことからも分かる。事実、吟香は一八七五(明治八)年から日本最初の盲学校設立に取り組んでいる。また、一八九八(明治三一)年には清国のアヘン防止事業を伊藤博文に提案したり、一九〇二(明治三五)年には中国に西洋医学を広める東亜同人会の設立に尽力したりしている。
こうした吟香の博愛精神や有益な西洋先進文明の導入は、共にヘボンに感化されたところが大きかったと思われる。そして、そうした吟香の開明的な慈善事業への取り組みは、後に見るように洋画家達の支援活動としても現れることになる。
これに加えて、吟香の事業として特筆すべきはその文筆活動である。吟香は、日本で初めて民間日本語新聞を発行しただけではなく、自ら記事を書く新聞記者の走りでもあった。これには、元々吟香に文才があったことに加え、一八六四(元治元)年以来ヘボンとの和英辞書編纂を通じて西洋語の文体に触れたことや、『海外新聞』で英字新聞の和訳に取り組んだことで、従来の漢文体に代わる新しい言文一致体を生み出せたことも大きく影響している。実際に、吟香は一八六四(元治元)年の日記『横浜異聞』や一八六六(慶応二)年の『呉淞日記』で、いち早く仮名文字を多用した言文一致体を自在に用いている。
吟香の分かりやすく機智に富んだ言文一致体は、当時の一般大衆に非常に人気が高く、一八六八(明治元)年に創刊して戊辰戦争を報道した『横浜新報もしほ草』は大評判となっている。また、一八七三(明治六)年には前年に日報社が創刊した『東京日日新聞』(後の毎日新聞)に要請されて主筆として迎えられ、翌一八七四(明治七)年の台湾出兵では志願して日本最初の従軍記者として同行している。この『東京日日新聞』は、「論説の福地桜痴、雑報の岸田吟香」が二枚看板だったと言われており、実際に三代広重の描いた浮世絵には二人の姿が描かれている(図4・図5)。

図4 三代広重《東京第一名所銀座通煉瓦石之図》1874-76(明治7-9)年

図5 図4の拡大図(左が岸田吟香・右が福地桜痴)
このように、吟香は幕末明治期に多面的な活躍をした一大事業家であり進歩的文化人であった。そして、ここではまず、彼が元々和漢の学問の素養を持つ国粋派として出発し、ヘボンとの出会いにより西洋先進文明の有用性を具体的に経験して開明派に転向し、単なる利益追求のためだけには留まらずに、博愛主義に基づいて広く一般大衆の日常生活に役立とうとした人物であることを確認しておこう。
二 岸田吟香と黎明期の洋画家達
ここで興味深いことは、吟香がこうした西洋先進文明の導入による日本最初の事業に精力的に取り組んでいた時期に、黎明期の洋画家達と深く交流している事実である。特に重要なのは、日本の洋画導入の最初の公的機関と言うべき開成所の画家達、つまり川上冬崖(一八二八(文政一一)年‐一八八一(明治一四)年)、島霞谷(一八二七(文政一〇)年‐一八七〇(明治三)年)、高橋由一(一八二八(文政一一)年‐一八九四(明治二七)年)との関係である。
黒船来航による開国から三年後の一八五六(安政三)年に、西洋文明を本格的に研究する学術機関を必要とした徳川幕府は藩書調所を開設する。これは、一八五五(安政二)年創設の洋学所をその前身とするもので、一八六二(文久二)年に洋書調所と名を改め、翌一八六三(文久三)年に開成所と改称し、一八六八(明治元)年以降は明治政府に引き継がれて開成学校となり、後に現在の東京大学となるものであった。
ここで、西洋画法研究のための絵図調出役として、次いで一八六一(文久元)年に同所内に設置された画学局で画学局出役筆頭として西洋画法の研究指導に当たったのが、川上冬崖である。冬崖は、油彩画材や実作例が乏しい中で、主に洋書の翻訳を通じて西洋画法の理論的研究に努めた。
吟香は、この文久年間に五歳年上の冬崖と知り合ったと言われている。実際に、一八六四(元治元)年の吟香の日記『横浜異聞』には「潭香冬崖柳圃にも用もないが逢いたい[iii]」という記述がある。この時期は、ちょうど吟香が尊王攘夷派の志士からヘボンの助手に転向する時期に当たっており、このことから当時吟香と冬崖の間には最新の西洋文明導入の同志という連帯感情があったことが推測される。
また、吟香は『和英語林集成』の印刷のためにヘボンと上海に滞在していた一八六六(慶応二)年に、日本の冬崖に宛てて長文の手紙を送っている。その内容は、上海を中心とする中国の美術家の報告や、翌一八六七(慶応三)年の第二回パリ万国博覧会に参加する徳川昭武一行が上海に立ち寄ったことの報告等であった。漢文調が一般的な当時において、「ままよの銀次」の署名で、「むかふじまはどうです。はやくかへつておそざくらでも見たい。とんだ魚で一盃やりませう[iv]」という異例なほど易しい言文一致体の文章で書かれているところに二人が気の置けない間柄であったことが窺える。
なお、この時に上海に寄港したパリ万博へ行く徳川昭武一行には、吟香の友人で、パリ万博に日本人商人として唯一参加出品した清水卯三郎等がいた。そして、吟香の『呉淞日記』には、「卯三さん云霞谷冬崖もここにきてみたらちがふとあてがはづれましたといふだろうとわらう[v]」と書かれているので、冬崖が上海に来たがっていたことが察せられる。
また、ここで名前が出てくるように、吟香は、同じ開成所の洋画家で、冬崖と同い年の島霞谷とも交友があった。実際に、吟香がヘボンの和英辞書編纂の手伝いをしていた一八六五(元治二)年二月四日付の『乙丑日記』には、「霞谷をとふ。るす。おかみさんにいろいろたのみおく[vi]」という記述があるので、吟香は霞谷と家族ぐるみの親密な付き合いをしていたことが分かる。
さらに、吟香の初期洋画家達との関係で重要なのが、同じく開成所の洋画家高橋由一との関係である。由一が「嘉永年間[vii]」に最初のいわゆる「洋製石版画体験」をして西洋画法に衝撃を受けた後、一八六二(文久二)年に西洋画法の習得を目指してまず入所したのが洋書調所画学局であった。
由一は冬崖の指導を受けるが、彼からは西洋画法を十分に学ぶことができなかったので、やがて横浜居留地の西洋人に直接指導を受けたいと熱望するようになる。その時に由一が相談を持ち掛けたのが、当時ヘボンの助手として横浜にいた吟香であった。
実際に、一八六六(慶応二)年八月の吟香の日記には、「十五日に江戸かぶらき、たかはしとひきたりて、のげの梅本で一盃のむ[viii]」という記述がある。そして、吟香はその幅広い交友関係を利用して由一と一緒に横浜で西洋人の画家を探し求め、結果的に由一はチャールズ・ワーグマン(Charles Wirgman:一八三二(天保三)年‐一八九一(明治二四)年)という画家を知ることになる。
吟香は由一に、伊勢勝という横浜商人への相談を勧め、この伊勢とその友人で英語のできる横山孫一郎が同行して、由一はワーグマンに弟子入りを許され、江戸から横浜まで歩いて通うことになった。実にこの時、吟香は三三歳、由一は実に不惑を目前にした三九歳であった。
その由一のワーグマン入門の翌年の一八六七(慶応三)年に、吟香と由一は上海で再会している。実は、先に述べた徳川昭武一行に由一も同行しており、吟香の同年一月一五日の『呉淞日記』には、「日本人が八九人、小船からさんばしへあがる。ひよいと顔を見やわせたのハ、かふらき立木、又あとからあがるのハ高橋佁之介〔…〕高橋云霞谷がよろしく申ました。たいそうきたがりました[ix]」と書かれている。どうやら、この上海行きには冬崖のみならず霞谷もかなり来たがっていたと察せられる。
また、由一の上海滞在日記である『上海日誌』には、同月二〇日に「岸田銀治來る」、翌朝「岸田退去」とある[x]。さらに、同月二一日には由一の手による吟香の肖像《吟香小照》(図6)が描かれており、続いて「岸桜草」「岸国華」という吟香の落款が付された漢詩が二篇書かれている[xi]。このことから、吟香と由一は上海で大いに旧交を温めたと推察される。

図6 高橋由一《吟香小照》1867(慶応3)年1月21日
また、吟香は由一に作品の買い手も紹介しており、上海滞在の翌年に吟香が病床の由一を見舞った一八六八(慶応四)年八月一八日付の手紙では、「油絵をうりこむ処がふと見つかりましたから、あなた先日中からかいておいたのがあるなら一二枚よこしてお見せ下されまし[xii]」と書かれている。さらに、吟香は由一の就職の世話もしており、翌一八六九(明治二)年に吟香は由一を当時大蔵少輔であった伊藤博文に紹介し、一八七一(明治四)年に由一は伊藤に推薦されて寺院小属という役職に就いている。
そして、吟香は文筆の上でも由一の制作を支援していた。一八七七(明治一〇)年の第一回内国勧業博覧会に由一が出品して三等花紋賞を受けた二点の内の一つ、《甲冑図》(図7)について、吟香は一八七七(明治一〇)年一〇月二六日付の『東京日日新聞』の記事「博覧会の記」で次のように評している。なお、吟香のこの新聞記事は日本最初の美術展覧会評と言われている。

図7 高橋由一《甲冑図》1877(明治10)年
弓矢鎧兜など実に本物を眼前に見るが如し。今日世に残りたる武具なるものは、聊かの変革はありと雖も、亦是我邦往古よりの遺製なりしが、此のたび兵制改革ありしに付ては、右等の武具は日々に腐朽に属するは必然なり、曽て聞く、油絵は能く数百年の久しきを保つ者なりと。若し、然らば、比画もまた後来学者の考証の一に備はらんも知るべからず。宜しく重襲して之を蔵すべし[xiii]。
当時、写真はまだ白黒で変色もしやすかったので、色彩の再現や保存性においては油彩画の方が写真よりも優れていた。吟香の着眼も、そうした油彩画の写実性に現在の写真の記録性のような実用的価値を見出したものだったと言える。
さらに、日本近代洋画史における吟香の交友関係で、また重要な意味を持つのが横浜を拠点にした五姓田派の洋画家達、特に山本芳翠(一八五〇(嘉永三)年‐一九〇六(明治三九)年)と、五姓田義松(一八五五(安政二)年‐一九一五(大正四)年)との交流である。
まず、山本芳翠は、初代五姓田芳柳の弟子で、芳柳の息子義松がワーグマンに師事していた縁で続いてワーグマンに師事した画家あり、由一にとっての弟弟子にあたる。吟香と芳翠は、一八七五(明治八)年に日本橋呉服町に開業した石版印刷所の玄々堂を通じて知り合ったと推定されている。実際に、一八七七(明治元)年に、玄々堂の亀井至一が玄々堂ゆかりの人物を描いた《玄々堂人物写生帳》における吟香の肖像画(図8)には、当時玄々堂で働いていた芳翠もまた吟香の肖像を描いたと記されている(ただし、残念ながら現在この芳翠筆の吟香の肖像は失われている)。

図8 亀井至一《岸田吟香像》1877(明治10)年
また、吟香の署名はないものの、この同じ一八七七(明治一〇)年五月三〇日付の『東京日日新聞』の次の記事は、その交友関係からおそらく吟香が書いたものと推定される。この記事もまた、由一の《甲冑図》評と同じく、日常生活のレベルで油彩画の写真のような写実的記録性の有用さを説いたものであると言える。
成ほど芳翠氏ハ弊社へも度々来られ社員の肖像も画かれしが実に虚言でハ五座らぬしゃしんありて以降孝子追慕の情と慰るに足るも油画ハ一層の精彩を加ふるものゆゑ父母の遺像などを作り置かんにハ人として長く忠孝の志を存せしむるに足るの功無しとせず画の徳も亦大ならずや[xiv]。
さらに、同一八七七年(明治一〇年)の第一回内国勧業博覧会に芳翠が出品して三等花紋賞を受賞した《勾当内侍月詠図》(図9)についても、吟香は同年一〇月二五日付の『東京日日新聞』の記事「博覧会の記」で言及している。

図9 山本芳翠《勾当内侍月詠図》1877(明治10)年
山本芳翠が勾当の内侍の図は円月東に登りて池水金波を漂すに驚き琴を止めて外面を眺め出したる横顔を燭光の照したるなど実に斯こそ有りけめと思ふ[xv]。
そして、この同じ年に吟香は林忠正に芳翠を紹介しており、この林を通じて芳翠は翌一八七八(明治一一)年にパリ万博事務局雇としてフランスに渡航することになる。その経緯を、初代五姓田芳柳に学んだ平木正次の『明治初期洋画壇回顧』(一九三六年)は次のように説明している。「翁の洋行に就ては、津田仙氏が非常に盡力したので、初め翁が洋行の希望を津田氏に漏らすと、氏は大に賛成して岸田吟香氏に話をし、岸田氏から、丁度其時巴里の萬國大博覧会へ松方伯が總裁で行かれるので、伯に頼んだのだが、伯の承諾を得て、首尾よく佛国へ渡航することになったのである[xvi]」。
芳翠はフランス到着後間もなく、この時のパリ万博に出品されていたサロン系の画家ジュール=ルイ・マシャールの《セレネ》(図10)を模写した《天女図》(図11)を、吟香に謝礼として海外便で送ってきている。この作品について、平木の『明治初期洋画壇回顧』には次のような記述がある。「銀座の岸田吟香さんお宅から使がきて、仏国の山本芳翠さんから油絵が届いたから、見に来る様にとのお話で、亀井君と同家へ拝見に上った。〔…〕図は妙齢の婦人が空中で三日月を、弓にして矢をつがえて居る天女の図であった。摸写物と察した[xvii]」。

図10 ジュール・ルイ・マシャール《セレネ》1874(明治7)年

図11 山本芳翠《天女》1878(明治11)年
そして、吟香は、芳翠の弟弟子の五姓田義松とも深く関わっている。義松は、由一の入門より少し早い一八六五(慶応元)年に一〇歳でチャールズ・ワーグマンに入門し、先に述べたように五歳年上の兄弟子芳翠がワーグマンに入門する機縁を作った画家である。吟香は、義松が一八七七年(明治一〇年)の第一回内国勧業博覧会に出品して最高賞の二等鳳紋賞を受賞した《阿部川富士図》についても、先の同年一〇月二五日付の「博覧会の記」で言及している。
芳松が画きたる富士山の夕景ハ駿府の市中より東北に望みたる図にて前山ハ日将に暮んとして淡煙模糊の間にあるに返照なほ峯頂の残雪に映じて晩霞もまた餐すべきが如し市中人馬往来の状に至りて実に真に迫りたるの妙あり[xviii]。
また、義松は、芳翠が吟香の尽力を得て渡仏した二年後の一八八〇(明治一三)年に二五歳で同じくパリに留学している。この時、吟香は義松からの資金援助を快諾し、義松に百円の餞別を贈り、それに添えて「申入迄も無御座候へども西洋江御着ニ相成候上者画学専門ニ日夜御勉強被成他年者必ズ々々世界上屈指之大家ニ御成被成候様奉祈候[xix]」と書いた同年七月六日付の書簡を渡している。
その翌年の一八八一(明治一四)年に開催された第二回内国勧業博覧会では、吟香は同年五月二一日付で再び『東京日日新聞』に「博覧会の記」を書いており、そこで「昨年の夏ごろ法国に趣き良師に就て学術の修行中[xx]」と紹介されている義松は《駿州清水湾曙ノ図》(図12)で妙技三等賞を受賞している。そして、義松が《画家デビビエの肖像》で日本人として初めて油彩画でパリの官設展覧会に入選を果たしたのは、正にその一八八一(明治一四)年のことであった。

図12 五姓田義松《駿州清水湾曙ノ図》1881(明治14)年
このように、岸田吟香の名前が黎明期の近代日本洋画史に度々出てくる背景には、吟香自身が日本最初の和英辞書編纂を始めとする西洋文化の移植に努めた進歩的知識人であった事情が大きく働いているように思われる。つまり、西洋美術という新しい文化を日本という全く異なる土壌に根付かせようと奮闘している洋画家達への共感は、決して小さいものではなかったと思われる。吟香は個々の洋画家達にとって有力な支援者の一人であり、さらに洋画界全体にとっても洋画の日本への定着の強力な推進者の一人であった。
なお、他に吟香と直接関係のあった重要な洋画家としては、下岡蓮杖(一八二三(文政六)年‐一九一四(大正三)年)を挙げられる。現在、彼は写真家として有名であるが、元々若き日にワーグマンに師事した洋画家でもある。
まず、下岡蓮杖は、吟香がヘボンの弟子として横浜に移り住むよりも早く横浜に写真舘を開設しており、吟香の最も早い時期の肖像写真を撮影している(図13)。また、蓮杖は石膏製の吟香像(図14)も制作しており、これは吟香が生前非常に大切にし、やがて劉生に受け継がれることになる。さらに、蓮杖は台湾出兵を描いた大パノラマ画《台湾戦争図》(図15)でも、日本人初の従軍記者として従軍していた吟香の姿を描き入れている。この作品について、一八七六(明治九)年四月七日付の『東京日日新聞』は次のように伝えているが、恐らくこれは吟香自身の筆によるものだろう。

図13 下岡蓮杖撮影《岸田吟香》明治初期

図14 下岡蓮杖《吟香像》制作年不詳

図15 下岡蓮杖《台湾戦争図》1876(明治9)年
余ほど評判が高いから昨日ちよッと浅草奥山の電気展覧場の前に出て居る油絵茶屋へ見物に行ましたが成るほど函館の戦争の絵も台湾の合戦の図も能く出来ました何にしても大きな物で一つの絵が巾三間に竪が七八尺ぐらゐ立て居る人物が三四尺にも見え自然と大砲の響も聞こゆる様な心地して黒煙の間から剣戦や旌旗がチラチラ見ゆる処ハ実に見るも物すごき有様なり台湾征伐の方ハ石門の要害を打ち破り牡丹人を追撃する処の図にて尤も妙なるハ新聞探報の為に彼の地へ趣きたる弊社の吟香もその画中に立てり[xxi]。
三 岸田吟香と銀座
それでは、吟香が洋画家劉生に与えた影響について見ていこう。
岸田劉生は、一八九一(明治二四)年六月二三日に東京の銀座二丁目一一番地に、吟香とその妻勝子の第九子四男として生まれている(図16)。劉生が生まれた時、吟香は五八歳で、「精錡水」の調合販売所である楽善堂を営みつつ既に事業の第一線からは引退していた。
劉生の生家である楽善堂本舗は、当時の東京最大の繁華街である銀座通りに面して築地側の広い一画を占めて立っていた。建物は煉瓦造の二階建てで、一階は江戸時代風の店先を持ち、二階は西洋風のバルコニーという明治時代の典型的な洋風建築であった。劉生はこの生家の外観を、一九二七(昭和二)年に『東京日日新聞』に連載した「新古細句銀座通(しんこざいくれんがのみちすじ)」という幼少時代の銀座を回想した随筆の中で挿し絵に描いている(図17)。

図16 岸田劉生

図17 岸田劉生《私の生家之図》1927(昭和2)年
当時、銀座通りでは同様の建物が軒を並べて銀座煉瓦街を形成していた[xxii]。これは、一八七二(明治五)年の銀座界隈を焼き尽くす大火事の後、西洋先進国並みの防火都市を目指す明治政府が立案した、東京全体を煉瓦街にしようとする都市計画の最初の取り組みとして建設されたものであった。
銀座煉瓦街建設の直接の契機は、そうした火災後の復興案であったが、その背景には同年に新橋=横浜間に日本で最初の蒸気鉄道が開通し、銀座が西洋と直接的につながる重要な位置を占めるようになったという事情があった。つまり、銀座は、江戸時代以来の商業の中心である日本橋や京橋、そして外国人居留地のある築地と、各国の公使館や外国人商館のある横浜に蒸気鉄道で結ばれた新橋との中間地点に位置することで、その重要性がにわかに注目されるようになったのである。
銀座煉瓦街の建設に当たっては、当初地元住民から強固な建設反対運動が展開されたことが伝わっている。実際に、一八七三(明治六)年の銀座煉瓦街落成時の入居希望者の数は、二一六戸中の半数以下の九九戸に過ぎなかった。これは、住民側の反発や、洋式の煉瓦造の家屋が従来の和式の生活に適さず敬遠されたことに加え、建設費の高額さが反映して払い下げ価格も高価だったこと等がその理由であると言われている。その結果、銀座煉瓦街は閑散とした状態が続くことになり、空家の中には破損するものまで出てくる始末であった。
これに頭を抱えた明治政府は、やむをえず香具師に空家を貸して見世物興行を行う許可を出している。銀座二丁目では熊相撲、竹川町(現銀座七丁目)では犬の踊り、そのほか貝細工や覗き眼鏡など各種の見世物興行が行われたことが伝わっている。興味深いのは、この時見世物の一つとして、高橋由一の油彩画(図18)も銀座煉瓦街で公開されている事実である[xxiii]。実際に、内田魯庵は「銀座と築地の憶出」(一九二六年)で、一八七五(明治八)年頃の銀座を次のように回想している。
銀座らしい見世物は油絵であった。今日なら展覧会だが、其の頃は画としてよりはキューリオとして扱われて見世物の仲間入りをしていた。画家の名は忘れて了ったが、重に高橋由一の天絵社の社中であったように記憶している。行燈の影でお婆アさんが縫物をしている図や壁に塩鮭が釣るしてある図や猫が魚を啗えて逃げて行く図があったのを今でも覚えている[xxiv]。

図18 高橋由一《鮭》1877(明治10)年頃
こうして建設直後には空家の多かった銀座煉瓦街であるが、一八七四(明治七)年に街路に最新式のガス燈が設置された頃から、次第に文明開化を象徴する近代的な繁華街として東京の流通の中心的機能を果たすようになっていく。
また、煉瓦造の建物は、新聞社にとって非常に都合の良いものでもあった。なぜなら、頑丈な西洋建築の煉瓦造は印刷機の設置に非常に適していたからである。これに、新橋駅が近いという鉄道輸送上の利点も相俟って、一八七四(明治七)年にはまず東京最初の日刊紙である『東京日日新聞』が銀座二丁目三番地に進出している(図4)。結局、関東大震災前までに銀座煉瓦街における新聞社の数は大小併せて三〇社を超えたと言われている。
ちなみに、吟香が楽善堂本舗の経営を始めたのは、その『東京日日新聞』が銀座に移った翌年一八七五(明治八)年のことであった。さらに、その隣には『東京日日新聞』の発行元である新報社の社屋があった。当時、吟香は『東京日日新聞』の記者であり、彼が銀座で開業したのは新聞社とのやり取りに都合が良かったからと、流通の中心地として商売に都合が良かったからの二つの理由があることは間違いない。
また、ちょうどこの一八七五(明治八)年には、明治最初の渡欧画家である国沢新九郎が、その画塾彰技堂を竹川町表通りに開設している。ここでは、「各種の油絵の外に諸家より借り受けたる石版色刷のコロム絵、銅版の墨絵、又生徒の稽古画等[xxv]」を一般に公開することもあったと伝えられている。また、残されている記録から、その観覧者の中に吟香や由一がいたことも判明している。さらに、この年の一〇月六日には、ここで日本最初と言われる洋画展覧会も開かれている。その時には、西洋人画家の作品の他、由一の「乾魚の図」も出品されていたと同年一〇月八日付の『東京日日新聞』は記している[xxvi]。これも無署名であるが、交友関係や地理的条件等から考えて吟香の手によるものであった可能性が非常に高い。
このように、吟香が単なる人間関係においてのみならず、地理的にも洋画と深く関係していたことは重要である。つまり、吟香が洋画の最前線――最初は見世物興行地、やがて展覧会開催地――である銀座に深く関与していたことも、彼と黎明期の洋画家達の関係を考える際には見逃すことのできない重要性を持っていたと指摘できる。
四 岸田劉生と銀座
それでは、こうした西洋の最新文化の情報発信地で生まれ育った劉生にとって、銀座とは一体どのような場所だったのだろうか?
幼少期の劉生の数あるエピソードの中で、特に興味深いものに次のようなものがある[xxvii]。ある日、銀座通りの真ん中に、血まみれの人間の小指が落ちていて大騒ぎになった。通行人の知らせで駆けつけた巡査が恐る恐るそれを拾い上げてみると、実は精巧にできたシンコ細工の作り物であった。当時、まだ小学生だった劉生少年の悪戯だったのである。
また同じ頃、黒髪を振り乱した恨みの形相凄まじい血みどろの生首を、これもシンコ細工で作って家の倉のお櫃の中に隠しておき、何も知らずに蓋を開けた女中が驚いて腰を抜かしてしまったという悪戯も行っている。この生首は、実によくできていたと後々まで語り草になったそうであるが、これらのエピソードは、劉生には生来迫真的なものに対する人々の反応を喜ぶという写実志向があったことを如実に示している。
そうした写実性向の強い劉生は、一九〇四(明治三七)年の中学二年生の時に、自宅楽善堂本舗の近所の竹川町にあった勧工場(最初期のデパート)跡で最初の本格的な洋画体験をしている。
この付近に、前にもちょつと書いたが竹川町の勧工場といふのがあつたが、日露戦争頃に止めになつた。その頃から、階段の壁に大きな油絵の額がかけられてゐて、絵の好きな私はそれをみるのが楽しみであつたがいつかその勧工場が閉ると共に、今度は、油絵や水彩畫の常設展覧所となつた。〔…〕何しろ、勧工場といへば長い道が可なり続いてゐる。そこへ持つて行つて、ずつと油絵水彩等の洋畫がかけてあるのだから、まだ展覧会といふものを、さう見る機会のなかつた私にとつて、この事は非常なうれしい出来事であつた。後になつてわかつたのであるが、これは、桜田本郷町の磯ヶ谷額ぶち店が当時展覧会出品のいろゝゝの作家の売れ残り品やあづかり品をたゞ蔵して置くのも無駄と、こゝを借りうけてやつてゐたものとか、だからそこに出てゐるものは皆相当の大家の筆であつて、事実私ははじめて真の洋畫をしみじみと見られる機を得たのであつた[xxviii]。
ここで興味深いことは、この洋画の常設展覧所には、先に見た芳翠が吟香に贈った《天女図》(図11)も展示されていたことである。
日露戦争の最中のことゝて、戦争畫が多く、コサツク騎兵が馬にのつて逃げて行く、その中の一人が弾に顔をうたれて手を以て掩ひ落馬しかけてゐる図などあつて、私は幾度もそれを真似て描いたものであつた、また出征に行く夫を門口まで送る若き妻が、愛児をだいて父親に別れを告げさせてゐる図の、その門内にある新緑の楓が日光にすけてゐる色など実に感服したものであつた。そこにはまた、父が山本芳翠さんに描いてもらつたダイアナ裸女が天上に半月を弓にして引いてゐる図が出てゐた、これは、昔宅の書房のところにかけておいたものだが、裸体畫であるところから警察から出しておくことを止められたゝめ、久しく物置きに入れてあつたのを古くなつたので、磯ヶ谷へなほし方々あづけてあつたものとか後に聞いた[xxix]。
これらの記述から、劉生は少年時代から、銀座の実家の近所にある勧工場跡の常設展覧所で相当熱心に洋画作品に親しんでいたことが分かる。そして、それらは「皆相当の大家の筆」による写実的な「真の洋畫」であり、その中には父親の旧友で、劉生の世代においても希少な洋画の本場フランスで活躍した洋画家である芳翠の《天女図》(図11)があったことも分かる(図19)。これらの実体験が、劉生に当時一般にはまだ極めて珍しい洋画に自然な親近感を抱かせる役割を果たしたことは間違いない。
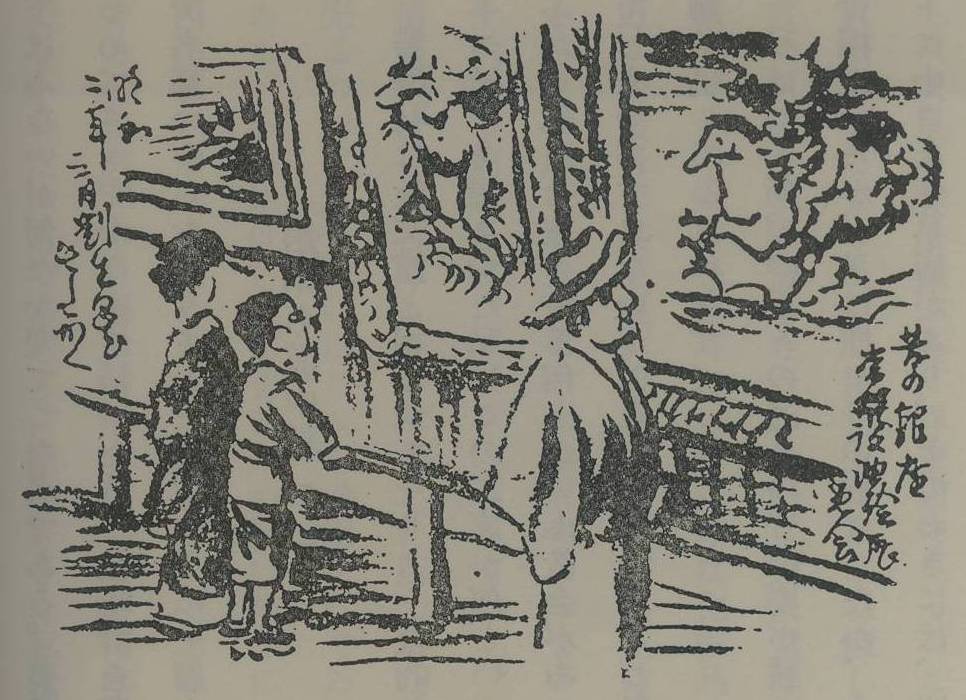
図19 岸田劉生《昔の銀座 常設油絵展覧会》1927(昭和2)年
その後、一九〇五(明治三八)年、劉生は一四歳の時に父吟香を七二歳で亡くし、続いてその年の内に母親も五〇歳で亡くしている。劉生は、一時キリスト教に入信して本気で信仰の道を歩もうとするが、やがてそこから離れ画家として身を立てようと決意する。その時、少年劉生が日本画家ではなく洋画家を自らの生業として選択したことは、その気質的な写実性向においても、身近な父親の交友関係や生育環境においても、ごく自然な流れであったと主張できる。
なお、一九二五(大正一四)年に劉生が三四歳の時に描いた《吟香案詩之像》(図20)は、彼が秘蔵していた下岡蓮杖の吟香像を手本としつつ父親を回顧して制作した作品である。

図20 岸田劉生《吟香案詩之像》1925(大正14)年
註
[i] 吟香と劉生の関係については、以下の文献を参照。土師清二『吟香素描』東峰書院、一九五九年。酒井忠康「楽善堂主人 岸田吟香」『神奈川県美術風土記 幕末明治初期篇』有隣堂、一九七〇年。東珠樹「父吟香のこと生家のこと」『岸田劉生とその周辺』東出版、一九七四年。神山圭介『修羅の春――吟香と劉生』文藝春秋、一九八二年。青木茂「劉生の『生』について」『油絵初学』筑摩書房、一九八七年。杉山栄『先駆者岸田吟香 伝記・岸田吟香』大空社、一九九三年。杉浦正『岸田吟香――資料から見たその一章』汲古書院、一九九六年。小林弘忠『浮世はままよ――岸田吟香ものがたり』東京経済新報社、二〇〇〇年。
[ii] 『岸田吟香・劉生・麗子――知られざる精神の系譜』展図録、世田谷美術館・岡山県立美術館・毎日新聞社、二〇一四年。
[iii] 『岸田吟香・劉生・麗子』展図録、一二六頁に所収。
[iv] 土方定一「川上冬崖と幕末、明治初期の洋画」『近代日本の画家たち』美術出版社、一九五九年、二一頁より引用。
[v] 鍵岡正謹「はじまりの吟香と美術」『岸田吟香・劉生・麗子』展図録、一四頁より引用。
[vi] 同前、一三頁より引用。
[vii] 柳源吉編「高橋由一履歴」、青木茂・酒井忠康編『日本近代思想体系17 美術』岩波書店、一九八九年、一七〇頁に所収。
[viii] 鍵岡正謹、前掲論文、一三頁より引用。
[ix] 同前、一四頁より引用。
[x] 澤村専太郎『東洋美術史の研究』星野書店、一九三二年、四八五頁に所収。
[xi] 青木茂「描かれた吟香像」『岸田吟香・劉生・麗子』展図録、一一五頁より引用。
[xii] 『岸田吟香・劉生・麗子』展図録、一〇八頁に所収。
[xiii] 同前、一二九頁に所収。
[xiv] 同前、一二八頁に所収。
[xv] 同前、一二九頁に所収。
[xvi] 三輪英夫『日本の美術 第三五〇号 明治の洋画――明治の渡欧画家』至文堂、一九九五年、四八頁より引用。
[xvii] 平木政次『明治初期洋畫壇回顧』日本エツチング研究所出版部、一九三六年、七三頁。
[xviii] 『岸田吟香・劉生・麗子』展図録、一二九頁に所収。
[xix] 『明治の宮廷画家――五姓田義松』展図録、神奈川県立博物館、一九八六年、二一〇‐二一一頁に所収。
[xx] 『岸田吟香・劉生・麗子』展図録、一三五頁に所収。
[xxi] 同前、一二八頁に所収。
[xxii] 銀座煉瓦街の建設経緯については、以下の文献を参照。東京都公文書舘編『都史紀要三 銀座煉瓦街の建設』東京都情報連絡室、一九五五年。初田亨『モダン都市の空間博物学――東京』彰国社、一九九五年。
[xxiii] 木下直之『美術という見世物』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、一九九九年。
[xxiv] 内田魯庵『魯庵随筆 読書放浪』平凡社(東洋文庫)、一九九六年、三〇‐三一頁。
[xxv] 三輪英夫、前掲書、二一‐二二頁より引用。
[xxvi] 同前、二二頁より引用。
[xxvii] 劉生の伝記については、以下の文献を参照。武者小路実篤『岸田劉生』小山書店、一九四八年。岸田麗子『父 岸田劉生』雪華社、一九六二年。富山秀男『近代の美術八 岸田劉生』至文堂、一九七二年。東珠樹『岸田劉生』中央公論美術出版、一九七八年。土方定一『岸田劉生』日動出版部、一九八六年。富山秀男『岸田劉生』岩波書店(岩波新書)、一九八六年。瀬木慎一『岸田劉生』東京四季出版、一九九九年。
[xxviii] 岸田劉生「新古細句銀座通」『岸田劉生全集 第四巻』岩波書店、一九七九年、三〇八‐三〇九頁。
[xxix] 同前、三〇九頁。
【初出】本章は、2014年9月19日に帝京大学品川キャンパスで開催された日本フェノロサ学会第35回大会で口頭発表し、『LOTUS』第35号(日本フェノロサ学会、2015年、39‐59頁)で論文発表した、「岸田吟香と近代日本洋画――洋画家岸田劉生の誕生に対する一考察」を加筆修正したものである。
■『岸田劉生と東京――なぜ近代日本美術において写実表現は凋落したのか?』
序論 日本人と写実表現
第3章 岸田劉生の東洋回帰――反西洋的近代化
第4章 日本における近代化の精神構造
第5章 岸田劉生と東京


























