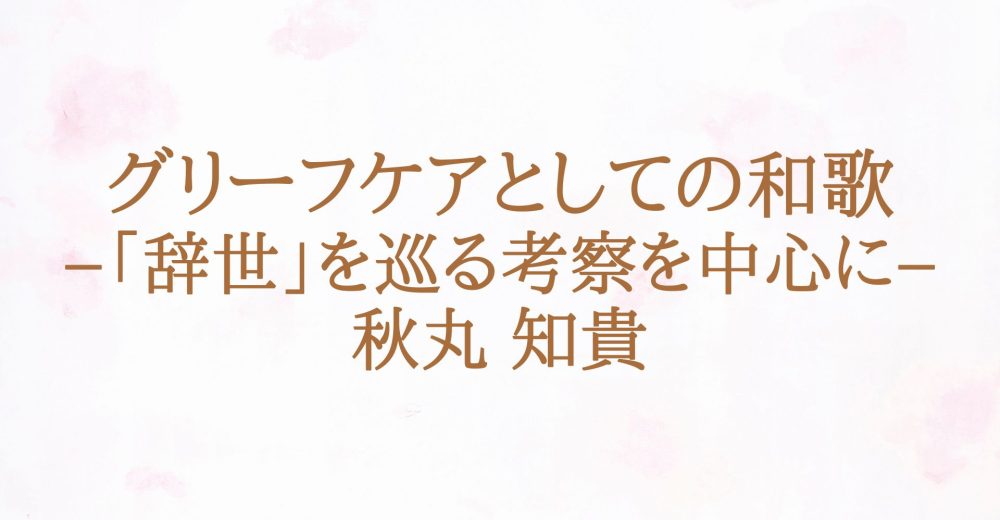水津達大《花の雲》2022年
はじめに
管見の限りでは、なぜ終末期の人が詠む辞世が本人を癒すのかについて、精神史的観点から詩歌様式の内容と形式の両面を総合的に分析した先行研究は意外にも存在していない。おそらく、それは短歌・俳句療法が効果を数値化しにくい上に臨床では十分に効果的なので、わざわざ学問的な反省がなされてこなかったためではないかと思われる。また、臨終あるいは死の予期悲嘆という極めて特殊で私的な状況で詠まれる辞世については、そもそも客観的な実証研究自体が困難だったとも考えられる。
本稿の目的は、和歌の内、特に辞世のグリーフケアとしての効能を分析することである。ただし、その主眼はもちろん自然科学的な実証ではなく、あくまでも辞世という慣習が日本では伝統的に存在している歴史的・文化的事実を前提に、その背景にはどのような心性が働いているのかを考察することである。
そのために、これまで個別に論じられてきた文化史・民俗学・宗教学や、美学・文芸学・言語学上の先行研究の知見を総合すると共に、新知見として従来明示されてこなかったそれらを貫く連関要素を読解する。それは、顕幽循環的世界観、和歌の大衆性、宗教的境地としての自然愛好等である。つまり、まず古来日本では、生者の世界と死者の世界が相互浸透的であるために死に対する相対的な親しさがある。それに基づき、形式において簡略化された定型の中で自らの感情を解放しやすく、内容において主題とする大自然の永遠の営みに自らの生死を仮託しやすいことで、辞世は生から死への移行の心理的受容の補助として働き、一定のグリーフケアの役割を果たしていたのだと指摘できる。
なお、本稿では基本的に、五・七・五・七・七の音節によるものを短歌、五・七・五の音節で季語を含むものを俳句と見なすが、この両者を統合する最適な概念がないので、便宜上「日本語で詠まれた伝統的な短型詩」の意味で「和歌」と定義しておく。また、上記の理由により、本稿で扱う「癒し」とは精神的緊張の緩和の謂であり、分析される和歌によるグリーフケアとは詠み手のセルフ・グリーフケアのことである。
1 和歌の大衆性と宗教的境地としての自然愛好
露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢
例えば、この和歌は豊臣秀吉(1536年-1598年)の「辞世」として広く知られているものである。この辞世では、秀吉の死に対する哀切が見事に昇華されているように感じられる。つまり、死の前ではどんな人生も「露」のように無に帰し、まるで夢の中で見る夢のように儚いが、それでも和歌に詠むことでその悲しみは一旦客観化されると共に、裸一貫で天下人にまで昇り詰めた栄光もきちんと「浪速のこと」として総括され、さらに自分の生死も大自然の永遠の営みの一部と感受されることで一定の心の救いも得られるように思われる。真偽のほどはともかく、もし本当にこれが秀吉の辞世だとすれば、臨終の際に彼に一定の諦めと慰めをもたらしたであろうと私達に想像させずにはおかない。
日本人にとってありふれた風習であるこうした辞世は、実は世界的に見れば特殊な文化である。少なくとも、西洋には日本のような意味での辞世を詠む慣習は存在しない。なぜならば、ドナルド・キーンが『日本の文学』(1953年)で示唆するように、西洋では詩作は神に選ばれた特別な才能を持つごく少数の詩人だけに許される極めて高尚な行為だからである[1]。
これに対し、ラフカディオ・ハーンが「小さな詩」(1899年)で指摘するように、伝統的に日本では詩作は身分才能や年齢性別を問わず誰もが親しむ。しかも、それは死も含む様々な悲哀に慰安を与えると共に、それに対する自制心を涵養するものである。
従って、往時あらゆる種類の心痛は詩歌に出会った。死別、生別、災難は、哀哭の代わりに詩歌を喚起した。貞操を失うよりは死を選ぶ淑女は、自らの喉を刺す前に詩歌を作った。自刃せよと言い渡された侍は、切腹の前に詩歌を作った。この浪漫ならざる時代の明治においてさえ、自殺を決意した若者達はこの世を去る前に詩歌を作るのが常である。また、不運な時に詩歌を作るのは今なお美風とされている。私は、最も耐えがたい困窮や苦難の境遇において――否、死の床でさえ――詩歌が作られるのを頻繁に見聞きした。それらの詩句は、たとえ何ら異常な才能を示さなかったとしても、少なくとも苦痛の中での異常な自制心を証明するものであった……。確かに、この道徳的実践として詩歌を作るという事実は、これまで日本の詩歌の作法について書かれたあらゆる論説よりも一層興味深いものである[2]。
こうした辞世の伝統は、現代まで継承されている。例えば、太平洋戦争(1941年-1945年)に出陣した学徒達の手記『きけ わだつみのこえ』を読めば[3]、文明化された20世紀半ばにおいても、死を目前にした彼等の多くが古式に則り数多くの辞世を詠んでいることが分かる[4]。また、今日でも終末期患者に対する短歌・俳句療法は広く行われている[5]。つまり、ある意味で和歌は現在も息づく日本の伝統的なグリーフケアの一つなのである[6]。
ここで重要な点は、辞世も含めて、和歌には自然を主題とするものが多いことである。実際に、前述した秀吉の辞世も「露」という自然現象に対する情感が重要な癒し効果を生じさせている。つまり、グリーフケアとしての和歌には、自然愛好という要素も大きく関わると推測できる。
実際に、芳賀矢一は「國民性十論」(1907年)で、辞世を含む和歌の大衆性とその自然愛好について次のように言っている。
日本人程國民全體が詩人的なのは恐らくは世界中にあるまい。歌心は誰にでもある。今日日本で歌を作る人はどの位の數であらう。宮内省の毎年の詠進は何萬といふ數である。歌を作らぬでも俳句を作る。どんな片田舎にも俳句の宗匠は居る。八百屋、魚屋は愚なこと、質屋でも、金貸でも、下手の横好きは到る處に多い。神社奉納の額は到る處に小詩人の名を列ねて居る。短くつて作り易い短詩形であるから、上手でこそなけれ、何人も作つて、花見遊山の時にも一興とするのである。この花見といひ、雪見といひ、月見といひ、春は花、秋は紅葉、小詩人はまことに忙しいのである。悪事をはたらいて死刑に處せられる大惡人でも死に臨んでは一首を口吟むといふ様なのは恐らくは他國にはない事であらう。我國民は全國民を擧げて抒情詩人であり、叙景詩人であるといつてもよろしい[7]。
さらに重要な点は、その和歌における自然愛好が宗教性と関わると考えられることである。例えば、磯部忠正は『「無常」の構造』(1976年)で、和歌における自然愛好と宗教的境地の関係について次のように語っている。なお、ここでいう「造化」とは今でいう「大自然」の謂である。
たとえば西行や宗祇や芭蕉や良寛のごとき、わが国の中世から近世にかけてのすぐれた宗教家や芸術家の到達した深い境地が、世界的にみても一種の宗教的な至境であることは疑うことができない。そしてその境地を体現した人々の多くが、その至境を、神や仏への祈りとか叫びとかの形で表わさず、三十一文字あるいは十七文字の詩形に託して詠みいでているのが、わたしには偶然とは思われないのである。絶対者とか造物主とかいうものと己れとの無限の距離を意識しながら、しかもその絶対者の前に跪いて救いを求め、これとの合一を願うという形での信仰のみが宗教的信仰のすべてであるとしたら、日本人は確かに宗教心が低い。しかし無心を求め、無我をめざして、ついに「造化にしたがひ、造化にかへれとなり」(芭蕉『笈の小文』)のこころを生活に実践しうるということは、やはり一種の宗教的な極限にちかい境地である[8]。
ここでは、まず議論の前提として、和歌の大衆性と宗教的境地としての自然愛好があることを確認しておこう。
2 詩作によるケアの基礎概念
次に、詩作一般によるケアについて考えてみよう。この問題について、小山田隆明は『詩歌に救われた人びと』(2015年)で次のように要約している。
どのような詩型の詩歌であっても、感情を強く揺さぶるような体験なくして、詩歌を詠むことは出来ない。そして、その体験が詩歌に表現されるとき、感情は解放され(カタルシス)、心理的な緊張は低下する。その結果、自分と外界についての硬直した見方(認知)は変化し始める(認知的変容)[9]。
ここでは、まず詩作一般によるケアには、「感情の解放」と「認知的変容」の二段階があることを確認しておこう。
それでは、詩と通常の文章ではケアにおいてどのような違いがあるのだろうか。ここでは、詩を概念的思考以前の状態にある言語表現と定義する。この場合の詩の特徴は、感性を触発することである。つまり、まず詩と通常の文章を分けるものとして聴覚的な一定の規則(韻や定型等)があり、それを持つ文章を「韻文」、それ以外の文章を「散文」と大別できる。また、この一定の規則に収めるために、詩では言語が凝縮的(省略・暗示等)や多義的(比喩・掛詞等)になり、通常の文章以上に情動を喚起しやすくなる。そして、これらの感性的要素の秩序の度合いが理性的に反省されたときに美として感受されることになる。
散文にも癒し効果があることは、よく知られている。つまり、本来主観的である個人内面の感情は、そのままでは曖昧で流動的であり明確に把握できないという意味では不快である。これに対し、そうした感情を理性を通じて言語として外的に対象化し客観化すると、その的確さの度合いに応じて明確に把握できたという快感が生じる。これが、まず言語化による癒しと感じられる。そして、新しい認識がもたらされる結果、より健全な認知の変容が可能となる。
この言語化による癒しは、負の感情が内攻し葛藤を生じているときにより大きな効果を発揮する。つまり、そうした負の感情は、感性のままに、喜怒哀楽等の態度として表明されたり、泣いたり喚いたり暴れたりする等の行動で表現されるとある程度発散されるが、理性を通じて言語として外的に対象化し客観化されることでもある程度解放される。これもまた、言語化による癒しと感じられる。そして、やはり新しい認識がもたらされる結果、より状況適応的な認知の変容が可能となる。
ここで注目すべきは、散文よりも韻文の方がそうした感情の解放に有利な場合があることである。つまり、一つは本人が気質的に理性よりも感性が豊かな場合である。もう一つは、表現されるべき感情が理性で制御できる範囲を超えている場合である。これらの場合、そうした感情は、理性の度合いの高い通常の文章(日記・手紙・随筆・論文等)よりも、感性の度合いの高い詩の方が言語化に適している。いずれにしても、詩が感情の解放において有益なのは、感性的要素が多い分だけ元の感情を生き生きと表現しやすいからである。
また、詩の中でも、伝統的に、西洋の詩が長詩型であるのに対し、日本の詩(和歌)は短詩型である。この詩型の長短は芸術効果及び癒し効果において文字通り一長一短であるが、和歌の方が文字数が少ない分だけ制作が容易という利点がある。さらに、和歌の内でも、短歌よりも俳句の方が短い分だけ制作が手軽という利点がある。
実際に、夏目漱石は『草枕』(1906年)で、「〔詩作の〕方便は色々あるが一番手近なのは何でも蚊でも手当り次第十七字にまとめて見るのが一番いい」と教えている。
十七字は詩形として尤も軽便であるから、顔を洗う時にも、厠に上った時にも、電車に乗った時にも、容易に出来る。十七字が容易に出来るという意味は安直な詩人になれるという意味であって、詩人になるというのは一種の悟りであるから軽便だといって侮蔑する必要はない。軽便であればあるほど功徳になるからかえって尊重すべきものと思う[10]。
それでは、そうした詩作によるケアとは具体的にどのようなものだろうか。この問題について、漱石は『草枕』で、主観的な負の感情は詩作で客観化することで解消できると考えている。つまり、負の感情は内攻して葛藤すると心身に悪影響を与えるが、その感情自身を詩作の対象とすることで、心的エネルギーを空回りから引き離すと共に、別の創造的方向へ向け直すことができるようになる。そうした「詩的な立脚地」に立つためには、「おのれの感じ、その物を、おのが前に据えつけて、その感じから一歩退いて有体に落ち付いて、他人らしくこれを検査する余地さえ作ればいいのである」[11]。
実際に、漱石はその例を二つ挙げている。ここでは、詩作がもたらす主観の客観化による癒し効果が語られている。
まあちょっと腹が立つと仮定する。腹が立ったところをすぐ十七字にする。十七字にするときは自分の腹立ちが既に他人に変じている。腹を立ったり、俳句を作ったり、そう一人が同時に働けるものではない。ちょっと涙をこぼす。この涙を十七字にする。するや否やうれしくなる。涙を十七字に纏めた時には、苦しみの涙は自分から遊離して、おれは泣く事の出来る男だという嬉しさだけの自分になる[12]。
なお、この箇所について、小山田隆明は『詩歌療法』(2012年)でやはり感情解放と認知的変容を分析している[13]。その指摘を基礎として、グリーフケアとしての和歌の内実についてさらに様々な観点からより詳しく分析していこう。
3 顕幽循環的世界観
それでは、なぜ日本では伝統的に死を目前にすると辞世がよく詠まれるのであろうか。言い換えれば、なぜ和歌には死を目前にした日本人の心を癒す効果があるのだろうか。この問題を考える際には、まず古来日本人が死をどのように捉えていたかが手掛かりとなる。最初に注目すべきは、日本最古の歴史書である『古事記』(712年)である。
よく知られているように、『古事記』では伊邪那岐命(いざなぎのみこと)は死んだ妻の伊邪那美命(いざなみのみこと)に会うために死者の国である「黄泉國(よみのくに)」へ行く。具体的には、「是に其の妹伊邪那美命を相見むと欲ひて、黄泉國に追ひ往きき[14]」と書かれている。この部分について、大野順一は『死生観の誕生』(1983年)で、日本人の伝統的な死生観では生者の世界と死者の世界が往還可能であることに注意を促している。
伊邪那岐命が黄泉国を訪れ、伊邪那美命を覗き見して畏れ、黄泉比良坂(よもつひらさか)を経て逃げ還る、という神話そのものに留意したい。すなわち黄泉国が往還可能な世界であるということ、生者の世界と死者の世界は黄泉比良坂を境として空間的に連続しているということである。死は生の対立ではなく、生の延長としてあるということである。「よみがへる」ということばは、ヨミからカヘルを語源としているとか[15]。
また、『古事記』では、亡き母である伊邪那美命を慕って号泣する須佐之男命(すさのをのみこと)が「僕は妣(はは)の國根(ね)の堅洲國(かたすくに)に罷らむと欲ふ[16]」と語っている。ここで「黄泉國」は「根の(堅洲)國」と言い換えられ、やはり生者の世界と死者の世界が交通可能であることが示されている。この部分について、大野は『死生観の誕生』で、生者の世界と死者の世界が重なっており、さらに死者の世界は再生の世界でもあることに着目している。
ここに妣の国(妣は亡母の意)、すなわち黄泉津大神ともよばれる亡母伊邪那美命の住む黄泉国は、同時に根之堅洲國(根の国)でもある。「根」とは、もともと生命の根源を意味するという。根の国とはアラユル生命ノ源ノ地の謂である。したがって須佐之男命のいう「妣国根之堅洲国」は、死者の訪れ住む世界と生命の根源の世界とが重なっていて、明確に分化区別されていないことを示しているといってよい。根の国はかくして、一方では生の根源であるとともに、他方では死者の住むところにもつながっている訳である[17]。
こうした『古事記』における死生観は、近代においても存続している。例えば、柳田國男は『先祖の話』(1945年)で、同時代の日本人の死生観を分析して、生者の世界と死者の世界が親しい関係にあることを力説している。
私がこの本の中で力を入れて説きたいと思ふ一つの點は、日本人の死後の観念、即ち霊は永久にこの國土のうちに留まつて、さう遠方へは行つてしまはないといふ信仰が、恐らくは世の始めから、少なくとも今日まで、可なり根強くまだ持ち續けられて居るといふことである[18]。
この『先祖の話』が語る内容で最も注目すべき点は、日本では一般に伝統的に「霊魂の不滅[19]」が信じられていたということである。もし人間が死ねば全て終わりではないとすれば、そうした死生観は人生のあらゆる局面に影響することになる。何よりもまず、本稿が扱う死を目前とした局面でも大きな意味を持つはずである。
柳田によれば、日本人の心的世界では、生者の世界である「この世(顕界)」と、死者の世界である「あの世(幽界)」が存在している。この顕幽両界は区切られてはいるが、部分的に相互浸透し、ある意味で連続的に繋がっている。つまり、「あの世の交通は近いところほど繁く、時が遠ざかると共に眼路が霞んで來て、末は幽かになる」が[20]、この世(現世)にはあの世が「隠世(かくりよ)」として重なっており、「我々の言ふことは聴かれて居る。することは視られて居る。それだから惡いことは出來ない」と考えられている[21]。
人間は亡くなると、亡骸は「この世」に留まるが魂は「あの世」に行く。「あの世」に行ったばかりの魂はまだ個性を強く残しており、「この世」の子孫を見守っている。そして、「あの世」の先祖と「この世」の子孫は仏壇や墓等を通じて日常的に交流する。顕幽両界の交流が特に強くなるのが、時間上は「祭事」であり、空間上は「祭場」である。一般的には、季節の節目に子孫が先祖の魂に改めて感謝の意を伝える「盆」や「彼岸」という伝統行事が普及している。
時々、先祖の魂は子孫として生まれ変わったりもするが、やがて三十三回忌をめどに個性を失いより大きな祖霊の中に溶け込んでいく。次第に、祖霊も個性を失いより大きな神と一体となっていく。
その上で、柳田は『先祖の話』で、日本人が西洋人ほど「死を怖れない[22]」という問題に言及している。すなわち、「生と死とが絶對の隔絶であることに變りは無くとも[23]」、顕幽循環的世界観が「死後の世界を近く親しく[24]」感じさせたのだと論じている。
茲に四つほどの特に日本的なもの、少なくとも我々の間に於て、やゝ著しく現はれて居るらしいものを列記すると、第一には死してもこの國の中に、霊は留まつて遠くへは行かぬと思つたこと、第二には顕幽二界の交通が繁く、単に春秋の定期の祭だけで無しに、何れか一方のみの心ざしによつて、招き招かるゝことがさまで困難で無いやうに思つて居たこと、第三には生人の今はの時の念願が、死後には必ず達成するものとおもつて居たことで、是によつて子孫の爲に色々の計畫を立てたのみか、更に再び三たび生まれ代つて、同じ事業を續けられるものゝ如く、思つた者の多かつたといふのが第四である[25]。
これを受けて、磯部忠正は『「無常」の構造』(1976年)で、そうした日本の伝統的な死生観は、「神中心」でも「人間中心」でもなく「自然中心」であると指摘している[26]。
つまり、生の世界である「この世(顕界)」と死と再生の世界である「あの世(幽界)」は分かれつつ連続しており、あらゆる生命の根源である大自然は「幽界」に根差している。
まず、「顕界」は意識が司る世界であるが、「幽界」は無意識が司る世界である。人間は「幽界」から伝わる大自然の働き(根源的なリズム)を「顕」の生活に生かしていくことが肝心である。この時、自らも自然の一部である人間において、内なる自然は純朴な感情や行動として現れる。もしそこで我執や私心に振り回されると、この大自然の働きから逸脱してしまい様々な不調が生じる。そこで、人間は大自然の働きに謙虚になり、無我無心で生きることが理想とされる。
また、「幽界」は真の世界であり無限の世界であるが、「顕界」は仮の世界であり有限の世界である。そのため、「顕界」では、個人においては様々な不満や苦悩が発生し、集団においては様々な矛盾や不調和が発生することになるが、「幽界」に繋がる大自然に触れて癒されたり、「幽界」から伝わる大自然の働きに基づく「祭り」を通じて調和を回復することになる。
そして、「幽界」から「顕界」を貫く大自然の働きは常に生々流転するので「無常」であり、これに対する人間の自然な感情が「もののあはれ」である。この「無常」における変化の絶対性と永遠性は、人間にかえって絶大な信頼感と安心感をもたらす。最終的に「顕界」では生の果てに死が訪れるが、これも大自然の働きによる「幽界」への回帰と感受されると癒しに繋がることになる。
これらを、磯部忠正は『日本人の信仰心』(1983年)で次のようにまとめている。
日本人は民族としての集団的無意識の、幽の世界に生命の根源をもち、それへの回帰を志向することによって、個人の現世におけるすべての不安や不満を超えて、魂の安定を求める。これはすなわち日本人の祖先回帰の本能であり、より具体的にいえば、回帰の行く先は、古典の『古事記』や『日本書紀』にもあるように、妣の国・根の堅洲国である。生命の根源は父性ではなくて、母性であると日本人は信じている。生きるということは、母から生まれるということを前提としており、死ぬということは、妣(亡き母)のもとに、祖たちのもとに還ることである。それは、もう一次元深めれば、自然から生まれ、自然に還るということである。その「自然」とは、古典(「日本書紀」他)にいう「草木咸能く言語ふ」世界である。そこでは人間と草木とは同一次元で、互いにものいい交わしている。これが日本人の心のふるさとの情景であり、幽の世界の実相である。〔…〕個人単位での信仰や思想がどうであろうと、日本人の集団的な、無意識の信仰はここにあるように思われる。個人の思想や生き方は、本人の意識しない深い奥のところで、不思議なほどこの無意識的信仰に影響されている[27]。
こうした『古事記』以来の日本の様々な伝統的な思想・芸術文化に見出される大自然回帰的な死生観は、現代においても継続している。例えば、加藤周一は『日本人の死生観』(1977年)で次のように説いている。
死の哲学的なイメージは、「宇宙」のなかへ入って行き、そこにしばらくとどまり、次第に融けながら消えてゆくことである。その三段階のなかで、「とどまる」期間は人によってちがうだろう。しかし宇宙のなかへ「入る」またはそこへ「帰る」感情は、多くの日本人共通だろうと想像される[28]。
加藤もまた『日本人の死生観』で、伝統的に日本では顕幽循環的死生観により死後の世界への親近感があると説明している。ここで重要な点は、「顕界」から「幽界」への移行の心理的受容が「諦め」と捉えられていることである。
一般に日本人の死に対する態度は、感情的には「宇宙」の秩序の、知的には自然の秩序の、あきらめをもっての受け入れということになる。その背景は、死と日常生活上との断絶、すなわち、死の残酷で劇的な非日常性を、強調しなかった文化である。〔…〕なしくずしに準備されるのは死ではなく、あきらめの心情である。そして自己制御があきらめを可能にするのではなく、あきらめが自己制御を可能にするのである[29]。
これらを受けて、相良亨は『日本人の死生観』(1984年)で、「日本人一般にとってこの生と死との断絶は、恐怖感というより悲哀感としてとらえられていたのではあるまいか[30]」と問うている。さらに、相良は『日本人の心』(1984年)で、そうした死に対する「悲哀感」は相対的に「恐怖感」よりも「諦め」をもたらしやすいとして次のように論じている。
日本人にとって、基本的には、死は安らかな世界である。その意味である親しさすら感じられる世界である。しかし、いうまでもなく、日本人にとっても、死はやはりきわめての「大事」である。死に親近感を持ちつつも、生に執着する。生との訣別としての死を、われわれも極めて深刻な感情をもって受けとめてきたのである。日本人が生の終焉、生との訣別を深刻な感情をもって受けとめてきたことを忘れてはならない。だがまた、もう一度考えると、生との訣別を深刻な感情をもって受けとめてはきたが、死後の世界にはある親しさをすら感じてきたのである。そしてもしこのように整理することが許されれば、生と訣別する深刻な感情も、死後の世界の親しさによって、やがて「あきらめ」られてくる可能性をもってくることになる。生と訣別する深刻な感情そのものが、やがて「あきらめ」に転ずる可能性を内包するような感情であったということになる。日本人がしばしば、死を捉えてきた悲しみという感情はそのようなものであったのではないだろうか[31]。
これらのことから、和歌、特に辞世が日本の伝統的なグリーフケアの一つであるのは、この「顕界」から「幽界」への移行の際の「諦め」を様々に補助するからであると推論できる。
4 和歌における形式面の癒し
それでは、和歌においては形式面では主に何が癒しに繋がっているのであろうか。ここでは、日本において和歌を「グリーフケア」と結び付けて論じた最初の一人である本居宣長を取り上げよう。
まず、本居は自身の最初の歌論『排蘆小船(あしわけおぶね)』(1757年頃)で、人間は誰でも死ぬときは悲しいと言っている。「死する今はのときにたれかかなしからざらん[32]」。また、本居は『排蘆小船』で、そうした大自然の無常性に触れることで生まれる強い感情を「(物の)あはれ」と表現し、そうした感情を持つことは人間として自然であると述べている。
今はのときに至りて、いなかる鬼のやうな荒男たりとも、物がなしく思ふことのなどかなからんや。此時にあたつて、親兄弟妻子を思ひ、何となくかなしく哀(あわれ)をもよほし、なげかはしく思ふは、千人万人人情の本然、聖人凡人かはることなし[33]。
そして、本居は『排蘆小船』で、そうした悲しみ等の強い感情を良い具合に言葉として発し、それをもたらした強い感情を発散させるのが、「和歌の本然[34]」であると語っている。
まづ歌と云ふものは、心に思ひむすぼるゝことを、ほどよく言ひ出でて、その思ひをはらすもの也[35]。
これらのことから、本居は、強い感情を言葉として発する和歌には死を目前にした際の悲嘆を解消する効能があると考えていると推測できる。
さらに、本居は続く歌論『石上私淑言(いそのかみのささめごと)』(1763年)でもこの考えを発展させている。まず、本居は『石上私淑言』で、やはり大自然の無常性に触れて自ずから生じる強い感情から自然に歌が生まれるとし、「歌は物のあはれより出で来る[36]」と言っている。また、これを言い換えて「あはれにたへぬ時は、必ず覚えず、自然と歌はよみ出でらるゝ物也[37]」とも述べている。
さらに、本居は『石上私淑言』で、そうした大自然の無常性に触れて自ずから生じる強い感情は、感極まると自然に言葉として発され、その声は必然的に長く伸びて良い具合に整うので、それが次第に歌になると説いている。
せむかたなく物のあはれなる事ふかき時は、さてやみなむとすれども、心のうちにこめてはやみがたく、しのびがたし。これを物のあはれにたへぬとはいふ也。さてさやうに堪へがたき時は、おのづから其おもひあまる事を言のはにいひいづる物也。かくの如くあはれにたへずして、おのづからほころび出づることばは、必ず長く延(ひ)きて文(あや)ある物也。これやがて歌也[38]。
そして、本居は『石上私淑言』で、そうした言葉として発され、声が長く伸びて良い具合に整った歌は、それをもたらした悲しみ等の強い感情を発散すると論じている。
さてかく詞にあやをなし、声を長く引きていひ出づれば、あはれあはれとおもひむすぼゝれたる情のはるゝ物也[39]。
ここで注目すべきは、本居は『石上私淑言』で、悲しみ等の強い感情は、愚痴をこぼしたり、ただ言葉にしただけでは発散されない場合でも、言葉として発された声が長く伸びて良い具合に歌として整うと発散されると説明していることである。
今人せちに物のかなしき事有りて堪へがたからむに、其かなしき筋をつぶつぶといひつゞけても、猶耐へがたさのやむべくもあらず。又ひたぶるにかなしかなしと、たゞの詞にいひ出でても猶かなしさの忍びがたくたへがたき時は、覚えずしらず、声をさゝげて、あらかなしやなふなふと長くよばはりて、むねにせまるかなしさをはらす。其時の詞は、おのづからほどよく文有りて、其声長くうたふに似たる事有る物也。是則ち歌のかたち也[40]。
そして、本居は『石上私淑言』で、そうした歌の形式で発散される悲しみ等の強い感情は、さらにその歌を他者に聞いてもらい共感されるとより一層発散されると解説している。
さて又歌といふ物は、物のあはれにたへぬ時よみいでゝ、おのづから心をのぶるのみにもあらず。いたりてあはれの深き時は、みづからよみ出でたるばかりにては、猶心ゆかずあきたらねば、人に聞かせてなぐさむ物也。人のこれを聞きてあはれと思ふ時に、いたく心のはるゝ物也。是又自然の事也[41]。
そうであれば、ここで本居は、和歌における「感情の解放」と「承認欲求の充足」という二つの癒しを論じていると推定できる。これは、前者を「個人内面における癒し」、後者を「他者関係による癒し」とも言い換えられる。
いずれにしても、本居によれば、強い感情は自ずから詩歌の形式を取る。そして、そうした詩歌は様々な癒しをもたらす。そのことが、日本では一千年以上前から広く認められていたことは、紀貫之の『古今和歌集』(905年)の有名な序文から分かる。この日本最古の本格的歌論と呼ばれる文章から、日本では伝統的に和歌が自己や他者へのグリーフケアの役割を果たし、人間関係の潤滑油と捉えられていたことは明らかである。
やまとうたは、ひとのこゝろをたねとして、よろづのことの葉とぞなれりける。世中にある人、ことわざしげきものなれば、心におもふことを、見るもの、きくものにつけて、いひいだせるなり。花になくうぐひす、みづにすむかはづのこゑをきけば、いきとしいけるもの、いづれかうたをよまざりける。ちからをもいれずして、あめつちをうごかし、めに見えぬ鬼神をも、あはれとおもはせ、をとこ女のなかをもやはらげ、たけきものゝふのこゝろをも、なぐさむるは哥(うた)なり[42]。
それでは、和歌はなぜ五言・七言なのだろうか。言い換えれば、なぜ五言・七言の辞世は癒し効果を持つのだろうか[43]。
この問題について、本居宣長は『石上私淑言』で、和歌は「大方五言・七言にとゝのひたるが、古今雅俗にわたりて程よき也」とし、それは「自然の妙」であると言っている[44]。要するに、これは人間の呼吸や発声や聞き心地において、和歌は最も快適なものとして自然に五言・七言になるということであろう。
これに関連して、井上ひさしは『私家版日本語文法』(1984年)で、和歌における五言・七言の形成過程についての先行研究を次のようにまとめている[45]。
井上によれば、まず岩野泡鳴は『新体詩の作法』(1907年)で、「七五調の普通であるのは一つは(七五調)が十二音の一種であるからで、邦人の音量は一般に十二音時を以て極限としてゐるのである。気息の定量は句調の上に大関係がある」と説いている。これについて、井上は「日本人の一呼吸で発音できるのは、十二音である。その十二音を五と七、あるいは七と五に分けた。それが七五調のはじまりである」と注している。
実際に、これを1928年に実験した相良守次によると、六人の学生達に無意味な文章を朗読させ一呼吸の間に何音読めるか計測したところ、平均読誦音数は十二音だったという。これについて、井上は「日本人は一呼吸の間に十二個の音を発語できる。この十二の音を一回句切って言う場合、〔1・11〕〔2・10〕〔3・9〕……〔9・3〕〔10・2〕〔11・1〕の十一のケースが考えられるが、もっとも普通なのは〔6・6〕と等分する句切り方である。だが〔6・6/6・6/6・6/6・6〕ではリズムが単調なので、ちょっとずらして〔5・7〕あるいは〔7・5〕と区切るようになったのだ」と注釈している。
その上で、井上の紹介によれば、土井光知は『文学序説』(1927年)で、「我々は一音、二音は発声器官の連続的な一回の努力、即ち一気力(monopressure)で発音する」、つまり「日本人は三音のことばを二音にして歌う傾向がある」という「気力説」を唱えている。また、福士幸次郎は『日本音数律論』(1930年)で、「一音は独立しては律格を形成しない」「三音は、頭音にあっても末音にあっても渋滞する」「四音はかならず中間に切れ目ができて、二音に分割される」という「二拍分節の説」を主張している。
これらを踏まえて、井上は、日本語の音の基本性質を「二音の塊りがいくつかに助詞ひとつ」を意味する「2n+1」と数式化している。すなわち、「日本語はリズムになろうとする前にまず二音ずつの音塊になる」のであり、「nが二個であれば五音、三個なら七音が得られる」。従って、「日本人が単数で、また複数で声をあげ調子をつければ、音は自然に二音ずつにかたまって、やがて五七、七五の調子になるのだ」と結論している。
もしこれらが正しいとすれば、五言・七言は身体的自然性において快感をもたらすという意味である種の癒しといえる。
また、別宮貞徳は『日本語のリズム』(1977年)で、日本語は「どの音(音節)もほぼ同じ長さ(時間)で発音される」という「等時性」や、「二音節ずつ一つにまとめて組み立てられること」を特徴としていると説いている。さらに、和歌では「一音に八分音符一つをあて、二音をもって四分の四拍子の一拍をつくる」のであり、五音には三つの八分休止符、七音には一つの八分休止符が加わるとしている。つまり、実際には、短歌は五・七・五・七・七ではなく八・八・八・八・八、俳句は五・七・五ではなく八・八・八の四拍子で読まれていると分析している。そして、五七調・七五調は、この四拍子に二音節+αを収めるために長短のバランスが最適な形で自然発生したと考察している。別宮は、こうした四拍子は農作業に由来し、このリズムは農耕民族を中心とする日本では和歌のみならず文化全体に内在していると主張している[46]。
もしこれらが正しいとすれば、やはり五言・七言は身体的自然性において快感をもたらすという意味である種の癒しといえる。
さらに、高橋義孝は「死と日本人」(1959年)で、日本人は大自然への回帰としての死を親しく感じるために、終末・完了・切断の印象を強く持つ五言・七言のリズムへの根強い愛着があると説明している[47]。
また、山折哲雄は『悲しみの精神史』(2002年)で、言葉を極限まで圧縮する短歌的叙情には「概念的思考を内側から融解」させ、死に対する苦悩を和らげる効果があると論じている[48]。そして、山折は『わたしが死について語るなら』(2013年)で、戦没学生達の辞世に関して、「五七調、七五調のリズム」は「われわれの呼吸のリズムであり、生命のリズム」であると述べ、「その和歌のリズムにわが身を託すとき、死を前にした学徒たちは、かつての万葉人たちと同じように、この世からあの世への道をたどることができる、死の不安と恐怖から逃れることができると、無意識のうちに直感したのではないか」と解説している[49]。
これらに加えて、筆者は、和歌においては、表現したい内容と五言・七言の定型の形式が一致した時の快感情による緊張の緩和もまた癒し効果に繋がっていると指摘しておきたい。
5 和歌における内容面の癒し
このように、和歌においては、形式面では、五言・七言による身体的自然性における快感が癒しに繋がっているといえる。それでは、内容面では、主に何が癒しに繋がっているのであろうか。この問題について、永井荷風は「大窪だより」(1913年)で、和歌の癒しが自然愛好の主題と関係することを次のように示唆している。
西洋人は恋人に捨てられ候時、遺瀬なき思ひを託すべき秋の月も雁の声も無之候故、自然と形無き宗教に馳せ哲学に赴く外致方なかるべく候。然るをわれ等日本人には其周囲に無数の美しき花あり鳥あるが上に、移り行くこの季節の情味を加へ候故、いかほど烈しき感情もつい美しく和げられ、わづかに水茎跡さはやかなる三十一文字をなす位に止り候[50]。
実際に、和歌の中でも俳句が自然の風物を「季語」として必ず詠み込むことを規則としていることは周知の通りである。また、あまりにも自明であるためについ見逃しがちであるが、辞世には自然を詠んだものが極めて数多いことも注目すべきである。実際に、次のように代表的なものを挙げただけでも、辞世が臨終の心境を自然の風物に仮託して詠む傾向が強いのは明らかである[51]。
紀貫之「手に結ぶ 水にやどれる 月影の あるかなきかの 世にこそありけれ」
小野小町「あはれなり わが身の果てや 浅緑 つひには野辺の 霞と思へば」
西行「願わくは 花の下にて 春死なん その如月の 望月の頃」
細川ガラシャ「ちりぬべき とき知りてこそ 世の中の 花は花なれ 人は人なれ」
良寛「形見とて 何か残さむ 春は花 山ほととぎす 秋はもみぢ葉」
吉田松陰「身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」
三島由紀夫「散るをいとふ 世にも花にも さきがけて 散るこそ花と 咲く小夜嵐」
川端康成「友みなの いのちはすでに ほろびたり われの生くるは 火中の蓮華」
松尾芭蕉「旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る」
与謝蕪村「白梅に 明くる夜ばかりと なりにけり」
ここで、和歌の癒しが主題面で自然愛好と関係することを考えるためには、古来日本人の自然愛好を示す「風流」という概念が手掛かりとなる。この問題について、最も重要な論考の一つである佐藤春夫の『「風流」論』(1924年)によれば、「風流」とは「人間自身の意志を最小限度にまで卑下し」て大自然に溶け込む精神態度である。つまり、我執や私心を捨て無我や無心になった時、自らの内なる自然と外なる大自然が照応する。その時、大自然の無常性の中にこそ変化の絶対性と永遠性が感受される。ここで生まれる精神態度こそが、「もののあはれ」であり「風流」である。そして、佐藤はその「風流」心の向かう先は、本稿の文脈でいう大自然の根源としての「幽界」であることを次のように示唆している。
一体、生のあまりにはげしい活動は、その生が不幸でなかつた場合でさへ、我々に屡々死のことを考へさせる。しかも我々は死を楽しく考へるほど疲れてゐる瞬時に於てさへも、生きてゐる限りに於てはやはり生の本能に執してゐる。さうして死を考へてゐることによつて生きてゐることを享楽してゐるといふ心理さへもあり得る。ただその場合に於ける生の執着も、生の享楽も、それが生としてはいかにも最小限度のものなのである。さうして「もののあはれ」と言ひ「無常感」といふのは、実は、この最小限度に於ての生の執着と生の享楽とに外ならないのである。活動によつて疲労した人が無意識的に静止を思ふ瞬間には、彼の人間的意志は影のやうに淡くなり、さうしてさういふ人々の目に現はれて出て来るところの自然の悠久は、我々が遂に包括されるであらうところの最後の故郷へのノスタルジヤの如き哀しい愛情として現はれて来る[52]。
そして、佐藤は『「風流」論』で、そうした我執や私心を最小化した「風流」を表現する芸術形式が、言葉を最も縮減する最小の定型詩である和歌であることを次のように洞察している。要約するならば、大自然に溶け込む無我や無心とは多言を要さない精神態度であり、用いる言葉を最小限度に限定することにより逆説的に大自然の絶対性と永遠性を無限に暗示するのである。これもまた、日本で、三十一文字、あるいは十七文字という、世界でも稀な極小詩型が創造された芸術上の内的必然性の一つと指摘できる。
さうして我我の祖先は――尠なくとも「もののあはれ」の詩人たちは、意志放擲的意志-(マイナス)的意志の把持によつて彼等特有の解決を勝得たのではなく、寧ろ、飽くまでも自然的に生の力の淡くなつてゐるその一刻に於て、偶然にそれを捉へ来つたかのやうに私には見える――意志放擲といふよりもそれは意志脱落の瞬間であつたといふ方がもつと適切であらう。彼らがその解決を得るために努力をした跡は一向に認め得ないばかりか却つてその反証だけを私は発見することが出来る。即ちこのやうにして得来つた詩情であればこそ、それは世界に比類ないほどの短小な詩形に於てのみ成立したのだ[53]。
これらのことから、古来日本人は和歌の内容面においても自然を主題に詠むことで、生命の根源である「幽界」から伝わる大自然の悠久の働きを内面的に感受して癒されていたのだと解釈できる。
この実例として、私達は既に冒頭で豊臣秀吉の「辞世」を分析しているが、最後にもう一つ別例として松尾芭蕉(1644年-1694年)の最晩年の句を読解しておこう。
芭蕉は、50歳で亡くなる2週間ほど前の1694(元禄7)年9月26日に次の句を詠んでいる。
此秋は 何で年よる 雲に鳥
この句作の頃、芭蕉はある句会に出席できず作品だけを送るほど体調を崩していた。「此秋は何で年よる」までは朝にできていたが、芭蕉はその後苦吟し、ようやく夕方に「雲に鳥」を得たことが分かっている。
この句について、大岡信は「俳句とハイク」(1992年)で、「芭蕉の苦心惨憺した末に得た傑作」だと評している。なぜなら、上の五・七の「此秋はなんで年よる」という極めて主観的な「痛切な老いの嘆きの言葉」が、「雲に鳥」という「客観的な、いわば描写にすぎない言葉によって吸い取られた瞬間に、その前の五・七のつらさとか、自分自身に対する嘆きとか、そういう心理的、主観的な心情が客観性に吸い取られて、そこに縹渺たる一種の象徴的空間が浮かんでいる」からである[54]。
大岡は、「芭蕉の『辞世』考」(1990年)でも、この「雲に鳥」という、「いわく言いがたい透明感のある表現」の「裏側には脱力感、自己放棄、行方知れぬ彷徨の感覚、そして心細さといったものが、じっとひしめいてもいたのだ」と推察している[55]。ある意味で、だからこそ芭蕉は、この「雲に鳥が消えていく」ことと「縹渺として人間の肉体と魂が空に向かってすーっと上がって行ってそのまま雲に消えていく」ことのダブルイメージを持つ言葉を獲得できたといえる。ここで大岡自身はそれほど強調していないが、これはやはり大自然への回帰という日本の伝統的な詩主題であり、この句はある種の「辞世」として芭蕉の死出の旅路の悲嘆をある程度確かに癒していたと理解できるだろう。
おわりに
以上のことから、和歌、特に辞世にはグリーフケアの効能があると指摘できる。つまり和歌は、形式上は、短詩型により特別な才能がなくても誰もが詩作しやすく、五言・七言がリズム的にも親しみやすいので負の感情を解放しやすいという利点がある。また内容上は、主に自然を主題とすることで永遠不変の大自然への内面的一体化を通じて安心感をもたらしやすいという利点がある。これらにより、和歌は人々の悲哀を日常的に慰め、特に辞世は「顕界」から「幽界」への移行の際の「諦め」を心理的に様々に補助し、死に対する予期悲嘆を少なからず癒していたのだと主張できる。
このように、もし辞世が日本の大衆的な文化伝統に即したグリーフケアであるならば、現代日本においてもある程度誰に対しても一定の効能を期待できる。そうであるならば、もちろん本人が望むことを前提としつつ、こうした辞世の慣習はぜひ今後もターミナルケアの臨床現場で積極的に導入される価値があるだろう。
[1] ドナルド・キーン『日本の文学』吉田健一訳、中公文庫、1979年、38頁。
[2] Lafcadio Hearn, “Bits of Poetry,” in In Ghostly Japan, Boston, 1899, pp. 153-154. なお、引用は拙訳している。
[3] 日本戦没学生記念会編『きけ わだつみのこえ』岩波文庫、1982年。
[4] 『きけ わだつみのこえ』における辞世の分析については、秋丸知貴「心理的葛藤の知的解決と美的解決――比較文化的観点から見たグリーフケアについての一考察」、髙木慶子・秋丸知貴『グリーフケア・スピリチュアルケアに携わる人達へ』クリエイツかもがわ、2023年、215-243頁を参照。
[5] 徳田良仁監修、飯森真喜男・浅野欣也編『俳句・連句療法』創元社、1990年。
[6] 大岡信は「死生観私見」(1993年)で、グリーフケアとしての辞世に関して次のように述べている。「第一には宗教が、第二には哲学が、このような場では有効な慰めを提供する。もちろん情緒的な慰撫の手段としてなら、詩歌や芸術があろう。いずれにしても、それらは死という事実そのものを無くさせることには役立たたない。ただ、死に関する意識を変化させ、受け入れ易くすることはできる。そしてこれは、いつの時代にも重要性を失わなかった死への抵抗の方法だった。この『抵抗』が、さらに進んで『克服』という能動的段階にまで発展するなら、意識のレヴェルにおける『死の克服』は可能だということもいえるようになるかもしれない。それが、人間が『文化』を持っているということの究極の意味だともいえる」(大岡信「死生観私見」『詩の時代としての戦後』岩波書店、2000年、94頁)。
[7] 芳賀矢一「國民性十論」『明治文学全集44 落合直文・上田萬年・芳賀矢一・藤岡作太郎集』筑摩書房、1967年、255頁。
[8] 磯部忠正『「無常」の構造』講談社現代新書、1976年、63-64頁。
[9] 小山田隆明『詩歌に救われた人びと――詩歌療法入門』風詠社、2015年、81頁。
[10] 夏目漱石『草枕』岩波文庫、1990年、39頁。
[11] 同上、39頁。
[12] 夏目『草枕』39-40頁。
[13] 小山田隆明『詩歌療法――詩・連詩・俳句・連句による心理療法』新曜社、2012年、183頁。
[14] 「古事記」『日本古典文学大系1 古事記 祝詞』岩波書店、1958年、63頁。
[15] 大野順一『死生観の誕生』福武書店、1983年、19-20頁。
[16] 「古事記」前掲書、73頁。
[17] 大野『死生観の誕生』20頁。
[18] 柳田國男「先祖の話」『定本柳田國男集』第10巻、筑摩書房、1969年、42頁。
[19] 同上、121頁。
[20] 同上、121頁。
[21] 同上、122頁。
[22] 同上、119頁。
[23] 同上、119頁。
[24] 同上、120頁。
[25] 同上、120頁。
[26] 磯部『「無常」の構造』98頁。
[27] 磯部忠正『日本人の信仰心』講談社現代新書、1983年。新版、磯部忠正『日本人の宗教心』春秋社、1997年、55-56頁。
[28] 加藤周一/M・ライシュ/R・J・リフトン『日本人の死生観(下)』岩波新書、1977年、211頁。
[29] 同上、214-215頁。
[30] 相良亨『日本人の死生観』ぺりかん社、1984年、17頁。
[31] 相良亨『日本人の心』東京大学出版会、1984年、196-197頁。
[32] 本居宣長「排盧小船」『排盧小船・石上私淑言』岩波文庫、2003年、64頁。
[33] 同上、64頁。
[34] 同上、74頁。
[35] 同上、74頁。
[36] 本居宣長「石上私淑言」『排盧小船・石上私淑言』岩波文庫、2003年、192頁。
[37] 同上、193頁。
[38] 同上、192-193頁。
[39] 同上、193頁。
[40] 同上、195頁。
[41] 同上、197-198頁。
[42] 『日本古典文学大系8 古今和歌集』岩波書店、1958年、93頁。
[43] これに関連して、大岡信は「死生観私見」で、和歌は概念的思考ではなく音律的定型により普遍性を獲得したのではないかと指摘している。「別の言い方をすれば、古来日本人は、死をも生をも短い言葉で要約し、抽象性を豊かに含んだ断言命題の形でそれを表現することには不得手だった。抽象的表現は、その抽象性ゆえに、個の現実を普遍性の場にいやおうなしに移してくれるものだが、それは大和言葉にはない性質だった。大和言葉の場合、ここで言う抽象性に該当する働きをある意味でなしえたものは、五七五あるいは五七五七七という音数律の存在だったのではないかと、私は一つの仮設として考えている。辞世の句や和歌は、音数律に乗せるおかげで、個人的述懐から普遍的断言に化することができたのではなかろうか。それでもなお、和歌や俳諧の形でのべられた辞世は、現世との親和性というか、ある暖かい生活的なつながりをさえ多分に残している。それがまた、特定階級の知識人だけでなく、農民であれ商人であれ、一般庶民の間にも、広く辞世という高度に文化的な人生最後の作品を遺す習慣を生んだ一因であったというのが、私の仮設にもとづくもう一つの推論である」(大岡「死生観私見」94頁)。
[44] 本居「石上私淑言」159-160頁。
[45] 井上ひさし『私家版日本語文法』新潮文庫、1984年。
[46] 別宮貞徳『日本語のリズム』ちくま学芸文庫、2005年。
[47] 高橋義孝「死と日本人」『日本文化研究』第3巻、新潮社、1959年、46頁。
[48] 山折哲雄『悲しみの精神史』PHP研究所、2002年、247頁。
[49] 山折哲雄『わたしが死について語るなら』ポプラ新書、2013年、215-216頁。
[50] 家永三郎「日本思想史に於ける宗教的自然観の展開」『家永三郎集 思想史論』第1巻、岩波書店、1997年、147頁より引用。
[51] 佐久間庸和『辞世の歌50選』サンレーグランド文庫、2010年等を参照。
[52] 佐藤春夫「『風流』論」『佐藤春夫文芸論集』嶋田謹二編、創思社、1963年、38-39頁。
[53] 同上、41-42頁。
[54] 大岡信「ハイクと俳句」、日本文体論学会編『俳句とハイク』花神社、1994年、18-20頁。
[55] 大岡信「芭蕉の『辞世』考」『詩の時代としての戦後』岩波書店、2000年、127-128頁。
【初出】秋丸知貴「グリーフケアとしての和歌――『辞世』を巡る考察を中心に」『スピリチュアルケア研究』第7号、日本スピリチュアルケア学会、2023年、83-97頁。
■ 秋丸知貴『ケアとしての芸術』
第1章 グリーフケアとしての和歌――「辞世」を巡る考察を中心に
第2章 グリーフケアとしての芸道――オイゲン・ヘリゲル『弓と禅』を手掛かりに
第3章 絵画制作におけるケアの基本構造――形式・内容・素材の観点から
第4章 絵画鑑賞におけるケアの基本構造――代弁と共感の観点から
第5章 フィンセント・ファン・ゴッホ論
第6章 エドヴァルト・ムンク論
第7章 草間彌生論
第8章 アウトサイダー・アート論