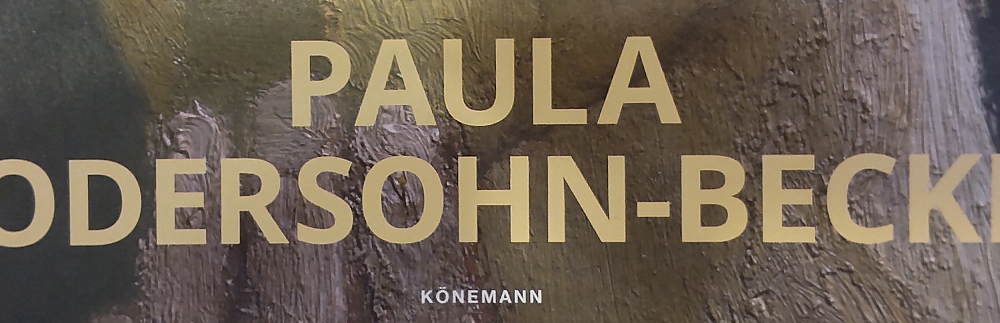歴史上、「初めて裸体の自画像を描いた女性画家」として知られる、ドイツのパウラ・モーダーゾン=ベッカー(1876~1907年)と言えば、2005~2006年にかけて国内でも3会場を巡る大規模な回顧展が催行されたので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
筆者は2006年に「神奈川県立近代美術館 葉山館」で展示を見ました。作品の質の高さに感銘を受け、興奮して購入した図録は今でも宝物です。ドイツのKoenemann社が2018年に刊行したパウラの画集巻末の「おすすめの文献」欄には3冊の書籍が紹介されていますが、その一番目が、何と日本での回顧展図録です。実は日本におけるパウラ・モーダーゾン=ベッカー受容の歴史はかなり古く、100年以上前から書籍や雑誌の中で紹介されているのです。
あの回顧展以降、パウラの作品を求めて何度もドイツを訪れました。と言うのも、彼女の作品は、ほとんどがドイツ国内にしか残っていないからです。オランダのアムステルダムとデン・ハーグ、スイスのチューリッヒとバーゼル、そしてアメリカのデトロイトにある美術館等でわずかに鑑賞できるだけで、それ以外の国でパウラの作品に出合った記憶はありません。
六回目の結婚記念日の自画像-207x300.jpg)
「6回目の結婚記念日の自画像」パリ、1906年5月、101.8×70.2㎝、ウィキメディア・コモンズより
パウラの生涯は、パリとのかかわりが非常に深いので、フランスの美術館にも彼女の作品が所蔵されていて当然だと思い込んでいたのですが、なぜか見られない(コレクションされていない)のです。つまり、パウラは現状、「ドイツの女流画家」という位置づけにとどまっています、残念ながら…。
もっと彼女の生涯に光を当てて、美術史に永遠に残るであろう世界的な画家であることを証明したいものだと思い続けてきた筆者の前に、何かの啓示のように一冊の本が現れました。
現代フランスの女性作家マリー・ダリュセック(1969~)の『ここにあることの輝き パウラ・M・ベッカーの生涯』(東京外国語大学出版会、税込み2530円)です。
フランス語による原書は2016年に刊行されました。荒原邦博による達意の翻訳を得て、国内で刊行されたのが2023年11月のこと。
本書は一応は「女性作家による女性画家の伝記」と言えますが、実際には「小説」といった方がふさわしいのです。なぜか?
ダリュセック自身を想起させる、語り手の「私」が、時空を超えて、あちこちに顔を出しているからです。もちろん、ダリュセックは適当に面白おかしく作家の生の軌跡を創作している訳ではありません。徹底的に専門家への取材を重ね、資料や文献を博捜し、作品そのものとの対話を積み重ねることによって、パウラに同化し、パウラに成り代わって、彼女の真情を吐露しているのです。-187x300.jpg)
客観性を担保しようとする、よそよそしい筆致の「伝記」を書いてもパウラの魅力には肉薄できない、とダリュセックは考えたのでしょう。
つまり、我が国の俳聖・松尾芭蕉の名言「古人の跡を求めず、古人の求めたるところを求めよ」と同じ方法論です。古人(=パウラ)の追い求めたことを現在、生きるダリュセックが追い求めているわけです。
そもそも、どんな厳密で客観的で禁欲的な記述を心掛けたと自負する伝記作者であったとしても、文献資料の取捨選択や文章の書きぶりを通して、自身の主観を排除することは不可能でしょう。ダリュセックは、パウラの跡を求めるのではなく、パウラの追求した真情や心情を活写しているのです。
横たわる母と子-300x198.jpg)
「横たわる母と子」パリ、1906年、82.5×124.7㎝、ウィキメディア・コモンズより
ダリュセックの方法論を端的に示した文章を引用しましょう。1907年11月20日、産褥熱から発した塞栓症で死去する直前にパウラは、最後の言葉として「シャーデ(Shade)」と言いました。ドイツ語で「残念」という意味の言葉です。
ダリュセックはこう綴ります。「私がこの伝記を書いたのは、この最後の言葉があったからだ。だってそれは残念だったから。会ったことがない人なのに彼女がいなくて寂しいから。彼女に生きてほしかったから。私は彼女の絵を見せたい。彼女の人生を語りたい。彼女の本当の価値を取り返す以上のことがしたい。私は彼女にそこにあること、輝きを返してあげたいのだ」(同書186ページより)
美術に造詣の深いダリュセックは、パウラの作品の美点を的確に指摘します。例えば、こんな風に。「パウラには、本物の女たちがいる。やっと裸になった女たち、男性のまなざしから裸になった女たちと私は言いたい。男の前でポーズを取るのではなく、男たちの欲望、欲求不満、所有欲、支配欲、苛立ちを通して見られたのではない女たち」(同書160ページより)
例えば、こんな風に。「パウラの作品で見られるのは、私が今まで絵の中で一度も見たことがなかったような赤ちゃん、でも私が現実の世界で出会ったような赤ちゃんだ。乳を吸う小さい人の、集中し、大きく見開かれた、ほとんど動かないまなざし、乳房に置かれた手、あるいはぎゅっと握った拳。手首はまるでなくて、皺がひとつ。首は座っていない。両脚は丸々としているものの筋肉は発達していない」(同書161~162ページより)
美術の世界で長らく支配的であった「男性のまなざし」から解放された対象の捉え方が、パウラの作品に定着していることをダリュセックは繰り返し、繰り返し綴るのです。
胸の前で指を広げる少女の肖像-238x300.jpg)
「胸の前で指を広げる少女の肖像」ヴォルプスヴェーデ、 1905年、41×33㎝、ウィキメディア・コモンズより
そして、女性がこうむらなければならない男性からの暴力は、女性にとってデメリットでもあり、メリットでもあることをダリュセックは喝破しています。
「女たちは姓を持たない。彼女たちにあるのは名だ。彼女たちの姓は一時的に貸与されたもの、不安定な記号、彼女たちの儚さだ。彼女たちは別の目印を見つける。彼女たちの世界における自己確立、『そこにあること』、創造、サインは、そうした目印によって決定される。彼女たちは男たちの世界に不法侵入することで、自らを発明するのだ」(同書56ページより)
女性は虐げられているがゆえに、新たな創造への可能性を持ちうる機会があるのです。一方、男性は自身の特権性・暴力性に居直っている限り、進歩発展の機会を永遠に失ってしまうのです。「自らを発明する女たち」の方が現世で甘い汁をすすっている男たちよりも清潔、かつ、クリエイティブであるのは言うまでもないでしょう。
パウラが1901年に結婚したオットー・モーダーゾーン(1865~1943年)は、妻の持つ「独立心、さらには虚栄心のせいで妻としての務めがしばしば疎かになること」を残念がってみせますが、それに対してパウラは1902年にこう記しています。「結婚においては、自分が理解されないという気持ちがいっそう募る。だって、結婚以前の人生は理解されるその場所を追い求めることにずっと費やされてきたのだから。ああした幻想もなく、大いなる、孤独な、唯一の真実に向き合う、そうした方がよくないだろうか」(同書97~98ページより)
夫に幻滅し、結婚に幻滅するパウラの姿は、現代社会を生きる女性にとっても激しく共感できるものなのではないでしょうか?
ライナー・マリア・リルケの肖像-230x300.jpg)
「ライナー・マリア・リルケの肖像」パリ、1906年5/6月、 32.3×25.4㎝、 ウィキメディア・コモンズより
本書の持つ高い意義は、翻訳者・荒原邦博による解説文が非常に的確にまとめています。
「パウラ自身がフランスとドイツを絶えず往還することによって前代未聞の作品を生み出した画家なのであり、そこにさらにダイナミックにヨーロッパの複数の国境を越え続けたリルケとの関係が絡んでいることを考えれば、ダリュセックによるフランス語の『伝記』こそが、この女性画家の作品をヨーロッパ的な広がりにおいて、その越境の意味を含めた複雑な様相の下に、十分に把握する通路(パサージュ)を新たに開いてくれるだろう」(同書217ページより)
そう、パウラに詩を捧げたリルケの逸話も本書には多く登場します。文学、美術を愛し、自由を希求する方に是非とも読んでほしいと思います。
「見る男」の貧しさ、「見られる女」の豊かさを心底から噛み締めれば、その先には「ここにあることの輝き」が必ず待っているはずですから。(2024年4月17日20時48分脱稿)