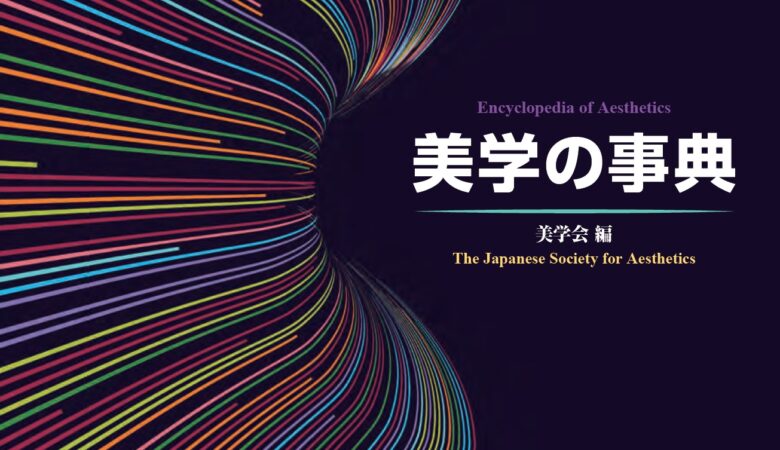東京都港区の泉岳寺駅から神奈川県横須賀市の浦賀駅までを結ぶ京浜急行電鉄(京急)の京急本線(KK)は、ご存じでしょうか?
鉄道好きの筆者は、KKが大好きです。沿線に「オヤオヤ」と思うようなトリッキーな場所・空間がたくさんあり、それらを散策しているだけで楽しめるのです。いくつかご紹介します。ただ、これは過去の筆者の体験談なので、現在も同じ状況なのかは確認しに行っていません。あくまでも思い出話と言うことでご理解ください。
まずは「世界一恐ろしい高架下」から。六郷土手駅を降りたら、多摩川の方へ歩いてください。やがて、多摩川の河川敷の遊歩道と京急の線路が直角にまじわる個所に到達するはずです。この高架下にはほとんど高さがありません。大人の身長ですと座ることもできないほどの狭い隙間です。ですから、この場所では横たわることしかできないのです。そして、その横たわった真上に京急のレールが通っているのです。目の上にはコンクリ製の床などありません。レールがほぼ直接、見えます。つまり、スケスケ、スカスカなんです。
いいですか、もう一度言いますよ。座ることもできないほどの低い低い空間なんです。つまり、寝ているあなたのすぐ真上を電車が走るのです。思わず目を閉じたくなりますよね。筆者の場合は、かっと目を見開いて、電車の裏(下)側を凝視します。普段、見られないパーツが何とか見られないか、という思いもありますが、もう一つ別の理由があります。
仮に私が横たわっている場所が、遊歩道ではなく、そこから少し上方の線路上ならばどうなるでしょう? 一瞬で轢死しますよね。私は、電車に轢かれる自分の姿をイメージしているのです。古い自分、ダメダメな自分をいったん消去し、もう少しマシな人間に生まれ変われないだろうか、という切なる願いが、この“荒行”の背景には潜んでいるのです。振動も音響もすさまじいですが、耳栓もサングラスもせず、私の中に電車を高速で通過させるのです。そう、私はトランス感を伴いながら、転生しようとしているのかもしれません。
私は様々な高架下をこれまで旅で訪れてきましたが、六郷土手駅近くの高架下ほど、電車と自分の距離が近い場所を見たことがありません。失恋してツライ方、事業に失敗してにっちもさっちもいかなくなった方、色々なことでお悩みのアナタに私は言いたいのです。自裁してしまう前に、「一つクッションを置いてみてはいかがですか?」と。
私のように高架下に横たわれとは申しません。でも、ほかにもたくさんの選択肢はありますよ。着の身着のままで野宿しながら日本全国、世界各地を歩いたっていいんです。一度、「死」を覚悟したくらいのアナタなら、なんだってできます。開き直って、何か「一つっこと」に集中して取り組めば、どんなことでも可能です。懸命に取り組んでいるうちに「死ぬことはないか。もう一度生きてみようかな」と呟く自分を見出すはずです。
死をシミュレーションすることにより、生を取り戻すーーこのメソッドは美術鑑賞でも可能です。人間の魂の闇、残酷さ、愚かさをこれでもかと描写したフランシスコ・デ・ゴヤ(1746~1828年)の作品の前に立つ。
あるいは、ダミアン・ハースト(1965~)のインスタレーション「A Thousand Years」の前に立ってもいい。この作品には大量の蠅を焼死させる仕掛けが施されています。筆者も海外の美術館で本作を鑑賞しましたが、蠅を殺すなんて残酷だ、と非難するよりも前に、「あぁ、この蠅はまさに自分自身の姿そのものじゃないか」という思いの方が先にきました。
ハーストの名言で「人は見つめることで、殺してしまう」というものがあります。つまり、大量の蠅を焼死させる作品に憤慨する、多くの良識ある大衆に対して、ハーストは「蠅はただのメタファーに過ぎないよ。オマエの視線が誰かを、何かを殺していない、と本当に言い切れるのかい?」と訴えているのでしょう。
ナチスによって焼却されてしまったユダヤ人、アメリカが落とした原爆によって一瞬で“蒸発”してしまった広島・長崎の日本人(含む、日本人以外の方)にまで、思いを馳せたーーそれがハーストの作品の前で立ち尽くした際の筆者の率直な感想です。
確かに作品のために、蠅を何百匹も焼死させるのは残酷です。でも、ハーストは蠅の命を奪ってまで、どうしても訴えたいことがあったのでしょう。「死」とは何ぞや、というアポリアを直接的に突きつけるために、あえて焼け焦げた蠅をそのまま見せている、と筆者は理解しました。このハースト作品は、ドイツの美術館で、「残酷すぎる」という理由で撤去されています。しかし、筆者のように、死んだ蠅の姿に自らの死を重ねている者にとっては、単純に「残酷」とは言い切れないと考えました。
アートは、死の表象と切り離せません。いや、むしろ、「死」のイメージで満ちあふれているのがアートと言っても良いくらいです。高架下まで足を運ばずとも、アートに触れれば、生と死を深く考えられること請け合いです。
精神的に辛いことがあったら、どうか美術館やギャラリーを訪れてみてください。きっと、アナタの抱える様々な問題を解決に導くヒントがそこにはありますから。
KKのびっくりスポット、お次は、戸部駅から日ノ出町駅の区間になります。戸部駅周辺の西戸部町や伊勢町は起伏差の激しい凸凹の場所です。そのせいでしょうか、戸部から日ノ出町の間には、御所山、上原、野毛山と3つもトンネルがあります。さらに言うと、トンネルはないけど、住宅街よりも少し下を走っているような箇所もあるのです。つまり、住宅と住宅との間を縫うように伸びる掘割状の空間に線路が通っているのですね。
筆者が住宅街を歩いていると、小高くなった行き止まりの場所に到達します。この上をヨイショと上ってみると、そこが、今ご説明した掘割状の空間なのです。ここまで上ると、電車と並ぶようにして歩けるのです。もちろん、そもそもこの掘割状の空間まで入り込んでいい訳はありません。危険すぎますから。確か立ち入り禁止になっているはずです。ただ、筆者が今、ここで描写した光景は立ち入り禁止エリアに入らずとも丸見えなのです。
狭い路地と路地の間をこじ開けるようにして進んでいるーーそんなイメージを持ってもらえば、大体、正解でしょう。こんなに住宅と線路が近い場所はなかなかないです。東京都の都電荒川線には部分的に住宅のすぐ脇を通る個所がありますが、それ以上の迫力がKKにはあるのです。
野毛山トンネルもすごいですよ。何がすごいかと言うと、トンネルを抜けたら、日ノ出町駅のホームが目の前にあるからです。普通は、トンネルを抜けて、少し距離を置いてから駅があると思うのですが、この駅は違います。戸部駅方面からの最後のトンネルを抜けたらすぐに駅なんです。トンネルの端っことホームの端っこが非常に近いのです。どうして、このような立地になってしまったのか、筆者には分かりませんが、いつ見ても、その面白い立地・構造に気持ちがはずみます。
この日ノ出町駅にも線路の下をくぐる小さいトンネルがあります。このトンネルは、昼でも薄暗い、ちょっと怖い感じが漂っておりますが、筆者が注目するのはその壁面なのです。

京急・日ノ出町駅近くの壁面。素晴らしい“芸術作品”だ
素晴らしい“作品”があちこちに点在します。人為的に手が加えられたものではなく、あくまでも生成りの造形です。鉄の錆が水と共に下部へと流れ落ち続ける、その軌跡が壁面に絵を描いています。様々なひび割れやコンクリの劣化が生み出した線も美しいです。
私が壁を見ているはずなのに、じっと見続けていると反転して、壁が私を見ている気がしてきます。まさにジャン・ボードリヤール(1929~2007年)の写真論そのままです。壁が何かの生き物のように思えてくるわけです。非常に生々しい感じで、いくら見続けても見飽きません。
残念ながら、高架下は素晴らしい場所ばかりではありません。日ノ出町駅と黄金町駅の間の高架下に現在、整備中の「黄金町ロックカク」という広場が、とても無惨なことになっています。「子どもたちが自由に遊べる広場 みんながいつでも集まれる広場です」と標榜しているのですが、その空間の実に禍々しいこと!

「黄金町ロックカク」の中にはバスケットボールを楽しめる施設も整備されているようだ。それにしても、この金網、何とかならないの?
高い金網で張り巡らされているのです。「黄金町バザール」を鑑賞するために、KKの高架下周辺をウロウロしている時に、筆者はこの広場を発見しました。第一印象は、「拘置所ですか、ここは?」でした。内部に入った人間を外に出られないようにするための空間にしか見えないのです。高く張り巡らされた金網が、そう思わせるのです。拘置所の後に思ったのは、巨大なごみステーション、でした。柵の内部に大量のゴミを保管し、収集車が来るまで誰かが立ち入ったり、持ち去ったりできないようにするための施設に見えてしまったのです。

京急本線の高架下を利用した「黄金町ロックカク」の遠景
お子さんに遊び場を提供したいという事業者の方たちの親切心はまったく否定しませんが、なぜ、ここまでセンスの悪い“広場”を作ってしまったでしょうか? 筆者は頭を抱えてしまいましたよ。「広場感ゼロ」なんですから、このロックカクは。遊びに来た子供たちを外に逃がさないようにするための檻に見えてしまうのが最大の欠点です。どうして、こんなことになるのか? 要するに、勉強不足なのだと思います。国内外の自治体の先進事例を丁寧に研究すれば、こんな威圧的な広場を作るわけがありません。
筆者が子どもだったら、こんな広場に足を踏み入れたくありません。広場に拉致・監禁されて、お家に帰してもらえないような気がするからです。どうせ作るんだったら、もっと子どもたちが自発的に集まってこられる雰囲気の空間を作りましょうよ。お金がもったいないです。
と、厳しいことも申し上げましたが、基本、KKの高架下は最高です。日ノ出町駅から南太田駅までの区間には、ビルとビルとの合間を滑るように進む車両が見える場所が何か所もあります。高架そのものはビルで隠れている。だけど、車両だけが空中に浮遊して進んでいるように見えるのです。車両の重さが感じられず、まるで無重力のように軽やかに見えるので、「ここは宇宙空間なのか?」と思わず錯覚してしまうほどなのです。
筆者のこの文章、決して大げさではありません。嘘だと思ったら、一度、日ノ出町、黄金町などを歩いてみてください。高架と高架下と車両と街並みが絶妙なバランスで併存しているーーそれこそが京急の魅力の本質そのものだと筆者は確信しております。
それだけに、ロックカクの無惨すぎる広場には本当にがっかりしています。この広場は長く使うことになると思います。今からでも遅くないので、あの巨大な資材置き場、ごみステーション、拘置所のような空間をもう少しましなものに変更しませんか? 関係者の皆さん、よろしくお願いします。
鉄道を愛する者は、街を愛する者。街を愛する者は、人を愛する者です。
KKもすばらしいですが、実はほかにも魅力的な路線はたくさんあります。「千葉県立美術館→千葉市立美術館」という定番のルートを回る際の千葉都市モノレールや神戸の六甲ライナーも素晴らしい。青森県の弘南鉄道大鰐線も最高です。皆さんも自分のお気に入りの路線を育ててみませんか? 乗って、沿線を歩けば、きっと生きる気力が湧いてきますよ。(2025年9月26日20時14分脱稿)