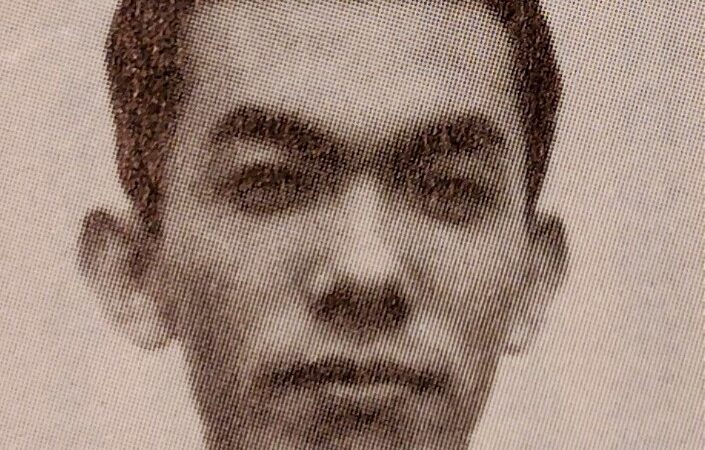毎年、陶芸雑誌の仕事で十数名の陶芸家を取材しているのだが、今年(2025年)の取材で、いつになく興味が湧いたのが“脱サラ陶芸家”というべき存在。異種業から転身した陶芸家はこれまでも少なからず出会ってきた。ただ、前職が美術・デザインや建築関係とか、社会に出て一時会社勤めをしはいたが、実家が陶芸関係の仕事だったとか……。何某か美術工芸と縁があることが多かった。しかし、今回取材したうちの三名は、普通のサラリーマンがある時、地元のワークショップや陶芸教室で初めて陶芸を体験し、そこから陶芸にのめり込み、ついに職業にするようになったのだ。
その一人、五十代半ばの唐津焼の作家は、郷里の島根でサラリーマン生活を送っていたが、三十歳の頃「組織の歯車になりたくない」という思いから、「最初から最後まで、自分で完結できる仕事」を考えていた時に陶芸に出会ったという。そして佐賀県の唐津に移り二人の師匠に師事。以来、古唐津に惹かれ、今日まで古唐津の写しに邁進する。
また、山口県出身で六十代半ばの萩焼の作家は、20代で自動車の整備士として働いていたが、萩での轆轤体験を切っ掛けに陶芸にひかれ、萩の製陶会社に再就職。そこで轆轤職人として大量生産の器づくりに励む。が、後に登り窯を体験して小工房に移り、土の配合から、轆轤、釉薬の調整まで一貫して取り組むことになる。そうして自身で登り窯を開窯。陶芸家として純朴な萩焼を模索する。
そしてもう一人は五十代半ばで青瓷に取り組む。彼は二十代後半のある日、陶芸教室の「スタッフ募集」の貼り紙がふと目に留まり、同教室に転職。仕事は陶芸とは関わりのないものだったが、教室の生徒さんたちが作陶する姿を見て、自分もやってみようと教室終了後や休日の教室で作陶を始めたという。そうして十数年教室で働きながら作陶を続け、大阪府の南端、泉南郡の実家に窯を開いた。
この三名に共通するのは、所謂“伝統工芸”を志向していること。アマチュアイズムは個性的表現に向かうと思いきや、むしろ技術的洗練に傾倒する。そこに一般的日本人の美意識を垣間見た思いがした。
会報その他の形式  美術評論家連盟 事務局2026年1月21日【会員短信】「“脱サラ陶芸家”に垣間見た日本人の美意識」藤田一人 はコメントを受け付けていません
美術評論家連盟 事務局2026年1月21日【会員短信】「“脱サラ陶芸家”に垣間見た日本人の美意識」藤田一人 はコメントを受け付けていません