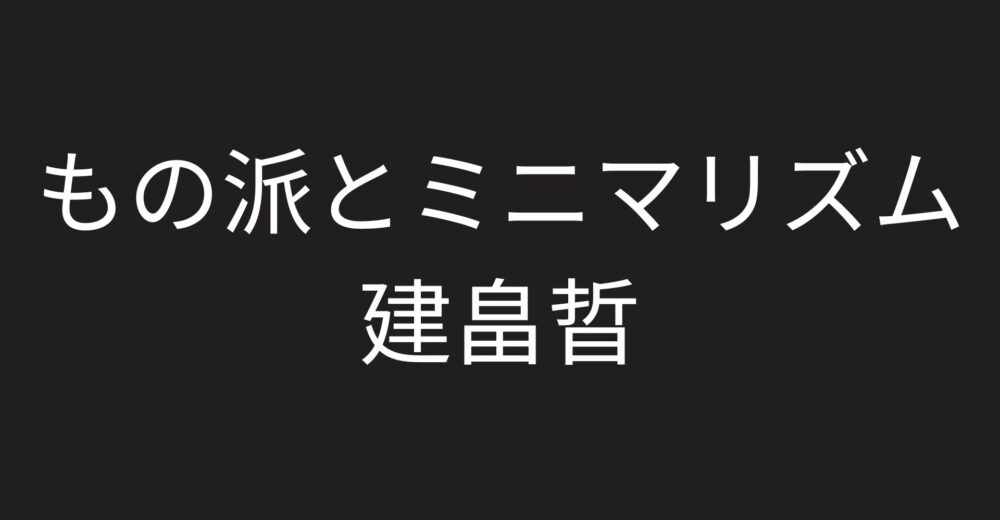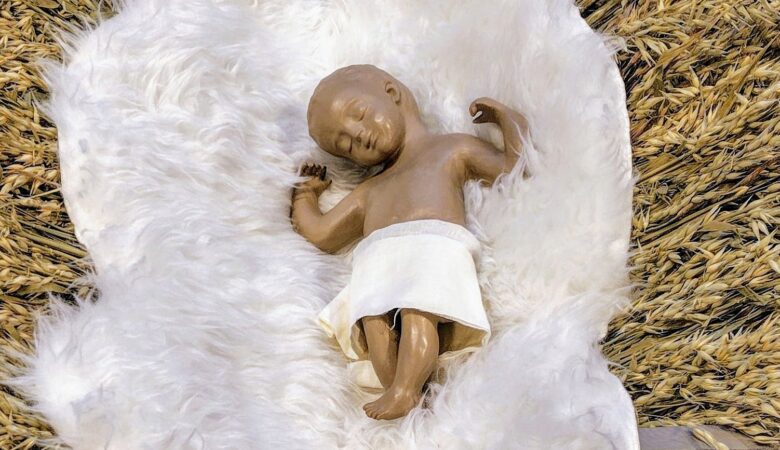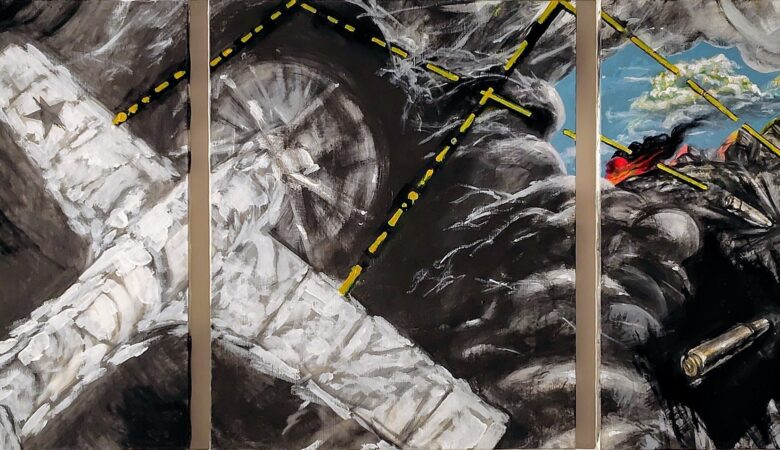(初出:建畠晢「もの派とミニマリズム」『ミニマル・アート』展図録、国立国際美術館、1990年より転載)
本展には、70年前後の一般に「もの派」と称される傾向に属していたと見なされる四人の作家、李禹煥、吉田克朗、小清水漸、原口典之の作品が出品される。最初に断っておかなければならないが、これは何も「もの派」自体をミニマル・アートの一環として位置づけることを意図するものではない。また影響関係を明らかにしようとするものでもない。むしろまったく別個の思想に依拠していたはずのある動向が、その一部において結果的に一見ミニマル・アートを思わせる表現を成立させたという興味深い事実を、対照的に示そうとするにすぎない。
もちろん両者の近似性は偶然ではなく、広い意味での反造形主義的な思潮を共有するものであったことは否定できないし、またミニマル・アートのみならずフルクサスやアルテ・ポーヴェラの動向が直接、間接に参照されていたであろうことは、時期的にも考えられることである。とりわけアース・ワークは彼らの中で、(反発をも含めて)強く意識されていたはずである。だがなおかつ、もの派の運動は内発的なものであり、その展開の過程でますます思想的な固有性が強化されていったと言わなければならないのである。[1]
*
峯村敏明はアルテ・ポーヴェラともの派に共通する背景として、工業化社会の産物に対するアンビヴァレントな感情、絵画芸術の死滅の予感、反芸術的気風の遺産、表現の客体性への希求、芸術の力の回復を自然の回復によって達成しようとする信条などを挙げている[2]が、こうした同時代的な背景はある程度まで60年代のアメリカにも言えることであった。ミニマル・アートの立体作家たちもまた、多くは無機的な工業素材を用い、たとえば基準単位を規則的に床に配置するカール・アンドレの「場の彫刻」や、彫刻の固有の属性を「ユニタリーな形態」へと還元するロバート・モリスなどのように、もはや(絵画、彫刻という)ジャンルの自己純化とは言いえぬ地点での“物体”のリテラルに提示に向かったのである。
フォーマリズムの極限的な実践であったこのようなリテラリズムは、しかしその還元的な方法論とはおよそ無縁な側面において、もの派の作家たちの反造形主義的な機運に大きな示唆を与えたものと思われる。端的にいえば彼らはミニマル・アートに即物的な感受性を刺激されたのであり(“シビれる”“ゾクッとする”というのが当時の彼らの用語である)、また床に直接作品を置くという“提示”の仕方を学んだのである。だがそのリテラリズムの内実は、両者では対極的ですらあった。ミニマル・アートではそれはイリュージョンの排除を意味したが、もの派ではまさしく「創造の否定」としてのあるがままの謂なのである。
*
「私は“秩序”と“構造”という言葉を放棄した」[3]と述べたのはドナルド・ジャッドである。たとえば彼は同形の箱を等間隔で一列に並べて見せるが、それは全体の秩序とか無秩序とは何ら関係のない「局部的な秩序、単なる配列」(local order, just an arrangement)[4]であり、それがただそうなっているという事実の直截な提示にすぎない。その上でジャッドは「形体、量、色彩、表面」といった造形的な要素を単なる物質の属性へと還元[5]することによって、イリュージョンなき物体を成立させようとしたのである。
だがこのような“態度”は、李禹煥によれば「対称性を失った事物の中性化」をもたらすに過ぎず、やがては観念のオブジェ化という表象行為として再び「近代の思想構造」へと埋没して行く危険性をはらむものであった。またもう一人のもの派の中心的な作家、菅木志雄にとっても、それは造形を「観念操作そのものの表象化」として提示することであり、やはり操作主義という近代概念の範疇での作業と見なされることになる。
このような近代批判にもとづくミニマリズムやコンセプチュアリズムの性急な解釈は、ある意味で60年代末の、操作の主体としての自己の否定という時代のスローガンに呼応したものであった。「すべては大初から実現されており、世界はそのまま開かれているのに、どこへまた何の世界を作り出すことができようか。」[6]と李は言う。あるがままの世界の無前提な受容という“態度”は、造形行為のみならず「還元」や「非関係的」という言葉を成立させる物体概念をも否定するものだが、それは結果的に彼(ら)の作品に開かれた構造としての“場所性”をもたらすことになった。
*
千葉成夫が指摘するように、関根伸夫の「位相‐大地」(1968年)の考えようでは多分にトリッキーな造作を、あえて「あるがままの世界」を顕在化させる作業として評価し、もの派の出発点を用意したのは李であった。これは地面に大きな円筒型の空を掘り、その傍らに掘り出した土を使ってちょうど同じ大きさの円筒型の土塊を配してみせたものである。李はその印象を「そのままで世界のあでやかさ、ともいうべき感動的な表情を見せ伝える一つの物体と化している」と述べている。すなわち「表象作業を行なう作家にとって世界は素材となるが、出会者にとってはすべてが世界のありようを顕わにする様相自体である。出会者の仕草において、大地を越えて」いるとし、その「構造は、あるがままの自然な世界を鮮かに発現している場所のありようの顕わな様相自体」であり、それ故に「直接的な触れ合いの世界を開示するものとなり得る」としたのである。[7]
だが、それはもちろん出会いのための作為を排除するものではない。李自身の作品に即しているならば、たとえば彼は自然石と人工的な鉄板を即物的に組み合せる。それは「非関係的」ではないが、二つの物質の在り方の“ズレ”そのものの構造化ともいうべき世界であり、自己完結的な作品とは別の空間の様相が開示されるのである。あるいは自然石がガラス板の上にのせられる。そこでガラスが割れようと割れまいと、それが「あるがままの世界」であることにかわりはない。しかし部厚いガラスに鋭いひびが放射状に走ったとき、あるいはわれわれは一瞬、顕在化された世界との鮮やかな出会いを体験することになるかもしれない。その時、“ズレ”という作為、“割る”という作為は、「時代の感得の形式」として選ばれたのであって、物体の概念には関わらず、イマジネイティヴでもなければリダクティヴでもないのである。
*
それにしても、トリッキーな造作の読みかえがもの派の出発点にあったという事実は興味深い。「位相‐大地」と同じ年に、東京画廊で「Tricks and Vision、盗まれた眼」展が開かれ、これにも関根伸夫は出品していたが、李は高松次郎の影の絵なども含めたこうした当時の「主知主義的視覚操作の伝統」[8]を価値転換させることによって、状況を一挙にリテラリズムに向かわせたわけである。しかし還元的な方法とは無縁にこのような鮮やかな転換が可能であったことの背景として、その視覚的な操作主義自体が(高松次郎のイリュージョニスティックな作品に典型的に示されているような)「『見えること』と『在ること』の剝離」[9]の実験をはらんでいたというもう一つの事実に注目しておかなければならないだろう。
それを逆に言えば、もの派の出発には、イリュージョンの排除という直接的な問題意識は、よくも悪くも稀薄であったということになる。関根ばかりではなく吉田克朗の太い鉄管の中に綿を詰めた作品や、小清水漸の石塊を中に置いた巨大な紙袋などの作品は、物質の即物的な存在感を顕在化させる作業であったと同時に、明確に操作主義的であり、また見方によれば(シュールレアリスティックとも言える)異化作用を有してもいたのである。非参照的であり自己言及的であるミニマル・アートとは、もの派は出自においても決定的に位相を異にしていたと言わなければなるまい。
*
だが、李の言う「あるがままの世界」を「状態」という言葉でとらえなおした菅木志雄は、当初から徹底して操作主義を拒絶した作家であった。もちろん彼も「物が一般的にある状態から極限としての『在る状態』を認識するには、媒体として人の行為を必要とする」と述べてはいる。この「在る状態」の認識もまた造形主義的な「新しく造りかえること、あるいはまたなにかしら構造的な組立の中に、ある実在感をぶち込んでユニークなしろものにする加虐的な性格を抹殺」[10]するものである。しかし、それのみではなく「置くこと」「提示すること」をもしりぞけて「放置という状況」のうちに「極限的に在る状態」を認識し、そのことによって世界に関わろうとするのである。彼が作品を直接床に配するのは、(プライマリー・ストラクチャーのように)台座を排除したからではなく、もともと「世界」(=状態)には「台座」などというものは存在しないからである。
ピエロ・マンゾーニは「世界の台」の上で地球をひっくり返してみたが、それはまさしく逆立ちをして世界を支えていると称している芸術の姿であった。世界の受容と創造のこれもまたトリッキーな転倒は、自然が彫刻となることの喩であると同時に、芸術の無根拠性(台座には台座がない)によって誘き寄せられた世界の観念化でもある。その意味では菅は世界の受容とも創造とも関わらない。彼はただそれを「極限として在る状態」に置きかえようとするのである。
彼はさらにこうも述べている。ものとその状況を「放置」しなければならないのは「その雄弁な語り口を封じ(中略)もの自体の持つイマジネーションを抜きさしならぬ状況でぶち壊さねばならない」[11]からだ。それは無作為ではなく、人為的に自然と等価であろうとすることであると言ってもよいかもしれない。したがって彼の“仕切る”場には「特殊な物体」(ジャッド)のような意味論的な葛藤はないが、しかしなお弛緩することのない相互依存的な関係が保たれているのである。
*
もの派とミニマル・アートを直接に対比させれば、他にもいくつかの事実を指摘しうるだろう。後者の主要な方法であった基準単位の機械的な反復が、もの派では李禹煥の平面作品や小清水漸の一時期を除けば、ほとんど見られなかったこと。もの派に絵画科の出身者が多かったにもかかわらず、色彩の問題が欠落していたこと。もの派がまったくと言ってよいほど、コンセプチュアル・アートには関わらなかったこと。また、もの派の一部の作品には(触覚的な意味での)即物感におもねるような面があったのに対し、ミニマル・アートは物体を(materialではなくobjectを)対象化していたこと。
しかし冒頭にも述べたように、もの派はミニマル・アートの一環でもなければ、その直接的な影響下に成立したわけでもなく、その異同を単に並べたてることには、さほどの意味はあるまい。もの派に若干影を落している汎神論的な思想の問題等、まだまだ検討すべき課題は多いように思うが、この小論は、とりあえず両者の共有したリテラリズムの問題の比較に留めておくことにする。
註
[1] もっとも「もの派」はいわゆる結社ではなく、“派”としての実体の有無についてさえ、議論が分かれているのも事実である。広く同時代の動向を言うならば、韓国の沈文燮らも含めて考える必要があろう。いずれにしても本展では、この四人を「もの派」を代表するものとしてではなく、ミニマル・アートの問題との対照において取り上げたわけである。
[2] 峯村敏明「『モノ派』とは何であったか」モノ派展カタログ、鎌倉画廊、1986年。
[3] Donald Judd, Statement, Complete Writings 1959-1975, The Press of the Nova Scotia College, Halifax, New York University Press, New York, 1975, p. 196.
[4] Donald Judd, Statement, Complete Writings 1959-1975, The Press of the Nova Scotia College, Halifax, New York University Press, New York, 1975, p. 196.
[5] もっともジャッド自身は例の「プライマリー・ストラクチャーズ」展(1966年)の際のステートメントで、還元的(reductive)という用語を否定してはいるが。Donald Judd, op. cit., p. 190
[6] 李禹煥「世界の構造」、『デザイン批評』1969年6月号。ただし引用は千葉成夫『現代美術逸脱史』(晶文社)1986年から。
[7] 李禹煥「出会いを求めて」『美術手帖』1970年2月号、p. 23
[8] 峯村敏明、前掲書
[9] 峯村敏明、同上書
[10] 菅木志雄「状態を超えて在る」『美術手帖』1970年2月号、p. 29
[11] 菅木志雄「〈放置〉という状況」『美術手帖』1971年7月号、p. 147