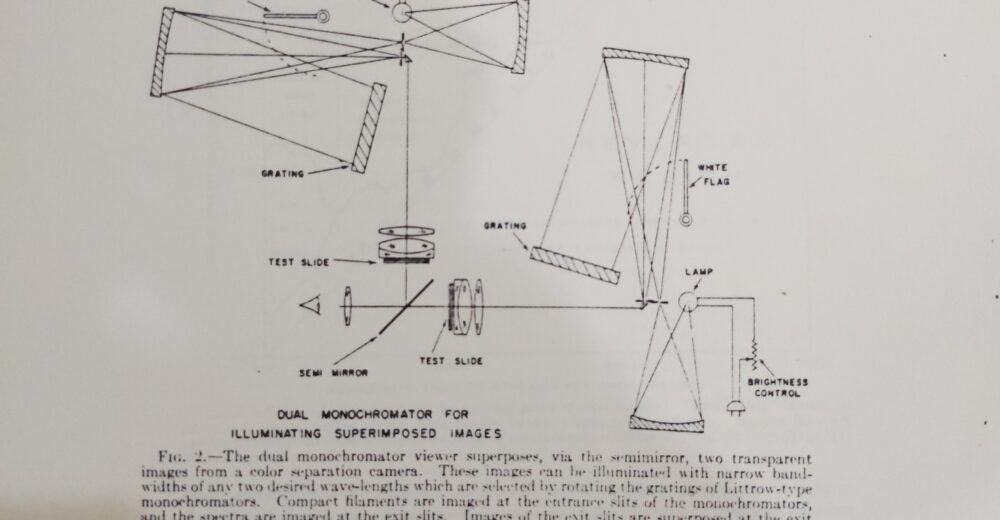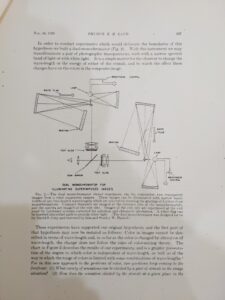
Edwin Herbert Land「Color Vision and the Natural Image Part II」『Proceedings of the National Academy of Sciences』(PNAS), Vol. 45, No. 4
河原温の「日付絵画」とランドの「レティネックス理論」をめぐる対話篇——地球の視覚経験と色の恒常性—
はじめに
河原温(On Kawara, 1932–2014)が研究していた「色彩論」が、エドウィン・ハーバート・ランド(Edwin Herbert Land, 1909–1991)のレティネックス(Retinex)理論であったという記事を執筆したところ、大きな反響を得た(註1)。河原は作品についてほとんど語らず、残された資料が創作の謎を解く数少ない手がかりとなる。そのため、彼が「色の恒常性」(color constancy)に関心を持っていたことが明らかになった点は重要である。「色の恒常性」とは、照明条件(光源の色や明るさ)が変化しても、私たちの知覚する物体の色が大きく変わらずに安定して見えるという視覚の働きである。しかし、それが通称「日付絵画」(《Today》シリーズ)とどのように結びつくのかは、いまだに大きな謎である。
今後の資料調査から両者を結びつける証拠が出てくるかもしれないし、まったく出ないかもしれない。そこで、ここからは美術史家の富井玲子との相談のもと、プラトンの「対話篇」に倣い、私たち自身の推論と、記事公開後に交わした識者との対話を紹介することで、より開かれた議論を喚起したい。
ランドの位置づけ 小松英彦との対話
ランドは19世紀以来の網膜中心の視覚研究を越え、幾つかの実験を経て網膜と脳のフィードバックによって色を認識する概念を提示した(Land 1964)。特にジョン・J・マッキャン(John J. McCann, 1938–)との共同研究によって、概念モデルだったレティネックス理論はアルゴリズムにまで発展し(Land and McCann 1971)、カメラのホワイトバランスや画像処理ソフトの補正技術に応用されていった(Jobson, Rahman, and Woodell 1997)。しかし、現在の色覚研究ではランドの名を目にすることは少ない。そこで神経生理学者の小松英彦名誉教授(生理学研究所)にその位置づけを確認した。
小松氏はこう述べる。「LandのRetinex理論は、70年代から80年代にかけて色覚研究の世界に大きな影響を与えた。David Marrの『Vision』(Marr 1982)は視覚の計算理論に大きな影響を与え、その中でLandの理論は詳しく取り上げられている。明暗や色の知覚に計算理論を持ち込んだ点でLandとMcCannの貢献は大きい。ただし、脳でそのような計算が行われているとは考えにくく、色恒常性は複数のメカニズムが関与しているのだろう、というのが現在の多くの研究者の見解である」
ランドとマッキャンが1971年にアメリカ光学会誌(JOSA)に発表した論文 “Lightness and Retinex Theory” は、反射率ではなく照明に依存しない明度(lightness)の生成によって、視覚が画素間の相対比をたどり大域的な色を推定する仕組みを示した(Land and McCann 1971)。さらに「Single-Scale Retinex」が開発され、照明補正済みの反射率を導き、カメラの自動補正に応用された(Jobson, Rahman, and Woodell 1997)。その後「Multi-Scale Retinex」へと発展し、スマートフォンやHDR処理に広く使われている。
ランドとゼキの交流 石津智大との対話
ランドを最も高く評価したのは神経生物学者のセミール・ゼキ(Semir Zeki, 1940–)であった。ゼキの研究室出身で神経美学者の石津智大教授(関西大学)に意見を聞いたところ、「ゼキ先生とランド博士には親交があった。相談事があるとプライベートジェットでロンドンに会いに来られたそうだ。ゼキ先生からはretinexのことを学んだが、Retinexは画面全体の光の波長比率で色知覚が決まる理論であり、ホワイトバランスに応用されているが、現在では記憶や知識によるトップダウンの影響も強調されており、Retinexはあくまで一つのモデルにすぎない」と答えた。
小松氏と石津氏はいずれも、レティネックスを「人間の色知覚を説明する一モデル」と位置づけつつ、アルゴリズムとしての応用の意義を認めている点で一致している。
石津氏はまた、美術評論家の峯村敏明が河原温の「日付絵画」について“グッゲンハイムの例の螺旋階段を最上階まで上りつめた時の光景だった。1966年から2013年までの、つまり、河原《TODAY》のタイトルで制作し続けた48年間の日付絵画が、生前の河原によって1年1点ずつ選ばれ、横一列に並べられていた。~中略~48枚のタブローはまったく違った表情を見せていた。~中略~気付かないわけにはいかない差異の強調である。河原本人の演出にちがいないと、私は直観した。”(註3)と書いたことを引き合いに出し、「Retinexが周囲との対比で色を決定するとしている点と、並置された『日付絵画』によって微妙な色差と独立性・唯一性に気付く効果は似ている」と述べた。そして、ランドがそれまでの「物理量と網膜上の処理」から「恒常性や経験による推論」といった脳の機能を組み込むことで更新しようとした色彩理論と、「“網膜的”な絵画のあり方を超えようとする、河原らのコンセプチュアル・アート」に対応関係があると指摘した。それらは確かに、眼(視覚)から脳(概念)への移行を象徴しているといってよいだろう。「日付絵画」は、視覚と概念が切り離されておらず、絵画という古典的な形式の中で融合しているため、その変遷を示すのに一層重要な意味を持つのである。
河原温にとっての絵画 富井玲子との対話
富井は「絵画であることが重要であったのではないか」と言う。欧米のアーティストとは違って、「赤瀬川原平、荒川修作、小野洋子、河原温、松澤宥といったコンセプチュアル・アートの先駆者は、すべて絵画から出発し、絵画との格闘の中から独自のコンセプチュアリズムを開発している」と指摘する。日本は西洋的な絵画では後進国であり、最新の絵画技法を追いかけてきた。欧米において絵画という形式自体が消失したり、後退していっても絵画へのこだわりを捨てきれなかったのかもしれない。富井は「絵画における遅延コンプレックスがコンセプチュアリズムにつながったのではないか」と考察する。
つづけて、「今回の発見で私が得た収穫は、河原温における具体的な関心の所在(の可能性)を突き止めて、色彩が概念に還元しきれない次元を持つことを、私自身が理解することができたことでしょう。私の理念的な日本型コンセプチュアリズム論はあくまで歴史論でしかないのです。いわば、歴史家のコンセプチュアリズムですかね。今回は、河原温の色彩論的研究の可能性を知ることで、河原温にとってなぜ「絵画」だったのか、という理由の一つがわかりました。つまり、色彩を問題にする限りは、ミニマル絵画すらもモダニズム的欺瞞をはらんでいるということでしょうか」と語った(註4)。
地球に注ぐ光のカラーチャートとしての「日付絵画」
私はこれに対し「日付絵画」の色の決定には、「都市の緯度と大気の色温度が関わっているのではないか」という仮説を示した。緯度が高ければ光は青みを帯び、低ければ黄みがかる。河原はこうした都市ごとの光環境を作品に取り込み、地の色で表現したのではないか。石津氏も「都市の緯度的なベースカラーの違いを意識してホワイトバランスを外していた可能性は面白く、日付と場所をセットにした説明になる」と応じてくれた。
河原温の「日付絵画」は、世界130以上の都市で制作されている。河原は滞在先の都市ごとに、その日の現地の言語(欧文アルファベットによらない場合にはエスペラント語)と表記で日付を描き、作品の箱にはその都市の新聞を貼り付けることもあった。したがって、「日付絵画」は常に「どの都市で描かれたか」と結びついている。
例を挙げると、ニューヨーク、東京、メキシコシティ、パリ、ベルリン、デュッセルドルフ、ケルン、ロンドン、ブエノスアイレス、ストックホルム、オスロ、ヘルシンキ、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ヒューストン、シカゴ、香港、ソウル、北京、シドニーなどである。まさに地球を何周も回っていることになる。
そして、現地の言語と表記で日付が書かれており、フィルム写真のような物質的な刻印ではないが、記号によって強く結びついている。アクリルで描かれた地の色は、黒や赤、緑といった様々な色が塗られている。そして1日で描くというルールが課されている。そこまで厳密に制作されている作品において、色だけが主観的で恣意的に決められているとは考え難いというのが私の見解である。
さらに、地球の様々な都市を回ることで、当然、その都市に降り注ぐ光の質の違いに気が付いていたはずである。その際、照明が異なるのに、なぜ同じ「白」と認識できるのか。という根本的な疑問を抱いても不思議ではない。それは印象派の画家たちですら経験していたことである。例えば、クロード・モネが描いた北フランスの空は、比較的高緯度に特有の青紫の色合いを帯びている。
緯度が高ければレイリー散乱によって空は青く、低ければ大量の水蒸気とエアロゾルの影響でミー散乱が起こり黄色っぽく見える。こうした色温度の違いは、日常生活では気づきにくいが、急速な移動では強く感じられるだろう。「日付絵画」には、緯度の低い都市ほど赤が多く、高緯度の都市ほど青が多い傾向がある。黒い地は夜を示しているのかもしれない。
緯度によって虹のように綺麗なスペクトルの変化があるわけではないが、ある程度、都市の大気の色温度と相関があると考えてもおかしくはないだろう。つまり、「日付絵画」は地球全体を覆う光のカラーチャートとして構想されたのではないか(註2)。河原が富井に「『日付絵画』(“Today”)を理解するためには『色彩論』を勉強しなければならない」と語ったのは、この意味であろう。
結び
これはあくまで仮説にすぎない。しかし、ランドの「色の恒常性」への関心と河原の制作態度を結びつける理屈として浮上してくる。秘密主義的に制作された河原の作品に対し、私たちはオープンな「対話」を通じてその謎に迫りたい。
註
1.「河原温の「日付絵画」と20世紀の「色彩論」『美術評論+』2025年7月28日https://critique.aicajapan.com/12318
2.色彩学者の日髙杏子教授(女子美術大学)は、2008年にMoMAで開催された「Color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today」展で河原温の《Today》シリーズを数多く見たことを知らせてくれた。
3.石津智大教授の記憶による。福田浩司氏のアドバイスにより現在、該当文献を確認中(2025年9月4日追記)。
峯村敏明「25時の美術と批評」『Booklet 24 美術と批評』慶應義塾大学アート・センター、2016年、pp.13-14。(石津教授により文献が特定された。2025年9月11日追記)
4.富井玲子による河原温の色彩研究に関する知見(2025年9月5日追記)。
参考文献(References)
- Land, E. H., & McCann, J. J. (1971). Lightness and Retinex theory. Journal of the Optical Society of America, 61(1), 1–11.
https://doi.org/10.1364/JOSA.61.000001
-
Jobson, D. J., Rahman, Z., & Woodell, G. A. (1997). Properties and performance of a center/surround Retinex. IEEE Transactions on Image Processing, 6(3), 451–462.
https://doi.org/10.1109/83.557356 -
Marr, D. (1982). Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information. San Francisco: W. H. Freeman.