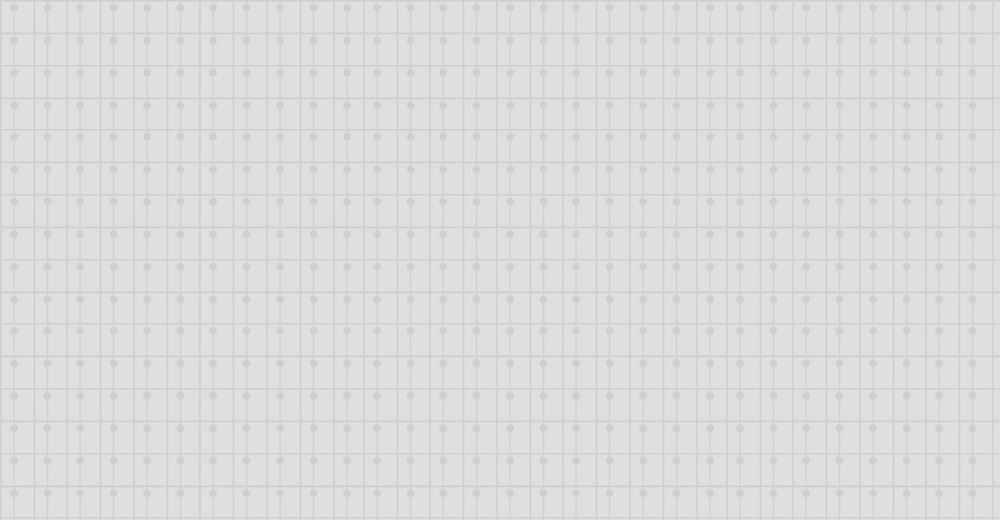言葉というのは不思議なもので、今喋ったり書いたりしている人の中で、その言語を一から発明したものは誰もいない(*1)。だから私の言葉も、当然に誰かから貰ったものだ(*2)。
作品が出来上がった後からなんやかんや言うだけの存在である美術評論家など、実際に作品を作り出してみせる作家になり損なってなるものであって、最初から批評を志す者など信用ならない。などというのはあくまで持論であるが、まずそれは自戒として弁えておくべきことだと思っている。自分の言葉は、できれば作家に、というか制作に寄与するものであるように願っているのであって、芸術が分からない者に偽の安心を与えるつもりも、芸術に達しない作品にエクスキューズを与えるつもりもない。その言葉たちも、そもそも作家から貰ったものが大半なのだ。
インターネットを検索しただけでも、「批評家とは公衆の書記にほかならない」とか、「パリにおいて、真の批評は談話の間に作られる」とか、批評家にまつわる「名言」が紹介されているが(*3)、いずれも批評家がそもそも孤立した判断の主体ではないことを指摘するフレーズである。芸術が議論喚起的な作品を歓迎するのは、このような人々の侃々諤々の議論の中からこそ、新しい芸術についての価値判断がようやく生まれてくるからだろうし、飲み会において、作家の「あの作品はさぁ」という一言が、評論家のそれよりもよほど正鵠を射ていることもしばしばある。批評という行為は、批評家の独占物ではなく、せいぜい書記にすぎないというのはそういう意味だろう。
前回、うっかり会報編集長などという肩書を得てしまったが、その際の編集テーマにあったものは「お喋り」であった。それは上記のように、批評の言葉が、最初は他愛ないリアクションとしての発語の応酬から生まれでてくるものだという観念があったからだ。COVID-19パンデミックとその対応の中で、展示芸術も様々に制約を被った。舞台芸術、音楽に比べれば、その影響は随分と穏やかと言えるレベルではあったがしかし、芸術の活動を下支えする作家らの経済状況や、「交流」そのものは随分と阻害された。その影響の顕在を指摘するには手持ちの具体的な材料が少ないのだが、まるで生長のための土壌が痩せていくような「実感」として感じられている。
とはいえ、作り手に資するというのは、作家を手放しに誉めるという事では当然ない。「評論家」という肩書でtwitterでつぶやいて見せれば、その肩書は権威に写るためか、想定外のリアクションを食らうこともある。たとえば、横尾忠則の多作さと、関心の在り方のアンバランスさについて、次のようにつぶやいたことがある。
「横尾忠則GENKYOを東京都現代美術館で見た。横尾忠則は、絵の内容よりも異常な物量(どんだけのペースで描いてんの?)と、モチーフに対するなんだか関心の無いような、そのくせ別に観察と描写は嫌いでないんだろうな、というような気持ち悪さがずいぶんあった。異常な仕事だ。」(*4)
「コラージュ的な仕事を、しかしペインティングでやろうという時に、変に描けちゃうのでじゃあ描くかってやってる感じ。モチーフに思い入れとか愛とかこだわりとか無いの。無いんだけど、まぁ描けるしそれなりに楽しいんだろう。でも詰め切らない(詰め切ってたらあの枚数描けてないだろう)。なんなん?」(*5)
すると
「この人の作品テーマには関心が無いような感想がこうまで賛同されているのは何故だろう。如何にもフォームの印象でしか語れなかった10年代の生き残りという感じ。ジャギーとドットの事しか語れないんだろうか。印象批評でさえ無いぞ、こんなの。参考にするとか言ってる奴、大丈夫⁉︎」(*6)
「要約したら、異常な作品量でそれが可能なのは題材に対して無関心で粗製濫造だからに違いない気持ち悪い、でしょ。
これをいう人が批評家を名乗っていて、間に受けてる人も多いというのには、ひとこと言っておかなきゃって気にもなるますわ。」
(略)」(*7)
とまぁ、SNSなので、誤読や伝わりきらないところがあるだろうが、最初からこの調子である(*8)。横尾作品における「気持ち悪さ」は作品の性質の話であり、それが即価値の低さではないのであるが(別に即価値が高いのでも、もちろん無いのだが)、そのように説明をしても通じない(*9)。しかし実は、「なるほど」というリアクションに味を占めるよりも、むしろこのようなリアクションにこそ応答していく必要があると考えている。一点には、それは、物言わぬ観客もまた、このやり取りを見るものだということ。もう一点は、芸術というジャンルが必然的に持つはずである、履行すべき「義務」にかかわるものだ。それは美術が、諸芸術の一ジャンルではなく、「代表」と見做される”特権”の正統性がどこから来るのかという問題から必然的に導き出されるものである。
現代美術を専門にしているというのは、日々更新されんとする新しい美意識について、ジャッジを下していくということである。その新しい美意識は、なんと驚くべきことに、専門家たちの一時的な結論を経て作品を保存、収集し、(理念としては永久に)後世に伝えていくという仕組みになっている。その仕組みは、篤志家の個人的な営為ではなく、行政機関が国際的な枠組みを策定までして行っているものなのだ。
民主主義国家において、行政が特定の美意識を擁護するというのは、当然(特に小さな政府志向の米国風リベラリズムからすれば)、行政の不要な介入でしかないだろう(米国において私立美術館が大きな存在であるのは、そのような国風と不可分であろう)。では何故国家の制度が教育制度や博物館行政を通じ、諸芸術のうち特定ジャンルであるはずの美術について擁護せんとするのか。それは、美術を代表としつつ、新たな美意識の展示、そして議論を通じて「美の公共圏」を形成し、それをもって国民の美的意識を涵養し、あわせて民主的な公共圏の形成に資するため、という形しかあり得ないだろう(*10)。「専門家が議論を先導し、非専門家である市民がその話を聞き入れる」とかアウトリーチとして「あなたもアートについて考えてみませんか?」ではない、各自がその美意識を開陳し、議論をしていくことで止揚される美意識の公共圏を想定する以外に、芸術が”特権”的であること、そこに権威が最終的に発生することの正当性は私には思いつかないし、その義務が発露する瞬間とは、まさに議論が喚起される時(や、過激には「炎上」が発生している瞬間)なのだと考える。加えて言えば、その時を好機とばかりに持論を展開しない論者や作家は、現代美術のプレーヤーとしての気概が実はないのではないかとさえ疑ってしまう。ということは、鑑賞者もまた、人のしてみた評価に噛みつくのであれば、「自分はこのように良いと思った」という主張が無ければ、結局は詮無いということでもある。そして放っておけば、専門家が下したジャッジに同意したことにされてしまうのだから、異論があればどんどんと言った方が良い。
何よりこの対話のなんと「平和」であることか。そこに賭けられているものが、正しさでも善悪でもなく、ただ美についての議論でしか無いのだ。それによって死ぬ者もなく、利益調整の政治闘争の場でもない(*11)。だからこそ、誰もが対等に、闊達に、自由な立場で、ただ互いの美意識の違いから来る豊かさと、論の妥当性だけを求めて、安全に対話していけるのだ。
(*1) いやいや、例外的な好事家やパフォーミングアーツの演者、フィクションを自作自演する場合や、暗号制作者、プログラミング言語の制作者を数えることができるかもしれない。意外といるな。
(*2) その基底には、思春期にインターネットから貰った言葉がたくさんある。
(*3) それぞれ三木清『哲学ノート』、サント・ブーヴ 「わが毒」らしいのだが、きちんとは調べられていません。すみません。
(*4) https://twitter.com/gnck/status/14185761614629068
(*5) https://twitter.com/gnck/status/1418577414133669896
(*6) https://twitter.com/cha_bo39/status/1418748521247694857
(*7) https://twitter.com/cha_bo39/status/1418812837351378953
(*8) ちなみに東京都現代美術館で大規模回顧展が開催される横尾とgnckのどちらに権威があるのかは論を待たないだろう
(*9) うえに、筆者に一応寄せてくれたのであろう語彙も使うのだが、良く分かりませんでした。
(*10) そうでなけば、芸術的価値を判断する美学ではなく、より汎用に適用可能な「造形学」こそが、美術の王道として選び取られるはずであろう。
(*11) むしろ専業になってしまえば、真の美の議論ではなく、自らのポジションをいかに独占し、堅守するのかというモチベーションが否が応にも発生してしまう。その悪影響をいかに打破するのかということがまさに専門家倫理の問題となってくる