
展示風景
「デコーディング・ワンダー」
アーティスト:インテクスト(外山央、真下武久、見増勇介)、金澤韻、廣田碧、八木良太
会期:2024年6月7日~6月23日
会場:The Terminal Kyoto
「デコーディング・ワンダー」と題された展覧会が、1932(昭和7)年に建てられた総二階の京町家を復元した多目的空間、The Terminal KYOTOで開催されている。もともとは、呉服問屋の名門、木崎呉服店の創業者、木崎安之助によって建てられ、当時は呉服商が営まれていた、間口約9m、奥行き50mという間口が狭く、奥に長い典型的な「うなぎの寝床」である。坪庭や奥庭、書の間、床の間がある、格式のある家といってもいいだろう。京町家が駐車場やマンションに置き換えられ、伝統的な風景に加えて、それを養っていた教養やコミュニティが喪失されることに対して危機感を抱いた運営者によって修復され、知識・知恵や技術を伝承し、新たな知恵とコミュニティを醸成する場として活用されている。
現代アートの展覧会の会場としても使用されているが、この伝統的な京町家を使いこなすのは難しい。いわゆる「ホワイトキューブ」ではまったくなく、むしろ江戸時代から継承される日本家屋の一様式であるし、そこに掛け軸や屏風、陶磁器といった古典的な様式で展示するのは確かに合うかもしれないが、「今日的」な表現にはならないだろう。
インテクスト、金澤韻、廣田碧、八木良太によって開催された「デコーディング・ワンダー」は、非常に今日的であると同時に、近年の現代アートの形式が抱えていた矛盾を創造的に解決したものであったといえる。
「デコーディング・ワンダー」の「デコーディング」(復号化)とは、ソフトウェア用語ともいえるが、今日においては圧縮されファイルや暗号化されたデータなどを復元する際に使用されることが多いだろう。この展覧会では、さまざまなコードが世界に漏れ落ちていて、それらをデコード(復号)したときに現れる驚きのようなものがテーマといえる。

展示風景
展覧会には、環境や物体、文章などが、読み取りが難しい状態に変換された作品が並ぶ。例えば、入口の「見せの間」に置かれた廣田碧と岩田拓朗の作品《新宿》(2020)は、スケルトンになって中身が見えて「看板」といってよいが、「看板」が普段、”感じている”ものを光と音によって復号する。ここは明滅する光と、新宿の雑踏が流れている。2020年の雑踏なので、コロナ禍の只中でおそらく前後のものとはかなり異なるだろう。

八木良太《Untitled》(2006)
八木良太の制作したルービックキューブの作品《Untitled》(2006)には、各ブロックにアルファベットが印字されており、回転を繰り返すと延々と別の単語が生成される。あるいは、かつて小学生の色覚検査で使用された「石原式色覚検査表」の中で、色覚異常者だけが視認できるという「石原表4類表」をモチーフにシルクスクリーンを制作している。

八木良太《Ishibashi Plate No.19》(2006)
この石原色覚異常検査表というのは、もともとは陸軍の軍医である石原忍によって徴兵検査のため使われたものだ。戦後も色覚異常を発見する優れたシステムとして継承されたが、差別を助長したり、不利益を被ったりするといった理由により、2003年には定期健康診断の必須項目から削除されている。しかし、大人になって気付くことで、希望した職種につけないというような問題も発生したため、2016年以降、法律が改正され、復活している学校もある。
そのような経緯もあって、この独特な表自体、若い人の中には知らない人もいるかもしれない。また、近年の研究により、いわゆる3色覚を正常、2色覚が異常とするのは問題があり、人類が生存するための多様性として継承されてきたものだという知見に変わってきていることも付け加えておきたい。また、「石原表4類表」は、「正常色覚」だけではなく、「異常色覚」でも認識しにくい、という指摘もあることも留意されたい。ともあれ、「正常色覚」には抽象画、あるいはドットを大きくした抽象的なポップアートにしか見えない「石原表4類表」を通して、さまざまな知覚の形態によって、感じられる世界があるということを知ることは重要だろう。
今回、テキストとして参加している現代美術キュレーターでもある金澤韻は、あえてキュレーター的な網羅的な解説を放棄し、アーティストや鑑賞者と同じ地平に立って、作品やわれわれが生きている世界の多様性を導く言葉を、エッセイのように、あるいは鑑賞の感想のように紡いで鑑賞体験を豊かにしている。
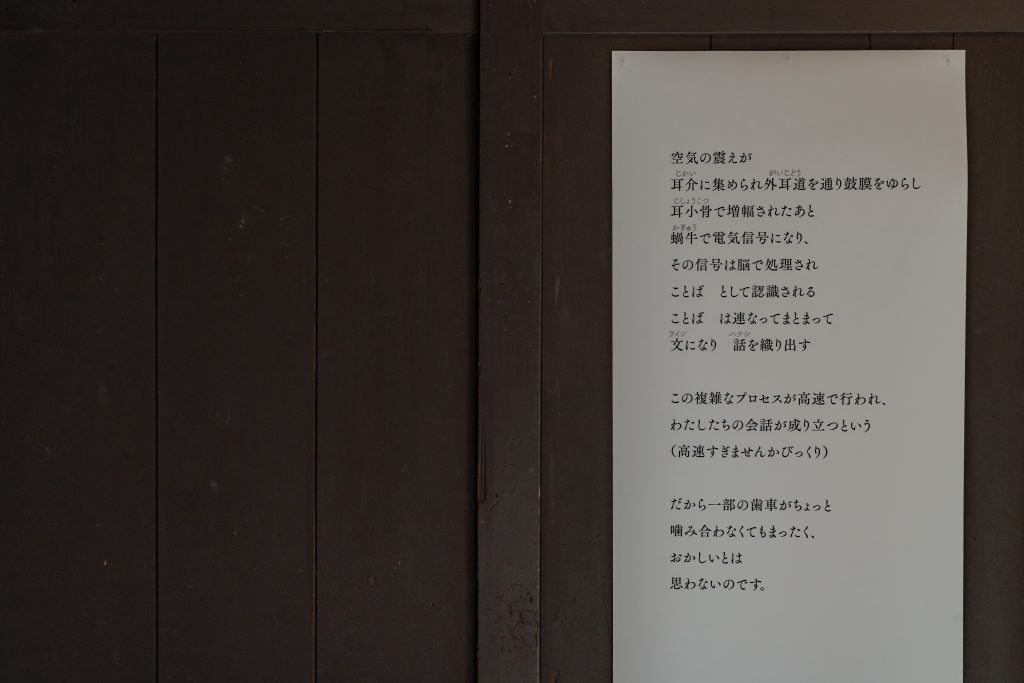
金澤韻《デコーディング・ワンダー》(2024)
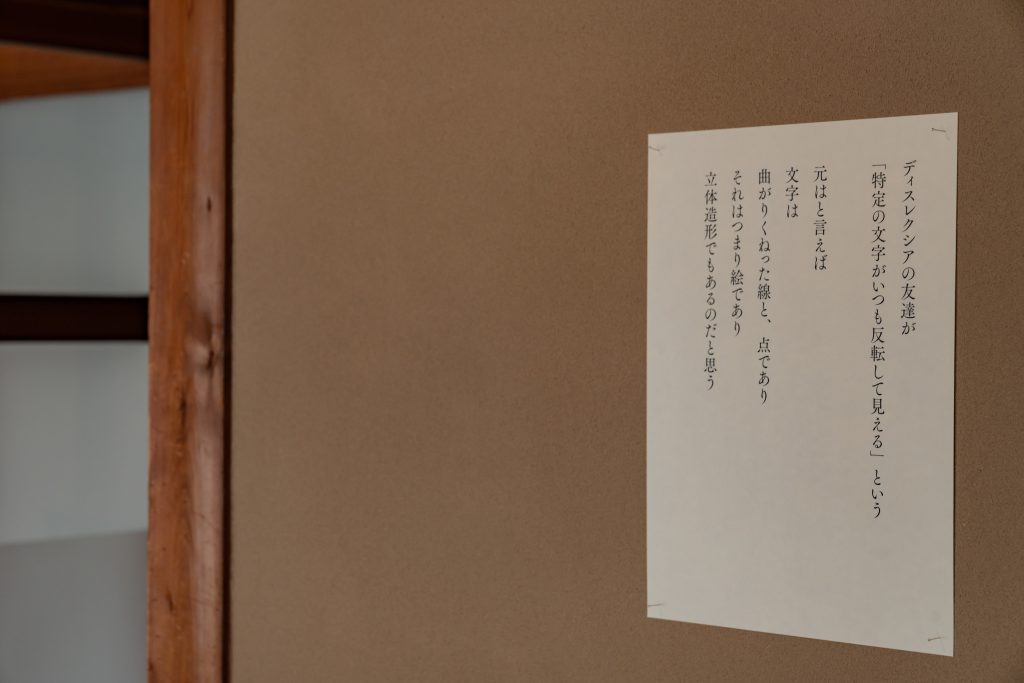
金澤韻《デコーディング・ワンダー》(2024)
なかには、LiD/APD(聴覚情報処理障害)やディスレクシア(読字障害)の解説を、私的なあるいは身近な友人のエピソードを交えて、言葉にしている。客観的で超越的な指揮者、あるいは演出家として振る舞うキュレーターの役割からは、逸脱した私的で最低限度の言葉の介入であるが、読み込むこと自体が困難な人がいることを考えると、作品に没入しやすい最適な方法であるし、実は、高度で難解な解説と、テキストや資料主体の現代アートでは、誰もがAPD/Lidやディスレクシアに陥っているのではないかと思わされる。

インテクスト《dimensional wall(book)》(2018-)

インテクスト《dimensional wall(book)》(2018-)

インテクスト《dimensional wall》(2018-)
インテクストは、デザイナーとプログラマーからなるチームでもあり、メンバーが世界各国で集めた辞書を持ち帰り、それらを裁断することで、意味からでは見えない、形から読み取れるものを提示している。例えば、ヨーロッパ語圏からアジア語圏まで裁断した辞書の断面を地理的な順番で並べる作品では、言語や組版の構造の類似と差異が見えてくる。当然同じヨーロッパ語圏とアジア語圏では視覚的に近いが、新しい人工文字であるハングル語は異なる様相を見せる。また、オランダとインドネシアといった遠い言語の類似性から、植民地支配の名残りが見えてきたりする。
町家全体に配置された作品群には、そのような謎かけのように変換された情報のコードの作品が展開されている。しかし、金澤の少しのエッセイのようなヒントを通して、それが何を示しているのか、読み取れないかもしれないが、何かあるのではないか、と想像させられる。

インテクスト《super reflection(WHAT’S THE COLOR OF MIRROR?)》(2021)

《reading method (Tower of Babel [ English]》(2019)
「デコーディング・ワンダー」とは、おそらくレイチェル・カールソンの「センス・オブ・ワンダー」から取られたものだと思うが、それぞれが感じている世界を「デコーディング」し、感じられたならば、もっと豊かで多様性に満ちた驚きの世界が立ち現れること示唆している。本展では、自然が感じられる町家で、自然や人間の知覚の複雑さ、それを感じることの豊かさ、驚きを示すことで、違いを巡って延々争う今日の私たちの世界に、違うことの豊かさの有り様を見せること成功しているといえる。
さて、本当はもっと多くの作品があり、今までのキュレータ―/アーティストシステムではない形式の創造的発明についてももう少し洞察ができると思うのだが、あまり時間がなく、本稿を書いている6月22日時点では明日まで、ということで会期中の情報提供を重視し、この後は大幅に改訂するかもしれないことをご容赦ください。




















