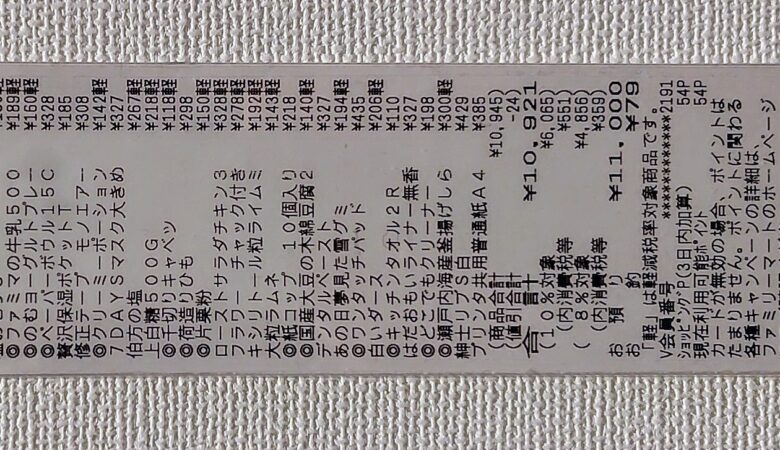「夢二式」という呼称で知られる細身で可憐な女性像を多く描いて巷で人気を博した画家、竹久夢二(1884〜1934年)が欧米を訪ねたのは、1931〜33年。50年の生涯においては最晩年のことだった。ここでは、その旅先の米国で描いた油彩画《西海岸の裸婦》に注目したい。異国の地では学べるものを学び取ろうという夢二の強い意欲が感じられる力作だからだ。この作品は今、大阪市のあべのハルカス美術館で開催中の「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」で展示されている。

竹久夢二《西海岸の裸婦》(1931〜32年、油彩、カンヴァス、夢二郷土美術館蔵)
この絵は、不思議な魅力をたたえている。まず興味を引かれるのは、横たわる裸婦をモチーフにしていることだ。ジョルジョーネの《眠れるヴィーナス》やティツィアーノの《ウルビーノのヴィーナス》をはじめとする、西洋美術の裸婦像を思い出す人は多いのではないか。欧州の前に渡米して1年数ヶ月を過ごしたということはあるが、19世紀後半には印象派の表現が渡るなど、米国ではやはり、欧州の伝統上で美術が展開していた。西洋の地を踏んだ夢二は、自分のヴィーナス像を描こうとしたのかもしれない。
腰布を描かなかったのはなぜか
夢二はほぼ独学で絵を描き、いわゆる画壇とは一線を画した活動をする中で、独自の画風で一世を風靡した。出版物を通じて広く認知された「夢二式」と呼ばれる少女の描写は、ポップカルチャーに近い世界の産物だ。しかしそれを本流を外れた要素と見るべきではない。ユーモアに満ちた戯画や奇想天外な内容のまるで漫画のような物語絵、市民を鑑賞者に想定して制作された浮世絵などが日本文化の根底に古くからあり続けてきたことを考えれば、むしろ夢二の絵画を本流の中での位置付けることも可能になるだろう。
さて、改めてこの絵をじっと眺めると、根底に「夢二式」があることが分かる。顔を見ると西洋人のモデルであることはわかるが、胴体は細くて腕が太く、決して妖艶だったり蠱惑的(こわくてき)だったりといった形容ができるヌードとは言えない。むしろそのアンバランスな描き方自体が、なんとも不思議な魅力を放っており、それこそが「夢二式」なのである。
背景の斜めの縞模様に同化する形で配置された裸婦の白い肌はなかなか輝かしく、装飾的な背景の中で存在感を際立たせている。夢二は、美しい白を出すのに腐心したという。だからこそ、なまめかしさが感じられるのだろうか。
当初、実は腰布が描かれていたそうだ。腰布がない欧米のヴィーナスの表現に近づこうとしたのか。警察の介入などで裸婦を腰布で覆ったいくつかの美術史上の事件を想起させるが、どうなのだろうか。ひょっとしたら、腰布が斜めのストライプの調和を乱すと考え、背景と同化させるために描かないことにしたのではないかと筆者は想像したのだが、いかがだろうか。耽美的な志向を貫いたのではないかと思うのだ。
夢二が絵を通して描こうとした美の本質とは?
「鳥はその声を描き、花はその香りを描く」
こんな一節が『竹久夢二遺作集』に収められているという。何と素敵な言葉なのだろう。鳥にしても花にしても、たいていの場合は、まずその姿を描くだけでも十分に美しさが伝わるはずだ。夢二は描く対象の内面をも描き出すことでこそ、美の本質を余すところなく表現できると考えたのではなかろうか。
そもそも声や香りを視覚的に描くことはできないはずだ。しかし、美しい声やいい香りを感じさせる描写は、すぐれた画家なら可能だろう。夢二は米国でモデルの姿を描くなどしたうえで《西海岸の裸婦》を仕上げた。夢二が感じた女性の本質的な美を、西洋の流れが育んだ美と夢二式の美とをないまぜにしながら、懸命に表現した跡がうかがえる。
【展覧会情報】
◎展覧会名:生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界
◎会場:あべのハルカス美術館
◎会期:2025年1月18日(土)~ 3月16日(日)
◎公式サイト:https://www.ktv.jp/event/yumeji2025/