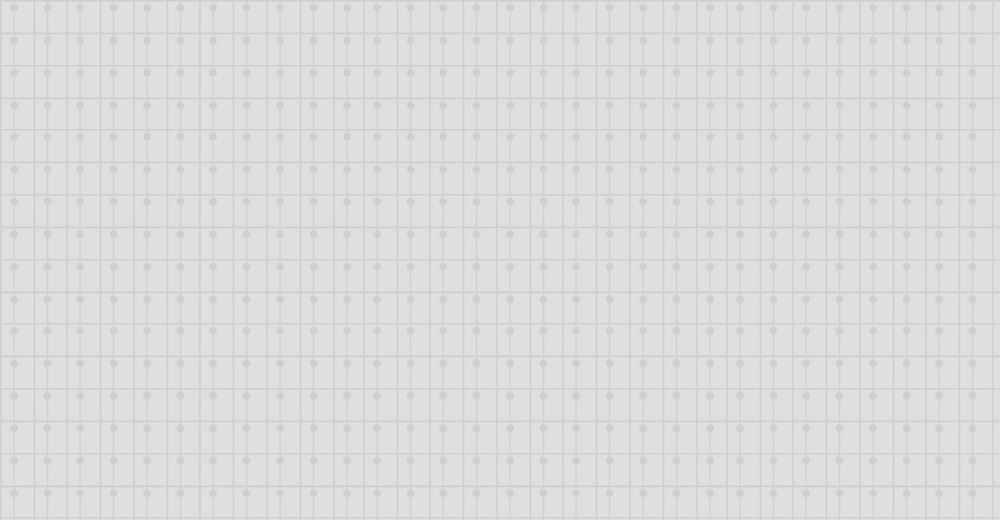1.消えていく言葉
本稿は、キュレーターでライターのジーン・マクヒューにとっての「ポストインターネット」という言葉の射程を、マクヒューのウェブブログが元となった『Post Internet』(以下、『PI』)から検討するものである。『PI』はマクヒューが助成金を得ていた期間中に書いた2009年12月29日から2010年9月5日に書かれたもので、特にインターネットと芸術に関する作品分析とその作品理解に視座を与える映画や理論紹介を中心に構成されている。
マクヒューの状況記述は計画的陳腐化といった資本主義の宿痾とインターネットが同一視される点において、web1.0の技術進歩史観ともweb2.0の享楽性とも異なるが、その一部は、民主主義的な文化生産ツールとしてのYoutube/Wikipediaやブログといったものが芸術の公開も民主化したという、今や素朴なインターネットと芸術表現の関係性があることもあり(PI:219)(作品を公開するのに使用するプラットフォームの情報共有アルゴリズムにおける人種差別性の発見など、その楽観的な局面を批判する事例は今や枚挙に暇がない)、これからも参照され続けるテキストだとは断言しづらい。
だが、40組以上のアーティストを取り上げた本書は、同時代的なシーンへ見事に形を与えたといってよいだろうし(*1)、joggingなどを筆頭にTumblrなどSNSを支持体とした作品や、作品を作家自身がウェブサイトから削除した作品についての記述もあり、当時を知るのに重要なテキストであることは間違いない。
しかし、「ポストインターネット」という言葉にマクヒューが託したシーンとその志向性に反し、言葉はむしろ商業的なバズワードとして霧散した。マクヒューが取り上げてきた作家たちは目下、「インターネット時代の」「デジタル時代の」「ポストデジタル」といった、より広域な時代区分のなかで紹介されている(*2)。ただし結論からいうと、この用語の霧散はマクヒュー自身が望んだ一面もあるのではないかというのが本稿の論旨だ。
2.作品群に形を与える
マクヒューは『PI』冒頭で、記事内での「ポストインターネット」の語用はバージョンのひとつにすぎないと明記したうえで、マクヒューにとって重要参照点となっている、アーティストでキュレーターのマリア・オルソンとコリー・アーカンジェルの言葉を引用し、芸術とインターネットの関わりに輪郭を与えていく。
とくにオルソンによるポストインターネットアートは、インターネットの慣習を美術に、美術の慣習をインターネットにもたらすものであり、オフラインの状態もインターネットに影響を受け変容した状態であり、インターネットアートはネット上の美術、ポストインターネットアートはネットが生まれた以降の美術だという区別(PI:11)を提示している。コリー・アーカンジェルは2006年3月にブリュッセルのキュレーター、カレン・ヴァーシューレンとの対談で、インターネット・アートではなく、インターネットがあるから存在する、あるいは影響されている、インターネット上で研究されたアートの存在を示唆した(PI:14)と述べているが、それはマクヒューにとっての「ポストインターネット」が深化する入口といってもいい。
マクヒュー自身は序盤で、インターネット自体の質感については、インターネットは自由な楽園ではなく、請求書のやりとりといった既存の慣例や世界に追われる場所となった(PI:6)と記述しているのだが、その上で美術とインターネットの関係性について次のようにまとめている。
「片足を美術史に、もう片足をネットワーク文化の体験に置いた作品を作ることで、『ニューメディア』というカテゴリーを美術全般に溶かし込むこと。ポストインターネットアートは、インターネットについてではない。また、芸術のことでもない。その両方についてである」(PI:15)
このマクヒューのインターネット観とポストインターネット論を、オルソンとコリーの言葉から逆照射してみたい。マクヒューは言外に、オルソンが語りだした「ポストインターネットアート」の思想はコリーの系譜にあることを示唆しつつ、それらを自身で美術動向として再度まとめ上げるにあたり、コリーとオルソンの言説の中にある状況反映論性、すなわち、インターネットがあったから作品が生まれた、という作品が社会の鏡であるというような解説を回避しようとしていることが分かる。そして作品の志向性を、ネットワーク文化の歴史化自体とその文化営為が美術の技法として登録されることにあるとし、オルソンよりも先鋭化させているといえるだろう。
3.作品記述の仕方
この言葉を軸に日記を振り返ると、なぜ彼の作品記述の一定数が絵画や彫刻や映像といった形式を記述してから作品の具体的な挙動について論じる傾向にあったのかがよくわかる。ホワイトニー・クラフィンやランス・ウェイクリングらの作品を絵画や彫刻や映像といった既存の形式へとまずカテゴライズして語りだすことは、本文においては美術全体にあらゆるテクノロジーが介在する思考の枠組みを描き出すための記述方法でもあるといえる。ウェブサービスの記述に特化するものもあるが、マクヒューは美術形式にとってどのようなものかを示した後に、個別の作品がどのようにインターネットが加速させた商品やサービスの陳腐化を作品に組み込んだものであるのかという順番で論じているし、絵画や彫刻といった美術史の延長線上からも作られている作品をそもそも選定している。
4.時間性というモチーフの傾向とその結果
その一方でマクヒューは、過去から当時にかかる諸作品を形式で貫き美術史の連続性と変化を示そうとしている。そこでポイントになるのは、作品の時間性である。まずは実際的な時間感覚の変化についての作品だ。Webブラウザにとっての10秒を表現するデイモン・ズコーニによるWebブラウザ作品《10 Seconds to Each Point》(PI:79)、1925年の映画『戦艦ポチョムキン』のショットを1分間に120カットにし、120BPMのダンスミュージックのビートと完全にシンクロさせたマイケル・ベル=スミスの《Battleship Potemkin Dance Edit(120BPM)》など(PI:137-138)、一見散漫なブログ形式の美術批評は、映画、テレビ番組、CM、そしてストリーミング配信における映像視聴の時間、リズム、デジタルネットワーク時代の時間とはなにかを問う作品(PI:78-84)を検討している。
もうひとつは、観者側の時間性だ。マクヒューが記述する視点と作品自体も、「一過性」への意識が非常に強い。作品が扱っている時代の気分は観者にとってみて、プライスが示す「使い終わったカレンダー」のような、誰もが無かったかのように忘れていく気分であり(PI:35)、オルソンやコリーやガスリー・ロナガンが扱う、毎年家電やソフトウェアやデバイスがより良くなっているかのように商業的に新しさの演出を行うという計画的陳腐化に生きる人間の時間性だ。よって、マクヒューにおけるポストインターネットアートにとっては、同時代性という陳腐化に向き合うこともまた主要なモチーフなのである。しかもその陳腐化はSNSの膨大な投稿と同等に作品が消費されるということを前提にしている。マクヒューは、猫動画も作品も同程度におもしろいという状態が起こっていると述べるのだ。
この点においてマクヒューは、美術史家のレオ・スタインバーグがパブロ・ピカソの全作品を通して論述するという特権的かつ労作である批評行為が、ポストインターネットアートにおいては誰にでも大抵可能な状態になっているということも同時に発生していると指摘する。そして、その一連のシリーズとして作品が作家やコレクティブに紐づいているという状況がインターネットにおけるミームと作品の違いであるとするのだ。
故に、自身の作品を様式の変化も含めて一連化させるという芸術家をピカソが創造したのと同様に、ポストインターネットアートアーティストは芸術家を創造することになるということである。そして更には、現代美術が常に前時代の価値を転換しつづけることが商業的にも理念的にも求められているという状況によって、アーティストを不安にさせ続けるというスタインバーグの推察が、インターネット以降の芸術の状況変化の加速により一層深刻化すると続ける。その不安と対峙するためにはアーティストは作り続けるということが必要であるし、毎日のようにポストする日々の作品へのアーティストとフォロワーの応答の中から、ポストインターネットアートの優れた作品は生まれてきたとマクヒューは導き出している(PI:219-222)。つまり、時間性という点でいうと、「現在であることを続ける」という性質を持つということだ。
5.美術批評への批判
マクヒューはなぜブログを執筆したのだろうか。その理由は本文では明言されていないが、当時の現代美術がインターネットを前提としない状況への批判があったことは推測できる。マクヒューはヨーロッパの美術館やチェルシーのギャラリーに、特定のニューメディアに特化した空間以外では、デジタルネットワークコンピューティングを取り巻く一連の技術が何ら影響を与えていないということを強く批判しており(PI:164-167)、本書では社会のすみずみまでインターネットを始めとしたテクノロジーが浸潤しているという状況とそれを扱う作家たちの活発さが見て取れる。
ただマクヒューは、その現代美術とポストインターネットが乖離している理由を多数の組織の運営に求めるのではなく、「インターネット・アートもインターネットに関するアートも、現代美術の議論の面白さには実は参加しておらず、そのため自分たちが参加することは難しい」(PI:164-167)と論じている。また、それに成功した作品とはどのようなものかというと、「あるレベルにおいて現代美術をネットワークに巻き込んだ」「デジタル・コンピュータ・ネットワークに巻き込まれた現代美術自体に関する作品」(PI:164-167)とも明言している。果たしてこれは、どういう意味をもつのだろうか。
6.「メディアアート」からマクヒューの「ポストインターネットアート」を考える
冒頭に引用したマクヒューにおける「ポストインターネットアート」を踏まえ、前述の「成功した作品」の条件を照らし合わせてみると、「現代美術になる」「現代美術にインターネットを分からせる」ということが、手段あるいは目的として存在することが浮かび上がってくる。
現代美術になるということは何を意味するのか。迂遠かもしれないが、日本の「文化庁メディア芸術祭」(*3)のうちアート部門の審査員でもあったアーティストの中ザワヒデキが第19回「審査を通じたメディア芸術批判と文化行政への提言」(2015年)の中で、今後の芸術祭の方針を検討するために以下のように述べていることを参照してみたい。
さて私は、メディアアートは美術の一翼であり、メディアアートの「上がり」は接頭語のないただのアートだと考えている。そして私の観測では、10年ほど前からすでにそれは達成されている(*4)
ここで中ザワが述べている「メディアアート(media art)」とマクヒューが(当時)無視されていると考えているところの「ニューメディアアート(New media art)」は同等だと私は考えてみたいのだ。
中ザワとアーティストの石田尚志とキュレーターの植松由佳が同芸術祭の座談会でも論じている通り、官製芸術である「メディア芸術(Media Arts)」とは、西欧中心主義的な大文字のARTから除外されていたアニメーションやマンガ、そして芸術祭開始時期の1998年の部門名である「デジタルアート(のちのメディアアート)」もまたARTにとって周縁的であるという意味で統合されたものだ。つまり、美術にとって周縁的な形式(絵画、彫刻それ以外)を扱ったものがメディアアートと名指されてきたし、絵画や彫刻それ以外のデジタル技術を用いて制作されるような作品がアートにとって周縁的でなくなりさえすれば、それはアートに組み込まれている(*5)。
ゆえに、ここで中ザワがいう「上がり」を次のように説明することができるだろう。「メディアアート」という括りでしか現れない作品があれば、その一群はアートが何を無視しているのかとアートを揺るがし、その無意識の変革を迫ることになるが、アートがそこで指摘された無意識を一定自覚し、「メディアアート」を受け入れたのであれば、受け入れられた「メディアアート」という枠組みはその他者性を失うのだ、と。
ただし、中ザワと植松が議論の中で「メディアアート部門」から「アート部門」への転換を提言するのではなく、メディアアートだったものがアートになった後も、またその時代ごとのアートの他者としての「メディアアート」は存在しうるという意味で、より狭義に「メディアアートとはなにか」という枠を提言していることは注目したい。その点から、マクヒューの話と比較していこう。
中ザワと植松にとっての「メディアアート」と違って、マクヒューの場合の「ポストインターネットアート」は時代と作品をある程度規定している。だからまず、マクヒューにとって「上がり」は1回なのだ。そしてマクヒューの議論は、現代美術が上位概念だから現代美術とニューメディアアートが混ざりあうことが「上がり」なのではなく、マクヒューがまとめたポストインターネットアートは、作品が示す時間性の新しさの陳腐化が前提であるために、それを現代美術という他者に伝達し終え、大文字の美術の中に残すことまでを志向するからこそ、ポストインターネットという用語が霧散することは予定されていたことだともいえるだろう。
しかしそれでいいのだろうか。「メディアアート」と同じで、マクヒューによる「ポストインターネットアート」という思考の枠組みが、また新しい時代の「ポストインターネットアート」をマクヒューの知らない所で生み出していたとしたらどうだろうかと考えるところである。
(*1) 扱っている作家や作品が一部被る後続のアンソロジー本の多くでマクヒューの『Post Internet』が参照されている。例として、以下を挙げておく(Melanie Buhler(ed), No Internet, No Art: A Lunch Bytes Anthology, Onomatopee, 2015)(Omar Kholeif(ed), You Are Here: Art After the Internet, HOME and Space, 2018 )。
(*2) インターネットの時代の美術における代表的なキュレーターで論者でもあるオマール・ホリーフが、アート・アンド・テクノロジーにまつわる言葉が商業的バズワードとしてアートワールドを満足させつつ困惑させていると指摘し、ポストインターネットをより拡張するように、ポストデジタルを使うほうが良いと述べている。(Omar Kholeif, “Hello world, goodbye world, and hello again!: looking at art after the internet,” ART IN THE AGE OF THE INTERNET 1989 TO TODAY , Yale University Press, 2018, pp.96-104.)
(*3) 2022年8月24日に次年度の公募を実施しないということだけをウェブサイトで発表した(しかし、『朝日新聞』や『IT medeia news』などが取材の結果「メディア芸術祭は終了」と報道しているという状況だ)。
(*4) 中ザワヒデキ「審査を通じたメディア芸術批判と文化行政への提言」『第19回文化庁メディア芸術祭 受賞作品集』文化庁メディア芸術祭実行委員会、2020年、243ー244頁。
(*5) 石田尚志、植松由佳、中ザワヒデキ「アート部門からメディア芸術祭へのメッセージ」『第19回文化庁メディア芸術祭 受賞作品集』文化庁メディア芸術祭実行委員会、2020年、246-250頁。
本稿は、2022年度小笠原敏晶記念財団の助成を受けて書かれました。