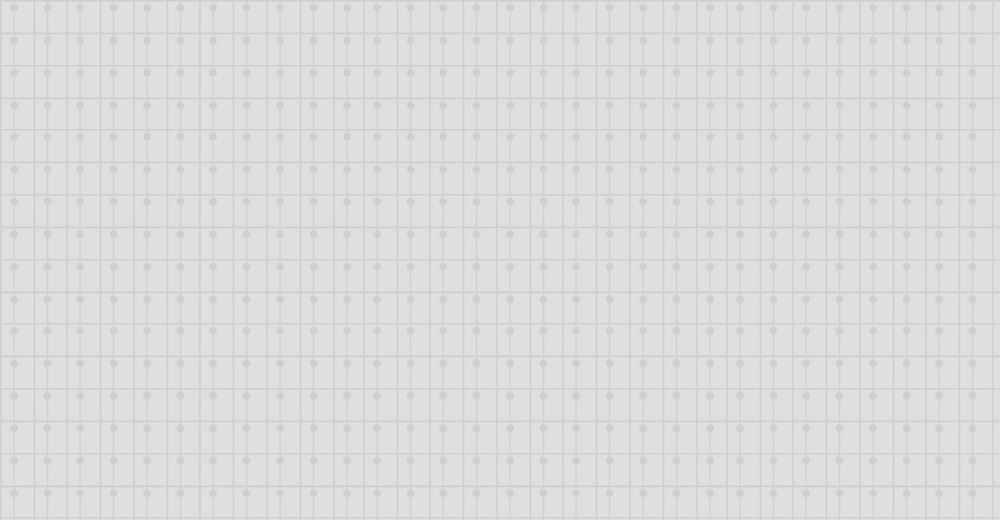はじめに
彫刻に何かが起きている以上、それについて書くことを急き立てられているものの、この小論に許された紙幅はあまりに限られている。だがそもそも、それは本当に起きているのか――この事態の推移は仮説というよりも、まだ一個人の感触の域を出ないほどの妄想かもしれないし、また「彫刻の近況」なるものを整理するには、筆者はあまりに非力である。そして彫刻というジャンルの領域画定はそれ自体、かつてほど自明ではないだろうし、「彫刻とは何か」をことさらに問うことの有効性も測りがたい。だがそれでもなお、「彫刻」の名のもとに練り上げられてきた数々の素材・手法や概念、問題構成を(遠巻きにであれ)めぐって展開される制作実践=〈彫刻的なもの〉が現にあることもたしかである。ならば、そうした〈彫刻的なもの〉を、筆者なりにめぐった近況について、書き留めてみたいと思う。
責めさせる彫刻
「調教都市」というその名称にふさわしく、小寺創太の個展(*1)がフレームアップしていたのは、その上に安らごうとする身体を拒絶し痛めつける、「排除アート」と通称される都市空間のオブジェ群である。それらは、居住場所を失った者の避難先となる、わずか一人分のスペースを残すことさえも頑なに拒絶する「彫刻」とも言い換えられるだろう。「アート」を装った、社会的排除の暴力。小寺は本展において、こうした暴力を逆手に取り、その凶暴な彫刻によって痛めつけられることをむしろ望む、マゾヒズム的な身体を提示することで、自ら受苦的な彫像となった。ギャラリーの1階部分を占める《調教都市》(2022)においては、レザーマスクを含むボンデージ衣装に拘束された人体(おそらくは小寺本人)が、多面体をなす抽象彫刻の上に放置され、その幾何的なクリスタルの鋭利なエッジによって処罰されている。
それにしてもこの、彫像がその上で悶える舞台として呈示される抽象彫刻、言い換えれば「彫刻のための彫刻」は、奇妙な地位を享受している。クリスタルは、それ自体が彫刻作品のようでありながら、その上の彫像を支える、本来彫刻がそれとして定義されるべく要請される装置、すなわち「台座」でもあるのだ(本稿では以降、台座の――あるいは台座に相当する――作用を享受した彫刻を〈彫刻〉と表記することにしよう)。彫刻は、それ自身でなんとか、それ自身に根拠を与えるもの=台座を偽装しようとしているのだ。言ってみればここでは、オブジェが(非典型的な)台座へと変貌し、〈彫刻〉を自作自演しようとする企みが繰り広げられている。
ラカン派精神分析において、マゾヒストとは、まさしくこうした自作自演を遂行する倒錯的な主体とされる。ブルース・フィンクによれば、一般に際限のない享楽へ向かってドライブすると思われている「倒錯」のイメージとは異なり、倒錯者の行動は実のところ、享楽に限界を定める「法」を生み出そうとするものであるという。主体の発達過程においては通常、法を与える象徴的な《他者》(Other)が介入することで、《他者》なる母(mOther)の要求の代替不可能な対象である状態から分離され、社会や文化における自らの位置を引き受けていく。法の作用を通じて、主体がそれ「自身の」位置をとるようになる、この象徴化の過程を経験していない倒錯者は、法の宣言を偽装的なシナリオとして上演する(というのも、この上演は「本当の分離」を与えるものではないからだ)。「マゾヒストは、自分が黒幕となってパートナーに法を宣言させるような仕方で、事をまとめなければならない」(*2)。
小寺の《調教都市》に、明示的なパートナー(サディスト)は見当たらない。一方的に視線を向ける観者がその役割を担うとも言えそうだ。しかし別の見方をすれば、すでに示唆した通り、彫刻=台座として二重化されたクリスタルが「法」を代行しているように思える。台座がその上にあるオブジェを〈彫刻〉として、他のあらゆる対象物から区別する装置であるとすれば、それは彫刻にそれ自身の地位を与える「法」と呼べるかもしれない。排除アートを参照した彫刻=台座はしかし、あたかも明確な台座を与えられなかった――ゆえに〈彫刻〉未満の〈彫刻的なもの〉に留まる――2つのオブジェ(人体とクリスタル)が共謀して、彫刻/台座の二項関係を偽装したかのような光景を導いている。
〈彫刻的なもの〉の倒錯的な実存
この彫刻=台座を制作した吉野俊太郎(「調教都市」展には制作協力として参加)の作品にはしばしば、「台座の擬人像」というべき形象が導入されている(*3)。《Plinthess》(2021)では、壁面に立て掛けられた白い直方体が、人形を押し潰している。直方体の表面に添付された写真には、白装束の黒子というべきこの人形が等身化し、直方体の荷重を受けるさまが記録されている。「黒幕」として陰で糸を引き、パートナーによる「法」の宣言をお膳立てするマゾヒストさながら、人形=黒子――この二重性は、可視的な「演者」(キャラクター)と密接した「操演者」がその活動を陰で支援する、人形劇の形式的特徴と関連しているだろう――は自らがその受け手となることで、直方体に刑を執行させているかのようだ。これらの写真に含まれる、黒子が直方体に乗っているイメージをさらなる手がかりとして、本作を小寺との協働が実演していた「〈彫刻的なもの〉による台座の偽装」の一形態として理解できるかもしれない。
しかしまた、本作において黒子の衣装(白装束)が直方体と同一色であること、直方体のサイズが黒子を演じている吉野自身の身長から決定されていること、直方体が台座というよりもミニマリズム彫刻のように設置されていることを鑑みれば、この黒子と直方体の存在論的地位がさらなる問いに晒される事態となるだろう。両者はともに、彫刻的なフォルムと台座の間で、身分を登録されないまま宙吊りになっている。黒子が人体の形象を模して製作された像であり、直方体が台座であるとすれば、そこには先述したような、台座の作為的な偽装に関与する彫像の姿を認められるだろう(彫刻的なオブジェこそが台座を支える=お膳立てする)。だが実のところ、本作においては、そうした「支えるもの」と「支えられるもの」の役割分担が、きわめて不安定な状態で推移する。黒子が「台座の」擬人像である以上、台座を持ち上げる黒子は、「台座を支える台座」とも形容できるかもしれない。加えて、同じ光景を、ミニマルな彫刻である直方体が、台座(の擬人像)に支えられていると読み替えることもできる。さらにまた、黒子も直方体も彫刻的なオブジェであるならば、両者の関係は、「彫刻を支える彫刻」ということになるだろうか。
しかし、〈彫刻〉と呼ばれる対象が「芸術」として、台座、あるいは――コンスタンティン・ブランクーシの《無限柱》やアンソニー・カロの作品が体現するように――上昇や浮遊といった感覚を介し、世俗的な「現実」の場から切り離され、自律性を与えられてきたコンテクストを踏襲するなら、「彫刻を支える彫刻」なるものは語義矛盾と見なされるだろう。支える-支えられるという非対称的な二項関係それ自体は、彫刻の内的属性として含まれてはならなかった。台座ないし(場からの遊離という)台座的な作用が要請されつつも透明化される――ブランクーシやカロの例では、物理的・現実的な支持関係の非対称性を知覚的に打ち消し、均衡化する――のも、そうした前提ゆえだろう。前段に挙げた最後の例は、「〈彫刻的なもの〉を支える〈彫刻的なもの〉」とでも呼び直すべきかもしれない。
〈彫刻的なもの〉と台座、「支えられるもの」と「支えるもの」の二項関係を自身の構成要件としつつ、それを透明化することで成立してきたのが〈彫刻〉であったなら、「台座を支える台座」「〈彫刻的なもの〉を支える〈彫刻的なもの〉」のように、二項関係すなわち〈彫刻〉を構成する制度の作為をあからさまに前景化する不条理な身振りは、一種の「制度批判 institutional critique」として、コンセプチュアリズムに連なる側面もあるだろう。しかしながらその身振りには、冷静で客観的な批判を超過する実質が備わっているようにも思えるのだ。
《調教都市》におけるオブジェの共演=共犯が見たところ、台座の偽装工作というひとまずの「目的」へと向かっていたのに対し、黒子と直方体の存在論的地位が次々とスリップする《Plinthess》においては、二項関係をめぐる操作の目標がより曖昧なものとなっている。互いの分身ともいえる黒子と直方体は、まさしく自作自演的に戯れるのだが、これが何のための作為・上演なのか、はっきりしない。それは「上演」という手続きそれ自体が目的化した、純粋な作為、純粋な偽装の終わりなきサイクルを遂行しているかのようだ。本作は〈彫刻〉という体制への批判的注釈であると同時に、「彫刻」なるものの輪郭を定着しようと繰り返し試みてはスリップし続ける、〈彫刻的なもの〉あるいは彫刻論の倒錯的な実存を呈示してもいるとは言えないだろうか。
中締めとして:彫刻批評の倒錯的な実存
〈彫刻的なもの〉による〈彫刻〉への制度「批判 critique」が、ストレートな告発によってではなく、むしろ彫刻にまつわる何かをなお、ある水準で「自演」することでこそ遂行される――。先に見たこの状況は、「批評 critique」にとっても無関係ではないだろう。批判と実演の二面性に直面することは、大文字の〈彫刻〉が創作上の規範としてもつ有意味性が擦り切れたとしてもなお残る、彫刻的な諸々のアプローチのポテンシャルを考究する糸口でもある。本論もまた、前段までの議論を発端として、数々の興味深い実例に即しながら、〈彫刻的なもの〉をめぐってどこまでも筆を滑らせていきたいところだったが、紙幅が尽きてしまった。この続きについては、他日を期したい。以降の論述に向けて待機しつつ、本稿の標題に「緒論」と記してひとまずの中締めとし、筆をおくことにしよう。
(*1)「小寺創太 個展「調教都市」」は、2022年3月5日から4月3日まで、Token Art Centerにて開催された。また、下記も参照。小寺創太ウェブサイト(https://sotakodera.myportfolio.com/home)、2022年10月2日閲覧。
(*2) Bruce Fink, A clinical introduction to Lacanian psychoanalysis: theory and technique, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999, p. 191. なお、訳文は下記を参照した。ブルース・フィンク『ラカン派精神分析入門――理論と技法』中西之信・椿田貴史ほか訳、誠信書房、2008年、277頁。
(*3) 吉野の作品については、下記を参照。吉野俊太郎ウェブサイト(https://shntryshn.com/work.html)、2022年9月25日閲覧。