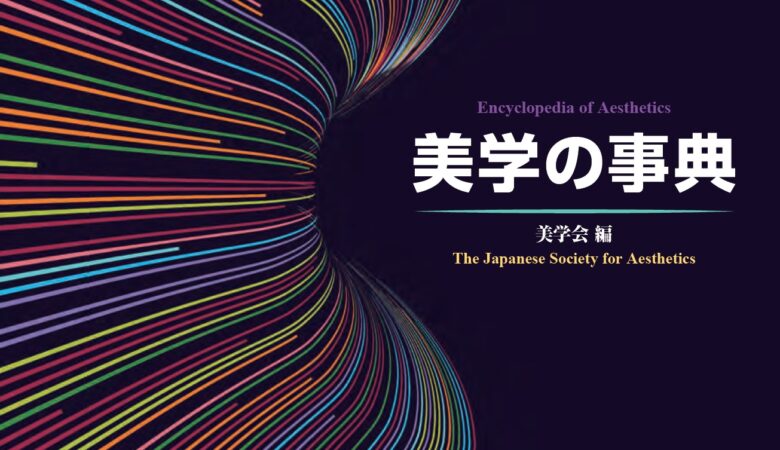すでに本サイトで発表済みの「恐ろしい、美術≒道徳『教科書』 市原尚士評」を執筆する際、図画工作や美術の教科書、そして小学校学習指導要領解説といったテクストを読み込んでいて、妙なことに気が付きました。今回の原稿では、その発見を詳述してみましょう。
図画工作や美術の教科書に、不自然なくらい「どうとく」「道徳」が入り込んでいる実態については、「美術≒道徳~」ですでにご報告いたしました。実は、「どうとく、道徳」と同じくらい、「SDGs」も入り込んでいるのです。
日本文教出版「図画工作 3・4下 ためす みつける」の32-33ページ、34-35ページの2つの見開きは、いずれも「つくる責任 つかう責任」を標榜する「SDGs12」と結びつけられています。廃品を再生して、社会の役に立つ創作を促すページではあるので、一応は自然に見えますが、唐突感は否めません。
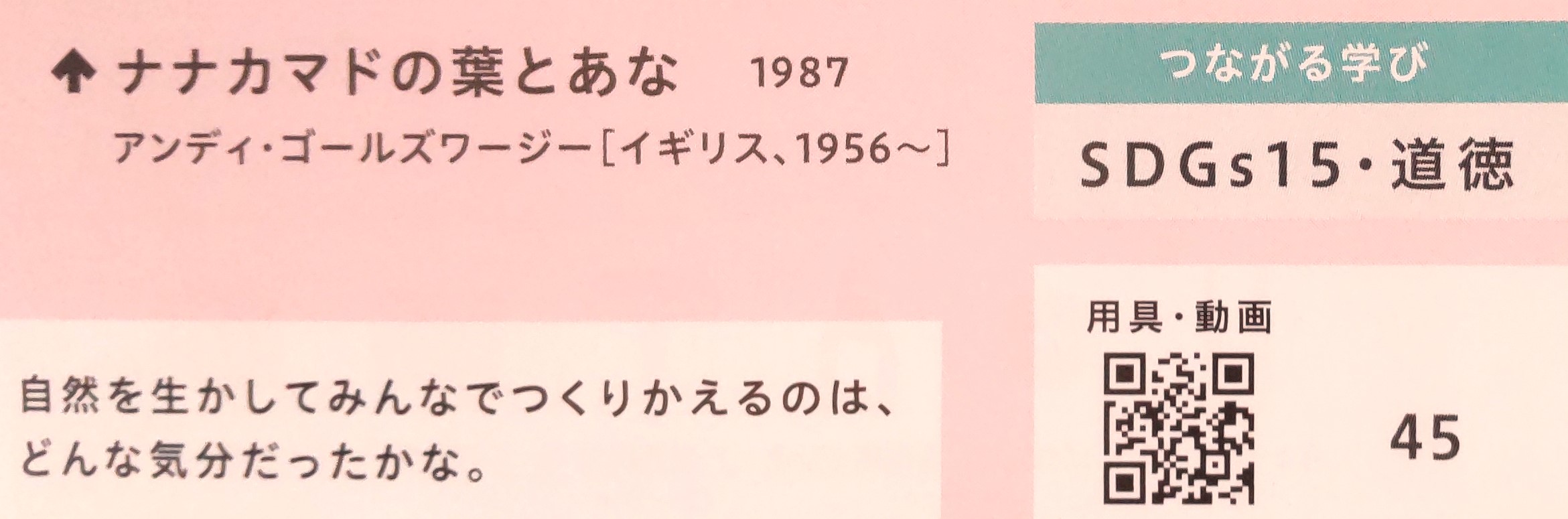
日本文教出版の教科書では、「つながる学び」として、SDGs15と道徳があげられている
日本文教出版「図画工作5・6下 わたしとひびき合う」の42-45ページ。「自然を感じるすてきな場所」で落ち葉や雪や砂を使って造形遊びや鑑賞をしようという趣旨ですが、ここは「陸の豊かさも守ろう」と訴える「SDGs15」及び「道徳」と結び付けられています。
同じ教科書の48-49ページは「平和と公正をすべての人に」を意味する「SDGs16」と「道徳」がピカソ作「ゲルニカ」などの作品を通して訴えられています。
続く50-51ページは、「こんな学校や公園があったらいいな」というプロジェクトを想像力を働かせて考える内容なのですが、こちらは「SDGs9」(産業と技術革新の基盤をつくろう)、及び「プログラミング」と関連付けられているのです。
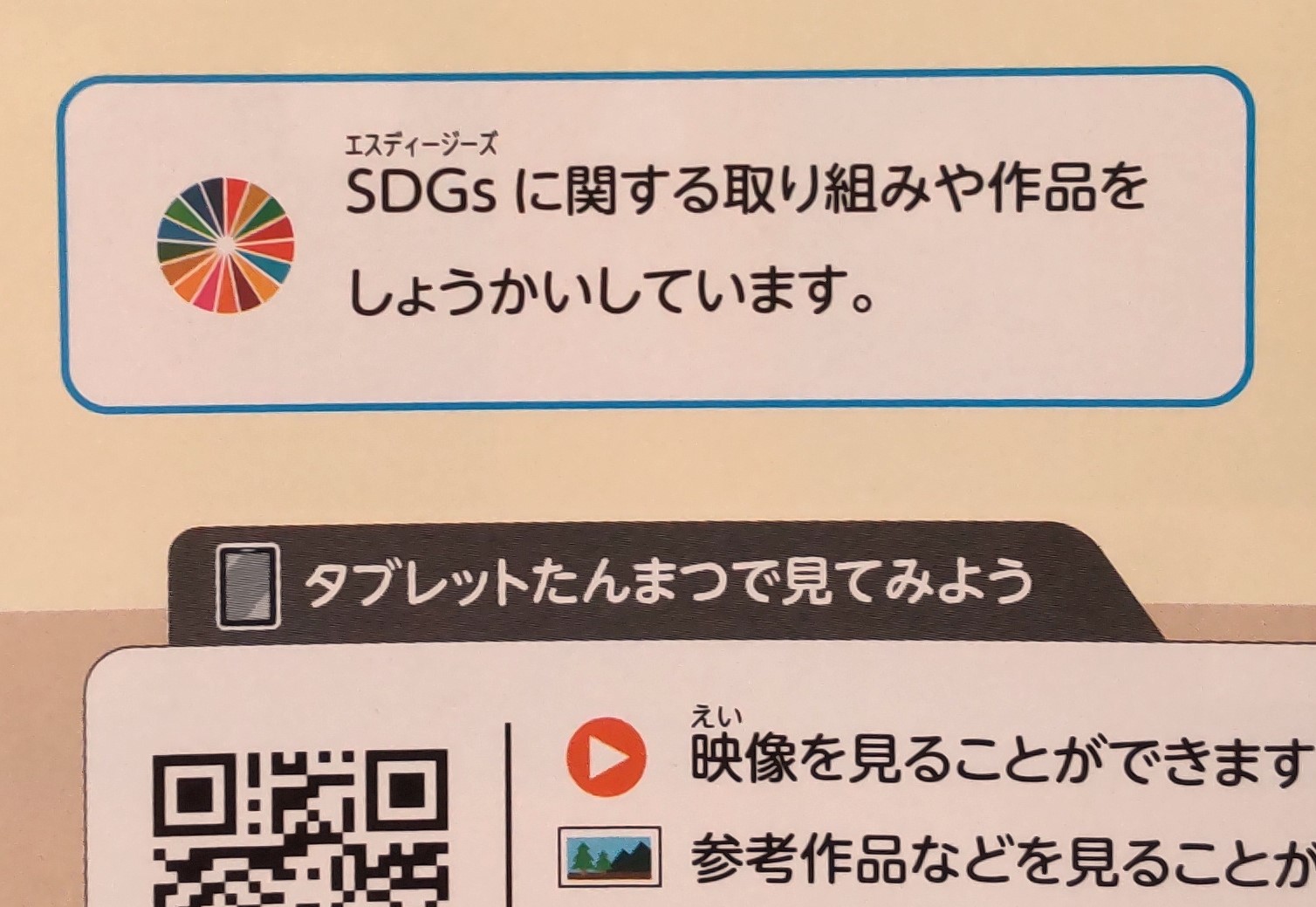
開隆堂の図画工作教科書では、SDGsに関連する作品などが紹介された
開隆堂「つながる思い図画工作5・6下」では、「SDGsに関する取り組みや作品をしょうかいしています」という名目のもと、ヨーガン・レールのランプ、ラトビアの11歳児童の風景画、北海道にある「安田侃彫刻美術館 アルテピッツァ美唄」の外観写真が紹介されています。
以上、小中学校向けの教科書に突然、出現するSDGsの事例を紹介しました。ここまで長々としつこく紹介をしたのには訳があります。出版社が文部科学省の教科書検定を受ける際、教科書の見本と一緒に出す「編修趣意書」という文書を読み込むと、教科書内にSDGsが頻出する理由が分かるからです。
編修趣意書は、教科書の基本方針や特色を文科省にアピールするためのものです。より具体的に言えば、教科書の紙面構成、内容ごとに教育基本法の目標にどうのっとって作ったかが記載されています。
光村図書の中学校向け「美術2・3」の編修趣意書の記載で頻出するフレーズを抜き出します。文科省の受けを良くし、検定をすんなり通るために光村図書がどんな“工夫”を凝らしているのかが一目瞭然です。
▽自他の敬愛と協力を重んずる態度を養う▽美術の学習が、豊かな情操と道徳心を培うことにつながっていることを意識できるように、ページ下に適宜「道徳科とのつながり」マークを示し、道徳の学習と関連する内容を示しました▽伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する態度を養うーーこんな言葉が目を引きます。光村図書だけではなく、どの出版社も同工異曲の内容です。
そして、私が光村図書の編修趣意書の中で、次のくだりを見た時、びっくりしました。
「美術の学習が、豊かな情操と道徳心を培うことにつながっていることを意識できるように、ページ下に適宜SDGsの17の目標の番号を入れ、関連を示しました」
そうです、豊かな情操と道徳心を培うために、教科書内に盛り込まれたマークは「道徳科とのつながり」「SDGsの目標番号」の2つなのです。つまり、文部科学省の覚えをめでたくしようと懸命な教科書会社は、道徳とSDGsを相互に入れ替えが可能なまるで同義語のような扱いで記述をしているのです。
なるほど、あれだけ教科書内で道徳とSDGsが紐づけられていたのも合点が行きました。文科省としては、とにかく教科書内に「道徳との結びつき」を多く盛り込んでほしい。しかし、あまりにも盛り込むと悪目立ちして、世の批判を浴びるかもしれない。だから、実質上は、道徳的なメッセージを放っているにもかかわらず、より現代的な装いを持った「SDGs」なる名称を利用し、道徳的なメッセージが増量されていることに気が付かないようにしているというわけです。
私は、「道徳=SDGs」とお上が考えているというカラクリが分かって、頭の中がすっきりしました。SDGsと道徳って確かにそっくり! 瓜二つなんですよ。
ここでいうところの道徳とは、「修身斉家治国平天下(しゅうしん・せいか・ちこく・へいてんか)」的な為政者に都合の良い道徳、あるいは、「努力すれば人は必ず成功するのだ」といきまく通俗道徳、あるいは新自由主義と相性の良い道徳を指しています。
「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 特別の教科 道徳編」(発行者・あかつき教育図書)の記述とSDGs17の目標には不思議な共通点があります。「人類は絶対に戦争をしてはいけない」という一番、重要なメッセージがどこにも書かれていないのです。前者には「生命の尊さ」が、後者には「平和と公正をすべての人に」が、それぞれ訴えられています。しかし、どうすれば生命を尊重し、平和な社会を作れるかについて、一番、肝要な「戦争の禁止・廃止」が訴えられていないので、説得力がまったくありません。
SDGsと道徳はほぼ同じ、と考えた上で、先の学習指導要領やSDGsの目標を読み直すと、結局、新自由主義的な社会の中で要領よく立身出世できる人間を道徳的に善とみなすだけのどうしようもないポンコツ、まがい物なのではないかという疑念しか湧いてきません。
SDGs17の目標の中から私が噴飯ものと感じた項目を意訳・超訳すると、こんな風になりました。

新自由主義のにおいが漂うSDGs17の目標
質の高い教育をみんなに
資本主義のお役に立つような立派な人材を開発途上国で育成し、先進諸国の利潤のために貢献してもらうための教育。
ジェンダー平等を実現しよう
女も男並みに、馬車馬のように働ける社会を実現しよう!
働きがいも経済成長も
男も女も、開発途上国も先進国も世界中のすべての労働者は死ぬほど働け! 高度な資本主義に参加し、資本家の儲けをもっと増やせ!
産業と技術革新の基盤をつくろう
もっと効率よく金儲けができるシステムを世界中に広く構築しよう。
人や国の不平等をなくそう
スローライフを楽しんでいる人びとも強欲な資本主義というゲームに参加させよう。世界全体でもっとがめつくなろう。
つくる責任 つかう責任
開発途上国は勝手に作るな、使うな! すべては先進国の管理下で作れ、使え! いいな、分かったか!
気候変動に具体的な対策を
気候変動をあおって、新たなビジネスチャンスを創出しよう!
陸の豊かさも守ろう
作物、細菌、家畜などの遺伝資源を利活用することによって、新たな富の鉱脈を見つけよう。
パートナーシップで目標を達成しよう
開発途上国も金をたっぷり稼げるようになれ! そこで得られた金は先進国がいただくから。
以上、私の意訳はいかがでしたでしょうか? 妄想が過ぎる内容では、と思われた方もいらっしゃるでしょう。しかし17の目標をより具体的に詳述した「169のターゲット」まできちんと読み込むと、私の意訳がそこまで見当はずれではないことがお分かりになるのではないでしょうか?
SDGsや文科省が言うところの「道徳」は、お金を稼げない人間、公共に奉仕できない人間に対して、非常に冷徹な視点しか持ち合わせていません。戦争に反対するメッセージを明確に打ち出さず、空理空論のように「生命の尊さ」や「平和」を訴える両者は、やはりまがい物と言わざるを得ないと思います。
SDGsについて言えば、先進諸国による、いわゆる「上から目線」の物言いが実に鼻に付きます。「この目標を書いているお前はいったい何様だ」とツッコミをいれたくなります。また、文科省の称揚する道徳も結局、一言でまとめるなら「一旦緩急あれば、義勇公に奉じ」ることのできる人材育成をしたいだけでしょう。新自由主義の考え方も盛り込み、バージョンアップした「教育勅語」を子どもたちに押し付けているだけです。
SDGsも道徳も、衣の袖から鎧が見えまくっています。私たちは、何だか聞こえの良い言葉に出会ったら、熟読をしなければなりません。自分の頭でよく考え、他者の意見にもよく耳を傾け、その真相に迫らなければなりません。また、現在、美術制作の現場でも、SDGsやダイバーシティやインクルージョンといった言葉が侵食してきていますが、その流れに無批判に乗っかってしまうのではなく、「ちょっと待てよ」と自分なりによく咀嚼する必要性があると思います。
ということで、本稿の結論。
SDGsにご用心を!
金と権力欲で頭がいっぱいの新自由主義者たちがひねり出した新手のインチキに過ぎないから。
(2025年4月6日15時11分脱稿)