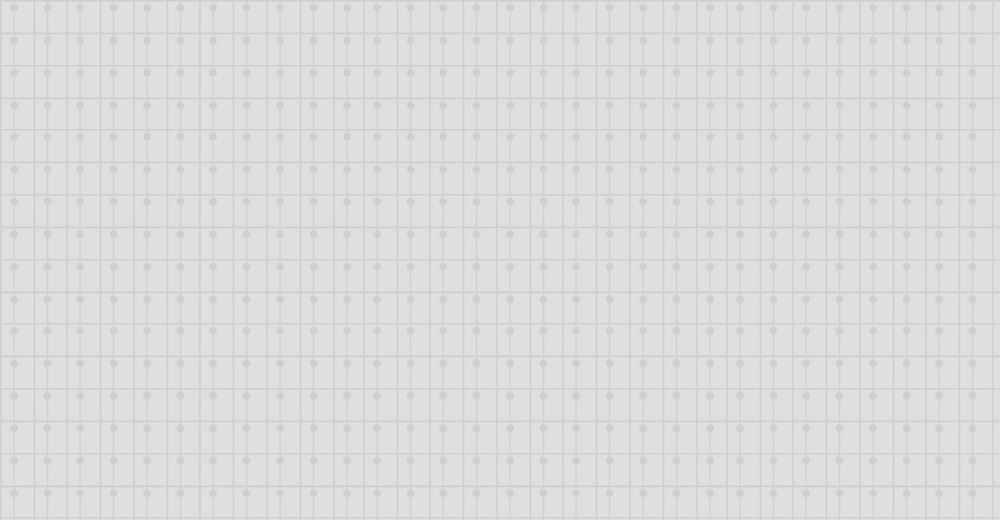作品について語る際、よく「強度のある作品」という言い方がされるが、「強い作品」とは一体何を意味するのだろうか。一つの解釈としてそれは、見る者の嗜好や快/不快感を超えたところにある「強烈なイメージ」、もしくは作家のもつ「強い世界観」だといえるだろう。換言すれば、ある時間が経過しても消えてなくなったりせず、他人の記憶の底に沈殿して留まることができる、つまりいつどのような場でも存在することができるイメージである。
今村哲の作品の強さの一つは、絵画が確固たる現実としてこの世に存在し、さらには現実の創造に関わることすらできるものだと、見る者の意識に訴えかける力を持っていることである。今回の新作から例を挙げるとすれば、作品のコンクリートの表面に、ギャラリーの壁裏にまで到達せんとばかりに深く開いた五つの穴をもつ《マザー・ファッカー》。描かれた飛行機の浮遊感、非現実感とは対照的な存在感を持つこの穴が本当にどこまで達しているのか、一瞬「もしかして・・・」と思ってしまった。後からこの作品に対応するテキスト――空に穴を開けてその穴がどこにつながっているのかを知りたいという「ぼく」の思いが綴られたもの――を読み、計らずして自分が「ぼく」の思いを追想していたことに気付いた。イメージが空想の別世界に属しているのではなく、視覚的に現実と直結しているのだ。それが、作品のイメージが現実を揺り動かし、現実の経験として記憶に定着するということである。
今村の絵画は一貫して、溶け出すものや消えゆくもの、対になるイメージ、トンネル、そして表面を覆う蜜蝋の乳白色の厚みにより、曖昧さのなかにこそあるリアリティを表出してきた。テキストもまた、絵画と異なる方法でそれを経験させるものとしてあった。今回の新作はその方法を踏襲しつつ物質としての存在感を増すことで、絵画が曖昧な現実に対して作用し得るものであると、改めて静かに示していた。
(初出)【レビュー】、芸術批評誌『REAR リア』、no.9、リア制作室、2005年2月28日、73頁。(掲載図版割愛)
(参考)https://www.tokyoartbeat.com/events/-/2004%2F1D61
[追記]
最初の投稿は、2004年12月に中部・東海地域の芸術批評誌『REAR リア』に寄稿した展評を転載した。約18年も前の原稿だが、これが(当時の)所属館発行以外の芸術媒体に掲載された最初の評論だからである。原稿依頼をいただいた時、嬉しかったのと同時に、私にレビューが務まるのだろうかと一抹の不安を覚えたことを思い出す。「まだ準備ができていない」と思っていたからだ。それまでは、当時在籍していた東京オペラシティアートギャラリーで手がけた展覧会に付随する論考や、館発行の各種定期刊行物、雑誌等の取材対応が記事になる機会はあっても、館外へ評論を寄稿したことはなかった。キュレーションは批評的な視座に基づく芸術実践の一環と認識しているし、論考の執筆も伴うが、評論は展覧会制作とはまたひと味違った文化的行為と感じてきたため、未経験の隣接領域に一歩踏み出すような緊張感があった。
当時、館のカタログや定期刊行物に執筆した原稿を内部校正に回すと、いつも先輩や同僚から原稿が真っ赤になって戻ってきたことを思い出す。校正を反映して改訂稿を書くことは初稿以上に難しく、毎回凹んだ。だが思えば、独りよがりから他者に読まれるために開かれたものへと「書く」意識および文章を鍛練し、成長させてくれた先輩や同僚、そして校閲や校正でお世話なった幾名かの編集者がいたからこそ、この文章もここに存在している。
時期からして、同年に実現した初の自主企画展「ウォルフガング・ティルマンス――Freischwimmer」と収蔵品展「野又穫――カンヴァスに立つ建築」のダブル個展の直後と思われる。両展についても、自他ともに「まだ準備ができていない」と思っていたことだろう。とはいえ、何事も万全の準備ができたからよっこらせと舟をこぎ出すような余裕はなく、新しく訪れる機会は大抵いつも切迫していて、決死の覚悟で体当たりしていくしかなかった。
「獅子の子落とし」というが、『REAR リア』は私にとって貴重な機会を与えてくれた「獅子」のひとつである。快くレビューの転載を許可してくださったことと併せて感謝の意を表したい。評論活動において初心と当時の緊張感を忘れることがないよう、最初のレビューを投稿した。
(2023年2月1日)