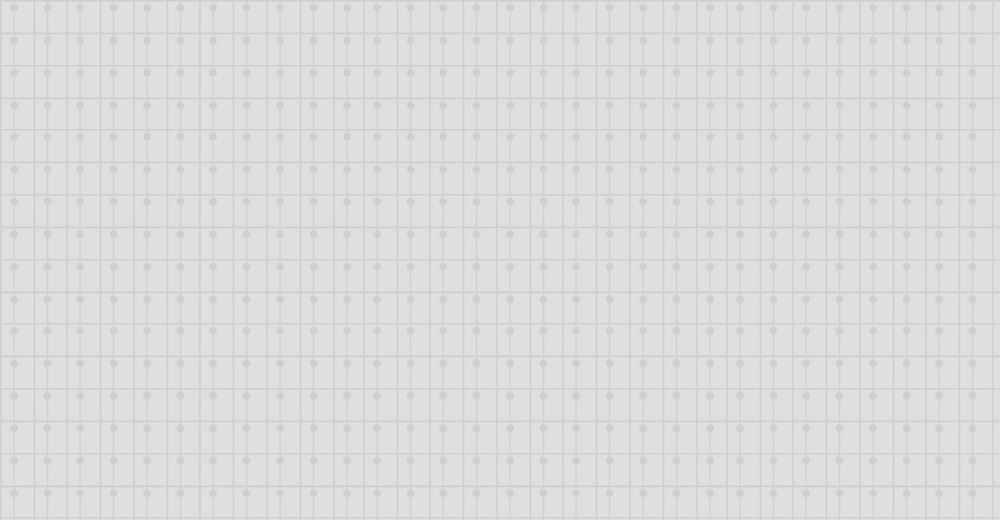現在の美術評論家連盟の会員名簿を見ると、美学・美術史の研究者・大学教員に、美術館の館長・学芸員が大半。それは今日の美術批評が、所謂“美術”のプロパーによって担われているということだろうか。しかし、かつての美術批評・評論はもっと多彩な分野の文筆家が関わっていた。例えば、武者小路実篤や中村真一郎といった作家、小林秀雄や花田清輝といった評論家、そして木村荘八や内田巌等の画家たち。彼らは、歴史的名作や巨匠はもとより、リアルタイムの美術も積極的に論じた。
栗田勇氏の訃報に接して、そんなことを思い浮かべた。栗田氏が美術評論家連盟の会員であったことが、かつての多様な美術批評のあり様、“美術”というものに世の文化人、知識人が注目していた時代を感じさせるのだ。
栗田氏はフランス文学を起点に、日本の宗教、風俗、芸能等、幅広い古今の文化観を論じた。特に“一遍上人”に代表される仏教思想の印象が強い。そんなななか、私にとって、美術評論家・栗田勇は、何と言っても“甲斐荘楠音”だ。大正期に描かれた甲斐荘の花魁の一幅を見て、その「妖しい情念」に魅せられた栗田氏は、画家の作品と人生を探り、ついには未完の遺作『畜生塚』を確認するに至る。それが評伝『女人讃歌-甲斐庄楠音の生涯』(1987年、新潮社刊)に結実し、同年西武アート・フォーラムで画家没後初の回顧展も開催されて、再評価に繋がった。いま思うと、そこには日本文化に奥深く息づき、時代を超えて日本人を突き動かしてきたのは「官能と情念」だという、栗田氏の文化観、芸術観の熱い主張が漲っていたようだ。西洋の近代的合理主義が世界を席巻するなかで、日本と日本人に根差す本能的な欲求や生きる喜び、それらを表す美的感性を探求し、世に問い続けたのが、栗田勇氏の評論活動といえるだろう。そこでの“美術”の存在は大きかったに違いない。
美術評論とは、美術作品や美術家を論じ、評価するだけではない。むしろ、美術を通して、この世の諸相、問題を捉え、議論をもたらすものだろう。これまでも、これからも、栗田勇氏のような存在が、美術批評においては大切なことは言うまでもない。