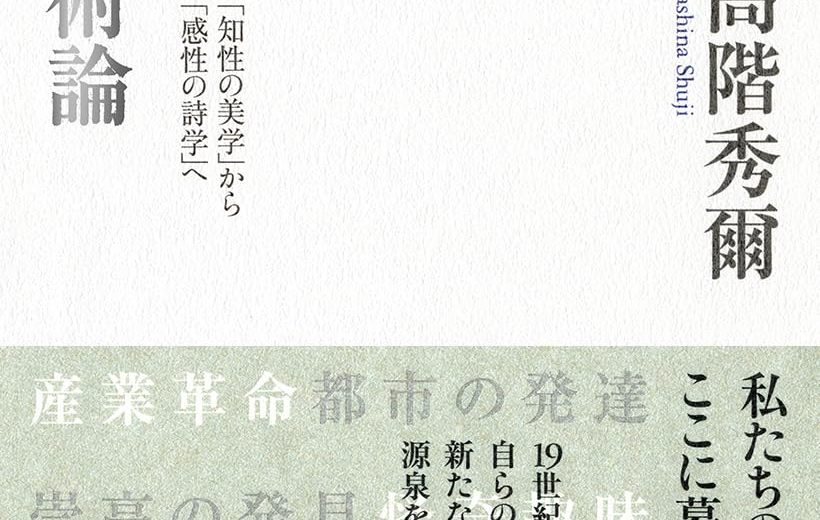高階秀爾著『ヨーロッパ近代芸術論――「知性の美学」から「感性の詩学」へ』
筑摩書房・2023年
本書は、東京大学名誉教授で国立西洋美術館館長や日本芸術院院長等を歴任した西洋美術史の泰斗、高階秀爾氏がこれまでに発表した近代西洋美術に関する論考をまとめた論文集である。それも、既刊の複数の論文集からさらに抜粋して再編集されている点で、高階氏の近代西洋美術研究の一つの集大成といえる。
その核となるテーマは、書下ろしの序文の冒頭が示すように「『近代』とは何か」である。「『近代』の登場により、十八世紀から十九世紀にかけて、西欧世界の社会のあり方とそれを理解するパラダイム設定に、もはや後戻りのきかない決定的な変化がおとずれたことは明らかであるように思われる」(9-10頁)。ここでは、副題の「『知性の美学』から『感性の詩学』へ」を手掛かりにその意味するところを探ろう。
まず、本書を読み解く補助線として、高階氏が『日本近代美術史論』で提出した「黒田清輝問題」がある。これは、印象派の輸入者と見なされていた黒田が日本に輸入したかったのは、実は印象派よりもむしろ西洋絵画の伝統、つまり「構想画」と「裸体画」であったという指摘である。
西洋絵画では、画題に明確な序列がある。宗教や歴史を主題とする物語画(ヒストリー・ペインティング)が上位にあり、風俗画、風景画、静物画の順に下位になる。この背景には、人は神の似姿として理性を与えられた自然管理者であるという旧約聖書の世界観がある。つまり、野性へと、無生物へと下降していくほど価値が低いという考え方である。高階氏の慧眼は、神(≒人)の理性を体現する物語を、画家もまた理性を駆使して知的に群像で構成した最上位の絵画を、「構想画」と呼んだことにある。
これに関連して、西洋絵画では神(≒人)を裸で描く「裸体画(ヌード)」を尊ぶ伝統がある。これもまた同様に、人は神の似姿として創造されており、聖なるものとして描かれた裸体は卑猥なものではないという約束事による。
西洋では、近代において、つまり「十八世紀から十九世紀にかけて」、この構想画や裸体画の伝統が崩れていく。なぜなら、ルネサンスから啓蒙主義を経て、人には神から理性が与えられているという旧約聖書の教えが理性による現世問題の解決という合理主義的世俗化を生じさせたからである。これが、市民革命を実現すると共に、分析と実験による自然支配としての科学技術も成立させ、逆に実証主義によるキリスト教の凋落を招く。この科学革命による科学技術の発達は、蒸気機関の発明を契機に産業革命に繋がっていく。
なおこの時、術(テクネー/アルス)の内、数理的な近代科学に結び付くものが技術(テクニック)として抜き出された時に、残ったものが芸術(アート)と呼ばれることになる。つまり、芸術は科学技術(テクノロジー)の補完概念なのである。やがて芸術の内、触覚性よりも理性的な視覚性の度合いの高いものが美術(ファイン・アート)と呼称されることになるだろう。
科学技術の発展は物質的繁栄をもたらす一方で、ハンス・ゼーデルマイヤーのいう「(キリスト教的)中心(理念)の喪失」を招来する。これにより、キリスト教的理性に統合されていた価値体系は解体し、社会は瓦解し始める。この精神的危機に対し、キリスト教を刷新した「新しい神話」を通じて再び人々の心を結合しようとしたのがロマン主義である。そこでは、中世趣味、異国趣味、異常趣味が噴出する。結局、理性の光は狂気の闇も召還したのである。
価値体系が解体すると、文化の諸領域(ジャンル)が分化し、各媒体(メディウム)も純化し始める。ここにおいて、絵画における物語性=文学性の称揚は疎まれ、「絵は詩の如く」という伝統的美学は否定され、レッシングの『ラオコーン』のように造形芸術と文学芸術は峻別され始める。その一方で、単なる名無しの脇役であったサロメが魔性の「宿命の女(ファム・ファタル)」に変貌したように、従来のキリスト教主題は再解釈され、絵画と文学の境界を超えて瀰漫していくという流行も生じる。
社会においては、画家とパトロンが乖離し、両者の仲介として美術評論家が登場し、サロンの代わりに個展や団体展が隆盛する。主題上の様々な制約から解放された芸術家は自由を獲得するが、新奇性と大衆受けに急き立てられると共に、社会に報われない「呪われた芸術家」の逸話も普及する。絵画では、理知的な一点透視遠近法が緩むと共に、理性による文学性よりも感性による音楽性が好まれ、客観的再現ではなく主観的表現が推進される。この傾向は、絵画ではドラクロワから始まり、マネ、モネ、セザンヌを経て、純粋抽象絵画へと到達する。同じ現象は詩でも生じていて、その筆頭に挙げられるのがマラルメである。これこそ正に、「『知性の美学』から『感性の詩学』へ」と形容できるだろう。
高階氏の著作は一貫して、単なる美術史に留まらず、比較文学や比較文化、さらに広義の比較精神史へと開かれている。本書にも、常に日本人にとって西洋とは何かという通奏低音が流れている。ぜひ、本書と同様の観点から「日本とは何か」という問題意識で高階氏の諸論考を厳選再編集する『日本近代芸術論』の出版を待ちたい。そして、筆者は何よりもまず、日本人の知性と美意識の最高峰として『高階秀爾全集』の刊行を心待ちにするものである。
※『週刊読書人』2023年12月1日号より転載。