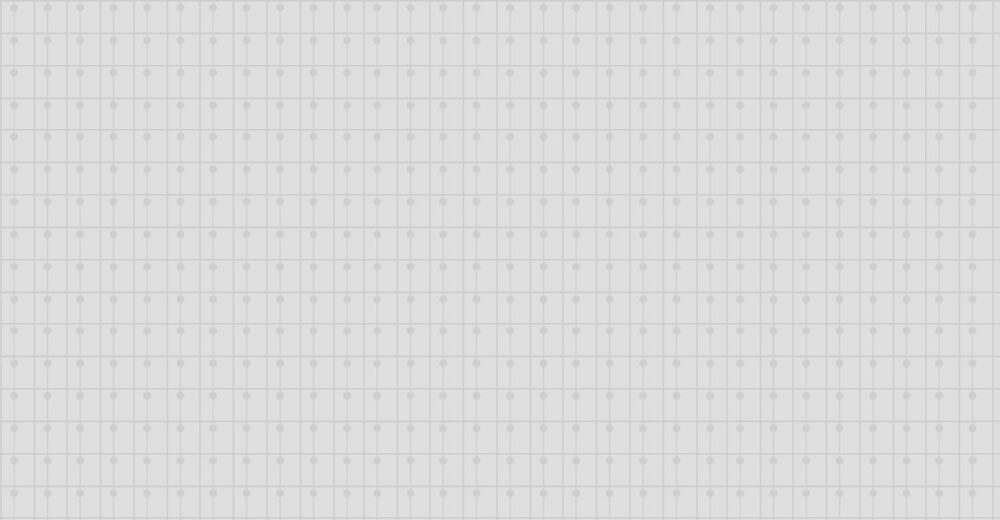(朝日新聞社「論座」2019年11月4日付の筆者の執筆記事を転載)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
落書きは楽しい。
授業中にノートの端っこに思わず描いたり、トイレの個室で便座に腰掛けたときに目の前で遭遇してにやりとしたり。
それらは、授業をしている先生の話をまともに聞いていない証しだし、公共の場や他人の所有物への落書きは器物損壊にもなりかねない。しかし、描いているほうは結構大まじめ。端(はた)から見ていても、描くことに夢中になっているように見える。
ある意味、「売れる絵描きになろう」などといった打算のない、純粋に表現の産物ともいえるのではなかろうか。
自称「ラクガキスト」が共感するバスキア
かくいう筆者は、自称「ラクガキスト」。落書き大好き人間だ。
もともと絵を描く趣味はなかった。だが、数年前に iPad のペイント系ソフトを使い始め、どんどんハマっていった。とはいえ、いわゆる上手な絵は、まったく描けない。美大に勤めてはいるが、教えているのは絵ではなく文章の書き方だ。
当然だが、美大生はデッサンの試験などを受けて入ってくる者が多い。彼・彼女らと比べると、自分が描くのはまさに下手な「落書き」のたぐいだ。自分の絵を見せようなどとは微塵も思うはずもなかった。
ところが、趣味とはおそろしい。あるとき試しに自分が描いた絵を T シャツに印刷してしまった。そして、何気なく大学に着ていった。 当然バレた。
「先生、その絵、ひょっとしたらご自分でお描きになったのでは?」 「そうだよ」「すごい! いかしてますね」
すっかり調子に乗った。「落書き」がどんどん T シャツになった。ヴァイオリンを弾くガイコツだとか、猫にごはんだとか、メトロノームの妖怪だとか。 T シャツ姿をスマホで撮影してコレクションする学生も現れた。
ある日、学外のある場所で知人に「制作現場」を目撃された。「すごく集中してる!と思ったら、絵を描いてたんだ」と言われた。確かに、これほどの集中力が注がれる時間はほかに見当たらないなと思った。自分は素人だと割り切っているので、上手く描こうなどとも思わない。ただひたすら、衝動に任せた「落書き」を楽しんでいることに気づいた。
恥を捨てて SNS で知人に「公開」すると、ある音楽家からは「作風が確立してますね」と言われた。上手でなくても、いや上手じゃないからこそ、描き手の個性が表れやすいのかもしれない。
そんな筆者が共感する画家。それがジャン=ミッシェル・バスキア(1960〜88年)だ。1980年代のニューヨークで活躍、若くして世を去った黒人アーティストだ。
ピカソとバスキアの違い
東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで開催中の「バスキア展 メイド・イン・ジャパン」(※)に出かけると、落書きとしか思えないようなたくさんの“作品”と出会う。絵の具を乱雑に塗りたくって顔を描いたような絵もあれば、「書きなぐり」という形容がふさわしい文字だけの作品もある。「こんなものが美術といえるのか」と感じる人もいるだろう。
(※2019年9月21日〜11月17日に開催された後に終了しています)
その点では、ピカソをほうふつとさせる。ただ、バスキアの絵はほんとうに落書きのような風情なので、現代美術に関する知識がなくても親しみやすく、楽しめる。
そもそもバスキアには、ピカソらの前衛画家とはまったく違った側面がある。スタートが正真正銘の落書きだったことだ。
幼い頃から絵心を自覚していたとしても、生き馬の目を抜くような行動力とパワーを必要とするニューヨークで、すぐに画家になれるわけがない。1970年代、10代のバスキアは地下鉄や街の壁にまさしく「落書き」をしていた(その後、美術批評の世界で、こうした落書きは「グラフィティ」と呼ばれることになる)。あくまでも違法行為である。
媒体を選ばず衝動的に描いた絵に天性が表れる
しかし、そこには創造性が開花があった。心の中から湧き出す表現の発露としてバスキアの「落書き」が、先鋭的な感性の持ち主を刺激するのは必然だったに違いない。やがて一部のギャラリストの目に留まり、随所で個展を開くようになり、80年代半ばにはポップアートの雄、アンディ・ウォーホルに認められて共同作業を始める。 アメリカン・ドリームを美術の世界で成し遂げたスター作家という見方もできる。
この展覧会を監修した美術史家の宮下規久朗さんは、「バスキアは最初文字の落書きから始め、80年以降絵を描くようになって大成功した。天性の色彩画家だ」と話す。一方で、「カンヴァスに描いた作品は少ない。人の家に泊まるとドア、冷蔵庫、棚、椅子などあちこちに勝手に絵を描いてしまい、問題になった」とも。
媒体を選ばず衝動的に描いた絵に天性が表れる。それが、バスキアだったのだ。
[画像削除]
前澤友作さんが約123億円で購入
80年代前半にバスキアが来日した際、多くの画廊や美術館の展覧会に作品が出品されており、日本でもスター作家としてすでに結構な話題になっていたようだ。しかし、日本でバスキアがこれほど有名になったのは、ZOZO 代表取締役社長だった前澤友作さん(現・スタートトゥデイ代表取締役)が2017年、作品《Untitled》(1982年)を約123億円で購入したというニュースが結構大きく寄与しているように思う。
この作品は、今回「バスキア展 メイド・イン・ジャパン」の目玉作品として出品されている。目の当たりにすると極めて強烈なパワーを感じた。並の「落書き」ではないことは明らかである。80年以降強烈に育まれたアーティストとしての意識が、表現力に磨きをかけたことがわかる。こうしてバスキアは、人種差別問題に対する主張など、さまざまな意味を暗号のように埋め込んだ作品をたくさん描き続けた。
絵画を活性化させるうぶな感覚の宝庫
最後に落書きの話に戻る。
落書きのすべてがバスキアの例のように美術として評価されることはありえない。だが、絵を描く衝動を何にも邪魔されずに実現したという視点では、すべての落書きにアートの成分の少なくともかけらが入っている。落書きは、絵画を活性化させるうぶな感覚の宝庫だからである。
そう考えると、世の中のいたるところにいるたくさんのクリエイターの面白い美術表現が見えてくるに違いない。そう、「ラクガキスト」を名乗る筆者は思うのである。