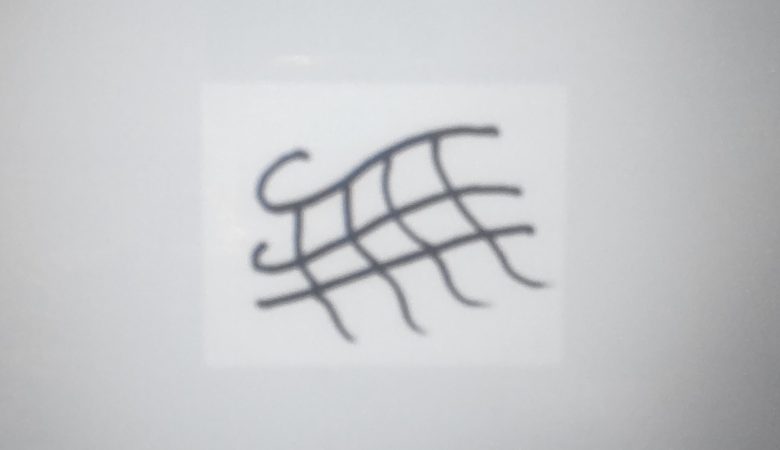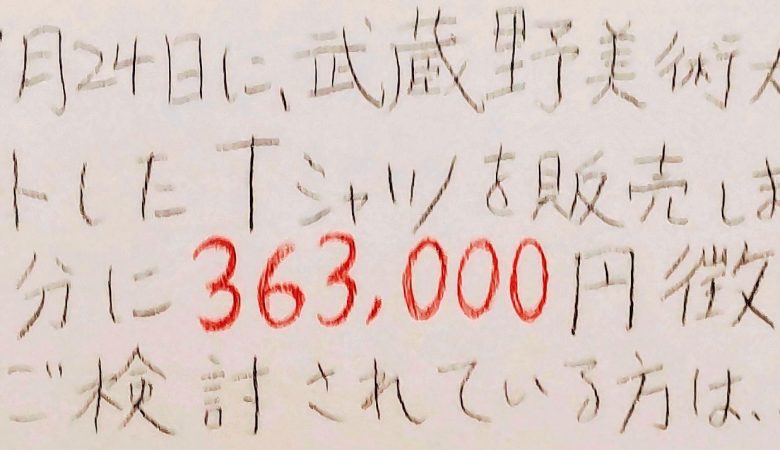「向こうの島」(植村真演出)は、東京都墨田区の向島地域の歴史の断層を示し、ふだんは「向こう」つまり彼岸にあるこの土地に潜む不可思議なものを感じさせる、ある種の市街劇だ。
ただし市街劇という演劇用語は適切ではないかもしれない。ほとんどの市街劇は、役者たちが演ずる劇が中心で、それが展開される地域は、単に舞台セットにすぎない。例えば、寺山修司は、ありきたりの場所を「劇場」にすることで演劇を街に展開していく。

向島百花園入口。「向こうの島」の開始地点
ところが「向こうの島」は、むしろ地域の方が主体だ。つまり地域に潜むものがあまりにも濃密で、そこにある過去の人間の営みを知ると、現代人が挑むことのできない境界にぶち当たる。その境界のあたりを掘り下げると、土地の記憶に連なるさまざまな風俗文化を見つけ出すことになる。(ただし細い路地の隙間や、空き地で、何者かが無言でさりげなく行き先を指すことがある。その導きなしには通過できない路地が続く。演出の植村真は「ツアーパフォーマンス」と呼ぶ。)

「向こうの島」の最終地点
地図と懐中電灯を渡されて、闇が濃厚な夜の向島百花園から浄めを受けて出発する。百花園は、江戸の文人墨客が集った優雅な場所として知られており、文字通りにまさにいつでも花が咲き乱れる美しいところだ。いまも多くの人々が訪れ植物を愛でる。しかしここが優雅な場所に生まれ変わるには、そこにあった霊を鎮めるという開園以前に通過した事の数々はほとんど知られていない。それを知ると向島百花園がこの催しの出発点に選ばれたのは、志怪小説の始まりのように感じる。
向島という地名は、浅草から見て隅田川の「向こう」にある雅な街という意味に由来しているらしい。花街として江戸時代に華やかに栄えた。 そういう華やかさの背景には、入り組んだ路地に長屋が続く市井の生活がある。地図を片手に東向島から京島へと歩いていくと路地の連なりが、より密になる。20世紀の初めごろは、ここは世界で最も人口密度が高かった。
私娼街の玉の井も、旧東京市向島区寺島町、現在の東向島地域にあった。永井荷風の小説「濹東綺譚」の舞台でもある。荷風はこの地域を「ラビラント(迷宮)」と呼んで歩きまわっていた。ラビラントは、現在の東向島駅がかつては玉の井駅であったように、時代の変遷の中で姿を変えている。
この夜にラビラントを彷徨うのは、シチュアショニストたちが言う「漂流(dérive)」や、古ノルド語のflanaに語源があるとされるフランス語の「遊歩者=フラヌール(flâneur)」たらんとすることかもしれない。
フラヌール、つまり目的もなくぶらぶら歩く人にとって、この地域はうってつけの漂流の場所でもある。

「すみだ向島EXPO」が開催される京島地区
向島の京島地域を中心に「すみだ向島EXPO」が10月いっぱい開催されていて、先述の「向こうの島」が夜間に行われた催しであるのに対し、こちらは昼間に開催されている。
この地域の中心となる場所は「下町人情キラキラ橘商店街」。長屋が連なった店が続き、ところどころに空店舗、空家もちらほらある。
この地域にアーティストたちが住むようになって、小さな店がギャラリーやスタジオやレジデンシーの場所になって、そのあり方もまた変わってきている。
たまたまこの京島に初めて足を運んだのは2023年春で、昨年のドクメンタ15でアーティスティック・ディレクターを担ったインドネシアのルアンルパ(ruangrupa)と共に、2018年から進めている教育的知識共有プラットフォームの「グドスクル」(Gudskul)のメンバーがここで開催したワークショップに参加した時だった。
彼らの活動の姿勢はとてもユニークで、ノンクロン(nongkrong) という。インドネシア語で「ぶらぶらする」とか「たむろする」というような意味の言葉だ。教育もアートもぶらぶらすることから始まる。
ワークショップの後、この地域を彼らと共にノンクロンした。
地域はその範囲で、地域性や地域文化との距離が変わってくる。全国各地でビエンナーレや芸術祭が開催されているが、都道府県庁所在地レベルで地名を冠した開催になると、むしろ国際的であることの方が強調されがちになり、地域性は薄れていく。
さらに狭い地域を選んでこそ、フラヌール、漂流、ノンクロンという、19世紀から21世紀を超えたぶらぶらが濃密な文化へと導く。
入り組んだ細道を通りぬけて確かめる空間の感覚と文化。

「向こうの島」指示・地図書表紙
向こうの島 https://www.uemuramakoto.com/the-island-beyond/
すみだ向島EXPO「百年の祝福」 https://sumidaexpo.com/