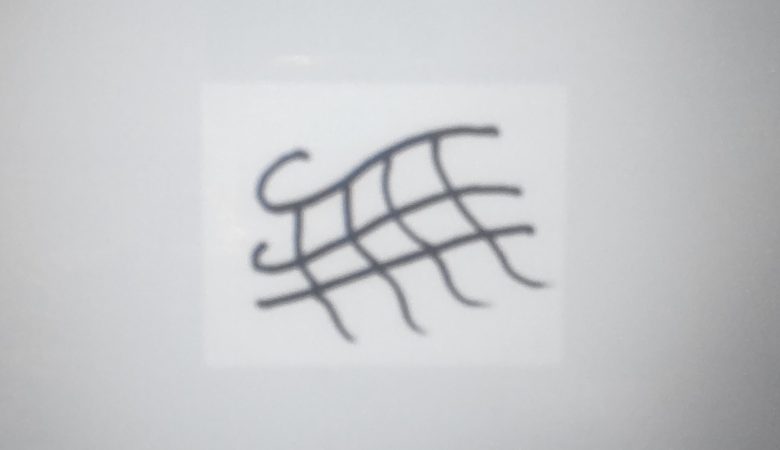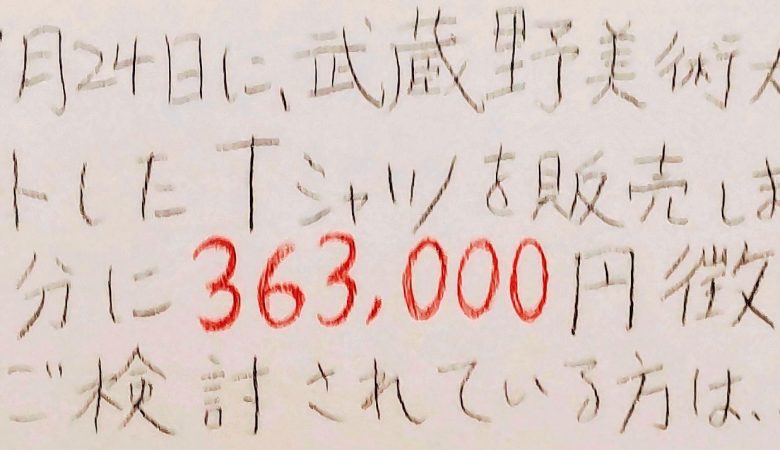会場風景
「Melting Rock, Still Wind / 溶ける岩、留まる風」
会期:2023年8月11日(金)~13日(日)、18日(金)~20日(日)
会場:山中suplexの別棟「MINE」
大阪の芸術文化が、貧しいのではないかとは昔から言われている。なぜだろうか。最近話題になっているが、大量のコレクションを購入しているが、大阪府には府立の美術館はないのだ。これだけ大きな都道府県の中で、美術館を持たないのは珍しい。
1980年代、大阪府立の「現代美術文化センター」をつくる予定で作品も購入されたが、財政難のため頓挫した。1974年に設立された大阪府立現代美術センターも、2012年に閉館された。一部の貸展示室事業は大阪市西区江之子島にオープンした大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco)に継承されているが、大阪府現代美術センターが主催していた「大阪・アート・カレイドスコープ」のような意欲的なプログラムは行われていない。第5回まで開催されて終了したが、4回と5回は大地の芸術祭や瀬戸内国際芸術祭で著名な北川フラムがプロデューサーを担っていた。大阪府の街を舞台に開催された「おおさかカンヴァス」は、アーティストだけはないさまざまな個人や団体が応募可能で、作品プランを提案し、制作費が援助されるユニークな取り組みであったが、2009年(1回目は壁画の事業だったので実質的には2010年)からはじまり、2016年までで終了した。
2010年12月26日、天保山にあったサントリーミュージアムも閉館している。いっぽう大阪市の近現代美術館は、構想から40年を経て、2022年に民間資本と運営を組み合わせたPFI方式によって、大阪中之島美術館としてようやく開館した。1年目は黒字になったということで期待は持てるが、美術シーンを牽引する中心地がないままさ迷っている印象は否めないだろう。
とはいえ、中之島は具体(美術協会)の拠点であるグタイピナコテカもあったし、骨董街のある西天満の老松町には、番画廊、ギャラリー白、ONギャラリーがあり、「万博音頭」と呼ばれ、関西ニューウェイブの作家たちの発表の場として賑わったのは確かだ。現在でも西天満にはコマーシャルギャラリーが集積するようになった。
また、戦前まで遡れば、船場の商人たちは、画家のパトロンになって、床の間に掛け軸を飾り、画塾もあった。あるいは大阪朝日新聞や大阪毎日新聞のようなマスメディアや百貨店があり、挿絵画家や図案家として成功する道もあった。ただし、そのような江戸時代を継承する和風の絵画(あるいは、文人画や中国趣味)や、ある程度のマーケットがあることが、逆にアカデミーとサロンからなる西洋的なシステムを導入した東京とまったく違った生態系を築いてしまった要因でもあるだろう。
つまり、近代美術の装置である、美術館と美術学校(大学)を持たないまま、戦後を迎えてしまい、発表の場としても、研究の場としても、作家や研究者が育ちにくい環境になっているのである。近隣に多くの美術大学や美術館を擁する京都があることで、棲み分けてしまったということもあるだろう。富裕層であった船場の商人も阪神間に住まいを移している。そのため芸術文化が構造的に困難な状況が続いているのだ。
その中で、千島土地が牽引する北加賀屋のアートプロジェクトのような民間における取り組みが目立つ。その影響もあってから、不動産業者がアートの積極的な支援をする例も出始めている。大阪の新町にあるNANEI新町bld.もその一つだ。現在、使用されていないフロアを、アートプロジェクトに提供している。もとは小さな住宅兼賃貸マンションである。

「MINE」が入居しているNANEI新町bld.。最寄りの駅は大阪メトロ西大橋駅。心斎橋駅から西に1駅である。
現在、滋賀と京都の県境にある共同スタジオ(その形態はコレクティブに近い)、山中suplexとそのメンバーが運営者となって、山中suplexの別棟「MINE」 と命名し、展覧会、海外のキュレーターとのトークイベントなどを実施している。8月11日(金)~13日(日)、18日(金)~20日(日)の2度の週末、「Melting Rock, Still Wind/溶ける岩、留まる風」が開催された。

会場風景
キュレーターは陳寅迪(チェン・インディ)。中国出身だが、イギリスのヨーク大学、ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツで、キュレーションと美術史を修めた。「The Art Newspaper China」や「C-print」(ストックホルム)などで執筆を行ったり、ニューヨーク(NY)のギャラリーで展覧会をキュレーションしたりしているという。
彼女が選んだ作家も、すべて日本出身でも、日本在住でもない。NYやベルリン、オランダ・ハーレムを拠点にしている作家たちだ。大阪のオルタナティブなスペースで、世界各国のアーティストによる展覧会が実現できるのは理由がある。現在、NYにレジデンスしているメンバーのアーティスト、石黒健一がキュレーターの陳と交流したことがきっかけで、陳が作家を選定したという。日本の都市部の住宅の空間に、世界各国から集まってきたアーティストの作品が転移しているのも興味深い。
キュレーターも作家も来日しているわけではないが、キュレーターと作家、受け入れ側の山中suplexが相談し、鬣恒太郎を中心に設営を行った。基本的に、映像や写真の作品なので、展示しやすいということもあるし、DIYに長けた作家を中心とした集まりであり、設営に慣れているとこともあるだろう。また、「岩」がタイトルに付けられているため、岩でスクリーンの布が押さえられているが、出品作家の曹舒怡(ツァオ・シューイ)の発案であるという。それを受けて、白川砂の産地跡である山中suplexから持ち込まれたものだが、自然なコラボレーションになっている。
展覧会のテーマは、「MINE」の英語(mine=採掘)と日本語(峯=山頂)から着想されたという。世界のさまざまな土地と採掘、石、微生物などを通して、人間と自然との関係を問うアーティストが選ばれている。近年アート界でも一つのトレンドといってもよい、「人新世」下の自然環境や、マルチスピーシーズ(複数種)の人類学の範疇に入るものであるには違いない。
また、これらの傾向は、クレア・ビショップが指摘するように、世界的にアーティストが高学歴になり、研究や調査と芸術表現が一体化していることとも関係しているだろう。そのような傾向を持つアーティストの場合、表現主義的な内面の表出は影を潜め、外側の環境を「印象」の範囲に留めることなく、様々なメディアを駆使した環境の観測と加工が主な方法となる。
その中で、近年のモードは、ドキュメンタリーのようなスタイルではなく、そこにフィクションやストーリーを入れ、エフェクトなどもされていることだろう。

アンドレア・ガラーノ・トロ《de allá pa’ acá》(2021)
例えば、最初の部屋に上映されているアンドレア・ガラーノ・トロの映像作品は、チリの鉱山の微生物が、ノートパソコンに含まれているリチウム電池の中に住み着くまでの旅を、実際の映像と加工された映像とを組み合わせて一つのストーリーにしている。それは、アンドレアが、チリで育っていることとも関係しているが、チリのアタカマ砂漠で撮影した映像と、宇宙創成からピノチェト独裁政権に至るまでの場所の物語がコラージュされているという。微生物は擬人化され、語り部になることで、非人間的な存在が、自然と人間の営みによって、旅をし、変容されていく状況をつむぎだしている。それはポスト・コロニアリズム的かつ非人間的な視点へのアプローチとなっている。

曹舒怡《果てしない煌めきが全てを覆う》(2022)
次の部屋に上映されている曹舒怡(ツァオ・シューイー)の映像作品も、バクテリア、古細菌、汚染物質が、身体や場所を侵食してく事実と虚構が入り混じった物語だ。その物語の起点は、核廃棄物処分場で白雁の死骸を遭遇することに始まるが、そのモデルは、ニューメキシコ州南部のデラウェア推積盆地の放射性廃棄物隔離試験施設(WIPP)と、1995年モンタナ州バークレー・ピット湖で起こった白雁大量死事件だという。そこで人間と非人間とが絡み合い、差異ボーク化していくが、ジェネレーティブ・アニメーションを使用することで、映像自体も人間と非人間の創作の境目がなくなっている。

ケース・ヴァン・レーヴェン《UNTITLED(REGIERUNGSBUNKER)》(2023) 下《CERRMONY OF CONNECTIONS》(2021)
対面の床の間に飾られたケース・ヴァン・レーヴェンの写真は、冷戦時代につくられた核シェルターを写したものだ。厚いコンクリートに覆われているが、すでに老朽化も目立つ。それは近代産業遺産のようでもあるし、人間が滅亡した後の古代遺跡のようにも見える。ロシアのウクライナ侵攻、台湾有事の可能性が叫ばれるなか、核兵器の使用は冷戦時代よりもリアリティが増しているのは皮肉だ。実際、ロシアの空爆に対して、ウクライナは地下鉄をシェルターにするなど、核戦争を想定した冷戦時代のインフラが有効活用されている。もし今、核戦争が起きれば、このシェルターも再び使われるかもしれない。それが、第二次世界大戦の空爆で約1/3が焼失し、「船場」の文化を喪失した大阪で展示されているのは皮肉な転移だ。それ以前、「MINE」のある新町は、巨大な遊郭街であったが明治末期に大部分が焼失し、衰退した歴史を持つ。
床の間の床畳には、小さなコンクリート片の「彫刻」が桐箱に納められているが、アーティストがつくったコンクリートと海から採取した砂を組み合わせたものだという。しかし、塩分の入った砂をコンクリートに混ぜると、脆くなるのだ。鉄筋コンクリートならば、鉄錆ができて膨張することで劣化が進む。コンクリートの原料、石灰石は太古の石灰藻や珊瑚、貝殻、石灰質プランクトン等が固まったものだが、海から採取した砂を混ぜると早く崩れていくだろう。コンクリートという近代の技術でさえ、巨視的に見えれば、地球の生態系を利用しているに過ぎないのだ。

アルケミーバース《火砕流》(2023)
奥の窓の前の廊下には、NY在住の梁必成(リャン・ビーチェン)と奕萱(イーシュアン)によるコレクティブ、アルケミーバースが、ハワイでサーベイしたデータを、オーディオビジュアルに変換して展示している。音響は水中、地層、廃壕などをフィールドレコーディングし、リミックスしたものだ。地形図のような3Dのポリゴンデータは、火砕流構成物を3Dスキャンし、噴火口から発せられる振動をデータに加味してプリントしている。
今回の展覧会は、キュレーターも含めて非白人男性、非西洋社会の出身かもしれないが、もっと重要なのは人類レベルの危機が共有され、非人間の視点や共生が視野に置かれていることだろう。もう一つ、ストーリーやナラティブが復活してきていることも指摘した方がよいだろう。現代アートのプレゼンテーションは、近年、サーベイと映像インスタレーションが急増しているが、ドキュメンタリー的な映像から、映画的な文法とは少し違うが、擬人化やストーリー、フィクションが含まれるようになってきている。人類が情報や感情を共有するために、現代アートにストーリーやフィクションが復活してきていることも、人類にとってアートとは何か問いかけられているようにも思えた。
ちなみに、この日、猛烈な暑さで展覧会場はエアコンがあまり効かず、映像を全部見ることはできなかった。我々がアートを鑑賞する場、もっと言えば生活する場自体も揺らいでいることを実感することになった。大阪においてもこのような地球レベルの危機意識やアートを共有するための場が必要なのは間違いない。MINEのようなオルタナティブな試みが、根をはり、街を浸食していくことを願いたい。