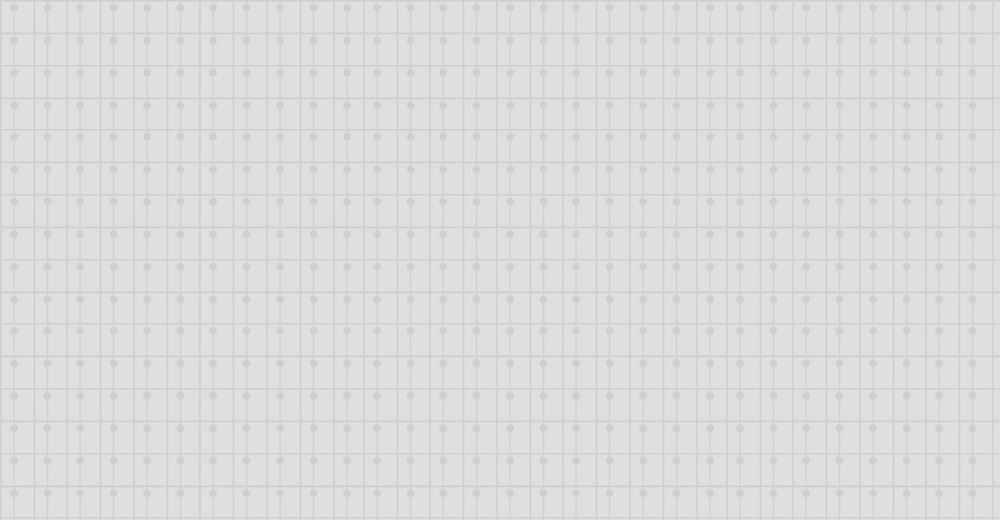2023年に出版された書籍を回顧する中で、ぜひ挙げておきたい1冊がある。望月昭秀編著『土偶を読むを読む』(文学通信、2023年4月、以下「望月本」とする)だ。
単刀直入に言えば、2021年4月に晶文社から刊行された竹倉史人著『土偶を読む』(以下「竹倉本」とする)で書かれた新説の内容を丁寧に吟味し、誤謬を解き明かした書籍である。

左)『土偶を読むを読む』(望月昭秀編著、文学通信、2023年4月 ※執筆は、望月昭秀、金子昭彦、小久保拓也、佐々木由香、菅豊、白鳥兄弟、松井実、山科哲、山田康弘、吉田泰幸) 右)『土偶を読む』(竹倉史人著、晶文社、2021年4月)
新説は実証的な検証のもとで概ね否定
「竹倉本」では、土偶は人間、特に女性をかたどったものであるという通説を覆す内容が話題を呼んだ。たとえば中空土偶はクリ、結髪土偶はイネ、遮光器土偶はサトイモをかたどったことを写真を並べて例証。土偶の形がさまざまな植物に由来することを強く主張した。確かに写真には説得力があった。
望月本の編著者の望月昭秀は書籍の装幀や雑誌の誌面デザインを主たる業務とするかたわら、「縄文ZINE」というフリーペーパーの編集長を務めている人物だ。望月本では、望月自身による竹倉本の批判的な分析のほか、数人の考古学者らによる論考や対談等を掲載している。全体を読むと土偶研究の最前線を知ることができる書籍になっており、竹倉本の吟味に終始せずに土偶研究の現在の状況を広く知らしめようと意図されている点も興味深い。
望月本では、竹倉本で論じられた新説が、丁寧で実証的な検証のもとで概ね否定されている。たとえば、どちらの表紙にも写真が載っているのは、中空土偶の頭部と食用植物のクリである。竹倉本は両者を「=(等号)」で結び、望月本では両者を「≠(不等号)」で結んでいる。
2冊の書籍の該当ページを開いてみる。竹倉本では、中空土偶はクリを模したものという新説を打ち出している。根拠は、写真を比べると両者が似ていること。全体の形のほか、土偶の目の少し上にある線の存在にも言及している。一方、望月本では、両者を写真という二次元媒体ではなく立体物として比較している。横から見た写真を掲載するなどして、立体物としては両者がまったく異なっていること、さらには、やや上から見ると頭に2箇所の大きな穴が空いており、類例の土偶と比較してもともとはラッパ状の突起がその穴の上に付いていた、つまり、欠損する前の中空土偶はクリとは似ても似つかない形をしていたことに言及した。中空土偶には時代や場所を検証する中でほかに多くの類例があるにもかかわらず、竹倉本では写真で似ているものだけを恣意的に選択したことを、望月本では批判している。こうした検証を竹倉本で挙げられたほとんどの事例で行い、竹倉本の新説が誤謬に満ちていることを論証しているのだ。
ただし、望月は竹倉の論を頭ごなしに否定しているわけではなく、むしろ新しい視点による研究自体には歓迎の意を示している。一方、竹倉からの具体的な反論を、筆者は現時点では目にしていない。
3つの権威が竹倉本を支持したことの余波
もっとも世の中には、誤謬に満ちた本はおそらくけっこうな数があるとも推測される。出版不況の中では短期間のうちに店頭から消える本も多い。その中であえて反論するために望月本が出版されたことには、大きな理由があったとみられる。竹倉本は出版された2021年にサントリー学芸賞という権威のある賞を受賞し、NHKの番組中でも新説が紹介されるなどのことがあったからだ(※)。翌年には同じ著者(竹倉史人)による『縄文を読む図鑑』が小学館から刊行された。大手の出版社から小学生をターゲットにした図鑑が出たわけだ。サントリー学芸賞、NHK、小学館という3つの権威が竹倉本を支持するに及び、このままでは間違いのほうが正論として世の中に定着しかねない。それゆえ、声高に反論する手段として新たな書籍の出版が企図されたと推察されるのである。
※筆者が見たNHKの番組の中では、出席していた考古学者の全員が新説には賛同していないことを紹介する場面もあったが、番組全体のごく一部(数十秒程度)だったと記憶している。
この件で特に興味深く感じるのは、「本」で出された新説への反論をあえて「本」で出したことである。「目には目を、本には本を」というべきか。とは言っても、書籍を出版するには、速報媒体の記事やSNSへの投稿と比べると、莫大な時間と手間がかかるし、赤字リスクも背負うことになる。まして反論をするための書籍を出す際には、より強力な理論武装をする必要がある。実現は、生易しいことではなかっただろう。
今春、望月本が刊行されたばかりの頃に、筆者は勤務先の大学の授業で、この論争について2冊の本を題材に学生たちと情報を共有した。中には、授業で取り上げる前に竹倉本を読み終えていた学生もおり、「まるっきり信じてました。こうした反論があるのはとても勉強になりました」という声を聞いた。後日、別の学生からは、「竹倉本が東京国立博物館のミュージアムグッズ売り場で堂々と販売されていて驚いた」という感想も聞いた。もちろん博物館の売り場については学芸員や研究員が運営に携わっているわけではないだろうから、十分にありうることである。しかし、学生が解せないと感じたのは無理からぬ話である。
出版社は文化をつくる存在
さらに昨日、竹倉本の版元の晶文社のSNSヘの発信で、竹倉本が10刷を達成したという投稿を目にした。来年度には「続編」が出るという記述もあった。筆者も出版社に在籍したことがあるので、出版不況が続く現在において、増刷が可能な書籍の存在は、実に貴重だと思う。
しかし、出版社というのは文化をつくる存在である。版元が望月本の存在を知らないはずはない。きちんとした望月本への反論ができていない状況が続いているとすれば、増刷をやめないどころか、「続編」まで出そうという版元の「見識」は疑わざるをえない。あるいは、「続編」に望月本への反論が書かれているのであれば、書籍でなされたある書籍への反論に対してさらに別の書籍で反論が上がってくるという、実に興味深い展開になるが、期待していいのだろうか。
竹倉が従来の考古学とは異なる視点で土偶に注目したこと自体は、喜ばしいことだ。現代人の目で見ても独創的で魅力的なあの造形美は、いったいどこから来ているのか。その秘密の解明は、ロマンを希求する現代人の心をも刺激するだろう。筆者は考古学の専門家ではないが、土偶独特の美についての探究が進むのは、非常に素晴らしいことだと思う。間違いがあった場合は修正しつつ、調査や研究が深まっていくことを切に願いたい。