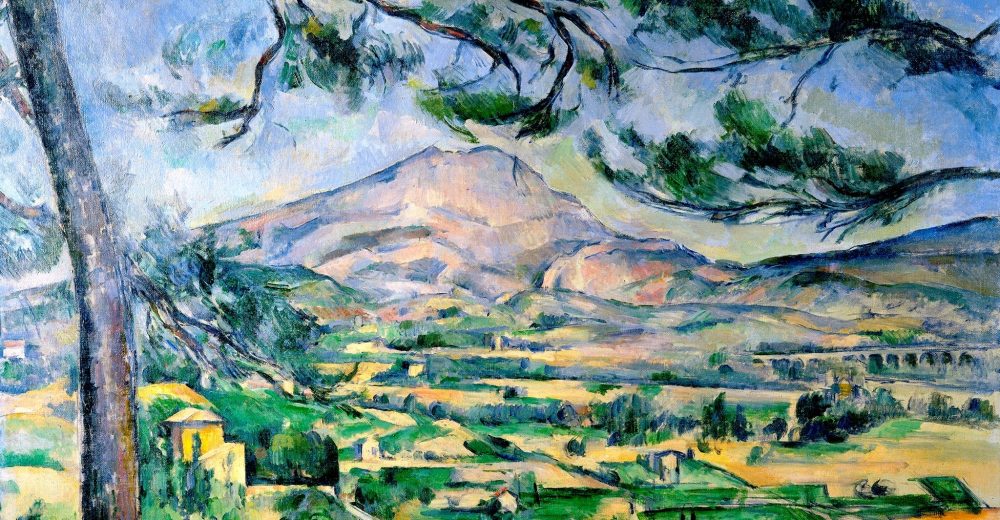図1 ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887年頃
ポール・セザンヌ(1839-1906)は、一体何を絵画で「実現」しようとしたのだろうか?
セザンヌは、19世紀における蒸気鉄道による視覚の変容を内面化し、それを絵画で表現した世界で最初の画家である。この重要な事実は、100年以上も見過ごされてきた。
実際に、セザンヌが成長した時代は、フランスの鉄道網が急速に発展した時代である。
フランスでは1837年に最初の旅客鉄道が開通し、セザンヌはその2年後に生まれている。1840年代に鉄道網は急速に拡大し、第二帝政期(1852–1870)にパリと主要な地方都市を結ぶ幹線路線が整備されている。
1861年、22歳の時に、セザンヌは生まれ故郷エクス=アン=プロヴァンスからパリへ初めて長距離列車で旅行した。その後も晩年に至るまで、彼はエクスとパリを蒸気鉄道で頻繁に往復している。
つまり、一般にセザンヌは自然愛好の画家として知られているが、同時に近代生活の画家でもあった。

図2 モンブリアンから眺めたサント・ヴィクトワール山とアルク渓谷の鉄道橋
(2006年8月24日筆者撮影)
移動手段が馬の速力と持久力頼みだった時代、馬車の平均速度はおよそ時速16キロメートルに過ぎなかった。これに対し、1845年の蒸気機関車の最高速度は時速約64キロメートルであり、馬車の約4倍の速さである。
そうした高速で走る汽車の車窓から見る風景は、目まぐるしく過ぎ去り、刹那的で断片的なイメージとして知覚された。この新しい視覚体験は、風景をゆっくり細部まで味わうことに慣れた年長世代にはしばしば嫌悪された。
しかし、まもなく若い世代は高速列車の窓から眺める風景を楽しみ、むしろこの流動的なイメージこそ美しいと感じるようになる。
例えば、ヴィクトル・ユゴー(1802-1885)は1837年8月22日付の妻宛の手紙で、動く列車から眺めた通過風景を次のように楽しんでいる。彼は、汽車の速度により風景が歪み、斑点や横縞のように見えると述べている。
蒸気鉄道は、断然とても美しい……。素晴らしい動きだ。それを分かるためには、体感する必要があった。スピードは、前代未聞だ。沿線の花々は、もはや花ではなく、赤や白の斑点、あるいはむしろ横縞だ。もはや、どんな斑点も存在せず、全てが横縞と化している[1]。
また、バンジャマン・ガスティノウ(1823-1904)は『鉄道人生』(1861年)で、汽車の車窓を次のように評価している。ここでは、蒸気鉄道が動きを孕んだ美を作り出すと説かれている。
蒸気鉄道が創造される前は、自然はピクリとも動かず、まるで眠れる森の美女だった。天空も、不変であるように見えた。蒸気鉄道が、全てに生気を与えた。天空は揺れる無限となり、自然は動く美となった[2]。
さらに、ジュール・クラルティー(1840-1913)は『パリ人達の旅行』(1865年)で、車窓風景を次のように称揚している。ここでは、速度空間における形体の純粋化が論じられている。
数時間の内に、蒸気鉄道はフランス全土を提示し、目の前に無限のパノラマ、つまり新奇な驚異という魅力的な画像の厖大な連続を繰り広げる。風景について言えば、蒸気鉄道は大まかな量塊しか提示しない。これは、巨匠級の芸術家こそが用いる手法である。蒸気鉄道には、細部を求めずに生き生きとした全体を求めよう[3]。
セザンヌはこうした汽車の車窓風景に美を感じる新世代の一人であり、列車から見た風景の運動的体験に影響を受けて、意識的にせよ無意識的にせよ、新しい絵画的表現を生み出した。実際、セザンヌの多くの作品では、筆致が横方向に繰り返され、稜線が水平に強調され、対象は大まかに捉えられると共に、視点の複数化が顕著である(図1–2)。
図3 アルク渓谷の鉄道橋の通過時に眺めたサント・ヴィクトワール山
(2006年8月26日筆者撮影)
何よりもまず、セザンヌ自身が1878年4月14日付の親友エミール・ゾラ宛の手紙で、疾走する汽車の車窓風景を賛美している。
マルセイユへ行く時、ジベール氏と一緒だった。この手の人達は見ることに長けているが、その眼は教師的だ。蒸気鉄道(le chemin de fer)でアレクシ邸の傍を通過する時、東の方角に目の眩むようなモティーフが展開する。サント・ヴィクトワール山と、ボールクイユにそびえる岩山だ。僕は、「何と美しいモティーフだろう(quel beau motif)」と言った。すると、彼は「線が揺れ動き過ぎている」と答えた。――そのくせ、『居酒屋』については、それについて最初に僕に話したのは彼なのだが、彼は非常に物分かりの良い褒め言葉を並べていた。しかし、いつも技量の観点からなのだ[4]!
ここでセザンヌが描写しているのは、エクス・アン・プロヴァンス駅からマルセイユ行きの汽車に乗って数分後の光景である(図3)。より正確に言えば、ここでセザンヌが「何と美しいモティーフだろう」と賛美しているのは、正に図1の画面右中央に描かれた鉄道橋(図4-図10)を通過する時に汽車の車窓から見渡せるサント・ヴィクトワール山なのである。

図4 アルク渓谷の鉄道橋の通過時に眺めたサント・ヴィクトワール山
(2006年8月26日筆者撮影)

図5 アルク渓谷の鉄道橋
(2006年8月22日筆者撮影)

図6 アルク渓谷の鉄道橋
(2006年8月22日筆者撮影)

図7 アルク渓谷の鉄道橋
(2006年8月22日筆者撮影)

図8 アルク渓谷の鉄道橋
(2006年8月22日筆者撮影)
図9 アルク渓谷の鉄道橋とサント・ヴィクトワール山
(2006年8月22日筆者撮影)
図10 アルク渓谷の鉄道橋とサント・ヴィクトワール山
(2006年8月25日筆者撮影)
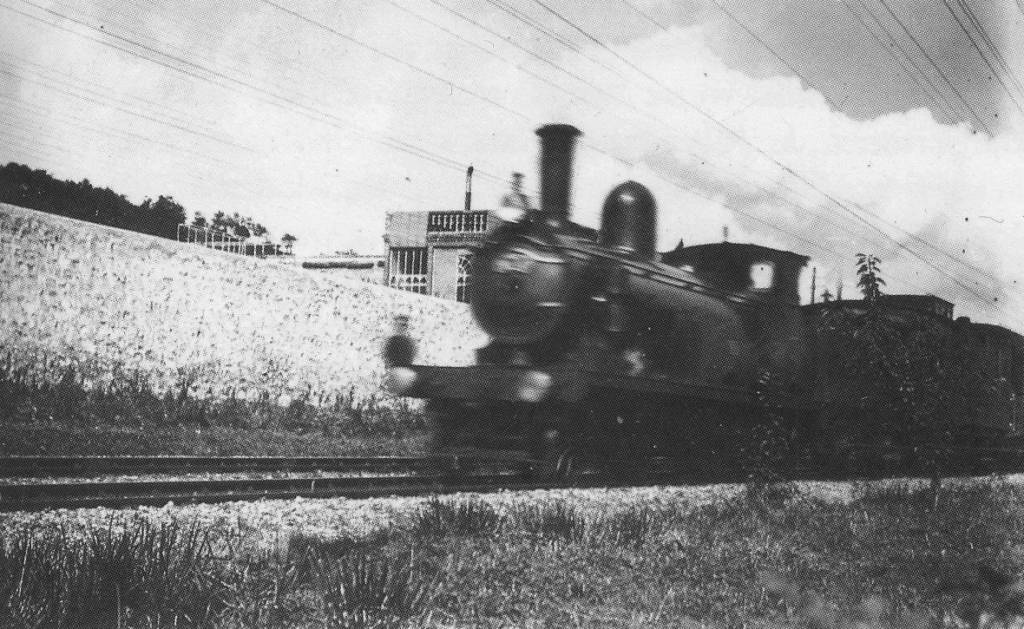
図11 19世紀後半のフランスの蒸気鉄道
(エミール・ゾラ撮影)
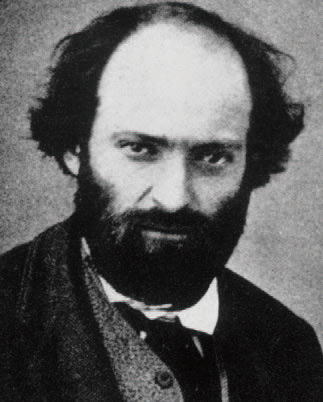
図12 32歳頃のポール・セザンヌ 1871年
(撮影者不詳)
ここで注目すべきは、このセザンヌの手紙が書かれたのが、この鉄道橋を含むエクス=マルセイユ線の開通(1877年10月15日)からわずか半年後である事実である。また、セザンヌがサント・ヴィクトワール山の連作を描き始めたのもちょうどこの1878年以後である。
つまり、39歳になって初めて取り組まれたセザンヌのサント・ヴィクトワール山連作は、このアルク渓谷の鉄道橋を汽車で通過する時の視覚体験に触発されて開始されている。少なくとも、セザンヌ自身が疾走する汽車の車窓風景を「美しい」と証言している以上、そうした美的体験がセザンヌの造形表現に反映している可能性を否定することは誰にもできない。
もちろん、セザンヌは蒸気鉄道に乗車しているときの車窓風景をそのまま描いたのではない。そうではなく、降車後に眺めた自然風景に蒸気鉄道による視覚の変容を適用している点こそが、近代的視覚の内面化とその創造的昇華において芸術的重要性を持つのである。
19世紀に普及した蒸気鉄道は、人々の日常生活に普遍的な視覚の変容をもたらした。そして、そうした視覚の変容に対する評価が否定から肯定へ変わったことは歴史的事実である。そうした人類史において画期的な視覚革命に鋭敏に反応し、それを絵画上にある種の新しい感覚として創造的に「実現」した点で、セザンヌは世界美術史において極めて重要な役割を果たすことになったのである(図11・図12)。
註
[1] Victor Hugo, Correspondance familiale et écrits intimes, tome II (1828-1839), Paris: Robert Laffont, 1991, p. 421. (Cited in Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1986, p. 55.)
[2] Benjamin Gastineau, La Vie en chemin de fer, Paris: E. Dentu, 1861, p. 31. (Cited in Walter Benjamin, The Arcades Project, translated by Howard Eiland and Kevin McLaughlin; prepared on the basis of the German volume edited by Rolf Tiedemann, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 2002, p. 588.)
[3] Jules Claretie, Voyages d’un Parisien, Paris: A. Faure, 1865, p. 4. (Cited in Schivelbusch, The Railway Journey, p. 60.)
[4] Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris: Bernard Grasset, 1937; nouvelle édition révisée et augmentée, Paris: Bernard Grasset, 1978, p. 165. (Paul Cézanne, Letters, edited by John Rewald, translated from the French by Marguerite Kay, New York: Da Capo Press, 1995, pp. 158-159.)
【関連論考】
■ 秋丸知貴『セザンヌと蒸気鉄道――19世紀における視覚の変容』
セザンヌと蒸気鉄道(1)――近代的視覚の秘められた起源
セザンヌと蒸気鉄道(2)――フランス印象派の最初の鉄道絵画
セザンヌと蒸気鉄道(3)――エクス・アン・プロヴァンスの鉄道画題
セザンヌと蒸気鉄道(4)――メダン、ポントワーズ、ガルダンヌ、エスタックの鉄道画題
セザンヌと蒸気鉄道(5)――造形表現の様式分析
セザンヌと蒸気鉄道(6)――画題から造形への機械の影響
セザンヌと蒸気鉄道(7)――感覚の実現とは何か?
■ Tomoki Akimaru, Cézanne and the Railway: A Transformation of Visual Perception in the 19th Century.
Cézanne and the Railway (1): The Hidden Origin of Modern Vision
Cézanne and the Railway (2): The Earliest Railway Painting Among French Impressionists
Cézanne and the Railway (3): His Railway Subject in Aix-en-Provence
Cézanne and the Railway (4): His Railway Subject in Médan, Pontoise, Gardanne, and L’Estaque
Cézanne and the Railway (5): A Stylistic Analysis of His Pictorial Form
Cézanne and the Railway (6): The Influence of the Machine on the Shift from Subject to Form
Cézanne and the Railway (7): What is the Realization of Sensations?