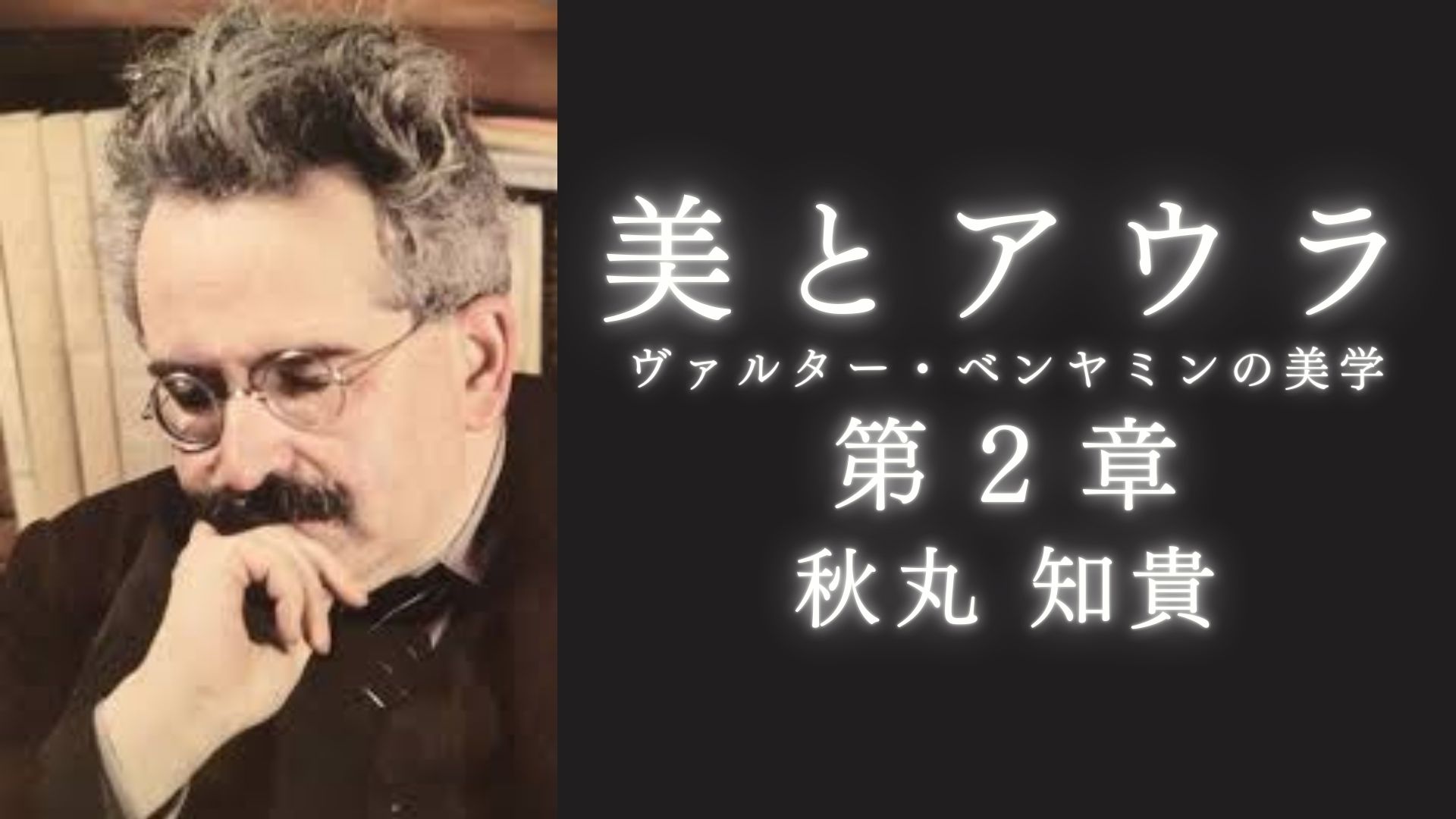
前章「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念について」では、九〇年以上謎とされてきたベンヤミンの有名な「アウラ」概念を、同一の時空間上に存在する主体と客体の相互作用により相互に生じる変化、及び相互に宿るその時間的全蓄積と読解した。これに基づき、本章ではベンヤミンのもう一つの有名な謎の概念である「アウラの凋落」について解読する。
1 アウラ的知覚
ベンヤミンは、「アウラ」を経験する知覚を「アウラ的知覚」と呼んでいる。例えば、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」(一九三九年)で、「アウラ」を知覚する能力について次のように言っている。
「知覚能力とは注意力」であると、ノヴァーリスは断じている。彼がそのように述べる知覚能力とは、アウラを知覚する能力に他ならない[1]。
また、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」(一九三五‐三六年)で、「アウラ的知覚」について次のように述べている。
美しい仮象の意義は、今や終焉に近付いているアウラ的知覚(auratischen Wahrnehmung)の時代において基礎付けられた[2]。
ベンヤミンによれば、「アウラを知覚する能力」は「注意力」である。そこで、「アウラ的知覚」は、主体が客体の「アウラ」を注意(=意識の持続的集中)して知覚することと読み解ける。また、こうした「アウラ」を注意して知覚することを「アウラの経験」とも形容できる。
この「アウラ的知覚」は、必然的に主体の意識的反応の変化を生じ続けるので「アウラ」を産出し続ける知覚でもある。また、ベンヤミンは、この「アウラ」を経験し産出し続ける「アウラ的知覚の時代」が「今や終焉に近付いている」と考えており、そこに「アウラの凋落」が関わると予測できる。
2 アウラの凋落
ここで、「アウラ的知覚の時代」が「今や終焉に近付いている」ことに関して注目すべきは、ベンヤミンが人間の知覚は自然的・生来的な条件に固定されずに知覚を生じさせる媒体の変化により歴史的に変化すると述べている問題である。事実、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」で、媒体の変化による知覚の変化について次のように告げている。
広大な歴史的時空間の内では、人間集団の存在様式が総体的に変化するのに伴い、人間の知覚の方法もまた変化する。人間の知覚が組織される方法——知覚を生じさせる媒体(Medium)——は、自然的にのみならず、歴史的にも条件付けられている[3]。
さらに着目すべきは、ベンヤミンが同時代に生じている知覚の変化を「アウラの凋落」と呼んでいる問題である。実際に、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」で、「アウラの凋落」について次のように説いている。
もし私達の同時代の知覚の媒体における変化をアウラの凋落(Verfall der Aura)として理解しうるなら、その社会的諸条件を明らかにできる[4]。
その上で、ベンヤミンは同稿で、この「アウラの凋落」における知覚について次のように論じている。
物をその被いから取り出すこと、アウラを崩壊させることは、ある知覚の特徴である[5]。
ここでベンヤミンのいう「被い」とは、「アウラ」と同格的に換言されていることから、物を被う「空間と時間からなる一つの奇妙な織物」としての「アウラ」、つまり物がその成立以来その存在する場所で持続的経験体として備蓄してきた固有の付加的変化全てと推測できる[6]。そして、ベンヤミンは、この本来は一体である物と「アウラ」を分離させる(つまり「物をその被いから取り出」し「アウラを崩壊させる」)「ある知覚」が同時代に発生していると考えていると推察できる。
ベンヤミン自身は、この「アウラを崩壊させ」る「ある知覚」の内容について詳しく説明していない。しかし、論理上、「アウラ的知覚」が「アウラを崩壊させ」ない知覚であり、注意(=意識の持続的集中)を特徴とするならば、「アウラを崩壊させ」る「ある知覚」は「脱アウラ的知覚」と形容でき、注意(=意識の持続的集中)の散逸を特徴とすると考えられる。その場合、「脱アウラ的知覚」は「アウラ」を経験し産出する働きも十全ではないと解釈できる。
そうした「脱アウラ的知覚」は、主体と客体の関係において、介在する媒体により、現存感を構成する原物性・直接性・五感性・静態性等のいずれかあるいは複数が阻害され、相互作用が減じ、主体の注意(=意識の持続的集中)が散逸する時に生じ、その程度に応じて「アウラの凋落」も発生すると想定できる。
なお、この文脈では、「アウラ」を経験し産出し続ける主体と客体の関係を「アウラ的関係」、「アウラの凋落」が発生する主体と客体の関係を「脱アウラ的関係」と呼称できる。
さらに、ベンヤミンは、この「アウラを崩壊させ」る「ある知覚」、つまり脱アウラ的知覚を「近代の感覚」と呼び、「ショック体験」とも呼び変えている。現に、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、「ショック体験」について次のように表現している。
ボードレールは、近代の感覚を得るための代償を明らかにした。つまり、ショック体験におけるアウラの崩壊である[7]。
この「脱アウラ的知覚」あるいは「ショック体験」を生じさせる媒体の例としては、写真、機械、大都市群集、百貨店、博覧会、蒸気鉄道、写真映像、映画等を挙げられる。それでは、次にそれぞれの媒体における「アウラの凋落」の様相を順に見ていこう。ここでは、特にそれらの構造的相似性に注意したい。
3 写真
まず、1839 年に登場した写真による「アウラの凋落」について見てみよう。
第一に、写真では被写体の原物性が失われる。つまり、写像は被写体の外見を感光的に写し取ったものに過ぎないので、被写体自体の物質的要素は消失する。第二に、写真では被写体への直接性が失われる。すなわち、観者が見ているのは被写体自体ではなくその写像に過ぎないので、被写体自体との相互作用は生じない。第三に、写真では被写体への五感性が失われる。つまり、単なる視覚像に過ぎない写像では、観者は被写体の姿をただ見ることができるだけであり、触れることも、聴くことも、嗅ぐことも、味わうこともできない。
これらの結果、写真では、観者の被写体への意識の持続的集中が失われる。すなわち、写像においては被写体との関係において原物性・直接性・五感性が失われ、被写体との相互交流も生じないので、次第に観者の注意は薄れ、ただ一方的な傍観的態度が生じる。
要するに、写真が観者に提供するものは、被写体のある時点での固定的・表層的な視覚情報だけに過ぎない。つまり、写真では、被写体の現存感は失われ、本来は被写体と一体であるそのアウラが脱落する。それと共に、観者と被写体は同一の時空間上に存在せず相互作用が減退するので、観者の意識の持続的集中としてのアウラ的知覚は衰退する。そして、その衰退の分だけ、観者には脱アウラ的知覚が発生することになる。
ただし、ベンヤミン自身が明確に説明していないために常に混乱を招くが、物質的な支持体上の写像自体、つまり感光板や印画紙上の写像自体に対しては、原物的・直接的・五感的な相互作用が生じうる。すなわち、物体としての写像にはアウラ的知覚が生じ、アウラが経験されることに留意したい。ここで凋落しているのは、あくまでも観者と被写体のアウラ的関係である。
こうした脱アウラ的知覚をもたらす写真は、従来の古い自然なアウラ的関係に馴染んだアウラ的知覚の持主には、非常にショックである。なぜなら、写真では、被写体を写像として永久に所有することが可能になるが、同時に被写体自体とは永遠に意思疎通が不可能になるからである。このことを、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、「写真機は瞬間に対し、言わば死後のショックを付与した[8]」と表現している。
とりわけ、この写真における脱アウラ的関係の問題が一番先鋭的に現れるのが、肖像写真である。なぜなら、言うまでもなく、肖像写真は「まなざしを送り返す」ことがないからである。それでもなお、ゲオルク・ジンメルが『社会学』(一九〇八 年)で指摘するように[9]、本来「目」の「相互の見つめ合い」が、「人間関係の全領域における最も完全」な「個人間の結合と相互作用」を生み出すならば、顔はアウラ的関係の最大の源泉である。従って、アウラ的関係に慣れ親しんだ心性は、肖像写真にアウラ的関係を最も希求せざるをえない。
これに関連して、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」で、肖像写真について次のように考察している。
写真では、展示価値が礼拝価値を全戦線で押し退け始める。しかし、礼拝価値は無抵抗に退却する訳ではない。それはむしろ、最後の砦に移住する。そして、その砦は人間の顔である。肖像写真が初期の写真の中心に位置していたのは、決して偶然ではない。遠くにいる、あるいは亡くなった愛する人々の記憶の礼拝に、イメージの礼拝価値は最後の避難所を得る[10]。
現実に、誰でも単なる風景写真であればほとんど心理的負荷なく引き裂くことができるのに対し、肖像写真、特に親しい肉親の肖像写真を引き裂く時には大きな心理的負荷が生じることは一般的に経験されることである。これは、被写体の顔の写しである肖像写真には、まだ感情移入の基であるアウラ的知覚が最も多く働くことの現れと理解できる。

アンディ・ウォーホル《黄金のマリリン・モンロー》1962年
4 機械
次に、機械による「アウラの凋落」について見てみよう。そのために、ここでまず「機械」とは何かを「道具」との差異から見ておこう。
まず、カール・マルクスは『資本論』(一八六七 年)で、主体的人間の客体的自然(他の人間を含む)に対する働きかけとしての「労働」について次のように分析している。このマルクスの「労働」概念は、ベンヤミンの「アウラ」概念に直接影響を与えていると推定される点で非常に重要である。
労働は第一に、人間と自然の間の一過程、つまり人間が自然との物質代謝を自分自身の行為により媒介し、規定し、調整する一過程である。人間は、自然素材そのものに対し自然力として相対する。人間は、自然素材を自分自身の生存のために使用できる形態で私有するために、自然力に属する彼の身体、つまり腕や足、頭や手を運動させる。この運動を通じて、人間は、自分の外なる自然に作用し、それを変化させると同時に、自分の内なる自然を変化させる。人間は、自分の内なる自然に眠る諸力を発現させ、その諸力の活動を自分自身の統御に服させる[11]。
主体的人間は、客体的自然に働きかけることにより、客体的自然を変化させると共に、主体自身の自然も変化させる。ここには、アウラ的関係、つまり同一の時空間上に存在する主体と客体の間における、相互の作用により相互の反作用が喚起され続ける相互作用を読み取れる。そして人間は、このアウラ的関係における意識の持続的集中を通じて、主観を客観化し、個人を社会化し、人格を陶冶する。その意味で、本来アウラ的関係は、個人や社会の健全のために必要不可欠なものである。
このマルクスの「労働」概念を受けて、ヴェルナー・ゾンバルトは『近代資本主義』(一九二七 年)で、「道具」について次のように書いている。
道具は、人間労働の補助として役立つ労働手段である[12]。
これに対し、ゾンバルトは同著で、「機械」について次のように記している。
機械は、人間労働に代替されるべき、つまりそれが無ければ人間が行うだろうことを自ら行う労働手段である[13]。
これを受けて、ルイス・マンフォードは『技術と文明』(一九三四 年)で、「道具」について次のように記述している。
人間の歴史の大部分において用いられてきた道具や用具は、主に人間自身の有機体の延長であった。つまり、それらの道具は、独立した存在ではなかった——より重要なことは、独立した存在ではないと思われていたことである。しかし、それらの道具は、作業者の親しい一部だったけれども、人間の目を鋭敏にし、技能を洗練し、取り扱う素材の性質を尊重することを教えることで、人間の能力にも作用を及ぼした[14]。
その一方で、マンフォードは同著で、「機械」について次のように叙述している。
機械は、その独立した動力源と、粗末な形式においてさえ半自動的に動くために、使用者から離れた一つの実在であり、独立した存在であるように思われてきた[15]。
つまり、道具は、人間を動力源とし、人間の肉体の連続的延長として、人間の意識の持続的集中に基づく意志に従属的な技術手段を指す。
基本的に、道具を用いる場合、主体的人間は、自分の意志に従う道具に有機的に作用し、その道具からの反作用も有機的に受ける。また、主体的人間が道具を用いて客体的自然に作用する場合、主体的人間は自分の意志に従う道具を通じて客体的自然に有機的に作用し、その客体的自然からの反作用も道具を通じて有機的に受ける。すなわち、主体的人間と道具と客体的自然の関係は、主体的人間の意志に基づく一貫的かつ連続的な有機的過程であり相互作用的である。この場合、主体的人間が道具や客体的自然に対する関係は原物的・直接的・五感的・静態的である。従って、道具を用いる労働ではアウラ的関係が成立し、主体にはアウラ的知覚が生起し、主体はアウラを十分に経験し産出し続けることができる。

フランシス・ピカビア《高速回転する機械》1916‐18年
これに対し、機械は、脱天然エネルギーを動力源とし、人間の肉体から独立し、自動的に動作する技術装置を指す。機械の原型は、一八 世紀に実用化される蒸気機関である。
基本的に、機械を用いる場合、主体的人間は自分の意志を無視して動作する機械に対しては有機的に作用できず、その機械からの反作用も有機的には受けない。また、主体的人間が機械を用いて客体的自然に作用する場合も、主体的人間は自分の意志を無視して動作する機械を通じてでは客体的自然に有機的に作用できず、その客体的自然からの反作用も機械を通じてでは有機的には受けない。すなわち、主体的人間と機械と客体的自然の関係は、主体的人間の意志に十分には基づかない相互に分断された反有機的過程であり、十全に相互作用的ではない。この場合、主体的人間が機械や客体的自然に対する関係は、原物的である場合も直接性や五感性や静態性が減少する。従って、機械を用いる労働では、脱アウラ的関係が出来し、主体には脱アウラ的知覚が発生し、主体はアウラを十分には経験したり産出したりすることができない。
換言すれば、機械は主体的人間を、機械からも、客体的自然からも、主体的人間自身からも疎外する。やがて、主体的人間は機械の自動運動に服従させられ、自発的能動性を喪失し、自らも機械のように自動的に反射的反復運動を行うようになる。そうした機械労働における人間疎外や人間性喪失の問題は、チャーリー・チャップリンの『モダン・タイムス』(一九三六 年)における戯画的風刺でよく知られている。

チャーリー・チャップリン監督『モダン・タイムス』1936年
要するに、機械では、主体と客体の関係において、原物的である場合も直接性・五感性・静態性が減衰し、相互作用が減退するので、脱アウラ的関係が生じ、脱アウラ的知覚が発生し、「アウラの凋落」が出現する。これは、チェーンソー・電動ドリル・油圧ショベル・ベルトコンベアー等の作業機械や、鉄道・自動車・飛行機等の移動機械のみならず、自動再生機能や一方的表象機能を持つ視聴覚機械、例えば映画・蓄音機・ラジオ・テレヴィジョン等でも同様に生じることに留意したい。
事実、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」で、機械による人間性喪失の問題について次のように言っている。
この成果に対する関心は甚大である。なぜなら、正に機械装置を前にして、都市住民の圧倒的多数は、事務所や工場の中で、一日の勤務時間の間、自らの人間性を放棄せねばならないからである[16]。
また、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、機械における労働過程の有機的連関の分断について次のように述べている。
機械に対する労働者の動作は、先行する動作の厳格な反復であり、正にそれゆえに先行する動作とは無関係である。機械に対するあらゆる動作は、先行する動作から遮断されている[17]。
さらに、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、道具労働と機械労働の差異について次のように告げている。ここでいう、「経験」はアウラを注意して知覚すること、「熟練」はアウラ的関係、「調教」は脱アウラ的関係と読解できる。
マルクスが手作業において労働の諸要素の連関がいかに流動的であるかを強調しているのは、理由無きことではない。この連関は、ベルトコンベアーに対する工場労働者にとっては、それぞれ独立した物的な連関として立ち現われる。部品は、労働者の意志から独立して、彼の作用範囲に入って来る。そして、同様に自律的に逃げていく。マルクスは書いている。「あらゆる資本主義生産に〔…〕共通するのは、労働者が労働条件を使うのではなく、逆に労働条件が労働者を使うことであるが、この転倒は、機械装置と共に初めて技術的に明白な現実となる」。機械の操作の中で、労働者は「自分本来の運動を自動装置の一様で規則的な運動に」調律することを学ぶ。〔…〕先に触れた文脈では、次のように言われている。「あらゆる機械労働は、労働者の早くからの調教を要求する」。この調教は、熟練とは区別されねばならない。〔…〕未熟練労働者は、機械の調教により最も深く辱められる者である。彼の労働は、経験から遮断される。そこでは、熟練は妥当性を喪失している[18]。
そして、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、「自動装置に順応してもはや自動的にしか自分を表現でき[19]」 ずに「自動装置としての生活を送る[20]」人間のあり方に触れている。また、「ベルト・ブレヒト」( 一九三〇 年)で、「機械の時代における人間の生理学的・経済学的な貧困」[21]についても言及している。
5 大都市群集
また、こうした機械が生産から交通に用いられた場合にも、「アウラの凋落」が発生する。その典型的な現象が、一九世紀後半にジョルジュ・オスマンのパリ大改造等で台頭する大都市群集である。
ここで注意すべきは、大都市群集は、単なる出生率の増加や死亡率の減少以上に、蒸気鉄道等による運輸交通の高速化・大量化を主な成立背景とする点で、本質的に機械の産物である問題である。そして、そうした機械的な高速性・大量性の介在により、大都市群集では主体と客体、つまり歩行者と通行人のアウラ的関係が凋落する。
事実、大都市群集では、誰もが足早かつ疎遠に行き交うので、基本的に歩行者は、通行人を一瞥しても、通行人一人一人と足を止めて全人格的交渉を行うことはなくなる。すなわち、大都市群集では、歩行者と通行人の関係は非常に瞬時的で表面的になる。これにより、誰もが匿名気分で散歩を楽しめるようになり、歩行者と通行人の持続的で充実的な相互交流、つまりアウラ的関係及びアウラ的知覚は減少する。つまりここでは、主体と客体の関係は、原物的ではあっても、直接性が減衰し、五感性・静態性が減退する。これにはさらに、通行人の大量性による注意散漫、つまり意識の持続的集中の散逸も加わる。
その結果、歩行者には、脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚が生じ、その程度に応じて、個々の通行人は親密性を欠いた単なる束の間の視覚印象に過ぎなくなる。やがて、歩行者には、視界に入る厖大で流動的な万華鏡的視覚印象全てと同時に向き合う特殊な知覚が生じる。この具象的奥行の減退した、動態的・疎外的・平面的・一望的知覚を、ヴォルフガング・シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』(1977 年)で、「パノラマ的知覚[22]」 と呼称している。

クロード・モネ《カピュシーヌ大通り》1873年
こうした知覚の変容は、技術の発達により、大都市群集のみならず、日常生活の様々な場面で頻出する。その例として、次に百貨店、博覧会、蒸気鉄道、写真映像、映画について見て行こう。
6 百貨店
それでは、百貨店における「アウラの凋落」について見てみよう。まず、一八五二 年創業のボン・マルシェに始まる百貨店では、買物客と商品の関係が、大都市群集における歩行者と通行人の関係に対応する。
基本的に、百貨店以前の小売店では、入店することは購入を前提としていた。従って、何も買わずに出て行く「ひやかし」は、断られるか、可能でも極めて心理的負担の大きいものであった。また、商品の値段は、仮に決まっていても店主との交渉により変更される余地が大きかった。そのため、買物客は商品を実際に手に取ってその使い勝手を丹念に吟味することが認められており、また実際にそうするのが一般的であった。
しかし、蒸気機関による産業・商業及び交通輸送の発達により、買物客と商品の高速大量循環が可能になると、薄利多売を経営戦略とする百貨店が誕生する。そして、売上増加のために、流通の加速化が促進され、全ての商品には事前に確定済の値札が付けられることになる。つまり、百貨店では、全ての商品の使用価値は後退し、その交換価値が前面化する。
このため、百貨店では、基本的に買物客は、商品の値札を一瞥しても商品を一つ一つ手に取ってその使用価値を入念に確認することはなくなる(「ちょっと見るだけ」)。すなわち、百貨店では、買物客と商品の関係は極めて瞬間的で表層的になる。これにより、誰もが買物気分で漫歩を愉しめることになり、買物客と商品のアウラ的関係は散漫化する。これにはさらに、商品の大量性による注意散漫も加わる。その上、その大量性により、百貨店以前の小売店では抵抗のある購入後の商品の「お取換え」も可能になり、買物客の心理的負荷は一層軽くなる。
その結果、買物客には、脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚が生じる。そして、その脱アウラ的知覚の度合に応じて、個々の商品は、購買義務のない単なる魅惑的な視覚印象に過ぎなくなり、やがて買物客には視界に入る膨大で潮騒的な多幸的視覚印象全てと一度に向き合う万華鏡的知覚、つまりパノラマ的知覚が生じる。さらに百貨店では、商品的パノラマ的知覚と共に、他の買物客に対する大都市群集的パノラマ的知覚も成立する。
事実、ベンヤミンは『パサージュ論』で、百貨店について「薄利多売こそが大量の買物客と大量の商品の主な影響に適する新しい原理である[23]」と書いている。また、ベンヤミンは同書で、「百貨店の目算では、値引交渉を廃することで小売店に比して時間を節約することが重要な役割を演じるとまず思われていた[24]」 と記している。さらに、ベンヤミンは同書で、「百貨店の特質。買物客は自分を群集と感じる。彼等は商品の山と対面する。彼等は全ての階を一目で見渡せる。彼等は定価を支払う。彼等は『お取換え』ができる[25]」と綴っている。
これを受けて、シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』で、「私達は、百貨店にある商品の外見を、古い型の店にある商品の外見と区別してパノラマ的と呼びうる。なぜなら、この商品は、鉄道や大通りで新しい型の知覚を創出したのと同じ交通の加速に関与しているからである。百貨店における、この交通の加速は、商品の売上の加速である。この加速は、鉄道の速度の加速が乗客と風景の関係を変えるのと同程度に、買物客と商品の関係を変える。両者の関係は、静態性、集中性、アウラを喪失し、より動態的になる[26]」と洞察している。
7 博覧会
これと同様の知覚の変容は、一八五一 年のロンドン万国博覧会以来世界各地で開催される博覧会でも生じる。博覧会では、観者と展示品の関係が、大都市群集における歩行者と通行人の関係に対応する。
事実、やはり蒸気機関による産業・商業及び交通輸送の発展が、観覧者と展示品の高速大量運搬を可能にして成立した博覧会では、大勢の入場者による接触破損や長時間占有を避けるため、基本的に観者は、展示品をただ一方的に見物するだけで、展示品を一つ一つ手にとってその使用価値を丁寧に触知することは禁じられる。つまり、博覧会でも、観者と展示品の関係は極めて淡白で見学的になる。これにより、誰もが物見気分で回遊を楽しめることになり、観者と展示品のアウラ的関係は放漫化する。これにはまた、展示品の大量性による注意散漫も加わる。
さらに、展示品が、常に本来の使用目的から乖離した単なる観察対象と化し、時々展示品そのものが模造品であるにつれて、その虚構性はより強まる。そして、この傾向は、展示品がガラスの中に展示される時にさらに顕著になる。なぜなら、ガラスは、視覚以外の五感全てを捨象することで観者の第三者的な見学態度を一層助長するからである。
その結果、観者には脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚が生じる。そして、その脱アウラ的知覚の程度に応じて、個々の展示品は、道義的責任のない単なる好奇的な視覚印象に過ぎなくなり、やがて観者には視野に入る多大で眩惑的な遊興的視覚印象全てと一時に向き合うパノラマ的知覚が生じる。なお、博覧会でも、他の観覧者に対する大都市群集的パノラマ的知覚が生じることは、百貨店と同様である。さらに、こうしたパノラマ的知覚は、一過性の博覧会を恒常化した博物館でも同様に生じることになる。
実際に、ベンヤミンは「パリ——一九世紀の首都(独語草稿)」(一九三五 年)で、博覧会について次のように語っている。
万国博覧会は、商品という物神への巡礼地である。〔…〕万国博覧会は、商品の交換価値を美化する。万国博覧会の創出する枠組では、商品の使用価値は後退する。万国博覧会は幻想を開陳し、人間は気晴らし〔=注意散逸〕のためにそこに入って行く〔括弧内引用者〕[27]」。
また、ベンヤミンは「パリ——一九世紀の首都(仏語草稿)」(一九三九 年)でも、博覧会について次のように話している。
万国博覧会は、商品という物神への巡礼の中心地である。〔…〕万国博覧会は、商品の交換価値を理想化し、商品の使用価値が二次的位置に後退するような枠組を創出する。万国博覧会は、消費から力尽くで遠ざけられていた群集が、商品の交換価値と一体化する程まで、交換価値を深く理解する学校である。「展示品に触れることは禁止されています」。こうして、万国博覧会は人間が気晴らし〔=注意散逸〕のために入って行く幻想への道を開く〔括弧内引用者〕[28]。
8 蒸気鉄道
また、同様の知覚の変容は、19 世紀半ば以降各地で発展する蒸気鉄道でも生じる。蒸気鉄道では、乗客と風景の関係が、大都市群集における歩行者と通行人の関係に対応する。
事実、蒸気機関を直接的な推進動力とする蒸気鉄道では、その機械的加速のために、基本的に乗客は、車窓に高速で展開される風景をただ一方的に眺めるだけで、風景の一つ一つを詳細に観察したり体感したりすることはなくなる。つまり、蒸気鉄道でも乗客と風景の関係は極めて刹那的で書割的になる。これにより、誰もが観光気分で遊覧を愉しめることになり、乗客と風景のアウラ的関係は散逸化する。これにはまた、風景の大量性による注意散漫も加わることになる。
さらに、風景が常に電柱と電線越しに眺められ、時々切通しやトンネルでは全く喪失されるにつれて、その架空性はより高まる。そして、この傾向は、風景を車窓のガラス越しに眺める時にさらに助長される。なぜなら、やはりガラスは、視覚以外の五感全部を捨象することで乗客の傍観者的な鑑賞態度を一層強化するからである。
その結果、乗客には脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚が生じる。そして、その脱アウラ的知覚の度合に応じて、個々の風景は、実感を伴わない単なる仮象的な視覚印象に過ぎなくなり、やがて乗客には、視界に入る陸続たる奔流的な仮想的視覚印象全てと平面的に向き合うパノラマ的知覚が生じる。さらに、こうした蒸気鉄道的パノラマ的知覚は、他にも一九 世紀後半以降に普及する電気鉄道・自動車・飛行機等の様々な移動機械でも同様に生じることになる[29]。
これに関連して、シヴェルブシュは『鉄道旅行の歴史』で、蒸気鉄道について次のように記述している。
大都市における刺激と、鉄道旅行における刺激の質の差異は、この文脈では重要ではない。決定的なことは、知覚器官が受容して消化せねばならない印象の量的な増加である[30]。
また、シヴェルブシュは同著で、蒸気鉄道について次のように叙述している。
鉄道旅行の文脈で見た、パノラマ的知覚の本質的特徴を再考しよう。速力が前景の消失をもたらすにつれて、速力は乗客を、彼を直接的に包含している空間から分離する。つまり、速力は、自らを「ほとんど実体なき障壁」として、客体と主体の間に挿入する。こうした方法で眺められた風景は、例えば鉄道旅行の批判者であるラスキンがまだそうであったように、集中的に、アウラ的にはもはや経験されずに、消失的に、印象派的に、正にパノラマ的に経験される。より正確に言えば、パノラマ的知覚においては、物はこの消失状態に基づいて魅力的に現れるのである[31]。
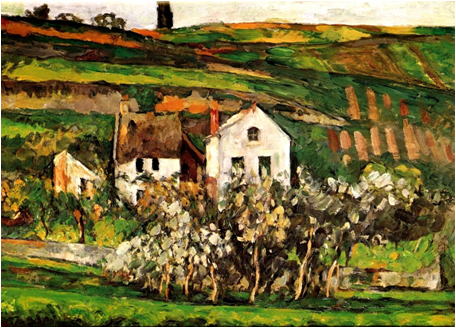
ポール・セザンヌ《オーヴェール・シュル・オワーズ近郊の小さな家並》1873-74年
9 写真映像
さらに、同様の知覚の変容は、一八六七年にコロタイプ製版が開発される写真映像でも生じる。この場合、鑑賞者と写像の関係が、大都市群集における歩行者と通行人の関係に対応する。
先述の通り、まず写真では、観者と被写体のアウラ的関係が脱落し、脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚が胚胎し、一方的傍観が登場する。これに加えて、写真自体や、それを夥しく掲載する新聞・書籍・広告等の写真映像が屋内や屋外に大量に氾濫すると、基本的に観者は、写像に一時目を留めても、写像を一つ一つ腰を落ち着けて真剣に注視することはなくなる。これにはさらに、同一の写像の反復提示による注意散漫も加わる。
その結果、観者には、さらに脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚が生じる。そして、その程度に応じて、個々の写像は、自動的に情動的価値の薄い単なる無害な視覚印象に過ぎなくなり、やがて観者には、視界に入る多数の惑乱的な幻影的視覚印象全てと通時的に向き合うパノラマ的知覚が生じることになる。
これに関連して、カール・パヴェークは『視覚時代』(一九六三 年)で、写真映像について次のように説明している。
人類の歴史において、人間がこれほど大量の映像表現に直面したことは未だかつてなかった。しかも、この映像表現は、絶え間なく変化し、絶え間なく更新されている。そもそも、私達のこれまでの掛け算には、時間という要素が含まれていなかった。私達は常に、世界には一日にどんな映像がどれほどあるかしか見積もってこなかった。しかし、人生には多くの日々があり、近代的なコミュニケーション手段は、映像のない日は一日もないように手配している。他方、映像の洪水は、その一部分が個々人に達するだけとはいえ、今日では誰もがこの洪水に飲み込まれている。従って、映像表現が、私達の知覚、印象、観念、認識の営みに、今日ほど大きな役割を演じたことは未だかつてなかったと言ってよい[32]。
また、オットー・シュテルツァーは『写真と芸術』(一九六六 年)で、写真映像について次のように解説している。
もし、私達が本当に「視覚時代」に踏み入れているとすれば、それは写真カメラという視覚によって引き起こされたのである。現代人の目に触れる映像の——少なく見積もっても—— 90 パーセントは、写真に由来している[33]。

アンディ・ウォーホル《二連画のマリリン》1962年
10 映画
そして、同様の知覚の変容は、一八九五 年に初公開される映画でも生じる。映画では、観者と写真映像の関係が、大都市群集における歩行者と通行人の関係に対応する。
前述の通り、まず写真では、観者と被写体のアウラ的関係は欠落し、脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚が出現し、消極的傍観が顕現する。これに加えて、そうした写真映像を高速で一方的に連続投影する映画では、基本的に観察者は、写真映像を一瞬知覚しても、写真映像を一つ一つ静止的に丁重に熟視することはできない。これにはさらに、同一作品の反復上映による注意散漫も加わる。
その結果、観者には、さらに脱アウラ的関係による脱アウラ的知覚が生じる。そして、その脱アウラ的知覚の度合に応じて、個々の写真映像は、構造的に倫理的負担の少ない単なる娯楽的な視覚印象に過ぎなくなり、やがて観者には、冒頭から終幕までの無数の夢幻的な動画的視覚印象全てと一貫的に向き合うパノラマ的知覚が生じる。さらに、こうした映画的パノラマ的知覚は、他にも二〇世紀以降に隆盛する、テレヴィジョンやインターネット等の様々な動画機械でも同様に生じることになる。
実際に、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、映画について「映画では、ショックの形を取る知覚が形式原理として効果を発揮する。ベルトコンベアーにおいて生産のリズムを規定するものが、映画では受容のリズムの基盤になる[34]」と論述している。
また、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」で、映画について「注意散逸における受容は、芸術のあらゆる領域で益々顕著になっており、統覚の根本的な変化の徴候であるが、そうした受容の実際の練習器具が、映画である。そのショック作用において、映画はそうした受容形式に適っている[35]」と強調している。さらに、ベンヤミンは同稿で、「映画は、統覚器官の根本的な変化に対応する。こうした変化は、個人生活の水準では、大都市の交通における全ての通行人が〔…〕経験しているものである[36]」と論評している。
おわりに
ここで興味深いことは、ベンヤミンがこうした「アウラの凋落」を「経験の貧困」とも呼んでいる問題である。その場合、「貧困」化している「経験」とは、「アウラ的経験」に他ならない。
事実、ベンヤミンは「経験の貧困」(一九三三 年)で、技術の発展による「経験の貧困」を次のように悲しんでいる。
この技術の途方も無い発展と共に、ある全く新しい貧困性が人間に襲来した[37]。
また、ベンヤミンは同稿で次のように嘆いている。
この経験の貧困は、私的な経験の貧困であるだけでなく、人類の経験全般の貧困である。そして、それと共に、この経験の貧困は一種の新しい野蛮状態である[38]。
さらに、ベンヤミンは同稿で次のように悲嘆している。
私達は、貧困になってしまった。私達は、人類の遺産を一つずつ、次々に手放し、しばしば一〇〇 分の一の価値で質に入れ、その代金として「当座的なもの」という小銭を受け取らねばならなかった[39]。
ここで重要なことは、ベンヤミンが、こうした技術の発展による「経験の貧困」つまり「アウラの凋落」は、人々自身が望んで求めた結果でもあると論じている問題である。
経験の貧困——これを、人々が新たな経験を切望しているかのように理解してはならない。いやそれどころか、彼等は諸々の経験から放免されることを切望している。彼等はまた、自らの貧困が——外的な貧困も、結局は内的な貧困も——非常に純粋かつ明確に効果を発揮することができ、さらにその結果、何か好ましい事態が明るみになる、そうした環境も切望している。彼等はまた、必ずしも無知や経験不足でもない。しばしば逆のことが言える。つまり彼等は、「文化」も「人間」も、全てを「貪り食って」しまい、そのため飽食し、うんざりしているのである[40]。
これに関連して、ヴェルナー・ゾンバルトは『技術の馴致』(一九三五年)等で、古来の「技術」とは質的に異なる「近代技術」の性格を「有機的自然の限界からの解放」と特徴付けている[41]。これを敷衍すれば、本稿で見た「道具」は「技術」に含まれ、「機械」は「近代技術」に内包される(ただし、動力源が天然エネルギーである場合は有機的自然の枠内という意味で「技術」に留まる)。
もし、人間の能力が有機的自然の限界に制約されている場合、つまり単なる「技術」の作用範囲に制限されている場合、主体は客体(自然及び他者)とのアウラ的関係を通じて弁証法的な自己陶冶を十全になしうるが、その生産力・移動力・伝達力等は一定の低い水準に留まり、その活動は非常に限定的である。また、こうしたアウラ的関係は、健全な人格形成や社会共和の必須的土台ではあるが、プライヴァシーへの干渉等の心身的負担とも常に背中合わせである。
これに対し、主体と客体の間に様々な「近代技術」的媒体が介入し始めると、主体には客体に対する脱アウラ的関係が生じ、大局的にあらゆる主客関係は反有機的で非人間的なテンポ・論理に支配されてゆくが、徐々に人間の行動は脱自然的に領域を拡大し自由度を高める。また、こうした脱アウラ的関係は、次第に心身の自然で共感的な相互交流を衰微させるが、全能的・透明人間的な解放感を招来する。
その意味で、「近代技術」による「経験の貧困」あるいは「アウラの凋落」は、人間が技術的進歩を通じて自由と繁栄を追求する過程で必然的に生じねばならなかった歴史的・文化的現象と言える。少なくとも、人間が生存における有利さを求める限り、「近代技術」を用いて「アウラ的関係」から離脱し、「アウラの凋落」を現出させたことには必然性があることを認めねばならない。
しかし、それでもやはり、個人や社会の健全のためには、自然で生来的なアウラ的関係は必要不可欠なのではないだろうか? そうでなければ、私達は浅薄な存在になり下がり、人生の充実から隔たってしまうのではないだろうか? もしそうだとすれば、私達は、既に日常生活の一部と化している各種の「近代技術」が構造的かつ自動的に「アウラの凋落」を発生させることを十分に自覚する必要がある。そして、本章は、そのことに改めて気付かせてくれる点において、ベンヤミンの「アウラの凋落」概念の重要性を主張したい[42]。
【註】
引用は全て、既訳を参考にさせていただいた上で拙訳している。
[1] Walter Benjamin, »Über einige Motive bei Baudelaire« (1939), in: Gesammelte Schriften, I (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974; Dritte Auflage, 1990, S. 646. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、四七〇頁。(以下、»Über einige Motive« 「いくつかのモティーフについて」と略す。)
[2] Walter Benjamin, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit [Zweite Fassung]« (1935/36), in: Gesammelte Schriften, VII (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, S. 368. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、六三三頁。(以下、»Das Kunstwerk« 「芸術作品」と略す。)
[3] Ibid., S. 354. 邦訳、同前、五九一頁。
[4] Ibid., S. 354. 邦訳、同前、五九二頁。
[5] Ibid., S. 355. 邦訳、同前、五九三頁。
[6] 秋丸知貴『美とアウラ』第1章「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念について」も参照。
[7] Benjamin, “Über einige Motive,” S. 653. 邦訳、ベンヤミン「いくつかのモティーフについて」四八〇頁。
[8] Ibid., S. 630. 邦訳、同前、四四九頁。
[9] Georg Simmel, Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Berlin, 1908, S. 484. 邦訳、ゲオルク・ジンメル『社会学(下)』居安正訳、白水社、一九九四年、二四八–二四九頁。
[10] Benjamin, “Das Kunstwerk,” S. 360. 邦訳、ベンヤミン「芸術作品」五九九頁。
[11] Karl Marx, Das Kapital, I, Hamburg, 1867; Berlin: Dietz, S. 192. 邦訳、カール・マルクス『資本論(二)』エンゲルス編、向坂逸郎訳、岩波文庫、一九六九年、九–一〇頁。
[12] Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus: historisch-systematische Darstellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, I, Duncker & Humblot, 1924, S. 6. 邦訳、ヴェルナー・ゾンバルト『近世資本主義(第一巻第一冊)』岡崎次郎訳、生活社、一九四二年、七頁。
[13] Ibid., S. 6. 邦訳、同前、七頁。
[14] Lewis Mumford, Thechnics and Civilization, New York, 1934; New York, 1962, p. 321. 邦訳、ルイス・マンフォード『技術と文明』生田勉訳、美術出版社、一九七二年、三九〇頁。
[15] Ibid., p. 322. 邦訳、同前、三九〇–三九一頁。
[16] Benjamin, “Das Kunstwerk,” S. 365. 邦訳、ベンヤミン「芸術作品」六〇七頁。
[17] Benjamin, “Über einige Motive,” S. 633. 邦訳、ベンヤミン「モティーフについて」四五四頁。
[18] Ibid., S. 631–632. 邦訳、同前、四五〇–四五一頁。
[19] Ibid., S. 632. 邦訳、同前、四五二頁。
[20] Ibid., S. 634. 邦訳、同前、四五四頁。
[21] Walter Benjamin, “Bert Brecht” (1930), in Gesammelte Schriften, II (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, S. 667. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「ベルト・ブレヒト」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、五三三頁。
[22] Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München, 1977, S. 166. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『鉄道旅行の歴史——19 世紀における空間と時間の工業化』加藤二郎訳、法政大学出版局、一九八二年、二三七頁。秋丸知貴『近代絵画と近代技術』第2章「印象派と大都市群集」も参照。
[23] Walter Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, p. 107. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅰ)』今村仁司・大貫敦子・高橋順一・塚原史・三島憲一・村岡晋一・山本尤・横張誠・與謝野文子訳、岩波書店、一九九三年、一一一頁。
[24] Ibid., p. 108. 邦訳、同前、一一二頁。
[25] Ibid., p. 108. 邦訳、同前、一一二頁。
[26] Schivelbusch, op. cit., S. 167. 邦訳、シヴェルブシュ、前掲書、二三七‐二三八頁。
[27] Walter Benjamin, “Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts” (1935), in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, S. 50. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「パリ——―十九世紀の首都」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、三三八‐三三九頁。
[28] Walter Benjamin, “Paris, Capitale du XIXème siècle” (1939), in Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, S. 64–65. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「パリ——一九世紀の首都〔フランス語草稿〕」『パサージュ論(Ⅰ)』今村仁司・大貫敦子・高橋順一・塚原史・三島憲一・村岡晋一・山本尤・横張誠・與謝野文子訳、岩波書店、一九九三年、三八頁。
[29] 秋丸知貴『近代絵画と近代技術』第3章「セザンヌと蒸気鉄道」、第4章「フォーヴィズムと自動車」、第5章「『象徴形式」としてのキュビズム」、第6章「近代絵画と飛行機」も参照。
[30] Schivelbusch, op. cit., S. 55. 邦訳、シヴェルブシュ、前掲書、七五頁。
[31] Ibid., S. 166–167. 邦訳、同前、二三五–二三六頁。
[32] Karl Pawek, Das Optische Zeitalter, Olten, 1963, S. 15. 邦訳、カール・パヴェーク『視覚時代』大久保良一・佐々木基一訳、美術出版社、一九七〇年、一一–一二頁。
[33] Otto Stelzer, Kunst und Photographie——Kontakte,Einflüsse,Wirkungen, München, 1966, S. 9. 邦訳、オットー・シュテルツァー『写真と芸術——接触・影響・成果』福井信雄・池田香代子訳、フィルムアート社、一九七四年、一一頁。
[34] Benjamin, “Über einige Motive,” S. 631. 邦訳、ベンヤミン「いくつかのモティーフについて」四五〇頁。
[35] Benjamin, “Das Kunstwerk,” S. 381. 邦訳、ベンヤミン「芸術作品」六二六頁。
[36] Ibid, S. 380. 邦訳、同前、六四〇頁。
[37] Walter Benjamin, “Erfahrung und Armut” (1933), in Gesammelte Schriften, II (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, S. 214. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「経験と貧困」『ベンヤミン・コレクション(2)』浅井健二郎編訳、三宅晶子・久保哲司・内村博信・西村龍一訳、ちくま学芸文庫、一九九六年、三七四頁。
[38] Ibid., S. 215. 邦訳、同前、三七五頁。
[39] Ibid., S. 219. 邦訳、同前、三八三頁。
[40] Ibid., S. 218. 邦訳、同前、三八二頁。次第に、ユダヤ人のベンヤミンはナチス・ファシズムへの対抗から共産主義に接近する。そのため、「経験と貧困」のわずか約2年後の一九三五年以後、「複製技術時代の芸術作品」で、共産主義の前提である技術発展による民主化を支持する立場から「アウラの凋落」した写真による芸術作品の大衆受容を積極的に肯定し、「経験と貧困」とは真逆の論陣を張ることになる。なお、同じく写真複製による芸術作品の享受に肯定的価値を見出す概念が、アンドレ・マルローの『東西美術論』(一九四七年)における「空想の美術館」である。
[41] Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin, 1935, S. 10. 邦訳、W・ゾンバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。
[42] 「アウラの凋落」について、ヴァルター・ベンヤミン以外のメディア論の先行研究を用いて補足しておこう。まず、ヴェルナー・ゾンバルトは『技術の馴致』(一九三五 年)等で、従来の単なる「技術」とは異質な「近代技術」の性格を「有機的自然の限界からの解放」と定義する。つまり、「近代技術」の近代性は、従来の「技術」に、科学革命後の科学的知識を結合し、観念的・論理的にではなく実在的・物理的に「有機的自然の限界からの解放」を実現することを意味する。また、ジョルジュ・フリードマンは『技術と人間』(一九六六 年)等で、産業革命以前と以後を区分する概念として、「自然的環境」と「技術的環境」を提唱する。すなわち、「自然的環境」では、技術は全て天然自然に基づいており、動力は人力・畜力・風力・水力等の天然自然力に依存していた。これに対し、「技術的環境」では、技術は人工の占める割合が複雑に増加し、動力は蒸気・ガス・電気・原子力等の脱天然エネルギーを多用する。そして、「自然的環境」から「技術的環境」への移行により、人間の心性や生活様式にも大きな変化が生じるとした。フリードマンは、この「自然的環境」から「技術的環境」への移行の原因を、自然に対する技術の人工的要素の量的増加による質的変化と見ている。しかし、この分節の曖昧な概念区分では、フリードマン自身が強調するこの環境変化の画期的革命性を正確に規定することができない。そこで、この質的変化に、ゾンバルトの質的変化としての「近代技術」による「有機的自然の限界からの解放」を代入すれば、この「技術的環境」を、より正確に「近代技術的環境」と再定義できる。つまり、主体と客体の間に「近代技術」が介入し、「有機的自然の限界からの解放」が生じると、「自然的環境」とは異質な「近代技術的環境」が生起することになる。基本的に、「自然的環境」における主体と客体の関係、つまり生来的人間と天然的自然の関係は、原物性・直接性・五感性・静態性等を特徴とする現存感に基づく、自然で無媒介的なアウラ的関係である。従って、「自然的環境」では、本質的に人間の知覚は意識の持続的集中を伴い、そうした充実的なアウラ的知覚に基づいて、主体は客体と、つまり自然や他者と、濃密で感情移入的な心身的相互関与を行っていた。これに対し、一九世紀以後、写真や蒸気機関を筆頭に、「有機的自然の限界からの解放」を発生させる各種の「近代技術」が広く日常生活に普及し、主体と客体の間に様々に介在し始めると、主客の自然な心身的相互交流、つまりアウラ的関係は現実的に阻害される。また、その知覚においても、主体には、マーシャル・マクルーハンが『メディア論』(一九六四 年)等でいう五感における「感覚比率」の変更あるいは捨象が生じ、アウラ的知覚は衰退する。その結果、「近代技術的環境」においては、日常生活の様々な場面で脱自然的知覚、すなわち脱アウラ的知覚が生じ、ベンヤミンのいう「アウラの凋落」が発生することになる。秋丸知貴『近代とは何か?』第6章「自然的環境から近代技術的環境へ」も参照。
【初出】秋丸知貴「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラの凋落』概念について」『哲学の探究』第39号、哲学若手研究者フォーラム、2012年、25‐48頁。ただし、本書再録に当たり加筆修正している。なお、初出は、2010年度から2021年度にかけて筆者が連携研究員として研究代表を務めた、京都大学こころの未来研究センター連携研究プロジェクト「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」の研究成果の一部である。
【関連論考】
■ 秋丸知貴『近代とは何か?――抽象絵画の思想史的研究』
序論 「象徴形式」の美学
第1章 「自然」概念の変遷
第2章 「象徴形式」としての一点透視遠近法
第3章 「芸術」概念の変遷
第4章 抽象絵画における形式主義と神秘主義
第5章 自然的環境から近代技術的環境へ
第6章 抽象絵画における機械主義
第7章 スーパーフラットとヤオヨロイズム
■ 秋丸知貴『美とアウラ――ヴァルター・ベンヤミンの美学』
第1章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について
第2章 ヴァルター・ベンヤミンの「アウラの凋落」概念について
第3章 ヴァルター・ベンヤミンの「感覚的知覚の正常な範囲の外側」の問題について
第4章 ヴァルター・ベンヤミンの芸術美学――「自然との関係における美」と「歴史との関係における美」
第5章 ヴァルター・ベンヤミンの複製美学――「複製技術時代の芸術作品」再考
■ 秋丸知貴『近代絵画と近代技術――ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに』
序論 近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究
第1章 近代絵画と近代技術
第2章 印象派と大都市群集
第3章 セザンヌと蒸気鉄道
第4章 フォーヴィズムと自動車
第5章 「象徴形式」としてのキュビズム
第6章 近代絵画と飛行機
第7章 近代絵画とガラス建築(1)――印象派を中心に
第8章 近代絵画とガラス建築(2)――キュビズムを中心に
第9章 近代絵画と近代照明(1)――フォーヴィズムを中心に
第10章 近代絵画と近代照明(2)――抽象絵画を中心に
第11章 近代絵画と写真(1)――象徴派を中心に
第12章 近代絵画と写真(2)――エドゥアール・マネ、印象派を中心に
第13章 近代絵画と写真(3)――後印象派、新印象派を中心に
第14章 近代絵画と写真(4)――フォーヴィズム、キュビズムを中心に




















